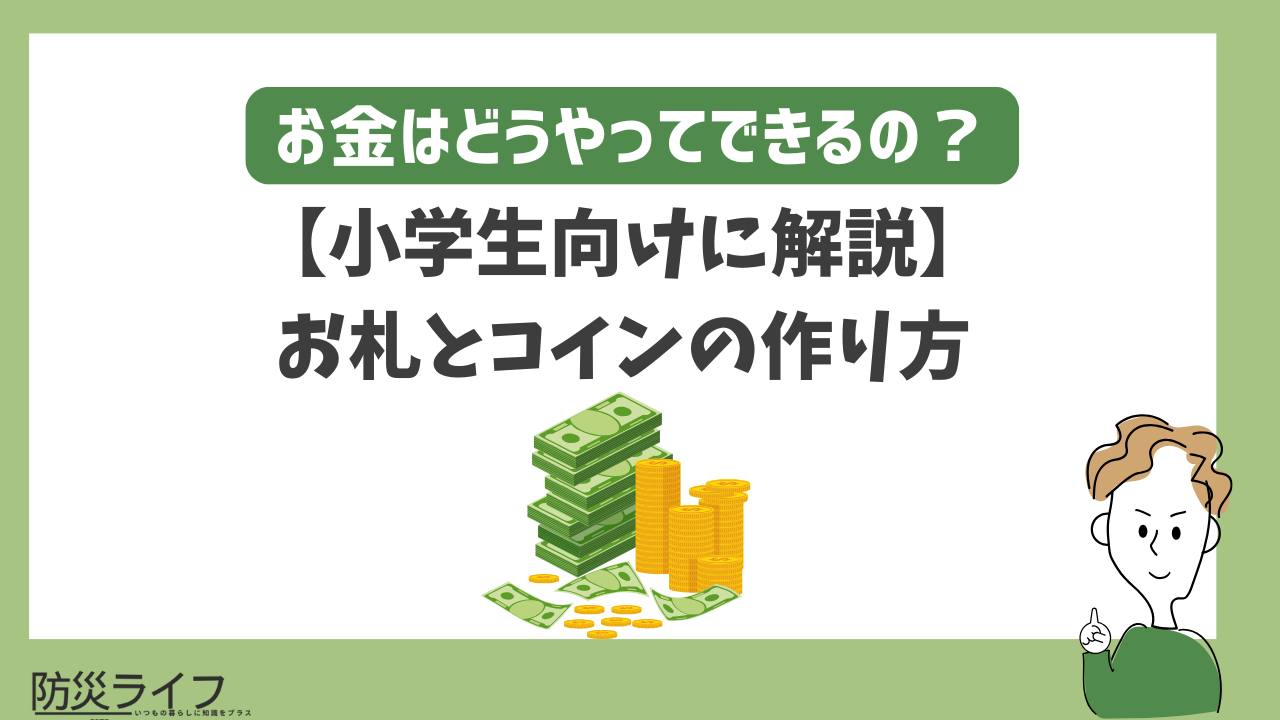毎日つかう「お金(お札とコイン)」は、どこで、どんな材料で、どうやって作られているのでしょう? この記事では、作り方の流れから安全のひみつ、工場のお仕事、観察・自由研究のコツまで、小学生にもわかる言葉でたっぷり説明します。読み終えるころには、きみも立派な**“お金博士”**!
お金づくりの全体像:どこで、誰が、どうやって
お札は「国立印刷局」、コインは「造幣局」
お札(紙幣)は日本各地にある国立印刷局で、コイン(硬貨)は造幣局で作られます。どちらもとても厳しい警備と専門の機械がそろった特別な工場。作られたお金は日本銀行や銀行を通じて、わたしたちの手元に届きます。
材料・安全・検査の“三本柱”
お金づくりは、①材料づくり(紙や金属)→ ②デザイン・加工(印刷・打刻・安全加工)→ ③検査(サイズ・色・重さ・キズ)という三本柱で進みます。どの工程でもミスや不良を見逃さない仕組みがあり、少しでもおかしければ作り直しです。
できたお金が全国へ届くまで
完成したお金はまとめて包装され、日本銀行→各地の銀行→お店→わたしたちの順に広がります。古くなったお金は回収され、新しいものと入れ替えられます。お金は「作る」「使う」「回収する」をくり返す**循環(じゅんかん)**で、いつもきれいで安全な状態が保たれています。
お仕事いろいろ(チームでつくる)
デザイナー/彫刻(ほる)職人/印刷・打刻のオペレーター/紙や金属の研究者/品質検査員/安全を守る警備員など、たくさんのプロが力を合わせています。
お札(紙幣)の作り方:特別な紙と印刷の技
「みつまた・こうぞ」の強い紙
お札の紙はみつまた・こうぞなどの植物を使った特別な和紙。破れにくく、手ざわりが少しザラザラ。水にぬれても簡単には破れず、長く使えるように作られています。原料の繊維はていねいに洗い、ゴミを取りのぞいてから**抄紙(しょうし)**という方法で紙になります。
紙そのものに仕こまれた“安全のタネ”
紙を作る時点で、
- すかし(光にかざすと見える絵)
- 細い色糸(キラッと光ることもある、目に見えにくい糸)
- 強さを出す繊維の配合
などを紙そのものに組み込みます。あとから絵を描くのではなく、紙の中にヒミツがあるのがポイント。
何色も重ねる高精細印刷
お札は何回も色や模様を重ねて印刷します。人物の顔、数字、建物、細い線、もようをぴったり重ね、小さな線のズレも許さない正確さで刷ります。顔の部分など一部は盛り上がって見える印刷(凹版印刷)で、指でさわるとデコボコを感じられます。最後に番号印刷で一枚ごとに異なる通し番号が入ります。
すかし・ホログラム・触って分かる加工
お札にはすかし、キラキラ光るホログラム、角度で色が変わるインク、触って分かる記号など、偽造を防ぐ工夫が何重にも入っています。券種ごとに模様や位置がちがうので、観察すると発見がいっぱい。視覚に不自由がある人のための**識別マーク(触って分かるしるし)**もあります。
裁断→検査→包装
大きな紙にまとめて印刷したあと、同じサイズにきれいに裁断。カメラやセンサーで色・位置・汚れ・キズを細かくチェックし、合格したものだけを**帯封(たいふう)**でまとめて包装します。
コイン(硬貨)の作り方:金属がお金になるまで
金属を混ぜて丸い板をつくる
コインは銅・ニッケル・アルミニウムなどの金属をまぜて、高温でとかして板にし、圧延(あつえん)して所定の厚みに整えます。そこから丸く打ち抜いた“素(もと)”の板(ブランク)を作ります。金属の配合で色・重さ・固さが決まります。
きれいにして、ふちも整える
ブランクは洗浄→熱処理(焼なまし)→ふちの加工をして、キズやゆがみをなくします。ふちにギザギザをつけたり、文字を入れたりするのは偽造対策にもなります。
強い力で模様と数字を打ち出す
丸い板に、年号・数字・花や建物のデザインを強い力でギュッと打ち出す(打刻)と、くっきり立体的な模様になります。これにより見た目が美しく、文字が読みやすいコインができます。
検査→枚数を数えて包装
重さ・直径・厚み・模様のずれなどを機械と目でチェック。合格品は決まった枚数ごとに包装され、出荷されます。基準に合わないものは溶かして再び材料へ。
安全と長持ちのひみつ:偽造防止とリサイクル
くらべてチェック!お札の見分けポイント
光にかざす→すかし確認/傾ける→ホログラムの動き/指でさわる→盛り上がり/細い線や小さな文字を観察。複数のポイントを組み合わせて見分けるのがコツです。夜でもスマホのライトで“すかし”確認ができます(お札は折り曲げすぎないように!)。
コインの見分けと検査のしくみ
コインはギザ・穴・大きさ・重さで見分けます。工場では重さの検査機や高精細カメラで、ほんのわずかなズレもチェック。おかしいものは溶かして作り直します。流通中でも銀行で傷み・変形を見つけると回収します。
古いお金の回収と再利用
汚れたり傷んだお札は回収して細かく裁断。展示や再利用素材に使われることも。古いコインは溶かして金属を再利用し、資源を大切にしています。お金もリサイクルの輪に入っているのです。
観察・自由研究に役立つ!見かた・作って学ぶ
お札・コイン観察チェックリスト
- お札:すかし/ホログラム/盛り上がり/細い線の4点を観察し、スケッチにまとめる。
- お札:番号(通し番号)の文字の形や位置の違いも観察。
- コイン:**穴/ギザ/大きさ/重さ(家庭用はかり)**を測り、どの券種も見比べる。
- コイン:音の違い(軽くコツンと当てたときの響き)をメモ。
家でできる“疑似”実験(安全第一)
- 紙すき風:キッチンペーパーで重ね紙を作り、水にぬらして乾かすと、重ねによる強さの違いが体験できます。
- 型押し風:硬貨に紙をのせて鉛筆でこすると、模様が浮き出る(※コインにキズをつけない・貸与品は不可)。
- 耐水テスト風:一般紙と厚紙を同じ条件でぬらして乾かし、強さの差をくらべる(お札は使わないこと)。
見学で深める(準備→観察→まとめ)
印刷・造幣の見学施設や展示室を活用すると、機械や工程を実物で学べる。
- 事前に疑問リストを作る(例:すかしはどうやって入れるの?)。
- 見学中は図とキーワードでメモ。
- 帰宅後に工程の流れ図と発見まとめを作れば、自由研究がグッと深まります。
マナー&安全
お金は口に入れない、なめない、必要以上にこすらない。観察後は手洗いを。お店や人の迷惑にならないように、会計中の観察はしないことも大切です。
お札とコインの“作り方・工夫”早見表
| 観点 | お札(紙幣) | コイン(硬貨) |
|---|---|---|
| 主な素材 | みつまた・こうぞの特別紙 | 銅・ニッケル・アルミなど金属 |
| 作る場所 | 国立印刷局 | 造幣局 |
| 形づくり | 紙づくり→多色印刷→安全加工 | 金属板→丸抜き→ふち加工→打刻 |
| デザイン | 人物・建物・細線・模様 | 数字・年号・花・建物・穴/ギザ |
| 安全の工夫 | すかし・ホログラム・色変化インク・盛上印刷 | 金属配合・重さ・大きさ・ギザ・穴 |
| 見分け方 | 光にかざす/傾ける/さわる | 触感(ギザ)/穴/サイズ/重さ |
| 長持ちの工夫 | 強い和紙・汚れ札は回収 | さびにくい金属・古貨は溶解再生 |
| 行き先 | 日銀→銀行→お店→わたしたち | 同左(銀行経由) |
工程まるわかり表(もう一歩くわしく)
| 工程 | お札の主な作業 | コインの主な作業 |
|---|---|---|
| 材料準備 | 原料植物の処理・抄紙・すかし・色糸 | 合金づくり・板材化・圧延 |
| 形づくり | 多色印刷・凹版印刷・番号印刷 | 丸抜き(ブランク)・洗浄・焼なまし |
| 仕上げ | カット・検査・帯封・包装 | ふち加工(ギザ等)・打刻・検査・包装 |
| 安全対策 | ホログラム・色変化インク・触感記号 | 大きさ・重さ・ギザ・穴・金属組成 |
Q&A(よくある疑問に答えます)
Q1. お札の“すかし”はどうやって入れているの?
A. 紙を作るときに“厚み”を部分的に変えることで絵が浮かぶ仕組み。あとから描くのではなく、紙そのものの工夫です。
Q2. 5円玉と50円玉に穴があるのはなぜ?
A. 軽くて持ちやすく、見分けやすくするため。さらに偽造しにくい形という安全面の理由もあります。
Q3. 古くなったお札はどうなるの?
A. 銀行などで回収→細かく裁断され、新しいお札と入れ替えられます。裁断片は教材や再利用品になることも。
Q4. 日本と外国でお金の作りは違うの?
A. 紙の種類・大きさ・色・金属の配合・デザインなど国ごとに違います。安全の工夫はどの国でもとても大切です。
Q5. 本物かどうか家で確かめられる?
A. すかし・ホログラム・盛り上がり・細線を複数チェックしましょう。心配なときは銀行で確認してもらえます。
Q6. お札の“盛り上がり”はなぜ必要?
A. 指で触ってわかる識別の助けになり、印刷の細かさを利用して偽造をむずかしくします。
Q7. コインの色が少しちがうのは?
A. 金属の種類や割合がちがうから。配合で色・重さ・かたさが変わります。
Q8. こわれたコインは使える?
A. 穴が広がった・曲がったなどのときは銀行で相談を。状態によっては取り替えの対象になることがあります。
Q9. 新しいお札や記念コインはどう決まる?
A. 国がデザイン・安全技術・使いやすさを考えて計画し、工場で準備して発行します。
Q10. お札は洗ってもいいの?
A. 洗うと傷み・インクにダメージが出ることがあります。洗わないで、汚れがひどいものは銀行で交換しましょう。
用語辞典(やさしい言葉で)
- 国立印刷局:お札を作る工場や研究施設を持つ国の組織。
- 造幣局:コインや勲章、記念メダルなどを作る国の工場。
- 抄紙(しょうし):どろどろの繊維から紙をすく作業。
- すかし:紙の厚みを変えて光にかざすと見える絵や模様。
- ホログラム:角度で色や模様が変わって見えるフィルム。
- 盛上(もりあが)り印刷:指で触ると少しデコボコを感じる印刷(凹版印刷)。
- 通し番号:お札1枚ごとにちがう番号。
- 打刻(だこく):金属板に強い力で模様・文字を押し出す加工。
- ブランク:コインになる前の丸い金属板。
- ギザ:コインのふちの細かな山。偽造対策や識別用。
- 焼なまし:金属をあたためてやわらかくし、加工しやすくすること。
まとめ:見て・さわって・くらべて学ぼう
お札は“特別な紙×高度な印刷”、コインは“金属×強い打刻”で作られ、どちらもたくさんの安全の工夫と厳しい検査を通って、わたしたちの手に届きます。
次にお金を使うときは、すかし・ホログラム・ギザ・穴などを観察して、本物を見分けるコツを体で覚えましょう。工場見学や自由研究に発展させれば、“お金博士”への第一歩**です!