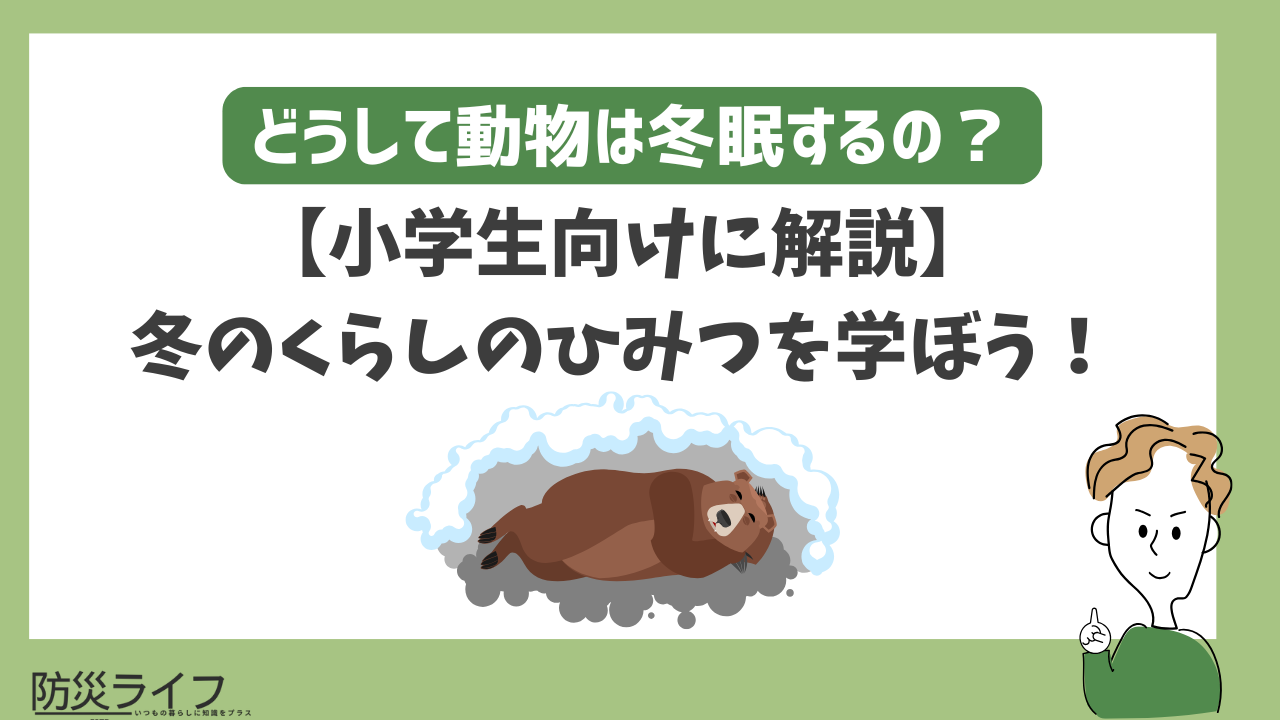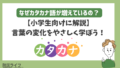冬になると、森や山、野原、池や川の近くでくらす動物たちの中に、長いあいだ動きをおさえてすごす「冬眠(とうみん)」という特別な生活をする仲間がいます。どうして寒くなると冬眠するのでしょう?どこでどんなふうにすごしているのでしょう?
この記事では、冬眠の理由、からだのしくみ、冬眠する動物の種類、冬眠前の準備、冬ごもりや鳥の渡りとのちがい、そして地球環境との関係まで、小学生にもわかりやすい言葉でくわしく解説します。表・チェックリストもたっぷり入れて、自由研究にもそのまま使える内容です。読み終えるころには、冬の森で何が起きているのかを、頭の中で想像できるようになります。
1.冬眠ってなに?なぜするの?
1-1.冬眠の基本:動きをおさえてエネルギーを守る
冬眠とは、からだの動きを大きくおさえて、使うエネルギーをできるだけ少なくするすごしかたです。ぐっすり眠っているように見えますが、完全に眠っているわけではなく、心ぞう・呼吸・体温などを「冬眠モード」に切り替えて命をまもっています。ゲーム機の「省エネ待機」や、家の電気の「節電モード」にたとえるとイメージしやすいでしょう。からだをゆっくりにして、春が来るまでエネルギーを大事につかうのです。
このモードへの切り替えは、一気にではなく、秋の深まりとともに少しずつ進みます。日照時間(昼の長さ)が短くなり、気温が下がるにつれて、からだの中の合図(ホルモンなど)が働き、食欲や眠気、体温の調節が「冬用」になります。
1-2.主な理由:寒さと食べもの不足をのりこえる
冬は草や虫が少なくなり、食べものが手に入りにくい季節です。むりに動き回るとエネルギーが足りなくなってしまいます。そこで動物たちは、からだの働きを下げて少ないエネルギーで冬をこえるという作戦をえらびました。雪や氷で動きにくくなること、外敵(てき)に見つかりやすくなることも、動かないほうが安全な理由です。
1-3.だれでもできるわけではない
冬眠は進化の中で身につけた特別なしくみです。人間はしませんし、すべての動物ができるわけでもありません。冬眠する仲間でも、住む場所(寒い・あたたかい)や年ごとの気温によって、冬眠の深さや期間が変わります。冬がゆるい年には、いつもより短くなったり、途中で目をさましてえさを食べることもあります。
| ポイント | 冬眠の役わり | くわしい説明 |
|---|---|---|
| 食べもの | 消費をへらす | ごはんを食べず、ためたしぼうを少しずつ使う |
| 寒さ | 体温を下げる | 体温を安全な範囲で下げ、熱のムダづかいを防ぐ |
| 外敵 | 見つかりにくい | 土の中や木の穴などで静かにすごし、身を守る |
| 切り替えの合図 | からだの反応 | ねらい |
|---|---|---|
| 昼が短くなる/気温が下がる | 食欲が変化・眠気がふえる | しぼうの貯金を増やし、動きをへらす準備 |
| えさ不足 | 代謝(たいしゃ)を下げる | 少ないエネルギーで生きのこる |
| 初雪・冷たい雨 | すみかへ移動 | 安全であたたかい場所の確保 |
2.どんな動物が冬眠する?種類と地域差
2-1.冬眠する代表的な動物たち
くま/リス/コウモリ/ヤマネ/ハリネズミ/カエル/カメ/ヘビ/イモリ・ヤモリ/一部の魚など。種類ごとに「場所・深さ・期間」がちがうのがポイントです。小さな体ほど熱がにげやすいので、深い冬眠になりやすい傾向があります。
2-2.地域によって行動が変わる
同じ動物でも、寒い地域では冬眠し、あたたかい地域では活動を続けることがあります。えさの多さや雪の量など、その土地の環境が大きく関係します。山地のリスは木の実が少なくなると冬眠をえらび、温暖な海沿いでは冬でも走り回ることがあります。
2-3.「深い冬眠」と「浅い冬眠」
ヤマネやコウモリなどは体温が大きく下がる深い冬眠、くまは体温を少しだけ下げ、ときどき目をさます浅い冬眠(冬ごもりに近い)をします。深い冬眠では、からだはひんやりして動きもほとんど見られません。浅い冬眠では、体勢を変えたり、ときどき子育てをしたりもします。
| 動物 | 冬眠の深さ | 期間のめやす | すみか | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヤマネ | 深い | 半年以上 | 落ち葉の下・土の中 | 体温が大きく下がる。まるくなって体熱をにがさない。 |
| コウモリ | 深い | 数か月 | 洞くつ・屋根裏 | 数十匹~大集団で冬眠も。ときに昼間の暖かい日に場所替え。 |
| ハリネズミ | 深い | 数か月 | 巣穴・落ち葉の中 | 体重がへるので春に回復。巣材選びが上手。 |
| くま | 浅い | 2~4か月 | 山の穴・土のくぼみ | ときどき目をさまし体勢を変える。巣で子育ても。 |
| カエル | 深い | 冬のあいだ | 土・池の底の泥 | 体内を工夫して凍りにくくする。春の雨で目ざめやすい。 |
| ヘビ・カメ | 深い | 冬のあいだ | 石のすき間・土の中 | 気温に合わせて目をさますことも。集団で入ることが多い。 |
コラム:魚の中には、深い池の底で動きをほとんど止めて冬をこす仲間もいます。水の底は温度が安定していて、急な冷えから身を守れるからです。
3.冬眠中のからだのひみつ(心拍・体温・代謝)
3-1.心ぞうと呼吸:ゆっくりにして節約
ふだん1分に100回の鼓動が、冬眠中は10回以下になることも。呼吸もとてもゆっくりになり、からだ全体でエネルギーの節約をします。長く息を止めているわけではなく、必要最低限だけ吸ってはいてをくり返します。
この「ゆっくりモード」はずっと一定ではなく、ときどき少しだけ速くなる時間がはさまります。これは、血のめぐりを保ったり、老廃物(いらなくなったもの)を流したりするための整とんタイムだと考えられています。
3-2.体温:安全な低さまで下げる
くまは数度だけ下げる浅い体温低下、ヤマネやコウモリは大きく下げる深い体温低下。カエル・昆虫などは、体の中で工夫をして凍りにくくします。細胞(体をつくる小さな部品)をこわさないように、体液に糖(とう)などをふやし、氷の結晶ができにくいようにする仲間もいます。
3-3.たくわえと代謝:しぼうをゆっくり使う
秋のうちにしぼう(エネルギーの貯金)をため、冬眠中はすこしずつ使います。体の中では、筋肉のこわばりや内臓の負担が出ないように、特別なたんぱく質や仕組みが働いています。長いあいだ動かなくても、春にすぐ動き出せるのは、この工夫のおかげです。
| はたらき | ふだん | 冬眠中 | ねらい |
|---|---|---|---|
| 心拍(しんぱく) | 60~120回/分(種類で差) | 数回~10回/分 | 熱の発生と酸素の消費をへらす |
| 呼吸 | 数十回/分 | 数回/分 | エネルギーの節約 |
| 体温 | 一定を保つ | 種類により数度~大幅低下 | 熱のムダづかいを防ぐ |
| 代謝(たいしゃ) | 通常 | 大きく低下 | しぼうをゆっくり使う |
ミニ知識:一部の小型の鳥は、夜だけ体温を少し下げて節約することがあります。これは一晩だけの「ちいさな冬眠」に似た工夫です。
4.冬眠の準備とすごしかた/似ている行動とのちがい
4-1.冬眠前の準備:食べる・ためる・選ぶ
- たくさん食べてしぼうをためる(くま・ハリネズミなど)。木の実・虫・魚など、その地域で手に入る高エネルギーの食べものを好むようになります。
- リスは木の実をかくしておく(のちに少し食べることも)。かくした場所をいくつも作り、においや地形で覚えます。
- 木の穴・土の中・岩のすき間・落ち葉の下など、あたたかくて安全な場所をえらぶ。風の当たり方、雨のしみ込み、外敵の通り道をよく確かめます。
| 準備の項目 | チェック内容 | できている合図 |
|---|---|---|
| 体づくり | しぼうの貯金・毛の生えかわり | 体つきが丸く、毛がふかふか |
| すみか | 雨・風・雪に強い/安全な出入り口 | すき間が少なく乾いている |
| 行動 | 活動時間の短縮・夜の動き | 日中の外出がへる |
4-2.すみかの工夫:ひとり?みんなで?
コウモリ・ヘビ・カエルなどは、たくさんの仲間と集まって冬眠することがあります。体を寄せ合うことであたたかく、外敵にも見つかりにくくなります。集団のすみかは温度が安定しやすく、目をさましにくいのも利点です。
4-3.似ている行動とのちがい
| 行動 | 体の変化 | 食べもの | 代表例 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 冬眠 | 心拍・体温が大きく低下 | 食べない/少量 | ヤマネ・コウモリ・カエル | 長期間じっとして冬をこす |
| 冬ごもり | 体温はあまり下げない | ほとんど食べないが、ときどき目をさます | くま | 浅い冬眠に近い。子育ても同時に。 |
| 渡り | ふつう | いつもどおり | ツバメ・ハクチョウ | あたたかい場所へ移動して冬をこす |
観察のマナー:冬眠中のすみか(穴・落ち葉・洞くつなど)をさがしたり、ゆすったりしないこと。静かに自然を見守りましょう。写真をとるなら、フラッシュは使わず、離れて短時間に。
5.まとめ・観察のコツ・Q&Aと用語辞典
5-1.冬眠のひみつまとめ表
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| なぜ冬眠する? | 寒さと食べもの不足をのりこえるため、動きをおさえてエネルギーを守る |
| どんな動物? | くま・リス・コウモリ・ヤマネ・ハリネズミ・カエル・カメ・ヘビ など |
| 体の変化 | 心拍と呼吸がゆっくり、体温と代謝が低下、しぼうをゆっくり使う |
| 準備と場所 | 秋に食べてためる/木の穴・土の中・岩のすき間・落ち葉の下 |
| ちがい | 冬眠(深い)/冬ごもり(浅い)/渡り(移動) |
季節カレンダー(目安)
| 季節 | 主なようす | 観察のポイント |
|---|---|---|
| 秋 | 食べる量がふえる/すみか探し | 木の実を運ぶ・巣材集め |
| 冬 | 動きが少ない/巣でじっと | 足あと・食べかす・巣穴の位置 |
| 春 | 目ざめて活動再開 | 初鳴き・初めの食事・子育て開始 |
5-2.Q&A(よくあるぎもん)
Q1.冬眠中におこしてしまったらどうなるの?
A.からだが冬眠モードのときに動くとエネルギーをたくさん使い、命にかかわることがあります。見つけても、さわらず静かにその場をはなれましょう。
Q2.冬眠中は水を飲むの?トイレは?
A.ほとんど飲みません。体の中で水分を上手に回すしくみが働き、トイレの回数もとても少なくなります。からだの中で出た水分を再利用する工夫もあります。
Q3.くまは冬眠中に赤ちゃんを産むって本当?
A.はい。くまは冬ごもりの最中に出産し、巣穴の中で子育てを始めます。母ぐまは体の栄養で子を育て、春の外の世界へ連れ出します。
Q4.温暖化で冬眠はどう変わる?
A.冬が短くなると冬眠の期間が短くなったり、地域によっては冬眠しない年が出ることも。季節の合図がずれると、目ざめのタイミングとえさの出現(虫や若葉)が合わず、子育てに影響が出るおそれもあります。
Q5.人間は冬眠できるの?
A.できません。人の体は安全に体温を下げるしくみを持たないためです。ただし医療の世界では、体を少し冷やして手術の負担をへらすなど、冬眠の知恵に学ぶ方法が研究されています。
Q6.冬眠する場所はどうやって見つけるの?
A.におい・地形・経験が手がかりです。前年のすみかを再利用することも多く、同じ場所に帰る習性がある動物もいます。
Q7.冬眠中に病気にならないの?
A.からだの動きが遅いあいだは、ばい菌も増えにくく、傷が広がりにくいと考えられています。とはいえ、弱っている個体には冬は厳しい季節です。
5-3.用語辞典(やさしい言いかえつき)
- 冬眠(とうみん):寒い季節にからだの働きを下げ、長いあいだじっとしてすごすこと。
- 代謝(たいしゃ):食べものなどをエネルギーに変えたり、体をつくったりするはたらき。
- 恒温動物(こうおんどうぶつ):くま・リスなど。体温をほぼ一定に保つ仲間。
- 変温動物(へんおんどうぶつ):カエル・カメ・ヘビなど。気温に合わせて体温が変わる仲間。
- 冬ごもり:体温は大きく下げず、あたたかい場所で静かにすごすこと。
- 渡り:鳥などが、季節に合わせて遠くの土地へ移動すること。
- しぼう:体にたくわえるエネルギー。冬眠中の大切な「食料」。
- 体液(たいえき):体の中を流れる水分。血やリンパなど。
- 日照(にっしょう):日の当たる時間。季節で長さが変わる。
自由研究のヒント:近所の公園や里山で、足あと・食べかす・巣材を観察し、季節カレンダーに記録してみましょう。動物をおどろかせない距離を保ち、自然をこわさないように気をつけることが、いちばん大切なルールです。
さいごに:冬眠は、自然の中で生きのこるためのすばらしい工夫です。次に森や湖へ行ったら、「どこが冬眠に向いているかな?」と考えながら、静かに観察してみましょう。自然をたいせつにする心があれば、動物たちのくらしがもっと見えてきます。春の第一声(鳥のさえずり)や、雪どけ後の足あとを見つけたら、冬眠からの目ざめに立ち会えた合図かもしれません。