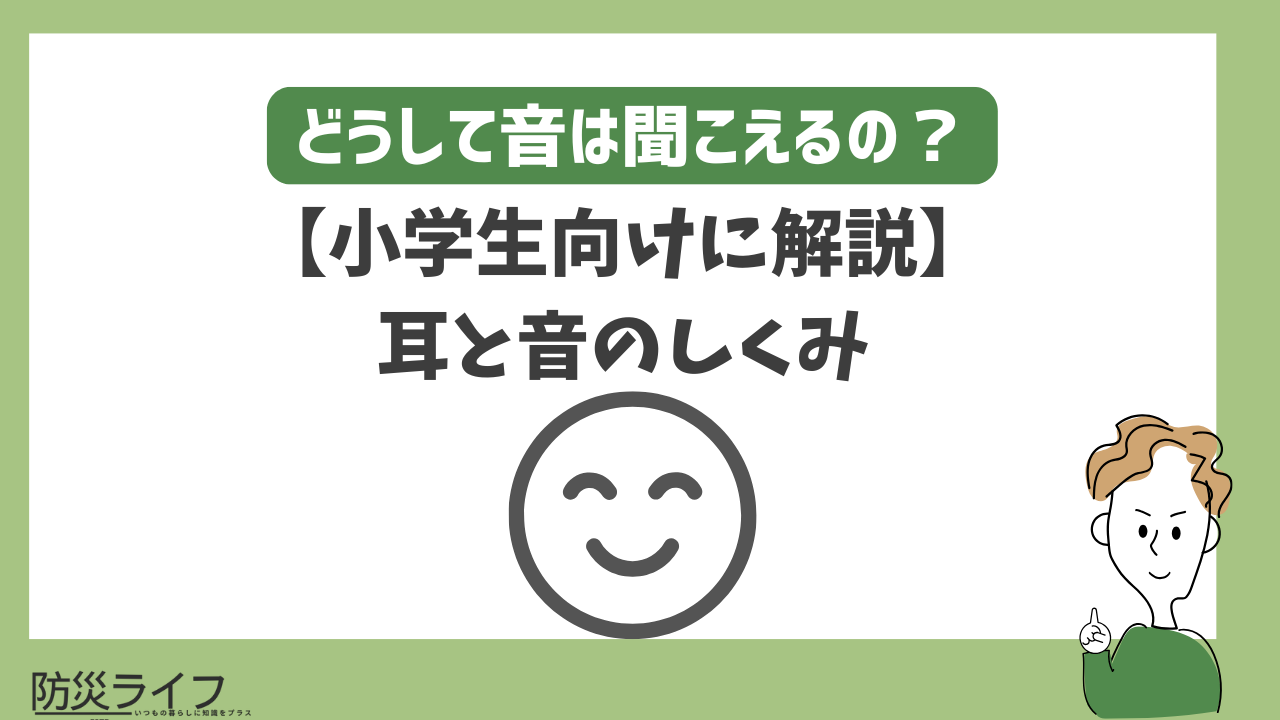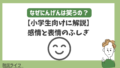毎日、わたしたちはいろいろな音に囲まれてくらしています。友だちの声、雨の音、ピアノやリコーダー、電車や車の音、テレビやゲームの音……。では音って何でしょう?そしてどうして耳で聞こえるのでしょう?
本記事は、もとの内容をぐっと広げた拡大版です。音の正体、耳のしくみ、音の性質、生活と安全、観察・実験にくわえて、音色(おんしょく)・共鳴(きょうめい)・超音波、動物の聞こえ、トラブル対処、自由研究の設計まで、図表とチェックリストでたっぷり解説します。
1.音の正体を知ろう—「ふるえ」と「波」がカギ
1-1.ものがふるえると音が生まれる
音のもとになるのは振動(ふるえ)です。太鼓をたたくと皮がブルブル、ギターやピアノは弦、リコーダーは管の中の空気がふるえます。人の声は**のど(声帯)**が小さくふるえ、空気を押したり引いたりして音をつくっています。
1-2.音波(おんぱ)が空気を進むしくみ
ふるえによってできた音の波(音波)は、空気のつぶ(空気分子)を押す→もどるをくり返しながら伝わっていきます。水面の波のように広がるので、わたしたちの耳に届くころには、音の形や強さが変わることもあります。
1-3.空気だけじゃない—水や地面、壁でも伝わる
音は空気だけでなく、水・木・鉄・地面などでも伝わります。プールで耳を水につけると聞こえ方がちがうのは、水が音をはやく運ぶから。壁越しに声がもれる、線路に耳を当てると遠くの音が聞こえる、これも伝わる道のちがいです。
媒質(音の通り道)でくらべる:音の進む速さ
| 通り道(媒質) | 音の速さの目安 | 例 | 体感のヒント |
|---|---|---|---|
| 空気 | 約340 m/秒 | 会話、楽器、街の音 | 雷の光→音の時間差で実感 |
| 水 | 約1500 m/秒 | 水中の声、クジラの通信 | プールでの聞こえ方が変わる |
| 鉄などの金属 | 約5000 m/秒 | 線路を伝わる音 | 地面や金属はとても速い |
ポイント:光はとても速いので、雷では光が先、音があとになります(数えた秒数×約340mで、雷までのおおよその距離がわかる。3秒で約1km)。
1-4.音は「波」だから広がる・重なる・はね返る
音波は広がり、重なり合い、はね返り(反射)ます。二つの音が重なると強く聞こえたり弱く聞こえたりすることがあり、これを干渉(かんしょう)といいます。お風呂場で声が響くのは、反射と干渉が重なって**残響(ざんきょう)**が生まれるからです。
2.耳のしくみを探検—外耳・中耳・内耳のリレー
2-1.外耳(がいじ):音をあつめて鼓膜へ
見える部分の耳介(じかい)と耳のあなが外耳です。ここで音をあつめて、鼓膜(こまく)へ届けます。耳の形は、前や横からの音を集めやすいつくりになっています。
2-2.中耳(ちゅうじ):鼓膜→耳小骨でふるえを増幅
中耳には、鼓膜と耳小骨(ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨)があります。鼓膜が音でふるえると、その動きをテコのしくみで大きくして内耳へ渡します。のどにつながる耳管(じかん)は、耳の中の気圧をととのえる役目です。
2-3.内耳(ないじ):うずまき管→神経→脳で「音」として感じる
内耳のうずまき管(蝸牛/かぎゅう)にはリンパ液と細かな毛があり、ふるえを電気信号に変えます。その信号が聴神経を通って脳へ。脳が「友だちの声だ」「ピアノだ」「車が近い!」と聞き分けます。
耳の中で起こること—流れでわかる表
| 段階 | 場所 | 何が起きる? | たとえ |
|---|---|---|---|
| ① | 外耳 | 音を集める | パラボラの受け皿 |
| ② | 鼓膜→耳小骨 | ふるえを増幅して内耳へ | テコで力を伝える |
| ③ | うずまき管 | ふるえ→電気信号に変換 | マイクの変換 |
| ④ | 脳 | 音の意味づけ・聞き分け | 司令塔の認識 |
両耳がある理由:右左で届く時間差や大きさの差を脳がくらべ、方向や遠さを知ります。右から車が来ると右耳が先に音を受け取り、脳は**「右から!」**と判断します。
2-4.耳だけじゃない「前庭(ぜんてい)・三半規管(さんはんきかん)」
内耳には、体のバランスを感じる三半規管と前庭もあります。素早く振り向いたとき気持ち悪くなるのは、耳と目の情報のズレが原因です。耳は聞くだけでなく、姿勢も助けています。
3.音の性質をつかむ—高さ・大きさ・速さ・反射
3-1.高い音/低い音:ふるえの速さ(周波数)
ふるえが速いほど高い音、遅いほど低い音。ピアノの右の鍵盤は高音、左は低音。鳥のさえずりは高め、太鼓や雷は低めの音が多いです。男の声が低め、子どもの声が高めになりやすいのも、声帯の長さ・太さのちがいからです。
3-2.大きな音/小さな音:ふるえの大きさ(振幅)
ふるえの幅が大きいほど大きな音、小さいほど小さな音。近くの大声は大きく、遠くの話し声は小さい。テレビの音量を上げると、音の波が強くなり大きく聞こえます。耳を守るために、音量はほどほどが大切です。
3-3.音の速さ・反射・ドップラー
- 音速は通り道でちがう(空気<水<金属)。
- 反射(こだま)は、音が山や壁ではね返る現象。廊下やお風呂場で手をたたくと反射音がよくわかります。
- ドップラー効果は、救急車が近づくと音が高く、遠ざかると低く聞こえるふしぎ。音源と聞き手の距離の変化が原因です。
音の性質まとめ表
| 性質 | 何で決まる? | 例 | 家での観察 |
|---|---|---|---|
| 高さ | 振動の速さ | 鳥=高音、太鼓=低音 | ゴム輪を強く張ると高くなる |
| 大きさ | 振動の幅 | 近い声は大きい | スピーカー音量で変化を見る |
| 速さ | 通り道の種類 | 水中の音は速い | コップの水に音叉を入れて比べる |
| 反射 | 壁・山でのはね返り | やまびこ | 廊下や風呂場で手をたたく |
3-4.音の「色」=音色(おんしょく)
同じ高さ・同じ大きさでも、ピアノとバイオリンの音はちがって聞こえます。これが音色。音の波の形(まざったふるえの作り)や、楽器の材料・形のちがいで生まれます。声のちがいも音色のちがいです。
3-5.共鳴(きょうめい)と倍音(ばいおん)—音がふえるふしぎ
コップの口を指でこするとフーンと鳴るのは、コップの決まったふるえやすい速さに音があったから。これが共鳴です。楽器には、基本の音に倍音(高い成分)が重なり、豊かな音色になります。
4.生活と安全—音の役立ち&耳を守るコツ
4-1.合図としての音:安全とマナー
踏切・チャイム・サイレン・緊急地震速報など、音は注意のサインです。音に気づいたら周りを確認し、安全行動をとりましょう。夜は大きな音を出さないなど、音のマナーも大切です。
4-2.音楽・自然音:集中とリラックス
音楽は気分を切りかえる道具。雨音や小鳥の声などの自然音は、心を落ち着かせることがあります。勉強の前後に短い音楽タイムを作ると、集中のリズムがつくりやすくなります。
4-3.耳を守る5ルール(イヤホンも安心)
1)音量は会話が聞こえる大きさに
2)60分使ったら5〜10分休けい
3)にぎやかな場所では耳せんやヘッドホンで保護
4)耳そうじはやさしく・奥まで入れない
5)水遊びやお風呂のあとは耳の水分をふき取る
環境と対策の早見表
| 場所・場面 | 音のようす | 耳を守る対策 |
|---|---|---|
| バス・電車 | 振動+連続音 | イヤホンは小さめ、長時間は休けい |
| ライブ・花火 | とても大きい音 | 耳せん・少し離れて聞く |
| 自宅学習 | 静かめ | 休けいタイムに好きな曲を短く |
| 工事の近く | 衝撃音がくり返し | 近づかない・耳せんを使う |
4-4.聞こえにくいときのトラブル対処
- 水が入った:片足ジャンプで反対側の耳を下にしてみる。強くこすらない。
- 耳がつまった感じ:高い所へ行ったあとなどはあくびやツバを飲むと耳管が開きやすい。
- 大きな音のあと耳鳴り:静かな所で休む。続くなら大人に相談。
5.観察・実験・自由研究—音のふしぎを体験!
5-1.家でできる簡単実験
- 糸電話:コップ2つと糸で作る。糸をピンと張るとよく聞こえる=固い道の方が音は伝わりやすい。
- ゴム輪ギター:箱にゴム輪を張って強さを変える。強く張るほど高い音になる。
- コップの水で音変化:水の量を変えたコップをスプーンで軽くたたくと高低が変わる。
- こだま測定:広い場所で手をたたき、反射音までの秒数を数える→秒数×340mで壁までのおよその距離に近い値がわかる。
5-2.聞こえ方ゲーム—両耳のしごとを感じる
- 方向あて:目を閉じ、友だちに左右どちらかで音を出してもらい方向をあてる。
- 遠さあて:同じ音を近い/遠いで出してもらい、違いをくらべる。
- 片耳実験:片方の耳を軽くふさぎ、聞き取りにくさを体験(安全な場所で)。
5-3.自由研究づくり(計画テンプレ)
テーマ案:
- 「部屋の場所による反響のちがい」
- 「材料(紙・木・金属)で音の伝わりがどう変わる?」
- 「糸電話の糸の長さと聞こえ」
記録テンプレ:
- 目的/使ったもの/手順/観察(日時・温度・場所)/結果(表・図)/考えたこと(なぜ?次は?)
6.動物と音—聞こえる世界をくらべよう
6-1.人と動物の聞こえる音の高さ(目安)
| 生き物 | 高い音の限界の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 人 | だいたい2万Hzくらい | 大きくなると高い音が聞こえにくくなる |
| 犬・猫 | 4万〜6万Hz | 小さな高音にすばやく反応 |
| コウモリ | 10万Hz以上 | 超音波でえさの場所を知る |
| イルカ | 10万Hz前後 | 水中で超音波のエコーを利用 |
6-2.水中の「音の世界」
水は音が速く遠くまで伝わります。クジラやイルカは、歌やクリック音で仲間と会話したり、位置を知ったりしています。
6-3.小さな生き物と振動
アリやコオロギなどは、地面の振動にも敏感です。音は聞こえなくても、ふるえで危険を感じとります。
7.超音波・低い音・静けさの科学(やさしく)
7-1.超音波ってなに?
人に聞こえないほど高い音。医療のエコー検査で体の中を見るのに使われます。動物ではコウモリ・イルカが活用。
7-2.とても低い音(低周波)
ゆっくりした大きな波。地震の初めのゆれや、大きな風のゴーという音にふくまれます。聞こえにくくても体で感じることがあります。
7-3.静けさはどう作る?
カーテン・本棚・カーペットは音の反射をへらすはたらきがあります。楽器の練習部屋がやわらかな素材でできているのは、響きすぎをおさえるためです。
8.音の活用—道具・通信・くらしの工夫
8-1.マイクとスピーカーの役目
マイクは空気のふるえを電気信号に変え、スピーカーは電気信号を空気のふるえに戻します。スマホ・パソコン・テレビも同じ原理です。
8-2.通信と合図
学校のチャイム、電車のアナウンス、車のクラクションは、音の形や高さを変えてわかりやすい合図にしています。耳が不自由な人向けには、光や振動で知らせる道具もあります。
8-3.暮らしの“音設計”
冷蔵庫やエアコンの運転音はなるべく小さく作られます。アプリの通知音は短く目立つように音色が工夫されています。
9.まとめ図鑑—ひと目でわかる音と耳
| テーマ | 要点 | 例 | 家での体験 |
|---|---|---|---|
| 音の正体 | ものの振動 | 太鼓・声・弦 | ゴム輪をはじく |
| 伝わり方 | 空気・水・金属など | 線路の音はよく届く | 糸電話で確認 |
| 耳のリレー | 外耳→中耳→内耳→脳 | 鼓膜・耳小骨・うずまき管 | 耳をふさぐと方向がわかりにくい |
| 高さ・大きさ | 速さ・幅 | ピアノの右高い/左低い | テレビ音量で変化 |
| 反射 | 山・壁で跳ね返る | やまびこ | 風呂場で手拍子 |
| 音色 | 波の形・材料で決まる | ピアノとバイオリン | コップの材質を変えて叩く |
| 共鳴 | ふるえやすい速さ | コップが鳴る | 瓶の口でボー |
| 安全 | 耳を守る工夫 | 耳せん・休けい | 60分ごとに休む |
10.Q&A—よくある疑問
Q1.音はどうして聞こえるの?
A. ものがふるえ、その波が耳→脳に伝わるからです。
Q2.耳は何でできている?
A. 外耳・中耳・内耳の3つ。鼓膜→耳小骨→うずまき管→脳の順で伝わります。
Q3.ドップラー効果ってむずかしい?
A. 「近づくと高く、遠ざかると低く」。救急車の音で体験できます。
Q4.水中で声が変に聞こえるのは?
A. 水は音の進み方が空気とちがうから。速く遠くへ伝わります。
Q5.こだまはなぜ起こる?
A. 音が山や壁ではね返る(反射)からです。
Q6.イヤホンの安全な使い方は?
A. 会話が聞こえる音量で、60分ごとに休けい。にぎやかな場所では耳せんも活用。
Q7.耳が“つーん”とするのは?
A. 高い所に行ったときなどに気圧が変わるため。あくびやツバを飲むと楽になります。
Q8.同じ音なのに楽器で違うのは?
A. 音色のちがい。波の形や材料のちがいで生まれます。
Q9.静かなほうが勉強にいい?
A. 人によります。気が散るなら無音、集中のスイッチに短い音楽もおすすめ。
Q10.聞こえにくい気がする…どうする?
A. 大きな音のあとなら休む。続くときは大人に相談しましょう。
11.やさしい用語辞典
- 振動(しんどう):ものが行ったり来たりする動き。
- 音波(おんぱ):空気などを押す・もどるで伝わる音の波。
- 鼓膜(こまく):耳の奥で音のふるえを受け取る膜。
- 耳小骨(じしょうこつ):鼓膜のふるえを内耳へ強く伝える骨。
- うずまき管(蝸牛):ふるえを電気信号に変えるところ。
- ドップラー効果:近づくと高く、遠ざかると低く聞こえる現象。
- 残響(ざんきょう):反射で音が残って聞こえること。
- 音色(おんしょく):音の個性。楽器や声のちがい。
- 共鳴(きょうめい):ふるえやすい速さが合って大きく鳴ること。
- 超音波(ちょうおんぱ):人に聞こえないほど高い音。
- 音速(おんそく):音が1秒で進む距離。通り道でちがう。
【まとめ】
音は振動が作る波です。波は空気や水、地面などいろいろな道を通って耳へ届き、外耳→中耳→内耳→脳のリレーで意味のある音として感じられます。高さ(速さ)・大きさ(幅)・速さ(通り道)・反射・音色・共鳴の性質を知ると、生活の中の音がもっとおもしろく見えてきます。耳を大切に守りながら、観察・実験で音のふしぎをたのしみましょう。