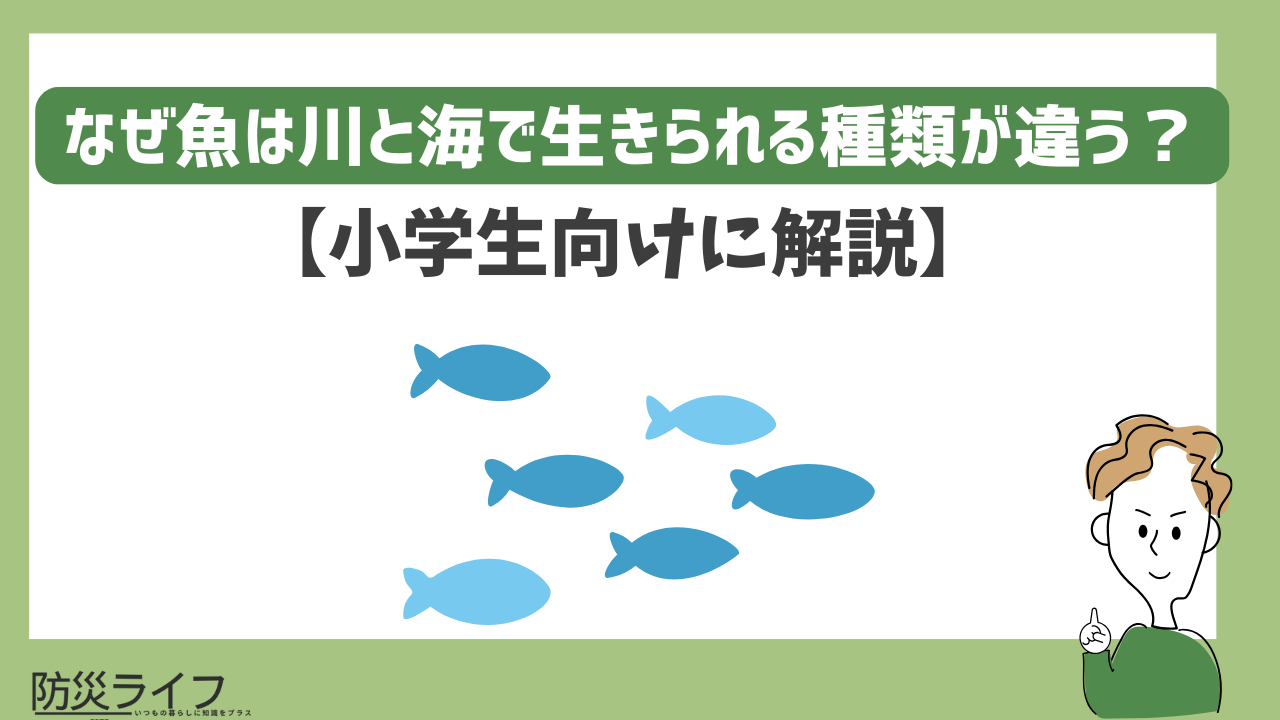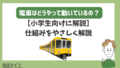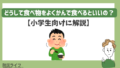はじめに:
「川の魚」と「海の魚」。同じ“魚”なのに、どうしてすみかが分かれているのでしょう?
秘密は、水のしょっぱさ(塩分)だけでなく、水温、流れの強さ、えさの種類、隠れ家の形、そして魚の**体のつくり(塩分や水分を調整する力=浸透圧調節)**にあります。
この記事では、川と海の水のちがい、魚の体の工夫、川と海を行き来する魚の大冒険、世界の魚のくらし、観察や自由研究のヒントまで、小学生にもわかりやすく“超ていねい”に解説します。最後にQ&Aと用語辞典、安全チェックも付けました。
川と海の水のちがいを知ろう(基本編)
川は「真水(まみず)」——塩分はほぼゼロ
山や森の雨・雪どけ水が集まる川は、塩分がほとんどありません。お風呂や水道水と同じ仲間です。川の水は上から下へ流れ続けるので、水が入れ替わりやすく温度差も大きいのが特徴。魚の体からは“水が入りこみやすい”環境です。
海は「しょっぱい水」——塩分は約3%(場所で変化)
海は大昔から川が運んだ塩やミネラルがたまり、塩分が約3%。暖かい海(例:紅海)はもっと高く、寒い海や氷がとけ込む場所は低くなることも。波・潮の満ち引き・潮流で水が常に動き、深さによって光や温度、圧力も大きく違います。魚にとっては“体の水が出ていきやすい”環境です。
まざりあう「汽水域(きすいいき)」——日ごとに性格が変わる水
川と海が出会う河口や干潟は、塩分が時間帯(潮汐)や雨量で大きく変わります。ここにはボラ、スズキ、ハゼ、エビ、カニなど、変化に強い生き物がくらします。育ち盛りの子ども魚(稚魚)の“ゆりかご”にもなります。
表:川と海の水のちがい(ざっくり比較)
| 項目 | 川(真水) | 海(海水) | 汽水域 |
|---|---|---|---|
| 塩分 | ほぼ0% | だいたい約3%(場所・季節で変動) | 0〜3%で大きく変化 |
| 水の動き | 上流→下流に流れる | 波・潮汐・海流で大きく動く | 川の流れ+潮の影響 |
| 温度の変化 | 1日の変化が大きい | 深さで差が大きい | 雨・潮で変わりやすい |
| 魚の感じる負担 | 体に水が入りやすい | 体の水が出やすい | その日その時に合わせて調整が必要 |
魚の体のしくみと塩分バランス(からだ編)
キーワードは「浸透圧(しんとうあつ)」と「塩類細胞」
体の外と中で塩分の濃さがちがうと、水や塩分は“濃い方へ・薄い方へ”移動しようとします(浸透圧)。魚はエラにある塩類細胞や**腎臓(じんぞう)の働きで、この出入りをコントロールして体内のバランス(ホメオスタシス)**を守っています。
川の魚の戦略——「水を出して、塩分を守る」
淡水では体に水が入りこみやすいので、川の魚はうすいおしっこをたくさん出して余分な水を追い出します。エラや腎臓は**塩分を体に戻す(再吸収する)**働きが得意です。
海の魚の戦略——「水を取り入れ、塩分を出す」
海水では体の水が出ていきやすいので、海の魚は海水をよく飲み、体に入った余分な塩分をエラから外へ捨てる仕組みが発達。おしっこは少なくてこいのが基本です。
体づくりの“ちがい”もポイント
- 体型:流れの速い川の上流に住む魚は、岩陰に隠れやすい“流線形”が多い。外洋の速い海では、マグロのような“超流線形”。
- 口の形:川底のエサを食べる魚は下向きの口、プランクトンをすくう魚は上向きの口など。
- うろこ・粘液:外敵や病気から身を守り、泳ぎを助ける大切な装備。
- 目・色:深海では目が大きい/発光器を持つ種も。川の魚はカモフラージュ色が多い。
表:魚の体はどう調整している?
| 住む場所 | 水の入りやすさ | 魚の主な対策 | おしっこ | エラの働き | 代表例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川(淡水魚) | 体内に入りやすい | 水を出し、塩分を守る | 多い・うすい | 塩分を体に戻す | コイ、アユ、ヤマメ |
| 海(海水魚) | 体内から出やすい | 水を取り入れ、塩分を出す | 少ない・こい | 塩分を外へ出す | タイ、アジ、サバ、カレイ |
| 汽水域・回遊魚 | 変化が大きい | 状況で切り替える | 状況で変化 | 切替能力が高い | ボラ、スズキ、サケ、ウナギ |
すみ分けと代表選手(生き物編)
淡水魚(川・湖・池)
コイ、フナ、アユ、ヤマメ、ナマズ、ウグイ、オイカワ、ドジョウなど。岩のかげ、水草の間、流れの速さがちがう場所を使いわけ、四季の温度変化にも対応します。**ダム・堰(せき)**は魚の移動をさえぎることがあるため、魚道が作られることもあります。
海水魚(海・沿岸・深海)
タイ、アジ、サバ、イワシ、カレイ、マグロ、ブリ、サンマ、カワハギ、フグなど。浅い砂地、岩場、サンゴ礁、外洋、深海とすみ場所は多様。サンゴ礁では共生(たとえばクマノミとイソギンチャク)も見られます。
汽水域・回遊魚(川と海の“あいだ”や“両方”)
ボラ、スズキ、ハゼ、テナガエビ、カニなどは汽水域の名選手。サケ、ウナギ、アユ、シシャモ、サヨリなどは川と海を行き来する回遊魚。稚魚期を汽水域で過ごす種も多いです。
表:すみ分け早見表(強化版)
| 住む場所 | 主な魚 | 水の特徴 | からだの工夫 | 食べ物の例 | 外敵・身の守り |
|---|---|---|---|---|---|
| 川(淡水) | コイ、アユ、ヤマメ、ナマズ | 塩分ほぼゼロ、流れあり | 水を出す・塩分を守る | 水草、虫、川底の小生物 | 岩かげに隠れる、体色でカムフラージュ |
| 海(海水) | タイ、サバ、アジ、マグロ、カレイ | 塩分たっぷり、潮流・波 | 水を取り入れ・塩分を出す | プランクトン、小魚、甲殻類 | 群れで守る、速く泳ぐ、トゲ |
| 汽水域 | ボラ、スズキ、ハゼ、エビ、カニ | 塩分が日々変化 | 変化に合わせて調節 | 底生生物、海藻、落ち葉由来の有機物 | 濁りを利用して身を隠す |
| 両方(回遊) | サケ、ウナギ、アユ、シシャモ | 時期で環境が変化 | 体の仕組みを切替える | 稚魚・若魚で変化 | 時期で縄張りや群れ方を変更 |
川と海を旅する魚の大冒険(一生編)
サケ——川で生まれ、海で育ち、故郷へ帰る
川で生まれたサケは、稚魚→若魚へと育ち、川を下って海へ。大きくなってから生まれた川の“においの記憶”を手がかりに、何千キロも旅して帰ってきます。川→海→川と、塩分のちがいに合わせてエラの塩類細胞のタイプや腎臓の働き、ホルモンが切り替わります。
ウナギ——海で生まれ、川でそだち、また海へ
ウナギは遠い海(外洋)で生まれ、レプトケファルスという葉っぱ形の幼生で旅をし、日本の川や湖で何年も暮らし、再び海にもどって産卵します。川へ上るころにはシラスウナギになり、成長につれて体の機能が淡水用から海水用へと段階的に変化します。
アユ・シシャモなど——日本各地の身近な回遊魚
アユは春に海から川へ上り、秋に産卵して一生を終える一年魚。シシャモ、サヨリ、ボラなども、季節や成長に合わせて移動します。干潟や河口は子ども時代の安全基地として重要です。
コラム:体を切り替える“合図”
日照時間・水温・塩分・川の流れ・体の大きさなどの変化が、体内のホルモン(成長や浸透圧調節に関わるもの)に合図を送り、エラの塩類細胞の数や働き、腎臓の再吸収の強さが変化します。
水だけじゃない!環境のちがい(発展編)
水温(すいおん)
川は朝夕の温度差が大きく、浅い場所は夏に高温になりやすい。海は深いほど冷たく、季節による海流の影響も。魚ごとに**好きな温度(適温)**があり、すみ場所を選ぶ大きな理由になります。
溶存酸素(ようぞんさんそ)と流れ
速い流れの川は酸素が多く、息がしやすい。海では波やプランクトンの光合成が酸素を増やします。酸素が少ない場所では、**エラの形や行動(口をぱくぱくするなど)**で工夫します。
光・にごり・隠れ家
川は雨でにごりやすく、岩・水草・倒木が隠れ家に。海は深さで光の量が変わり、サンゴ礁や海藻の森、岩場や砂地など立体的なすみかが広がっています。
食べ物(食物網)
川では落ち葉や土(デトリタス)→微生物→小さな生き物→魚へとつながる食物網。海では植物プランクトン→動物プランクトン→小魚→大きな魚へ。どちらも命のリレーでつながっています。
世界の川・海の魚たち(地理編)
- アマゾン川:ピラニア、ドラド、アロワナ、電気ウナギなど多様性の宝庫。
- ナイル川:ナイルパーチや多くのシクリッド。
- マラウイ湖:色あざやかなシクリッドが数百種以上。
- 北極・南極海:冷たい海でも生きられる“不凍たんぱく質”を持つ魚がいます。
- サンゴ礁(グレートバリアリーフなど):クマノミ、チョウチョウウオ、マンタ、ウミガメ、サメ。
- 深海:アンコウやチョウチンアンコウなど、光のない世界に特化した魚も。
観察・自由研究のコツ(実践編)
基本の持ち物とマナー
- ライフジャケット、長ぐつ、軍手、帽子。保護者といっしょに。
- 水辺では走らない・むりに入らない・天気と潮汐を確認。
- 採集は必要最小限。生き物はやさしく、もといた場所へそっと返す。
観察アイデア(学年別の目安つき)
- 低学年:形や色、動き方のスケッチ。川と海の“におい”や“音”のちがいメモ。
- 中学年:えさの種類しらべ(網でとれた小さな生き物を観察)。日当たり・にごりと魚の数の関係。
- 高学年:塩分濃度・水温・pH・溶存酸素の簡易計測と魚の分布の関係をグラフ化。汽水域での時間帯別しらべ。
おうちでできるミニ実験
- 塩分しらべ:コップの水に食塩を小さじで少しずつ入れ、卵やジャガイモが浮く量を記録。真水と“海水”での違いを体感。
- 浸透圧のモデル:きゅうりに塩をふって出る水を観察(体から水が出るイメージ)。
- 水温と酸素:水温ちがいのペットボトルで金魚すくいの紙片の動き方を比べ、酸素の溶けやすさを推理。
まとめ方のテンプレート
- 調べた場所/日時/天気・潮汐
- 水のデータ(温度・塩分・にごり・pHなど)
- いた生き物(数・大きさ・いる場所)
- わかったこと(仮説→結果→考察)
- 安全・マナー・気づき(次回への改善)
よくある質問(Q&A)
Q1:淡水魚を海水に入れたらどうなる?
A:体の塩分バランスがくずれ、短時間で弱ってしまいます。逆に海水魚を真水に入れても同じ。魚は“その水に合う体”で生きています。
Q2:同じ種類でも川と海で色や形がちがうのは?
A:えさ・天敵・光・温度など環境に合わせた適応の結果。成長段階で見た目が変わる魚も多いです。
Q3:汽水域の魚はなぜ強いの?
A:塩分の変化に合わせて**エラや腎臓の働きを素早く切り替える力(調節力)**が高いから。稚魚の“育ちの場”としても役立ちます。
Q4:サメやエイは川に入れるの?
A:種によります。オオメジロザメのように汽水〜淡水へ入る力が強いサメもいますが、多くのサメは海でしか生きられません。
Q5:外来種(がいらいしゅ)はなぜ問題?
A:もともといた魚のエサやすみかをうばったり、病気を広めたりするから。放流や飼育魚の放しがしはしないことが大切です。
用語辞典(やさしいことば)
- 淡水魚:川・湖・池など真水にすむ魚。
- 海水魚:海にすむ魚。
- 汽水域:川と海の水がまざる場所。塩分が大きく変わる。
- 浸透圧:塩分の差で水や塩が出入りしようとする“みえない力”。
- 塩類細胞:エラにある、塩分を出したり取り入れたりする細胞。
- 回遊魚:季節や成長で長い旅をする魚(サケ・ウナギなど)。
- 食物網:食べる・食べられるのつながり。命のリレー。
- 魚道:ダムや堰の横に作る“魚の通り道”。
チェックリスト:観察の安全マナー
- 大人といっしょに行動。危ない場所(深み・速い流れ・崩れやすい土手)に近づかない。
- 長そで・長ズボン・すべりにくい靴。暑さ・寒さ対策と飲み水。
- 天気・川の増水・潮の時間を必ず確認。
- 生き物にさわる前後は手を洗う。持ち帰らない/外来種を放さない。
- 観察後はゴミを持ち帰る。自然に“ありがとう”。
まとめ
魚が川や海で生きられるのは、水のしょっぱさ・温度・流れ・光・えさなどの環境のちがいに合わせて、エラや腎臓、塩類細胞を使い分け、体内バランスを保つ“すごい仕組み”を持っているからです。
淡水魚・海水魚・汽水域の生き物・回遊魚——それぞれが得意な環境でくらし、時には長い旅で体を切り替えながら命をつないでいます。
近くの水辺や水族館で観察し、自由研究でデータを集めてまとめれば、自然のふしぎがもっと好きになります。
次はあなたの番! 川と海の“すみ分け”を見つける冒険に出かけよう。