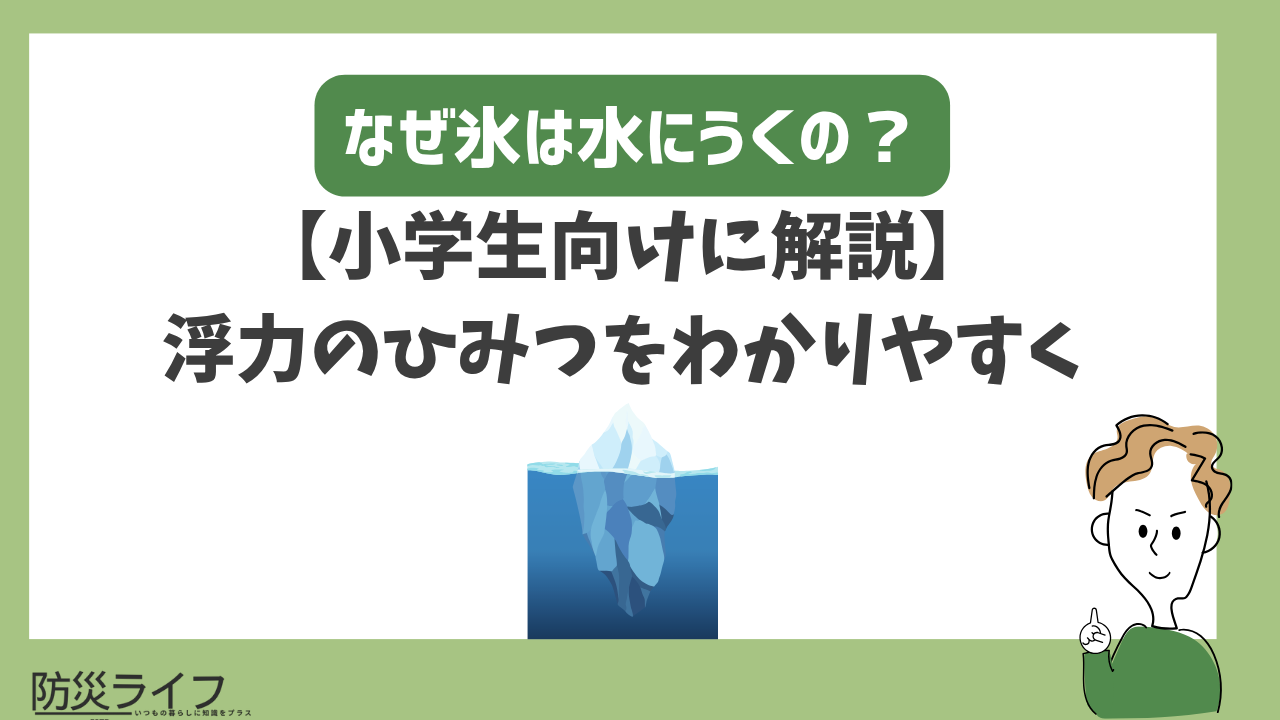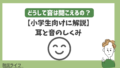夏の日、コップに氷を入れると、氷は水の上でぷかぷかうかびます。ジュースやお茶を飲むとき、「どうして氷は沈まないの?」と不思議に思ったことはありませんか。
この記事では、氷が水にうく理由と、ものを下から持ち上げる浮力(ふりょく)について、身近な例・安全にできる実験・自由研究のヒントまでたっぷりやさしく解説します。読み終えるころには、家や学校で自分で確かめられる力も身につきます。
1.氷が水にうくほんとうの理由—「密度」と「分子のならび」を見てみよう
1-1.水と氷は同じ“水”でも性質がちがう
水は液体、氷は固体。同じ量でも、氷は水より軽くなります。これは、氷になると分子(ぶんし)のならびが広がってすきまが増えるから。だから同じ重さでも体積は氷のほうが大きいのです。
1-2.キーワード「密度」—ぎゅうぎゅう? それともスカスカ?
密度は「同じ大きさ(体積)の中に、どれだけ中身がつまっているか」を表す言葉。中身がぎゅうぎゅう=密度が高い、スカスカ=密度が低い。氷は水より密度が低いので、軽く感じ、うきやすくなります。
1-3.氷は体積がふくらむ—約9%アップのわけ
たとえば1リットルの水をそのまま凍らせると、できた氷の体積は約9%大きくなります。これは分子が六角形の形にきれいに並ぶとき、すきまがたくさんできるから。結果として密度が下がり、氷は水にうくのです。
1-4.“水だけの特別な性質”を知ろう(4℃でいちばん重い)
水は約4℃でいちばん密度が高くなります。寒い季節の池や湖では、底の水が4℃、その上は0℃近くになり、いちばん上の表面だけが氷になります。これが冬でも生き物が生きられるひみつです(→5章でさらに深掘り)。
水と氷のちがい(イメージ表)
| 比べること | 水(液体) | 氷(固体) | うく・しずむへの影響 |
|---|---|---|---|
| 分子のならび | まとまりながら自由に動く | 六角形のきれいな並びですきまが多い | 氷はスカスカで密度が低い→うきやすい |
| 体積(同じ重さ) | 小さめ | 大きめ(約9%増) | 体積が大きい=密度が下がる |
| 密度 | 高め | 低め | 密度が低いものほど水にうきやすい |
2.浮力ってなに?—水や空気が下から押す力を体感しよう
2-1.浮力の正体—「押しのけた水の重さ」だけ持ち上がる
水の中にものを入れると、そのものは自分の体積ぶんの水を押しのけます。このとき、押しのけた水の重さと同じ力で下から押し上げられる——これが浮力です。浮力がものの重さより大きいとうく、小さいとしずむ、同じだと真ん中で止まるように見えます。
覚え方:浮力=押しのけた水の重さ(ここがポイント!)
2-2.形や中の空気も“うきやすさ”に関係
同じ材料でも、大きく広がった形や中が空っぽ(空気が多い)だと、押しのける水の量がふえるので浮力が強くなります。だから鉄でも船のような形だとうくのです。
2-3.計算してみよう(かんたん算数)
1辺が2cmの氷(サイコロ形)を想像。体積は2×2×2=8cm³。氷の重さはだいたい0.917g/cm³×8=約7.3g。押しのける水の重さ(浮力)は8gです。浮力(8g)>氷の重さ(7.3g)なのでうきます。沈んでいる割合(しずんでいる体積)は7.3/8 ≒ 0.91、つまり約9割が水中、残りが水面の上というイメージです(ざっくり計算でOK)。
うく・しずむの見分け表
| 状態 | 条件 | 例 |
|---|---|---|
| うく | 浮力 > ものの重さ | 氷、葉っぱ、木片、空のペットボトル |
| 真ん中で止まる | 浮力 = ものの重さ | よくできた潜水おもちゃ、よく調整した卵の塩水実験 |
| しずむ | 浮力 < ものの重さ | 石、鉄のかたまり、ビー玉、コイン |
3.くらしと自然でわかる「うく・しずむ」—地球規模の役立ちまで
3-1.おふろやプールで体が軽いわけ
おふろでふわっと体が軽く感じるのは、体にも浮力が働くから。空気をたくさん吸うと体積が少し増え、よりうきやすくなります。浮き輪やビーチボールは中が空気なので、とてもうきやすいのです。
3-2.氷が水にうくから、生き物が守られる
冬、湖や池は表面だけが氷になります。氷はうくので、下の水は凍りにくいまま。魚やカエルなどの生き物は水の中で冬をこせるのです。もし氷がしずむなら、湖のそこまで全部凍ってしまい、生き物がくらせません。
3-3.真水と塩水のちがい—塩水のほうが“うきやすい”
水に塩をとかすと、塩水の密度は高くなります。だから同じものでも真水ではしずむ卵が、塩水ならうくことがあります。海で体がうきやすいと感じるのも、このためです。氷も海水のほうがより高くうく(水面上に出る割合がやや増える)という性質があります。
3-4.船・潜水艦・浮沈子(ふちんし)
- 船:鉄で作っても中に空気があり、広い形でたくさんの水を押しのけるからうく。
- 潜水艦:中のタンクに水を入れる・出すことで**重さ(密度)**を調整し、しずむ/うくを切り替える。
- 浮沈子:ペットボトルの中の小さなおもちゃを、握る力で沈めたり浮かせたりできる実験道具。空気の体積を変えて平均の密度を変えるのがコツ。
身近な“うく・しずむ”早見表
| もの | うく? しずむ? | ポイント |
|---|---|---|
| 氷 | うく | 水より密度が低い+浮力 |
| 葉っぱ・木片 | うく | 繊維の間に空気、密度が低い |
| 空のペットボトル | うく | 中が空気で体積が大きい |
| 砂利・石 | しずむ | 密度が高い、体積の割に重い |
| 鉄のかたまり | しずむ | 材料の密度が高い |
| 鉄の船 | うく | 形で体積を大きくして浮力アップ |
| 生卵(真水) | しずむ | 真水は密度が低い |
| 生卵(塩水) | うく | 塩水は密度が高い |
4.家でできる!安全・かんたん実験&自由研究
4-1.実験① いろんなものを水に入れて比べよう
用意:ボウルかバケツ、水、消しゴム、ビー玉、葉っぱ、木片、プラキャップ、クリップ、空ペットボトル、アルミホイル
手順:一つずつ入れてうく/しずむ/真ん中を観察。形・中に空気・重さのどれが効いているかメモしよう。
発展:アルミホイルの形を変える(丸める/お皿に広げる)だけで結果が変わることも確かめよう。
安全:こぼれた水はすぐふく。小さなものは口に入れない。
4-2.実験② ペットボトルの“浮き沈み装置”
用意:500mLペットボトル、キャップ、ビー玉、砂、ストロー
手順:ボトルに水を入れ、空気の量や重りの量を変えて浮いたり沈んだりを調整。空気が多いほどうきやすいことを確かめよう。
発展:キャップをゆるめる/しめるで中の空気量をコントロールしてみよう。ストローで空気を足す・抜くと変化がよくわかる。
4-3.実験③ 卵で試す「塩水と真水」
用意:コップ2つ、水、塩、卵、スプーン
手順:片方は真水、もう片方は塩をよくとかした塩水(小さじ1→2→3…と段階的に)。卵を入れてうく/しずむをくらべる。
ポイント:塩をふやすほど密度が高くなり、うきやすくなる。卵の沈み方の深さを定規で測るとデータ化できる。
4-4.実験④ 氷はどれだけ水面から出る?
用意:透明コップ、氷(同じ大きさ)、水、油性ペン
手順:氷をそっと入れ、水面の高さと氷の出ている高さに印をつけて観察。塩水に変えると、出る高さが増えるのもチェック。
4-5.工作:沈まない“わたしの船”を作ろう
材料:スチロールトレー、ペットボトル、わりばし、アルミホイル、テープ、クリップ(重り)
ねらい:どんな形だとたくさんの荷物をのせても沈まない? 底を広く、軽く作る、中に空気を残す、などを工夫して浮力アップ!
評価:同じ重り(クリップ)を何個のせられるか競争しても楽しい。
観察ノートの書きかた(テンプレ)
| しらべたこと | 使ったもの | 手順 | 結果 | わかったこと・次の工夫 |
|---|---|---|---|---|
| 例:卵の塩水実験 | 卵、水、塩、コップ | 真水と塩水に入れる | 真水=しずむ/塩水=うく | 塩水は密度が高い→うきやすい/塩の量で変化 |
| 例:アルミホイルの形 | アルミホイル、水 | 丸める/皿状にする | 丸める=しずむ/皿状=うく | 形で押しのける水の量が変わる→浮力が変化 |
安全メモ
- 床がぬれるとすべりやすい→タオルを準備。
- 卵は割らないようにやさしく。
- 小さな部品は誤飲注意。低学年は保護者同伴で。
5.もう一歩ふかぼり—温度・氷山・水そう・飲みものの密度
5-1.水は4℃でいちばん“重い”
水は約4℃のときいちばん密度が高くなります。冬の池で底の水が4℃、上が0℃近くになり、表面だけが凍るのはこの性質のおかげ。生き物が底で冬をこせる理由です。
5-2.氷山や海の氷—どれだけ水面に出ている?
海にうかぶ氷山は、見えているのはほんの一部。大部分は水の中にあります。これは氷の密度が水より少し低いだけなので、水中に沈んだ部分が多くなるからです。塩水ではさらにうきやすくなります。
5-3.コップの氷がとけたら水はふえる?(よくあるギモン)
コップの中で水にういた氷がとけても、水の高さはほとんど変わりません。氷がしずめていた分の水の体積と、とけて水になった体積が同じくらいだからです(塩や砂糖が入っていない場合)。
5-4.砂糖やジュースだとどうなる?
砂糖が入ったジュースも真水よりやや密度が高いので、氷はわずかに出方が増えることがあります。炭酸は気泡で一時的にうきやすく見えることも。飲みものの温度差(冷たいほど密度が高い)でも沈み方が少し変化します。
5-5.気候と海の循環にも関係がある
海水の温度や塩分による密度のちがいは、海の流れ(循環)をつくります。冷たい海水は重く沈み、温かい海水は軽くうく。こうした動きが地球の気候にも影響しています。
ふかぼりメモ(知っていると“理科名人”!)
- 氷→水に変わると体積がへる(だから密度が上がる)。
- 塩水は真水より密度が高い→よりうきやすい。
- 船は材料が重くても、形と空気で浮力を作ってうかぶ。
- 炭酸飲料は気泡で一時的にうきやすく見えることがある。
6.まちがえやすいポイント—ここを直せば理解がグンと深まる
- 「軽いものは必ずうく」→ ×
とても軽い石でも密度が高ければしずみます。 - 「重いものは必ずしずむ」→ ×
鉄の船は重くても形と空気でうきます。 - 「浮力はいつも同じ」→ ×
押しのけた水の量が増えれば浮力も増えます。形で変わります。 - 「氷がとけると海面は大きく上がる」→ △
海の上に浮いている氷(海氷・氷山)がとけても、海面の高さはほとんど変わりません。ただし陸の上の氷(山や大陸の氷)が海へ流れ込む場合は別です。
7.チャレンジ算数—やってみよう(解答つき)
問1:体積が10cm³の氷(密度0.917g/cm³)が水に入っています。押しのける水の重さは?
ヒント:押しのける水の重さ=体積(cm³)=g。
答:10g(氷の重さは約9.17gなので、うきます)。
問2:真水ではしずむ生卵(60g)が、塩水ではうきました。卵がうくために必要な押しのけ体積は何cm³?
ヒント:塩水の密度を1.05g/cm³とします。
答:60g ÷ 1.05 ≒ 57cm³(これだけ押しのければうく)。
問3:アルミホイル10gで船を作るとします。押しのける水の重さ>10gになればうきます。最低でも何cm³の水を押しのければよい?
答:10cm³以上(実際は余裕が必要)。
8.Q&A—氷と浮力のギモンを一気に解決!
Q1.どうして氷は水にうくの?
A. 氷は水より密度が低い(スカスカ)から。水に入ると浮力で下から押し上げられ、水面にうくのです。
Q2.密度ってなに?
A. 同じ大きさの中にどれだけ中身がつまっているかを表す数。つまっているほど重い(密度が高い)、すきまが多いほど軽い(密度が低い)。
Q3.塩を入れると、ものはうきやすくなる?
A. はい。塩水は密度が高くなるので、同じものでもうきやすくなります。
Q4.氷がとけると水はふえる?
A. コップの飲みものの氷なら、水位はほとんど変わりません。氷がしずめていた分と、とけて水になった分がつり合うからです。
Q5.鉄は重いのに、どうして船はうくの?
A. 形で体積を大きくし、中に空気を取りこむことで押しのける水の量(=浮力)を大きくしているから。
Q6.おふろで体が軽いのはなぜ?
A. 体にも浮力が働くから。空気を吸うと体積が少し増え、よりうきやすくなります。
Q7.氷は塩水だとどうなる?
A. よりうきやすくなり、水面から出る部分が少し増えます。
Q8.炭酸の泡は浮力に関係ある?
A. 小さな空気の泡も体積なので、うきやすさに少し影響します。泡が消えると沈みやすくなることも。
Q9.真ん中で止まるのはなぜ?
A. 浮力と重さがつり合っているから。少し形や空気量を変えると、ういたり沈んだりが変化します。
9.用語辞典(やさしいことばで)
- 密度(みつど):同じ大きさの中身のつまっている度合い。重ければ密度が高い。
- 体積(たいせき):ものが占める大きさ。コップ何杯ぶん、箱何個ぶん、などのイメージ。
- 分子(ぶんし):水や空気を作っているとても小さな粒。
- 浮力(ふりょく):水や空気が下から押し上げる力。押しのけた水の重さぶん働く。
- 比重(ひじゅう):水と比べた重さの割合。1より小さいとうきやすい。
- 海氷(かいひょう):海の水がこおってできた氷。表面にうく。
- 氷山(ひょうざん):氷の山。見えているのは一部で、ほとんどが水中。
- 押しのける(排水):ものを入れたときによけられる水の量。これが浮力のもと。
- アルミホイル船:軽くて形を変えやすい船の模型。形で浮力を調整する練習に最適。
【まとめ】
氷が水にうくのは、氷の密度が低いことと、水の中で働く浮力のおかげ。くらしの中の「うく・しずむ」を観察すると、形・空気・密度の関係がよく見えてきます。
安全に気をつけながら実験や工作にチャレンジして、身の回りの浮力のひみつをたくさん見つけてみましょう。塩水/真水、冷たい/あたたかい、形が細い/広いなど条件を変えて比べると、理科の目がどんどん育ちます。次は、潜水艦の仕組みや気球が空にうく理由にも挑戦してみてください!