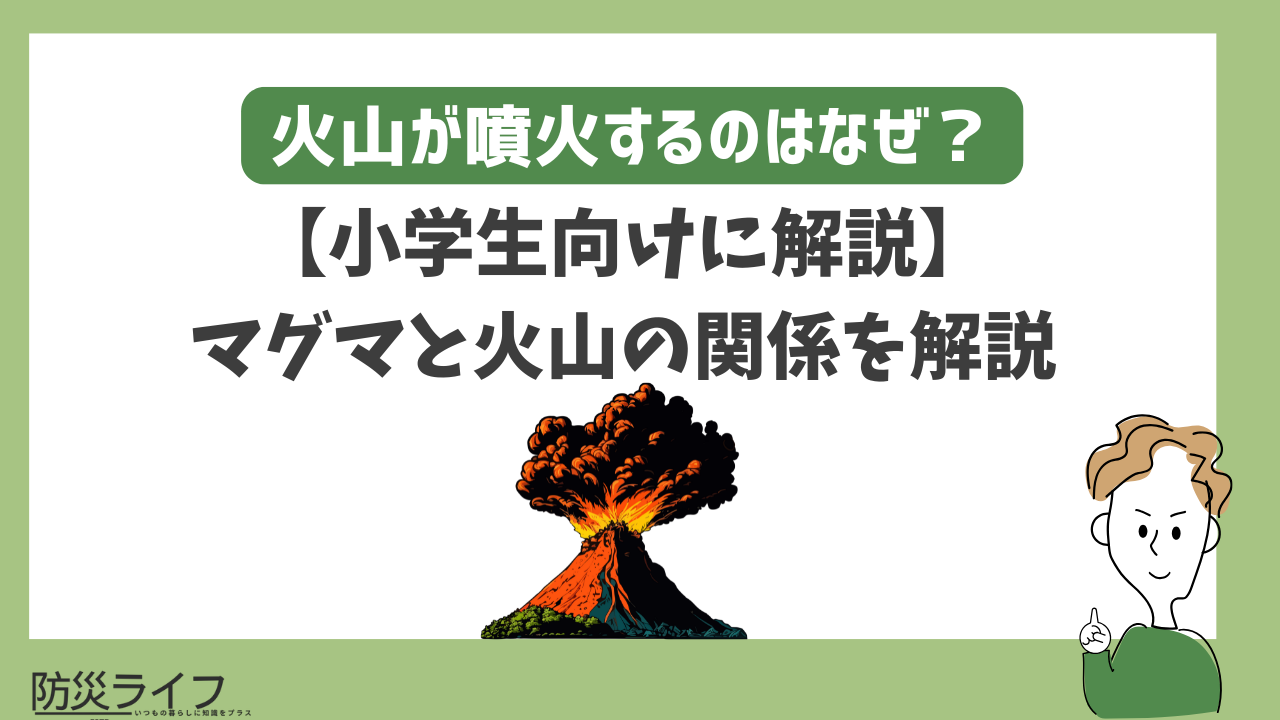火山(かざん)は、地球の中の熱と物質が外へとどく“出口”。 山の形をしていても、その下にはマグマ(とけた岩石)やガスが動く道があり、ときに噴火という形で外へ出てきます。日本には多くの活火山があり、温泉や豊かな土をもたらす一方で、火山灰や火砕流などの危険もあります。
ここでは、子どもにもわかる言葉で、火山とマグマの関係、噴火のしくみ、火山の種類、世界と日本の火山のようす、恵みと注意点、自由研究のヒントまで、読みごたえたっぷりに解説します。
1.火山とは何?――大地の中をのぞいてみよう
1-1.火山は「地球の出口」
火山は、地球の中で生まれたマグマやガスが外へ出る特別な山です。見た目はふつうの山でも、内部にはマグマだまり(マグマがたまる場所)や、地表へつながる火道(かどう)、上に開いた火口(かこう)があります。火山のふもとには温泉がわき、ミネラルゆたかな土が広がることも多いです。
1-2.マグマってどんなもの?
マグマは、地球の深いところで岩石がどろどろにとけたもの。温度はおよそ1,000〜1,200℃で、赤やオレンジ色に光ります。冷えて固まると岩石になり、地上へ出たマグマは溶岩(ようがん)と呼ばれます。マグマには、水蒸気・二酸化炭素・硫黄をふくむガスや、鉱物の粒がまざっています。
1-3.火山の内部を言葉で模型にする
下の表を見て、火山の中のしくみを押さえましょう。
| 場所・用語 | どこにある? | はたらき |
|---|---|---|
| マグマだまり | 地表の下の深いところ | マグマがたまる池のような空間 |
| 火道 | マグマだまり〜火口まで | マグマやガスが通る道 |
| 火口 | 山のてっぺんや横 | 噴火でマグマや灰が出る穴 |
| 側火口 | 山の横腹 | 主な火口以外から出る出口 |
| カルデラ | 大きくくぼんだ地形 | 大噴火後にできる大きなくぼみ |
| 岩脈(がんみゃく) | 地中を横切る板のような溶岩 | 固まって壁や板の形になる |
1-4.火山とほかの山のちがい
ふつうの山は、大地が押し上げられてできたり、川にけずられて形づくられます。火山は、マグマや灰が積み重なって育つ山。山の内部に「熱とガスの通り道」がある点が大きなちがいです。
1-5.火山がくれるもの・気をつけること
温泉・きれいな湧き水・火山性の土・金属の鉱石などの恵みがある一方、噴火による降灰・火砕流・土石流・有毒ガスといった危険もあります。火山は「恵みと注意」をセットで学ぶと理解が深まります。
2.なぜ噴火するの?――圧力とガスのものがたり
2-1.マグマはどこで生まれる?
地球の外がわの地殻(ちかく)の下にはマントルという厚い層があり、そこで熱と圧力の影響で岩石が部分的にとけてマグマができます。とけたマグマはまわりより軽いので上へ上へと動き、途中で集まってマグマだまりを作ります。
2-2.上にのぼる力とガスのはたらき
マグマには水蒸気・二酸化炭素などのガスがふくまれています。地下深くではガスは液体の中にしずんでいますが、浅い所へ上がるほどガスがぶくぶく出やすくなり、風船のようにふくらんで圧力を高めます。
2-3.ねばりけ(粘り)で変わる噴火
マグマのねばりけ(粘り)が強いと、ガスがうまく逃げられず爆発的になりやすいです。ねばりけが弱いと、ガスが抜けやすく、溶岩がゆっくり流れる噴火になります。
| マグマのタイプ | ねばりけ | ガスの量 | おこりやすい噴火 | できやすい地形 |
|---|---|---|---|---|
| 玄武岩質 | 弱い(さらさら) | 少なめ | 溶岩噴火・なめらか流 | 盾状火山・溶岩台地 |
| 安山岩質 | 中くらい | 中くらい | ときに爆発的 | 成層火山 |
| 流紋岩質 | 強い(ねばねば) | 多め | 爆発的噴火・灰多い | 溶岩ドーム・カルデラ |
2-4.噴火は「圧力の出口」
マグマだまりで圧力が地面の強さをこえると、火道を通って一気に外へ。溶岩が流れ出たり、灰や石が空高くふき上がったりします。これが噴火です。前ぶれとして小さな地震・地面のふくらみ・ガスの増加・温度の変化などが観測されます。
2-5.噴火の大きさをくらべるめやす
噴火の大きさは、ふき出した灰や石の量や噴煙(ふんえん)の高さで表されます。数字が大きいほど、広い地域に影響が出やすくなります。
3.噴火のタイプと火山の形――見分け方を学ぼう
3-1.噴火のタイプをくらべる
| タイプ | ようす | 出やすいもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 溶岩噴火 | ゆっくり流れ出る | 溶岩流 | 熱いが動きは比較的おそい |
| 爆発的噴火 | 灰や石を高くふき上げる | 火山灰・火山弾 | 広い範囲に降灰・音と衝撃 |
| 水蒸気噴火 | 水が急に温められ爆発 | 水蒸気・灰 | 溶岩は少ないが爆発が急 |
| 火砕流(かさいりゅう) | 高温の灰・ガス・石の混ざった流れ | 火山灰・石・有毒ガス | もっとも危険。近づかない |
3-2.火山の形のちがい
| 形 | 見た目 | でき方 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 成層火山 | 円すい形で美しい | 溶岩と灰がくり返し積もる | 富士山・浅間山 |
| 盾状火山 | なだらかに広い | さらさら溶岩が遠くへ広がる | マウナロア(ハワイ) |
| 溶岩ドーム | ぼこっと盛り上がる | ねばりの強い溶岩が積み上がる | 昭和新山 など |
| 火砕丘 | 小さな円すい | 灰や小石が積もってできる | スコリア丘 など |
| カルデラ地形 | 巨大なおわん状のくぼみ | 大噴火で地下が空洞化し陥没 | 阿蘇地方 など |
3-3.灰・石・溶岩のちがいを整理
| 名前 | 大きさのめやす | ようす | 観察の注意 |
|---|---|---|---|
| 火山灰 | 目に見えない〜砂ぐらい | さらさらの粉。遠くまで飛ぶ | マスク・ゴーグル必須 |
| 火山砂・火山礫 | 小豆〜こぶしくらい | ザラザラの石。周辺に降る | ヘルメット・屋内退避 |
| 火山弾 | それ以上 | 空に投げられた大きな塊 | 近づかない |
| 溶岩流 | 流れ | 高温の液体が地表を流れる | 早めの避難・近寄らない |
4.火山とくらし――恵みとリスクを両方知ろう
4-1.火山の恵み
温泉・湧き水・豊かな土は火山からのプレゼント。灰にふくまれるミネラルで畑の土が豊かになり、野菜や果物がおいしく育ちます。景勝地や観光、珍しい生き物との出会いも火山地域ならではです。
4-2.火山のリスクと備え
| 危険 | 何が起きる? | 備え・行動 |
|---|---|---|
| 降灰 | 空が暗くなり灰が降る | マスク・ゴーグル・室内へ/車は速度を下げる |
| 火砕流 | 高温の灰とガスが高速で流下 | 近寄らない・早期避難 |
| 溶岩流 | 熱い溶岩が地表を流れる | 避難路を確かめて退避 |
| 土石流(ラハール) | 雨で泥と石が一気に流れる | 川沿い・谷筋から離れる |
| 有毒ガス | 硫黄のにおいなど | 風下を避ける・指示に従う |
4-3.家庭の「もしもノート」
| 項目 | チェック | メモ |
|---|---|---|
| 避難先と道順 | ✔︎ | 学校・公民館・高台 |
| 連絡方法 | ✔︎ | 家族の集合場所・電話が使えない時 |
| 持ち出し袋 | ✔︎ | 水・食料・マスク・ゴーグル・懐中電灯 |
| 家の対策 | ✔︎ | 雨どい清掃・車の燃料・窓の養生 |
4-4.安全に観察・学ぶコツ
出かける前に火山情報と警報・注意報を確認。現地では立入禁止を守り、谷筋・火口周辺に近づかないこと。火山博物館や学習施設を活用し、観察ノートに雲・におい・音・温度・地形・植物の変化などを記録しましょう。
5.地球規模で見る火山――プレートと世界の火山
5-1.プレート境界の火山
地球表面はプレートという大きな岩の板でできています。ぶつかる所(沈み込み帯)や、はなれる所(海嶺や大地の割れ目)ではマグマが生まれやすく、火山が並びます。日本が火山国なのは、いくつものプレートが出会う場所だからです。
5-2.ホットスポットの火山
プレートのまん中でも、地下深くから熱の柱がのぼる場所では火山ができます。ハワイの火山はこのタイプで、プレートが動くにつれて火山列がならび、古い島から新しい島へと並び方が変わります。
5-3.世界と日本の火山地帯
太平洋をとりまく火山帯、インドネシア、イタリア、アメリカ西部、南米アンデスなど、世界各地に火山が分布。日本では北海道〜九州・沖縄まで活火山が点在し、地域ごとに形や噴火のしかたがちがいます。
前ぶれチェック&行動の早見表
| 前ぶれ | 見え方・感じ方 | 行動のめやす |
|---|---|---|
| 小さな地震が増える | 浅い場所での揺れ | 最新情報を確認・備えを点検 |
| 地面がふくらむ | 測量や衛星で検知 | 立入規制を守る |
| 火山ガスの増加 | におい・測定値が上がる | 谷筋や風下を避ける |
| 温泉の変化 | 色・温度・量が変わる | 近づかない・管理者に連絡 |
| 噴煙の変化 | 色や高さが変わる | 写真で記録・規制情報を確認 |
自由研究アイデア(安全第一でおうち学習)
- 紙ねんど火山モデル:中央にストローで火道を作り、重曹+酢で安全な“噴火”実験。泡の量や色水で記録。
- 火山灰の観察(入手できる標本で):拡大鏡で粒の形を比べ、重さや沈み方を調べる。水に入れて沈む速さも計測。
- 火山地形しらべ:地図アプリや地形図でカルデラ・溶岩台地を探し、写真やスケッチでまとめる。
- 灰の片づけ実験:灰に見立てた粉を使い、ほうき・水・掃除機のどれが効率的かを比べ、最適な手順表を作る。
- 温泉の色と成分しらべ:案内板の表示から色と成分を写し取り、なぜ色が違うかをまとめる。
Q&A――火山のギモンに答えます
Q1:溶岩はなぜ赤いの?
A:とても高温なので光を出して見えます。冷えると黒や灰色の岩になります。
Q2:噴火はいつ起きるか当てられる?
A:前ぶれを観測して予測しますが、正確な時刻まで当てるのはむずかしいことがあります。
Q3:火山灰は触ってもいい?
A:粒がとがっていて目や肺に良くないので、素手や素顔でさわらず、マスクや手袋を使いましょう。
Q4:溶岩流は走ってにげられる?
A:場所によって速さがちがいます。立入禁止を守り、早めの避難が大切です。
Q5:火山は海の中にもある?
A:はい。海底にもたくさんあり、海底火山の活動で新しい島が生まれることもあります。
Q6:温泉の色がちがうのはなぜ?
A:ふくまれる成分がちがうからです。鉄で赤、硫黄で白や乳青色になることがあります。
Q7:富士山は今も活火山?
A:はい。過去に噴火していて、今後も活動の可能性がある火山です。
Q8:噴火は地震を起こす?
A:火山の下で小さな地震が増えることはありますが、大地震と直接の関係は場所によりちがいます。
Q9:黒曜石(こくようせき)や軽石はどうできる?
A:黒曜石はねばりの強い溶岩が急に冷えてガラスのようになった岩。軽石は気泡を多くふくんで軽くなった岩です。
Q10:溶岩の表面がなめらかだったりゴツゴツなのは?
A:流れる速さや温度、成分で変わります。速くて温度が高いとなめらか、冷えてゆっくりだとゴツゴツしやすいです。
Q11:火山の近くで野菜がおいしいのはなぜ?
A:灰や溶岩がこわれてできた土はミネラルがゆたかで、水はけ・水もちのバランスがよいからです。
Q12:灰が降ったら学校や家ではどうする?
A:窓や戸をしめ、エアコンの外気取り込みを止めます。外ではマスク・ゴーグルを使い、車は低速で走ります。
用語ミニ辞典(やさしい言いかえ付き)
| ことば | 意味 | やさしい言いかえ |
|---|---|---|
| マグマ | どろどろにとけた岩石 | 熱い岩のスープ |
| 溶岩 | 地表に出たマグマ | 外へ出た熱い流れ |
| 火道 | マグマが通る道 | 地下のトンネル |
| 火口 | 噴火が出る穴 | 山の出口 |
| 火山灰 | とても細かい灰 | 粉のような石 |
| 火山礫(れき) | 豆〜こぶし大の粒 | ざらざらの石 |
| 火砕流 | 高温の灰とガスの流れ | 灼熱のつむじ風 |
| 火山弾 | 空にほうり出された岩のかたまり | 飛んでくる石 |
| カルデラ | 大噴火でできた大きなくぼみ | 巨大なおわん地形 |
| プレート | 地球表面をおおう岩の板 | 大地の板 |
| マントル | 地殻の下の厚い層 | 地球の内側の厚い部分 |
| 噴煙 | 火口から上がる煙の柱 | 空へ伸びる煙 |
| ラハール | 灰と水がまざった土石流 | 泥の急流 |
まとめ――知れば安心、火山は学びの宝庫
火山は、地球の中の力が形になったもの。 マグマが生まれ、たまり、圧力とガスで噴火が起きます。マグマのねばりけやガスの量で、噴火のようすや火山の形が変わります。恵み(温泉・豊かな土・景観)とリスク(降灰・火砕流・土石流)を両方学び、最新情報を確認・早めの行動を心がけましょう。
観察ノートや安全な実験で学びを深めれば、ニュースや現地の景色がぐっと理解しやすくなります。火山を知ることは、地球のしくみと命のつながりを学ぶ近道です。