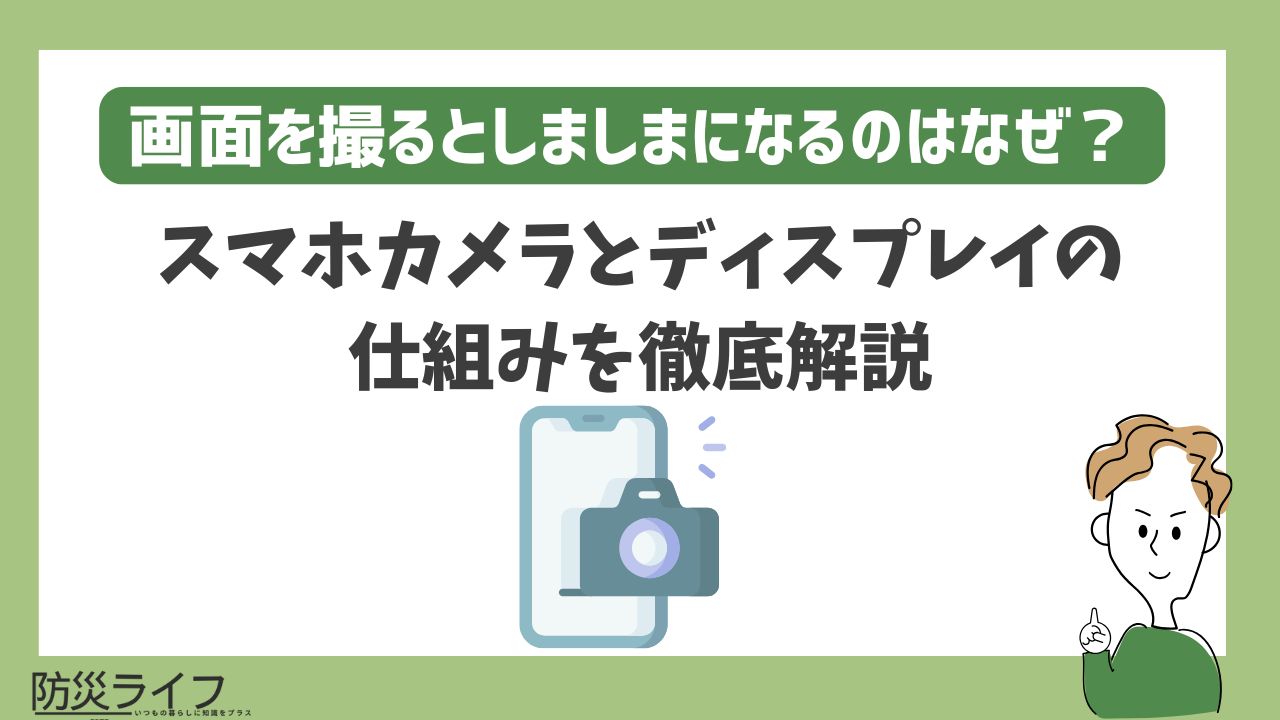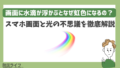テレビ、パソコン、他のスマホ画面を撮ったときに写り込むしましま模様(縞)やチラつき。目で見ると滑らかなのに、カメラ越しでは帯が流れたり、横線が走ったりして「思った通りに撮れない」。この原因は、ディスプレイが高速に明るさを切り替えるのに対し、カメラが一定の間隔で光を切り取るという、時間のズレにあります。本記事はその正体を**“フリッカー(点滅)”**としてとらえ、
- なぜ縞が生まれるのか(仕組み)
- 画面の方式ごとに何が違うのか(出やすさ)
- カメラ側の設定はどう合わせるか(同期)
- 現場で効く具体策とチェックリスト
- うまくいかなかった時の後処理(編集での軽減)
まで、実践的に解説します。まずは「なぜ」を理解し、次に「どう合わせるか」を順番に押さえれば、今日から縞のない画面撮影に近づけます。
1.しま模様の正体—なぜ起きる?
1-1.原因は“フリッカー”と“時間の食い違い”
縞の正体は、ディスプレイがとても速い周期で明暗を繰り返す(フリッカー)一方、カメラは一定の時間幅で光を積み上げるため、点灯していない瞬間を拾ってしまうことにあります。人の目は残像のはたらきで連続光に感じますが、カメラはフレームごとに別々に記録するため、点滅の谷が暗い帯として写ります。
1-2.ディスプレイは“常時点灯”ではない
- 液晶(LCD)は、画面裏のバックライトを高速に「点けたり消したり」して明るさを作ります。
- **有機EL(OLED)**は、各画素そのものを高速にオン・オフして明るさを作ります。
どちらも省電力や低輝度表示のときほど消灯時間(オフの割合)が長くなり、フリッカーが目立ちやすくなります。
1-3.“周波数”と“シャッター”のズレが縞になる
ディスプレイはリフレッシュレート(例:60Hz、120Hz…)で表示を更新し、照明や電源は地域で異なる50Hz/60Hzで明滅します。カメラはフレームレート(例:30fps/60fps)とシャッタースピード(例:1/60秒)で光を切り取ります。これらが整数倍の関係にないと、波どうしがぶつかって**“干渉(ビート)”**が生まれ、帯となって見えます。
1-4.照明のフリッカーも“加害者”になる
室内の蛍光灯や一部LEDは、電源周波数の影響で明るさが微妙に揺れます。被写体の画面に加えて、照明のフリッカーも同時に写り込むと、縞が増幅されることがあります。屋外の日光はフリッカーがほぼ無く、有利です。
1-5.“モアレ”との違いを知る
縞の見た目でも、**モアレ(格子の干渉)とフリッカー(時間の干渉)**は別物です。
- モアレ:カメラの画素格子とディスプレイのサブピクセル配列が空間的に干渉して起きる細かな斑模様。対策は距離・角度・ズームで解像関係をズラす。
- フリッカー:点滅と露光の時間的なズレで生じる横帯。対策はシャッター・フレームレートの同期。
両方が同時に現れることもあり、対策は**空間(距離・角度)と時間(露光)**の両輪で行います。
1-6.“出にくい条件”を見極める
- 被写体の画面輝度が高い(オフ時間が短い)
- 日光下やフリッカーの少ない照明
- カメラのシャッターが周波数に一致(1/50・1/60・1/100・1/120秒など)
この3点がそろうと、縞は目立ちにくくなります。
2.ディスプレイ方式ごとの“出やすさ”
2-1.液晶(LCD):PWM調光で縞が出やすい
液晶はバックライトの明るさをPWM(パルス幅変調)で作ります。暗くするほど消灯時間の割合が増え、フリッカーが強く出ます。最近はローカル調光(部分ごとに光らせる)やスキャン型バックライト(列ごとに順番に点灯)も増え、周波数が複雑になることがあります。
2-2.有機EL(OLED):画素のオン・オフが高速
有機ELは各画素が自発光します。機種や設定によっては低周波のPWMを使うことがあり、低輝度表示で帯が出やすい傾向があります。一方で近年は**直流調光(DC調光)**や疑似DC制御に対応し、低輝度でも縞が出にくい機種も増えています。
2-3.高リフレッシュ(90/120/144/240Hz)との関係
リフレッシュレート(画面の更新回数)とPWM周波数(明るさ制御の点滅)は別物です。120Hz表示でも、PWMが低周波ならしま模様は残ります。対策はシャッターをPWMや電源周波数の整数倍に寄せることです。
2-4.CRT/電子ペーパー/屋外サイネージ
- CRT:電子ビームで走査するため、動画では走査線が帯として現れやすい。1/50〜1/60秒付近で緩和。
- 電子ペーパー:表示保持型で点滅がほぼ無く、縞は出にくい。
- 屋外サイネージ:LEDを列・行で時分割しており、読み出し順との組み合わせで帯が出やすい。角度・距離・シャッターの総合調整が必要。
ワンポイント:“PWM周波数”と“電源周波数(50/60Hz)”は別。どちらにも配慮しつつ、まずは電源周波数に整えると失敗が少なくなります。
3.カメラ側の要因—設定が縞を生む/消す
3-1.シャッタースピード:まず“分母”から合わせる
周波数に同期する分母に固定します。
- 50Hz圏:1/50秒、1/100秒(25/50fpsに相性良)
- 60Hz圏:1/60秒、1/120秒(30/60fpsに相性良)
高リフレッシュ(120Hz)画面は1/120秒が第一候補。合わないときは1/60秒も試し、縞が最小の値に固定します。
3-2.フレームレートと“シャッター角”の考え方
映画の慣習(180度ルール)では、30fpsなら1/60秒が自然な動きですが、縞対策では周波数との同期が優先。25/50fps&1/50秒(50Hz圏)、30/60fps&1/60秒(60Hz圏)が基本です。
3-3.ローリングシャッターの読み出し時間
スマホや多くのミラーレスはローリングシャッターで、センサーを上から順に読み取ります。読み出しが遅いほど、画面の上と下で点滅のタイミングがズレ、帯が強く出ます。可能ならアンチフリッカー機能やメカシャッター、高速読み出しモードを選びます。
3-4.オート露出の落とし穴
自動制御は状況により速いシャッターを選びがちです。M(マニュアル)またはS(シャッター優先)で分母を固定し、明るさはISOと絞りで追い込みます。スマホはプロ(マニュアル)モードや専用アプリを使うと確実です。
3-5.色温度・露出固定で“明るさ揺れ”を防ぐ
画面側が自動で明るさや色を変えると、カメラのオートが反応して明るさ揺れや色のちらつきが発生。被写体の自動明るさ/色適応はオフ、カメラ側も露出・ホワイトバランス固定が安全です。
4.現場で効く対処法—設定・運用・編集まで
4-1.撮影前チェックリスト(準備編)
- 被写体の画面設定:輝度高め/自動明るさオフ/省電力オフ/リフレッシュ固定(60 or 120Hz)。
- 照明:日光が理想。室内はフリッカーの少ない照明に切り替え。不要な点灯はオフ。
- カメラ設定:シャッターを1/50・1/60・1/100・1/120sで試し、最も縞が少ない値に固定。動画はフレームレートも合わせる。
- ホワイトバランス・露出:固定。AF補助の点滅はオフ。
- 位置取り:画面に対してわずかに斜め、距離は少し離れて中望遠で。
4-2.その場でできる“即効テク”
- 輝度を上げる:オフ時間が短くなり、帯が薄くなる。
- 角度を2〜10度だけ振る:走査方向と読み出し方向の重なりを崩す。
- 距離を取りズーム:サブピクセルの格子干渉(モアレ)も同時に緩和。
- 偏光フィルター(PL):反射対策に有効(ただし光量低下に注意)。
4-3.シーン別おすすめ設定(実践表)
4-4.“そもそも撮り方を変える”代替策
- 画面録画(内部収録):スマホやPCの録画機能を利用(著作権や機密に注意)。
- キャプチャ機器:PCやゲーム機はHDMIキャプチャで直接取り込み。
- 資料用は静止画に:動きを止めて長めの露光で撮ると帯が目立ちにくい。
4-5.編集での軽減(あとからの処置)
- 動画編集ソフトの“フリッカー低減”:専用フィルタで縞の明暗を平均化。
- 時間方向のぼかし:数フレームを重ねる時間的ななだらかしで帯を薄める。
- 明滅の色だけを抑える:色相・輝度キーで帯の成分を狙って減らす(効きすぎ注意)。
- 静止画は多枚数合成:短時間に複数枚撮り、明るい画素を優先合成して帯を打ち消す。
後処理は“応急”です。現場での同期合わせがいちばん効きます。
5.トラブル別チェックリスト/Q&A/用語辞典
5-1.トラブル別チェックリスト(詳細版)
- 縞が強い:シャッターを1/50⇄1/60⇄1/100⇄1/120sで順に試す/被写体の輝度アップ/リフレッシュ固定。
- 画面の一部だけ縞:ローリングシャッター影響。角度を数度振る/読み出しの短いモードに切替。
- 縞が流れて動く:フレームレート不整合。**25/50fps(50Hz)/30/60fps(60Hz)**に変更。
- 明るさが勝手に揺れる:被写体の自動明るさOFF、カメラは露出固定。
- 色がちらつく:ホワイトバランス固定。照明の混在を避ける。
- モアレと縞が混在:距離を取り中望遠に/角度をわずかに振る/シャッターも再調整。
5-2.よくある質問(Q&A)
Q:縞は故障ですか?
A:いいえ。正常な点滅動作と露光のズレで起きます。設定で軽減できます。
Q:最初に触るべき設定は?
A:シャッタースピードです。50Hz圏は1/50 or 1/100、60Hz圏は1/60 or 1/120が基準。
Q:写真と動画、対策は違いますか?
A:動画はフレームレートも同期が必要。25/50fps(50Hz)や30/60fps(60Hz)に合わせます。
Q:どうしても消えないときは?
A:角度・距離・ズームを微調整し、被写体の輝度最大/省電力OFF/リフレッシュ固定を併用。照明も見直します。
Q:屋外の電光掲示板は難しい…
A:行列スキャンのため難度高。1/100〜1/250sで試し、距離を取り中望遠で。角度も少し振ります。
Q:編集で直せますか?
A:完全除去は難しいですが、フリッカー低減や時間方向ぼかしで目立ちにくくできます。
Q:モアレとの見分け方は?
A:モアレは細かな斑点・波模様で画面を拡大・縮小すると変化。フリッカーは横帯が流れるのが特徴。対策も異なります。
5-3.用語の小辞典(やさしい言い換え)
フリッカー:高速の明滅。縞の主因。
PWM(パルス幅変調):点灯時間の割合(パルスの幅)を変えて明るさを作る方式。
リフレッシュレート:画面の書き換え回数(Hz)。
ローリングシャッター:センサーを順番に読み出す方式。明滅や高速動体に弱い。
アンチフリッカー:周波数に合わせて露光を調整し、縞を抑える機能。
直流調光(DC調光):点滅を使わずに電流値を調整して明るさを変える方式。
モアレ:格子パターンが重なって生じる斑模様(空間の干渉)。
まとめ
縞は、ディスプレイの点滅とカメラの露光の時間関係が噛み合わないために生じる、きわめて一般的な現象です。まずは周波数に合ったシャッター(1/50・1/60・1/100・1/120s)とフレームレートを合わせ、被写体側の輝度アップ/リフレッシュ固定、アンチフリッカー、角度・距離の最適化を重ねていきましょう。
編集でのフリッカー低減は最後の手段。仕組みを理解して正しく合わせれば、実務でも通用するクリーンな画面撮影が十分に実現できます。今日からチェックリストを使い、あなたの**“縞ゼロ”レシピ**を育ててください。