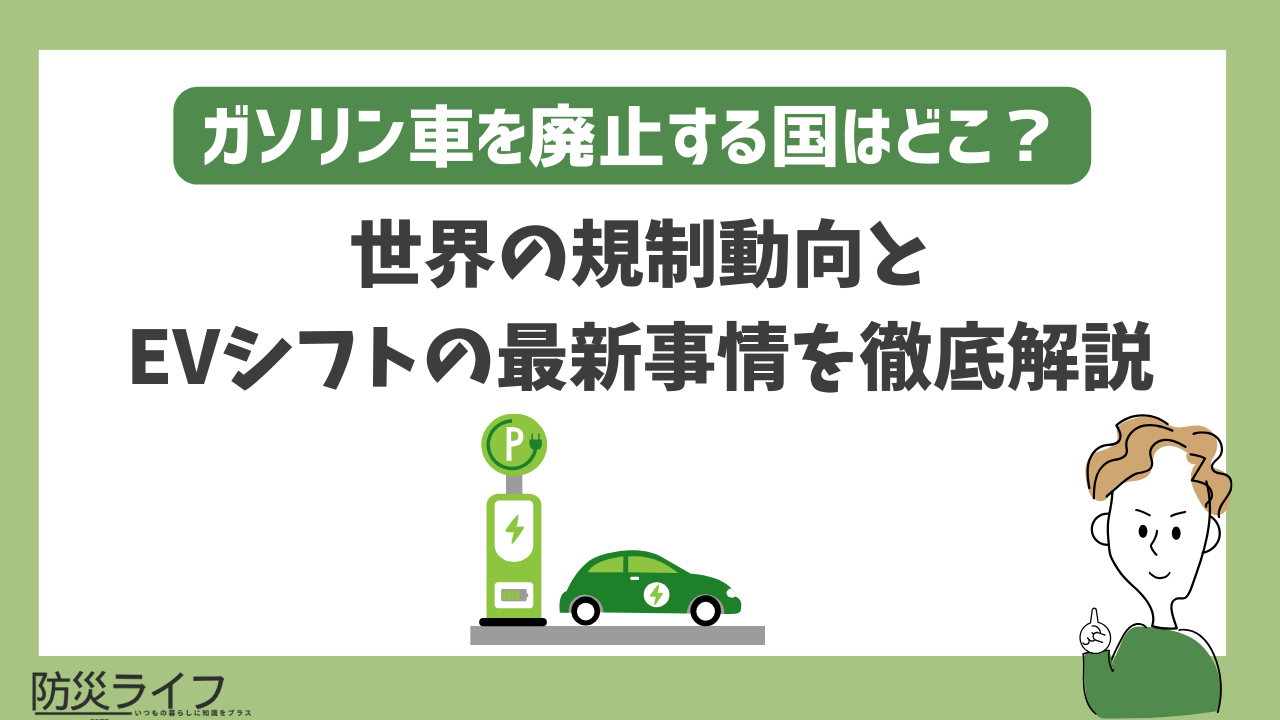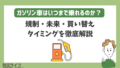地球温暖化への対応、都市の空気の改善、産業競争力の刷新という三つの課題を背景に、各国が「いつ内燃機関車の新車販売を終えるか」を明確化しています。節目は2030〜2035年で、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)・燃料電池(FCV)などの電動車への移行が現実味を帯びました。本稿は、国・地域別の具体策と年限、移行の実務、購入や事業の判断軸まで、今日の意思決定に直結する形で整理します。
1. 世界の「ガソリン車廃止」—定義と最新の全体像
1-1. 何が「廃止」の対象になるのか
多くの国・地域で対象は新車の販売です。既存車の使用や中古車の売買は直ちに制限されないのが一般的で、主に対象となるのは乗用車と小型商用車です。大型車やバスは別枠で段階移行が定められ、都市部の走行規制は販売規制よりも先に強まる傾向があります。
1-2. 2030〜2035年が節目になった理由
電池の量産と価格低下、航続距離の伸長、充電網の拡充に加え、産業政策としての国際競争が要因です。欧州は2035年の実質ゼロ排出を旗印に、英国は年次の販売比率目標で市場を慣らし、北米は州・州の先行で実質標準を作っています。中国は2035年の電動車中心化で巨大市場をけん引しています。
1-3. 例外と周辺規制の広がり
一部では合成燃料(再エネ由来の水素とCO₂から作る燃料)対応の限定的な例外が検討・整備されています。また、多くの都市で低排出・無排出ゾーンが広がっており、街中の入域規制が先に厳しくなる現実も見逃せません。
2. 欧州・英国・北欧の動き(年限・中間目標・都市規制)
2-1. 欧州連合(EU):2035年に新車は実質ゼロ排出へ
EUは2035年以降の新車を実質ゼロ排出とする共通ルールを採択しました。途中の見直し機会は設けつつも、最終目標は堅持の姿勢です。各国はこれに合わせて充電網の整備、電池産業の育成、都市の走行規制を一体で進めています。
2-2. 英国:2035年に全面到達、年次比率で市場をならす
英国は2035年に新車100%をゼロ排出へ。移行期はZEV販売比率の年次目標を段階的に引き上げます。建物側では新築等に充電設備を備える建築規定が導入され、住まいと車の同時転換が進みます。
2-3. ノルウェー・オランダ:先行事例が示す成功の条件
ノルウェーは新車に占める電気の割合が世界最高水準で、「2025年に内燃車の新車販売ゼロ」を政策目標として掲げ、市場は事実上の達成段階に入っています。オランダは2030年に新車は排出ゼロのみとし、中心部では無排出ゾーンが拡大しています。成功の条件は、価格・充電・体験価値の同時前進です。
欧州・英国・北欧の比較(乗用・小型商用の新車販売を中心に要約)
| 国・地域 | 新車の基本方針 | 節目の年 | ハイブリッド扱い | 現状の補足 |
|---|---|---|---|---|
| EU(加盟各国) | 2035年以降は実質ゼロ排出のみ | 2035年 | 原則対象外(合成燃料に限定例外の整理) | 都市の走行規制が並行拡大 |
| 英国 | 年次比率で段階移行し2035年に100% | 2035年 | 移行期に限定的な許容 | 新築等への充電設備義務 |
| ノルウェー | 政策目標は2025年に内燃新車ゼロ | 2025年(目標) | 実需はEV中心 | 税制・通行優遇が充実 |
| オランダ | 2030年は新車ゼロ排出のみ | 2030年 | 原則対象外 | 中心部で無排出ゾーン拡大 |
| ドイツ/フランス | EU方針に準拠(2035年) | 2035年 | 限定例外の議論あり | 電池・半導体の産業支援 |
3. 北米の動き(米国の州規制とカナダの全国ルール)
3-1. 米国:カリフォルニアを起点に州採用が拡大
米国は連邦一本の販売禁止ではなく、州ごとの先行が実態です。カリフォルニアは2035年に新車をゼロ排出車と一部PHEVに限定し、ニューヨークやワシントンなどが追随。採用州が増えるほど、メーカーの全国展開で実質的な標準になります。
3-2. 東海岸の主要州:都市改善と産業誘致が後押し
ニューヨークなどは2035年ゼロ排出へ向けて制度を整備中です。都市の空気の改善と新産業の誘致という二つの狙いが、州議会での合意形成を後押ししています。
3-3. カナダ:全国ルールで2035年に到達
カナダは2035年に新車100%をゼロ排出とする連邦ルールを掲げ、2026年・2030年の中間目標を設けました。全国で購入支援や充電網の整備が計画的に進んでいます。
北米の要点は、規制が「州と州」「州と連邦」の二層で進むことです。事業者は拠点のある州の規則を起点に、最も早い州・都市に合わせて前倒しの車両更新を設計すると混乱が少なくなります。
4. アジア太平洋の動き(中国・インド・日本・韓国ほか)
4-1. 中国:2035年に電動車が主流となる青写真と都市規制
中国は2035年に新車の大部分を電動車とする国家計画を示し、ナンバー発給や購入優遇で移行を加速。電池や資源確保まで含めた産業一体型の推進が特徴で、世界の価格形成にも影響します。
4-2. インド:2030年に新車の3割を電動化、用途別の先行
インドは2030年に新車のおよそ30%を電動にする目標を掲げ、二輪・三輪・バスなど用途別の先行が進みます。広い国土と多様な所得層を踏まえ、小型商用の電動化が勢いを増しています。
4-3. 日本:2035年に新車100%電動化(HV含む)と自治体の前倒し策
日本は2035年に新車のすべてを電動車とする目標を掲げ、EV/PHEV/FCVに加えハイブリッドも電動車に含めます。東京都などは新築等での充電設備整備を前倒しし、集合住宅向けの支援も拡大。国内メーカーは量産・電池連携・リサイクルまで視野に入れています。
アジア太平洋の比較(要点の俯瞰)
| 国・地域 | 新車の基本方針 | 節目の年 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 2035年に電動車が主流 | 2035年 | 都市の登録制限や購入優遇、電池産業の強み |
| インド | 新車の約3割を電動化 | 2030年 | 二輪・三輪・バスの先行、商用の電動化が加速 |
| 日本 | 新車100%電動化(HV含む) | 2035年 | 自治体の前倒し策、V2Hなど家庭連携の拡大 |
| 韓国 | 2035年前後の段階移行を検討 | 2035年目安 | 大手メーカーのEV拡充、都市の低排出ゾーン |
5. いつ・どう備えるか(個人・企業・インフラの実務とQ&A/用語)
5-1. 個人:買い替えの適期と費用の見方
次の一台が最後の内燃になる可能性を見込み、売却時期の相場下落リスクを織り込みます。通勤・買い物中心なら自宅や職場の普通充電で十分に実用です。長距離が多い人は、冬場の実走距離と急速充電の配置を確認し、電費(1kWhで走る距離)と時間帯別の電気料金まで含めて比較すると安心です。PHEVは日常は電気、遠出はエンジンの安心感が強みですが、家庭での充電環境を前提に選ぶと真価を発揮します。
5-2. 企業:保有車と物流の更新設計
社用車はリース満了年を並べ、規制が最も厳しい拠点の州・都市に合わせて3〜5年前倒しで計画。小型配送や定常ルートから先に電動化し、拠点内に普通充電を整備して夜間に戻し充電します。残価・電池保証・税制優遇を含めた総費用(TCO)で比較すると投資判断がぶれません。
5-3. インフラ:自宅・職場・集合住宅での整備
戸建ては200V屋外コンセントからでも実用十分です。分譲・賃貸の集合住宅は、幹線となる基礎配線を先に整えると将来の台数増に対応しやすくなります。職場は来客用数基+従業員用の常設から始め、運用データを見て増設。課金は駐車管理と一体で運営するとトラブルを抑えられます。
移行時の主な課題と現実的な対策
| 課題 | 起きやすい事象 | 実務的な備え |
|---|---|---|
| 初期費用 | 車両価格・充電設置のまとまった出費 | 補助の活用とTCO比較、リースやサブスクで平準化 |
| 冬場の航続 | 実走距離の短縮 | 余裕ある容量選択、出発前のプレコンで軽減、経路上の充電把握 |
| 集合住宅 | 配線や決済で合意形成が難しい | 基礎配線方式で段階増設、管理規約とセット運用 |
| 繁忙期の長距離 | 急速充電の待ち時間 | 100%出発・80%止めの回転、候補充電器の事前把握 |
5-4. よくある質問(Q&A)
Q. 「廃止」といっても、今の車にすぐ乗れなくなるのですか?
多くの国では新車販売の限定であり、既存車の使用は継続可能です。ただし都市中心部の走行規制が先に強まるため、日常の行き先に合わせて余裕をもった予定を組むのが安心です。
Q. どの国が最も早いのですか?
ノルウェーは2025年目標を掲げ、市場はすでに電気が主流です。オランダは2030年、EUは2035年が節目です。英国は年次比率目標で2035年到達を設計しています。
Q. 日本ではハイブリッドはどう扱われますか?
日本の2035年新車100%電動化は、EV・PHEV・FCVに加えてハイブリッドも含む考え方です。購入時は走行距離・充電環境・燃料費などを総合して判断します。
Q. 企業はどこから切り替えるべきでしょうか?
台数が多く稼働が安定した定常ルートから。夜間の拠点充電で稼働率を確保し、データに基づいて台数の最適化や人員配置を見直すと、効果が見えやすくなります。
5-5. 用語の小辞典(やさしい言い換え)
電動車:EV(電気)、PHEV(外部充電できるハイブリッド)、FCV(水素)、HV(回生付きのハイブリッド)。
ゼロ排出車:走行時に排出がない車(EVやFCVなど)。
合成燃料:再生可能エネルギー由来の水素とCO₂から合成する燃料。
普通充電/急速充電:自宅や職場などの比較的ゆっくりの充電/道路沿いなどで短時間に行う充電。
総費用(TCO):購入・電気代・保守・税金・残価を合算した費用。
まとめとして、世界の基調は「2030〜2035年に新車を電動へ」という一点に収れんしています。国や都市で定義や例外が異なるため、自分が使う街と州・国の実ルールを基準に、前倒しで準備するのが最小コストの近道です。個人は生活動線に合う充電を、企業は用途別・拠点別の段階導入を設計し、政策・補助・税制を総費用で見比べながら進めましょう。