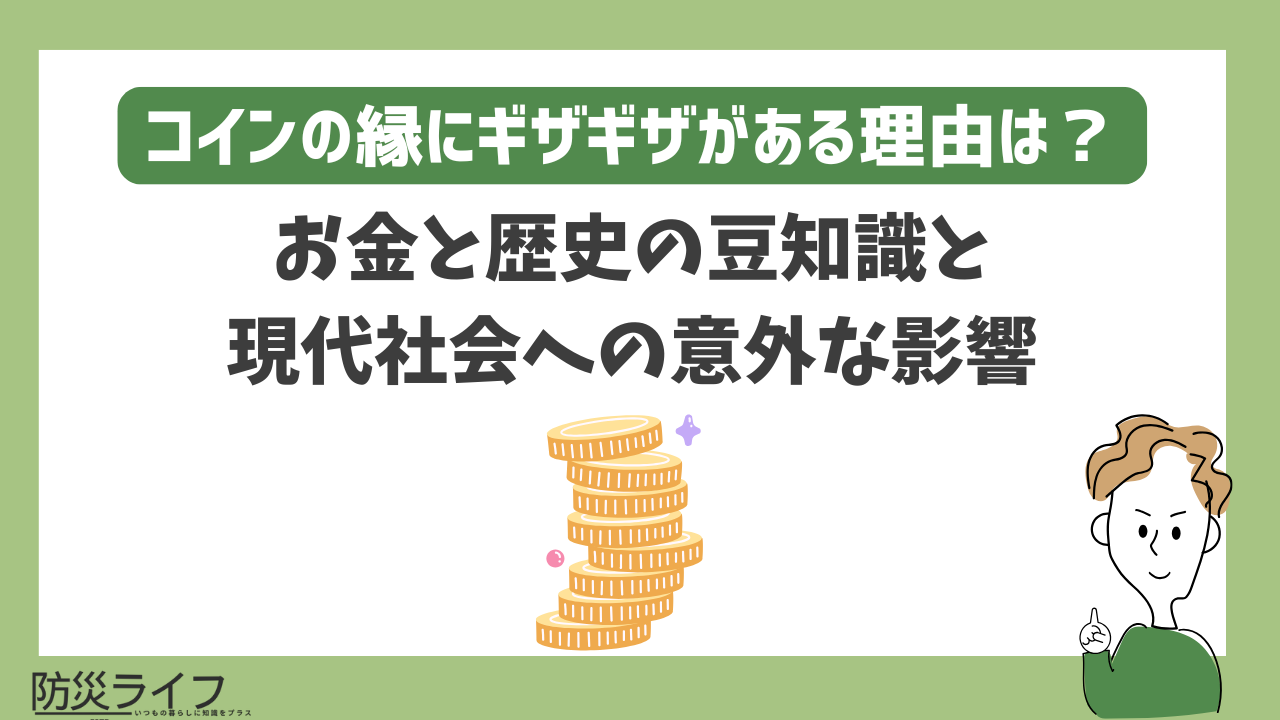財布の中にある100円玉や500円玉、海外旅行で手にするクォーターやユーロ硬貨。よく見ると、多くのコインの**縁(エッジ)**には細かな“ギザギザ(ミリング/リーデッドエッジ)”が刻まれています。なぜ、わざわざ縁に刻みを入れるのか?——その答えは、歴史・防犯・ユニバーサルデザイン・機械識別・意匠性が折り重なった総合設計にあります。
本記事では、ギザギザの誕生から最新の偽造防止技術、製造工程のしくみ、世界比較、キャッシュレス時代の役割までを、図解的に一気通貫で解説します。読み終える頃には、コインの縁の“溝ひとつ”に宿る知恵と技術が、はっきり見えてくるはずです。
1. ギザギザの起源——「縁を削る不正」を見破るために生まれた仕掛け
1-1. クリッピング(削り取り)という歴史的問題
近世ヨーロッパでは、金貨・銀貨=素材そのものが価値というコインが広く流通していました。そこで横行したのが、縁を少しずつ削って貴金属を“チリ積も”で盗み取るクリッピング。見た目には同じ額面のまま、実質的な価値だけが目減りするため、市場の信頼を大きく損ねました。
1-2. ミリング(縁刻み)の発明と普及
対策として考案されたのが、縁に細密な刻みを入れる方法。ほんの少しでも削られればパターンが崩れて即判明します。やがてこの仕組みはヨーロッパ各国で標準化し、ミリング(reeding)として定着。硬貨の真贋・価値保全の可視化に成功しました。
1-3. 日本への導入と変遷
明治期、日本の近代貨幣制度は欧州の造幣技術を取り入れました。以後、高額硬貨を中心にギザギザが採用され、現在の500円・100円などに継承。時代に応じて形状・本数・角度・刻字が最適化され、偽造防止力と使い勝手の両立を図っています。
時間軸でざっくり
古代〜中世:素材価値のコインが主流
17〜18世紀:クリッピング対策としてミリングが普及
19世紀:産業化とともに精密造幣が進展
20〜21世紀:多重偽造防止(微細文字・多層材・潜像・特殊ギザ)へ
2. ギザギザの主要機能——防犯・識別・デザインを“ひとつの縁”に集約
2-1. 偽造や削り取りを見破る「視覚の物差し」
ギザギザはオリジナルの縁の姿を記録する“物差し”。削れば必ず乱れ、誰の目にも異常が分かります。さらに精密な規則性は再現の難易度が高く、偽造のハードルになります。自販機・券売機・両替機などは縁の周期や角度、微妙なクセまで読み取り、真贋判定に活用します。
2-2. ユニバーサルデザイン——触ってわかる安心
ギザの有無・深さ・角度・段差、そして穴・直径・厚み・重さの違いを組み合わせることで、目に頼らず識別しやすくなります。子どもや高齢者、視覚に障がいのある方にもやさしい、触知性重視の設計です。
2-3. 光の反射で“縁が語る”——意匠性と存在感
刻みは光を多方向に反射し、コインの品位・存在感を高めます。縁の刻み×表裏図柄×地金の色調の調和は、その国の価値観や時代性を映し出す小さな工芸。縁文字(エッジレターリング)や波型・斜めギザなど、造形は年々多彩になっています。
3. 製造のしくみ——ギザギザは“叩く瞬間”に生まれる
3-1. 造幣の基本工程
- 圧延・打抜き:金属帯を所定の厚みに圧延し、円形の**ブランク(素片)**を打ち抜く。
- 焼鈍・洗浄:硬さを整え、酸洗いで表面を清浄化。
- アップセット(縁起こし):縁を立てて直径精度と積み重ね性を確保。
- 本打ち(プレス):**上下の金型(ダイ)と外周のカラー(襟金)**で一撃。カラー内面の溝がギザを転写する。
- 検査・選別:寸法・質量・外観・ギザの連続性を多段階でチェック。
3-2. なぜ“斜めギザ”が作れるの?
一般的なギザはカラーの縦溝で直立の刻みになります。斜めギザは、カラーに螺旋状(ヘリカル)の溝を設けるなどして転写。これにより模倣難易度が跳ね上がり、機械識別の判定軸も増やせます。
3-3. 多層材・異種金属の活用
多層クラッド(例:外層と内層の材質を変える)やバイメタル構造は、電磁特性・質量・色調・切断面の複数要素で真贋判定を強化。縁のギザとの多重防衛が、最新硬貨のスタンダードです。
品質保証の要点
・ギザの本数・ピッチ・深さのばらつき管理
・縁文字の欠け/重なりの検査
・重量・直径・厚みの統計管理
・表面硬度・耐摩耗の材料評価
4. 世界と日本の“縁”の比較——仕様・技術・デザインの最前線
4-1. 日本の主要硬貨(現行)の縁の特徴
- 500円硬貨:斜めギザ・多層材・微細文字/潜像など多重防止。高額ゆえ最新技術を集中。
- 100円硬貨:均一ギザ(例:一周で約118本とされる仕様)。流通量が多く、自販機との相性に優れる。
- 50円硬貨:中央に穴+細かなギザで触知性を確保。サイズ・穴・縁の組合せで誤認を減らす。
- 10円硬貨/1円硬貨:いずれも現行は平滑(ギザなし)。10円は過去に“ギザ十”期があり収集人気。
※年号・改定で細部が異なる場合があります。実流通コインで観察してみましょう。
4-2. 海外硬貨の多様なエッジデザイン
- 米国クォーター:細かな連続ギザ(例:一周で約119本とされる)。
- ユーロ圏:額面ごとにギザ/波型/段差/縁文字を使い分け、多言語・多国流通でも識別容易。
- 英国:伝統的なリーデッドエッジや縁文字を活用。多角形硬貨やバイメタルも普及。
4-3. 比較表①:縁の仕様と狙い
| コイン | ギザ形状 | 代表的特徴 | 主な狙い |
|---|---|---|---|
| 日本500円 | 斜めギザ+多層 | 微細文字・潜像と併用 | 高額の偽造耐性・機械識別 |
| 日本100円 | 均一ギザ | 大流通・自販機親和 | 誤判定抑制・触知性 |
| 日本50円 | 穴+細ギザ | 触って区別しやすい | バリアフリー |
| 日本10円 | 平滑(現行) | 過去にギザ期 | 意匠の変遷・収集性 |
| 米クォーター | 連続ギザ | 全国統一規格 | 機械識別・耐摩耗 |
| ユーロ硬貨 | 種別で差別化 | 波型・段差・文字 | 国際流通での識別 |
4-4. 比較表②:触知性・見分けやすさの工夫
| 識別手段 | 仕組み | 例 |
|---|---|---|
| ギザのパターン | 本数・深さ・角度で差をつける | 100円の均一ギザ/500円の斜めギザ |
| 穴 | 触るだけで一意に分かる | 50円(丸穴)/5円(丸穴・平滑) |
| 寸法 | 直径・厚み・質量の違い | 1円<5円<10円<50円<100円<500円 |
| 材質 | 磁性・電磁特性の差 | 多層クラッド・バイメタル |
5. 自販機は“縁”の何を見ている?——機械識別の裏側
5-1. センサーの多重判定
自販機・券売機は直径・厚み・重量に加え、電磁応答(渦電流)や磁性を測定。さらに縁の周期・ピッチを光学/機械的に読み取り、複数の合否判定を合算して一瞬で可否を決めます。
5-2. なぜギザが有利なのか
平滑縁よりも特徴量が豊富で、摩耗でも特徴が残りやすいため、長期流通に向きます。斜めギザや縁文字は模倣が難しく、多重チェックの強力な柱になります。
5-3. 運用面のメリット
ギザは滑り止め効果があり、硬貨搬送・選別の安定にも寄与。詰まりや二枚送りを抑え、機械ダウンタイムを減らします。
6. キャッシュレス時代の“ギザギザ硬貨”——それでも残る価値
6-1. 非常時のバックアップ
停電・通信障害・災害時に現金は即時性と確実性を発揮。触って識別でき、機械でも人でも確認可能なギザ硬貨は、最後の砦として機能します。
6-2. 金融包摂とアクセシビリティ
キャッシュレス環境になじみにくい人々にとって、手触りで分かる通貨は安心の基盤。ギザは**金融包摂(インクルージョン)**を支える静かな技術です。
6-3. 文化・教育・観光への波及
記念硬貨や地域図柄、縁の違いの“観察”は、歴史・材料・工学を学ぶ教材として優秀。ミュージアムや観光体験でも人気です。
7. 未来のギザギザ——AI識別・新素材・サステナブル
7-1. AI×画像・電磁プロファイル
画像AIと電磁プロファイルの融合で、摩耗・汚れ・欠けがあっても高精度で識別。縁の微妙な乱れやピッチの“ゆらぎ”まで学習できます。
7-2. 新素材・多層構造の最適化
耐摩耗・耐腐食に優れた新合金やクラッド設計で、寿命延伸・ライフサイクルコスト削減が進展。ギザの形状も材料特性に合わせて最適化されます。
7-3. リサイクルと環境配慮
回収・溶解・再圧延の工程を高度化し、資源循環を強化。縁のギザはリサイクル後も品質検査の指標として機能します。
8. まとめ・Q&A・用語辞典
8-1. まとめ(ポイント再整理)
- ギザギザは削り取り・偽造の可視化から生まれ、今や触知性・機械識別・意匠性を兼ねる総合機能。
- カラー(襟金)転写によって一撃で成形。斜めギザ/縁文字/波型など多彩なバリエーションが存在。
- 500円のような多層材×斜めギザ×微細文字は世界水準の多重防衛。
- キャッシュレスでも非常時・アクセシビリティ・学習の面で硬貨の価値は続く。
- 未来はAI識別・新素材・資源循環の時代へ。
8-2. よくある質問(Q&A)
Q1. 10円玉にギザギザがないのはなぜ?
A. 現行の10円は意匠・製造合理性から平滑縁。過去の“ギザ十”期(収集人気)を経て、現在はギザなしで安定供給されています。
Q2. 100円玉のギザは何本?
A. 一般に約118本とされます。年号や製造ロットによってわずかな差が生じうるとされます。
Q3. 500円玉の“斜めギザ”は何のため?
A. 模倣困難化と機械識別の強化のため。多層材・潜像・微細文字と合わせて多重防衛を構築しています。
Q4. ギザが摩耗した硬貨は使える?
A. 通常の摩耗であれば流通可能です。極端な変形・欠損がある場合は金融機関で交換を相談しましょう。
Q5. ギザのない硬貨は偽造に弱い?
A. いいえ。材質・磁性・微細模様・寸法精度など多要素で守られます。縁は全体設計の一部です。
Q6. 海外の硬貨はギザの本数が同じ?
A. 国・額面ごとに本数・深さ・波型・文字入れは異なります。歴史・造幣技術・自販機規格が反映されます。
8-3. 用語辞典(やさしい解説)
- ミリング/リーデッドエッジ:縁の細かな刻み。削り取り対策・触知性・意匠性に寄与。
- クリッピング:縁を削って素材を盗む不正。ミリングの発端となった歴史的課題。
- カラー(襟金):本打ち時に外周を囲むリング。内面の溝や螺旋でギザや縁文字を転写。
- アップセット:打刻前に縁を立てる前加工。直径精度・積み重ね性・縁成形の前提を整える。
- エッジレターリング:縁に文字や模様を刻む手法。真贋性・意匠性を高める。
- クラッド/バイメタル:異種金属を貼り合わせた多層構造・二重構造。識別性と防犯性を強化。
- 潜像・微細文字:角度や拡大で現れる極小要素。再現困難で偽造抑止に有効。
- 渦電流検査:金属にコイル磁界を当て、材料の電磁応答を測る識別法。機械判定の柱。
おわりに
コインの“縁の刻み”は、小さな溝に数百年の知恵と最先端の工学が詰まった証です。次に硬貨を手にしたら、図柄だけでなくエッジの光と手触りにも注目してみてください。暮らしの中に、歴史とテクノロジーの交差点が見えてきます。