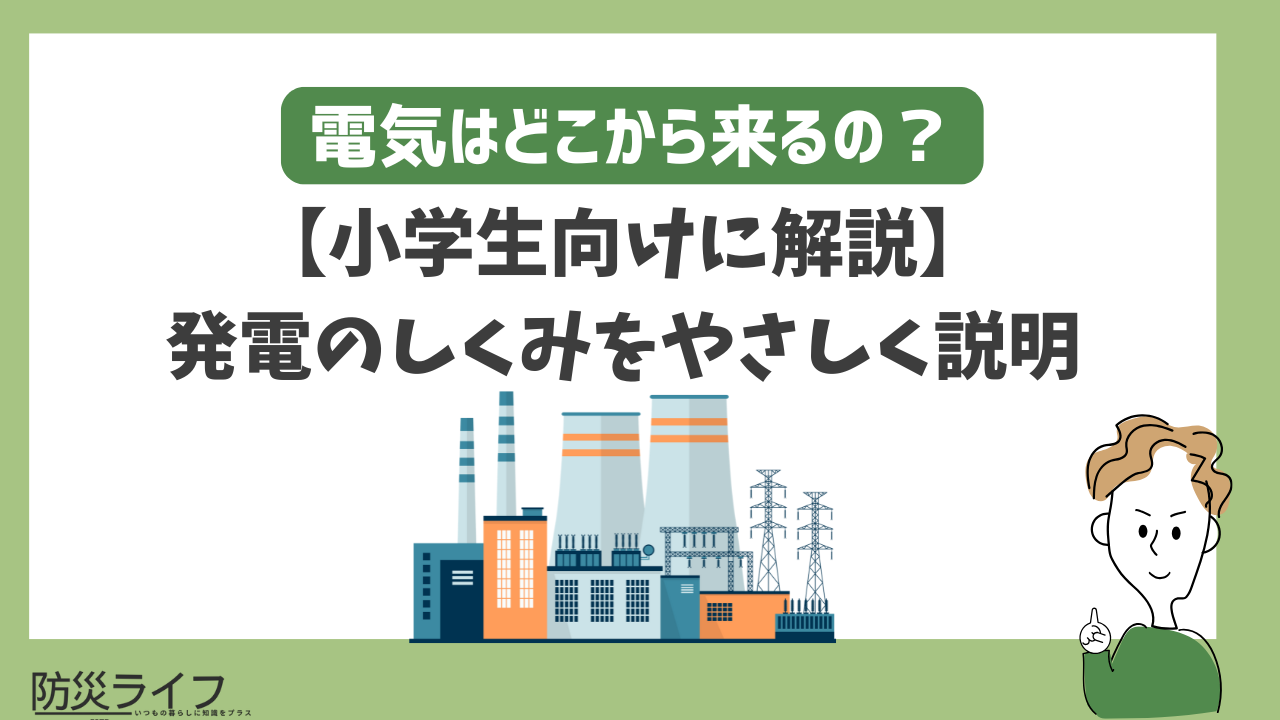結論:電気は「発電所でつくる → 高い電圧で遠くへ送る → 変電所で使いやすく整える → 配電線で家や学校に届ける」しくみで毎日とどいています。
この記事では、電気の正体/発電のしくみ/家に届くまで/未来の電気と地球/自由研究アイデアを、実例・図解イメージ・表でわかりやすくまとめました。最後にQ&Aと用語辞典もついているので、読み終わったらそのまま学習ノートに使えます。
1.電気ってなに?身近にある電気のふしぎ
1-1.目に見えないけれど大活やくのエネルギー
電気は、物の中にある小さな粒「電子(でんし)」が動くことで生まれるエネルギーの流れ(電流)です。電気は光・音・熱・運動などに変えることができ、照明をつけたり、テレビを動かしたり、冷蔵庫で食べ物を冷やしたりします。見えないけれど、社会を動かす大きな力なのです。
1-2.もし電気がなかったら?
夜は真っ暗で勉強も家事も大変。冷蔵庫が止まると食べ物が保存できないし、病院の機械や信号、電車も動きません。工場やスーパー、図書館、学校も困ってしまいます。つまり電気はわたしたちの生活の土台です。
1-3.自然界の電気もあるよ
冬にドアノブで「パチッ」とくる静電気や、空でピカッと光る雷も電気のなかま。雲の中で電気がたまり、いっきに流れると雷になります。電池の電気(化学の力)とコンセントの電気(発電所の電気)は作り方が異なりますが、どちらも電子の動きという点では同じです。
1-4.電池の電気と発電所の電気のちがい
- 電池:からだの中で化学反応が起こり、+と-のあいだに電気の押し出す力(電圧)が生まれます。小さな機器向け。
- 発電所:大きな力で**回転(タービン)**を起こし、**発電機(コイル×磁石)**でたくさんの電気をつくります。町全体に送るのに向いています。
2.電気はどこで作る?発電所の種類と特徴
2-1.火力発電:熱→蒸気→タービンで発電
石炭・石油・天然ガスを燃やして水を蒸気にします。蒸気の勢いで**タービン(羽根車)**を回し、発電機を動かして電気をつくります。
- 長所:天気に左右されにくく、大量に安定して発電できる。
- 短所:燃やすとCO₂が出る。燃料費の変動に影響される。
- 自由研究のヒント:やかんの蒸気で小さな羽根車が回る模型を観察(※やけど注意、必ず大人と)。
2-2.水力発電:水の高低差でタービンを回す
ダムや高い場所にためた水を高い所から低い所へ流し、その力でタービンを回します。
- 長所:CO₂がほぼ出ない。発電量の調整がしやすい。
- 短所:大きなダムが必要で、自然環境への配慮が欠かせない。
- 観察ポイント:地図でダムと発電所の位置・高さの差(落差)をチェック。
2-3.風力・太陽光・地熱・バイオマス・原子力:特徴まとめ
- 風力:風で風車が回り発電機を動かす。CO₂ほぼゼロ。ただし風が弱い日は発電が少ない。
- 太陽光:太陽電池パネルが光を直接電気に変える。屋根に設置できる。天気や昼夜で発電量が変わる。
- 地熱:地面の奥の高温の蒸気でタービンを回す。安定しているが設置場所が火山帯などに限られる。
- バイオマス:木材チップや食品残さなどを燃やしたり、ガス化して発電。ごみを資源にできるが、燃料集めに手間がかかる。
- 原子力:原子の反応熱で水を蒸気にし、タービンを回す。大量発電できる一方、安全対策や廃棄物の管理が重要な課題。
2-4.発電方式のえらび方(地域の条件)
海に近い場所は洋上風力、日照が多い地域は太陽光、山と川が多い地域は水力が得意。**いくつかを組み合わせる(エネルギーミックス)**ことで、安定して電気を届けられます。
3.どうやって作る?発電の“中身”を大解剖
3-1.発電機の基本:コイル×磁石=電気が生まれる
発電機の心臓はコイル(細い銅線をぐるぐる巻いたもの)と強い磁石。コイルが磁石の近くで動くと電流が生まれます。これを電磁誘導といいます。動かす力は、蒸気・水・風・地熱など発電方式によってちがいます。
3-2.タービンは“回す役”、発電機は“作る役”
- 回す役(タービン):羽根に流れ(蒸気・水・風)が当たって回転。
- 作る役(発電機):回転エネルギーを電気エネルギーに変える。
この2つがチームで働くことで、動き→電気への変換が行われます。
3-3.身近な発電で体感しよう
- 自転車ライト:タイヤに接した小さな発電機(ダイナモ)を回して点灯。
- 手回しライト/ラジオ:自分の力でコイルを回し、充電なしで使える。防災にも役立ちます。
- 自由研究:磁石とコイルでLEDをチカッと光らせる実験(※ネオジム磁石は強力。指はさみ・飲み込みに注意)。
3-4.電気の「形」もいろいろ(直流と交流)
- 直流(DC):電池の電気。向きが一定。
- 交流(AC):コンセントの電気。向きが周期的に入れ替わる。交流は高電圧にしやすく遠くへ送るのに向いています。
4.家までどう来る?“発電所→おうち”の旅
4-1.送電:高い電圧で遠くまで一気に
発電所で生まれた電気は、何万ボルトという高電圧にして送電線・鉄塔で遠くの都市へ。高電圧にすると電気のムダ(損失)が少なくなります。
4-2.変電所:使いやすい電圧に“着替え”
途中の変電所で電圧を段階的に下げ、工場やビル、学校、住宅など用途に合った強さに整えます。見えないけれど、**町の要(かなめ)**です。
4-3.配電:電柱から家・学校・お店へ
町に入ると配電線と電柱で細かく分け、各建物へ。家の分電盤(ブレーカー)でさらに分けられ、コンセントや照明に届きます。ブレーカーは電気を守る安全装置でもあります。
4-4.停電はなぜ起こる?どう防ぐ?
雷・強風・地震・雪・工事ミスなどで配線や機器にトラブルが出ると、安全のため自動で電気を止めることがあります。最近はルートを分ける仕組みや地下ケーブル、高感度の保護装置で、停電を短く・少なくする工夫が進んでいます。
5.これからの電気:地球にやさしく、かしこく使う
5-1.クリーンエネルギーをふやす理由
地球の温暖化をおさえるため、CO₂の少ない発電(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)の割合を増やしています。地域の特色に合わせて最適な組み合わせを考えるのがポイントです。
5-2.ためて・分けて・むだなく使う
- 蓄電池:昼につくった電気を夜までためて使う。
- スマートグリッド:コンピューターで電気の流れを監視し、必要な場所へ自動的に分ける。
- V2H(車から家へ):電気自動車の電池を家庭の電源として活用。
5-3.今日からできる節電アイデア
照明をLEDに、使わない家電の主電源オフ、冷蔵庫の開け閉め短く、エアコンは温度を1℃工夫、昼間は自然光で学習。小さな積み重ねが地球も家計も守ります。
5-4.安全とくらし:電気を正しく使う
濡れた手でコンセントにさわらない、コードをねじらない・踏まない、たこ足配線をしすぎない。異臭や発熱があればすぐ電源オフ+大人に相談。
電気と発電の比較早見表(保存版)
| 発電方法 | エネルギーのもと | 仕組み・特徴 | 長所 | 短所 | 例・向いている場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火力発電 | 石炭・石油・ガス | 燃やして蒸気→タービン | 大量&安定 | CO₂や燃料費 | 都市近郊・需要の大きい地域 |
| 水力発電 | 高い所の水 | 落差でタービン | CO₂少・即応性 | ダム建設の影響 | 山地・降水が多い地域 |
| 風力発電 | 風 | 風車で発電機 | CO₂ゼロ | 風が弱いと× | 海岸・高原・洋上 |
| 太陽光発電 | 太陽の光 | パネルで直接発電 | 屋根に設置可 | 天気で変動 | 住宅屋根・空地・学校 |
| 地熱発電 | 地下の熱 | 蒸気でタービン | 安定 | 設置場所が限定 | 火山帯・温泉地 |
| バイオマス | 木材・食品残さ等 | 燃焼やガス化で発電 | ごみの資源化 | 燃料集めが大変 | 農林業地域 |
| 原子力発電 | 原子の反応熱 | 蒸気でタービン | 大量発電 | 安全・廃棄物 | 大規模基地 |
自由研究&観察アイデア(そのまま使える)
① おうちの“電気の一日”を調べよう
- 朝・昼・夜で使う家電を一覧表にして、使用時間と目的を記録。
- 節電ルール(待機電力カット・照明LED化)を1週間ためし、消費電力の変化を棒グラフに。
- 感想:「どの家電がいちばん電気を使った?なぜ?」をまとめる。
② ミニ発電にちょうせん
- 手回し発電ライト:1分回して何分光るか測定。家族で記録を比べる。
- ソーラーパネル+LED:晴れ/くもり/室内での光り方の差を観察。天気と発電量の関係を記録。
③ 町の電気マップを作る
- 家の近くの電柱・変圧器(灰色の大きな円筒)、送電鉄塔を見つけてスケッチ。
- 地図アプリで送電線のルートをたどり、どの発電所の種類につながるか調べる。
④ 安全第一の観察ルール
- 送電設備や川・ダムには近づきすぎない。監視区域には入らない。
- 実験は大人と一緒に。熱・磁石・工具はていねいに扱う。
Q&A:よくあるぎもんに答えます
Q1.電気はためられるの?
A.蓄電池にためられます。家庭用蓄電池や電気自動車の電池、学校の非常用電源などが例です。
Q2.停電はなぜ起こるの?
A.雷・強風・地震・落ち葉や雪・工事などが原因で設備が傷つくと、安全装置が働いて一時的に止まります。今は別ルート送電や自動復旧の仕組みが進み、短時間で戻ることが増えています。
Q3.太陽光だけで家の電気をまかなえる?
A.屋根の広さ・日当たり・家族の使い方によります。蓄電池と組み合わせると自給率を上げられます。雨や夜は電力会社の電気と上手に助け合うのが一般的です。
Q4.原子力は危なくないの?
A.たくさんの安全対策で運用しますが、万が一の事故や長期間管理が必要な廃棄物の課題があります。長所と短所を理解して社会全体で話し合う必要があります。
Q5.いちばんエコな発電はどれ?
A.地域の自然条件で答えが変わります。多くの国で再生可能エネルギーを組み合わせ、足りないときは他の方式で補うやり方が選ばれています。
Q6.電気はどうして見えないの?
A.電気は粒(電子)の動きなので目では見えませんが、光る・回る・あたたまるといった変化で存在を確かめられます。
Q7.コードの“たこ足”はなぜダメ?
A.電気の道が混み合って熱がこもると、火災の危険があるから。**定格(使える合計の量)**を守りましょう。
用語辞典(むずかしいことばをやさしく)
- 電流(でんりゅう):電気の流れ。単位はアンペア(A)。
- 電圧(でんあつ):電気を押し出す力。単位はボルト(V)。
- 発電機:コイル×磁石で電気をつくる機械。
- タービン:蒸気・水・風の力で回る羽根車。
- 電磁誘導:コイルが磁石のそばで動くと電流が生まれる現象。
- 送電・配電:電気を遠くへ運ぶ/建物へ分けるしくみ。
- 変電所:電圧を上げたり下げたりして使いやすくする施設。
- 蓄電池:電気をためて後で使える電池。
- 再生可能エネルギー:自然の力を使い、くり返し取り出せるエネルギー。
- スマートグリッド:ITで電気の流れをかしこく管理する仕組み。
- ブレーカー:電気を使いすぎたり、故障があったときに自動で切る安全装置。
まとめ:電気を知れば、未来が見えてくる
電気は発電所でつくる → 高電圧で送る → 変電所で整える → 配電線で届けるというチームワークで毎日わたしたちに届いています。これからはクリーンエネルギーを増やし、ためる・分ける技術でむだなく使うことが大切。
今日からできる小さな節電を続ければ、地球にも家計にもやさしい未来につながります。仕上げに、自分の町の電気マップを作って、家族や友だちに発表してみよう!