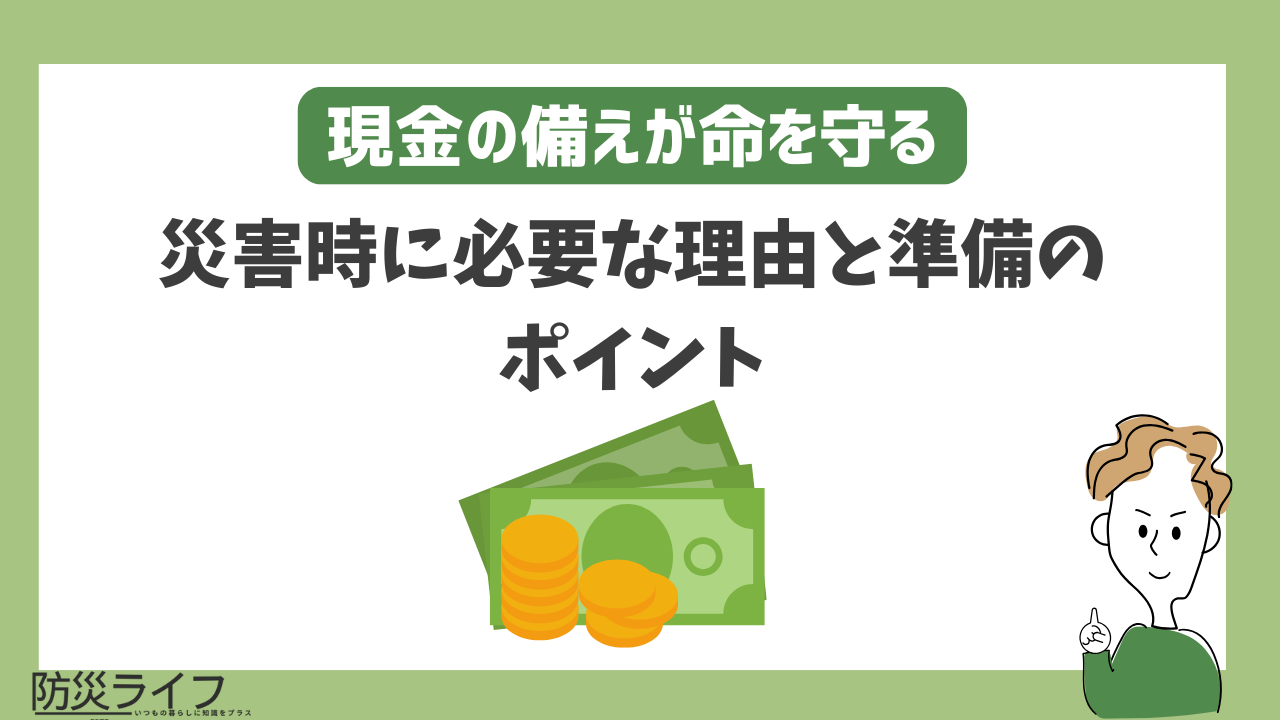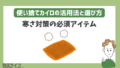停電・断水・通信障害でキャッシュレスやATMが機能停止——そんな“お金の断絶”に備える最も確実な手段が現金です。本記事は、災害時になぜ現金が強いのかから、人数・期間別の最適額、金種の内訳、保管と分散の設計、被災時の安全な使い方、復旧期の切替運用までを実務目線で徹底解説。
なぜ災害時に「現金」が必要か(最新事情と実例)
電力・通信が止まると“決済”はこう止まる
- 停電でATM/決済端末が停止し、引き出し・カード決済不可。
- 通信障害でQR決済・電子マネーが認証エラー、店側も現金のみに切替。
- 初動は釣り銭不足になりやすく、高額紙幣が通りにくい。
決済手段と必要インフラの関係
| 決済手段 | 必要インフラ | 災害初期の稼働性 | 備考 |
|---|
| 現金 | なし(人的対応のみ) | 高い | 釣り銭確保で更に安定 |
| デビット/クレカ | 電力+通信+端末 | 低〜中 | 復旧後に段階的回復 |
| 電子マネー/QR | 電力+通信+サーバ | 低 | 認証集中で遅延・落ちやすい |
実災害の“初動72時間”で現金が担う役割
- 飲食・水・電池・ガス缶など、命に直結する購入に即効性。
- 交通(タクシー/臨時バス)、病院/薬局の会計で小口現金が強い。
- 露店・個人商店・臨時販売所は現金前提で動きが早い。
現金が生む“交渉力と即決力”
- まとめ買いや共同購入で会計を簡素化し、列の停滞を防げる。
- 釣り銭に配慮した1,000円札・硬貨は店側の受け入れがスムーズ。
いくら・どの種類を備えるか(人数・期間・避難形態で最適化)
期間別の現金目安(1人あたり)
| 期間 | 推奨額(目安) | 用途イメージ |
|---|
| 1日分 | 5,000円 | 飲食・移動の最小限 |
| 3日分 | 10,000〜30,000円 | 食料/水の補充、移動・医療の備え |
| 7日分 | 50,000円 | 在宅・車中泊の継続、緊急宿泊も視野 |
家族構成・避難形態での目安(上乗せ条件も考慮)
| 構成/形態 | 推奨総額 | 上乗せ条件 | 備考 |
|---|
| 1人 | 10,000〜30,000円 | 持病/常用薬がある | 追加の薬代・移動費を想定 |
| 2人 | 20,000〜50,000円 | 片方の通勤・通院が必要 | 分散携行で紛失リスク分散 |
| 4人(大2+子2) | 50,000〜100,000円 | 乳幼児/学童 | 牛乳・紙おむつ等の追加費 |
| 避難所生活中心 | 1人1〜2万円 | 売店・自販機利用 | 配給ありでも小口出費は発生 |
| 在宅避難中心 | 家族で5〜10万円 | ガス缶・簡易食の補充 | スーパー/ドラッグ想定 |
| 車中泊避難あり | 家族で7〜12万円 | 燃料・駐車・簡易宿泊 | 高速/有料道路の利用も |
金種バランスの作り方(“使える”内訳)
原則:1,000円札を主役に、500円/100円を厚め。1万円札は最小限。
- 軽量モデル(大人1人・7日分 50,000円例)
- 10,000円×1、5,000円×3、1,000円×20、500円×6、100円×20 = 50,000円
- 釣り銭を確保しつつ、コイン枚数を抑え携帯性を重視。
- 小口重視モデル(自販機/釣り銭確実化)
- 1,000円×15、500円×10、100円×40、50円×10、10円×50、5,000円×2、10,000円×1 = 50,000円
- 自販機・公衆電話・ロッカーなど硬貨需要に強い。
- 介護・通院重視モデル(家族2人・3日 50,000円例)
- 5,000円×4、1,000円×20、500円×12、100円×30、10,000円×1 = 50,000円
- タクシー/薬局会計の小口連打に強い。
1週間フルシミュレーション(家族4人・在宅中心)
| 用途 | 予算/日 | 7日合計 | メモ |
|---|
| 食料・飲料 | 2,500円 | 17,500円 | 主食+水の補充 |
| 生活消耗品 | 1,000円 | 7,000円 | ティッシュ・電池等 |
| エネルギー | 1,200円 | 8,400円 | ガス缶・固形燃料 |
| 交通・通院 | 1,000円 | 7,000円 | バス/タクシー等 |
| 予備 | 1,500円 | 10,500円 | 想定外の出費 |
| 計 | 7,200円 | 50,400円 | 5万円目安妥当 |
保管と分散の設計(在宅・車・持ち出しで“取り出せる”)
場所別の推奨配分と容器(家族4人例)
| 保管場所 | 推奨金額 | 推奨容器/保護 | 取り出しやすさ | 補足 |
|---|
| 防災リュック | 2〜3万円 | 防水/防火ポーチ・小分け封筒 | ◎ | 最優先の持出し枠 |
| 玄関収納(在宅用) | 2〜4万円 | 耐火金庫 or 金属ケース | ○ | 帰宅困難時にも家族がアクセス |
| 車内(車中泊用) | 1〜2万円 | 防水ケース・目立たない場所 | ○ | 昼は保管、夜は携行へ切替 |
| 財布の非常用ポケット | 5千〜1万円 | ジッパー袋・薄型ポーチ | ◎ | 単独外出時の即応 |
容器・耐火・防水の選び方(要点)
- 耐火:ポーチは短時間耐熱、金庫は延焼時の温度上昇を遅らせられる。
- 防水:止水ファスナー+二重袋で浸水リスクに備える。
- 偽装:目立たない文具箱や衣装ケースの内ポーチにして盗難抑止。
小型耐火ポーチ vs 耐火金庫(比較表)
| 項目 | 小型耐火ポーチ | 耐火金庫 |
|---|
| 可搬性 | 高い | 低い |
| 初期費用 | 低〜中 | 中〜高 |
| 耐火・盗難 | 短時間/限定 | 強い |
| 向き | リュック・車内 | 在宅据え置き |
家族共有ルール(誰でも“迷わず取れる”設計)
- 色分け封筒:赤=緊急、青=生活、緑=医療/交通、黄=予備。
- 合言葉:子どもには金額を言わず用途のみ伝える簡潔フレーズを共有。
- 棚卸し日:防災の日・年度末など年2回に固定して確認・補充。
災害時に安全に使う(防犯・詐欺・公的手続き)
携行と支払いのオペレーション
- 大金を一度に持ち出さない。必要額だけ小分けポーチで携行。
- レジ前での高額紙幣の露出は最小限に。1,000円札と硬貨で会計を速く。
- レシートは用途別封筒へ即収納し、家計の可視化と紛失防止。
詐欺・便乗商法の回避ポイント
- 相場から大きく逸脱する価格、“今だけ”強調は要注意。
- 自称ボランティアや業者の前払い要求は原則回避。
- 取引は信頼できる店舗・公的窓口に限定し、領収書を確保。
行政・医療・交通での“現金の出番”
- 罹災証明や各種申請の印紙/手数料が現金のみの場合に備える。
- 夜間・救急の薬代/診療費は小口現金が安全・迅速。
- 交通の臨時便や地方の路線は高額紙幣不可の場合があるため1,000円札中心で。
支払い優先順位の考え方(家族4人例)
| 優先 | 支出 | 理由 | 推奨金種 |
|---|
| 1 | 水・食料 | 生命維持 | 1,000円+硬貨 |
| 2 | エネルギー | 調理・保温 | 1,000円 |
| 3 | 医療・薬 | 健康維持 | 1,000円/5,000円 |
| 4 | 交通・通信 | 移動/情報確保 | 1,000円/500円 |
| 5 | 宿泊 | 一時避難 | 5,000円/1,000円 |
現金と併用する金銭ツール(復旧フェーズ対応)
キャッシュレス復旧期の使い分け
- 復旧が見えたら高額支払いはキャッシュレスへ、現金は小口に温存。
- モバイルバッテリー・紙のメモ・筆記具を常備し、ID類は見せすぎない。
重要情報の控え(最小限テンプレ)
| 種別 | 控える項目 | 保管先 |
|---|
| 銀行 | 支店名・種別・下4桁のみ | 耐水メモ(封筒内) |
| カード | 緊急連絡先・最少枚数 | 同上(番号全桁は書かない) |
| 携帯 | キャリア連絡先・契約者名 | 同上 |
併用で便利な“紙のツール”
- 封筒・付せん・輪ゴム:レジ前での仕分けを素早く。
- 小型ノート:購入履歴・在庫・次の買い出し先を整理。
- 予備切手/レターパック:連絡手段の冗長化(状況により活用)。
ケーススタディ:初動48時間の現金運用(在宅+近隣買い出し)
| 時間帯 | 行動 | 現金の使い方 | ポイント |
|---|
| 0〜12時間 | 家族の安否確認・在庫点検 | 支出ゼロ | まず把握・移動は最小 |
| 12〜24時間 | 近隣で水・主食を購入 | 1,000円×2〜3枚 | 小口でスピード会計 |
| 24〜48時間 | ガス缶/電池/薬を確保 | 1,000円×5+硬貨 | 釣り銭不要を心掛ける |
まとめと今日すべき準備
- 基準額:1人あたり**1〜3万円(3日)/5万円(7日)**を目安に算出。
- 金種:1,000円札中心+500円/100円多め。1万円札は最小限。
- 分散:防災リュック・在宅・車・財布に用途別色分けで配置。
- 運用:年2回の棚卸し→不足補充→家族共有。
付録:金種別・用途別の“使える”早見表
| 用途 | 最適金種 | 理由 |
|---|
| コンビニ・スーパー | 1,000円札、500円 | 釣り銭発生が最小でスムーズ |
| 自販機/ロッカー | 100円、500円 | 認識率・流通量が多い |
| 交通(タクシー/バス) | 1,000円札、500円 | 高額紙幣NG・釣り銭不足対策 |
| 医療・薬局 | 1,000円札、5,000円 | 会計が読みづらく小口が安心 |
| 宿泊 | 5,000円、1,000円 | 現地の釣り銭事情に対応 |
災害の最初の3日を“お金で止まらない”ように。**数(額)・質(金種)・場所(分散)**の3点を今夜決め、封筒とポーチに小分けして配置すれば、明日からの安心が一段階上がります。