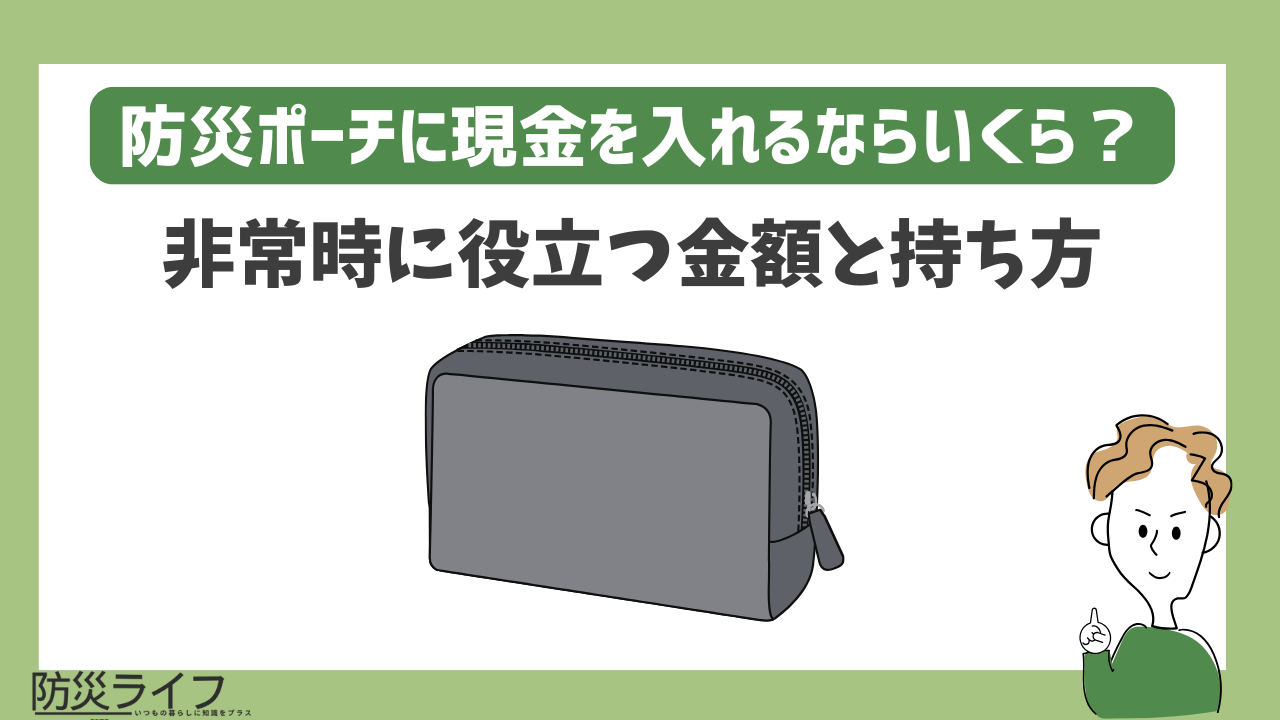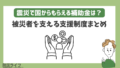はじめに|防災ポーチに現金を入れる理由
災害直後は停電・通信障害・レジやATMの停止が同時に起きやすく、キャッシュレスは電源・通信・決済センターのどれか一つでも止まると機能しません。だからこそ、最後に残る決済手段=現金を“計画的に”備えておくことが、初動の行動力を左右します。本稿では、金額の決め方(人数×期間×移動)/札と硬貨の内訳/分散保管と防水・防火/決済手段の多層化/ケース別の必要額を、そのまま真似できるレベルまで具体化します。
なぜ現金が必須なのか(仕組みから理解する)
1) 停電と通信断が“決済の根本”を止める
キャッシュレスは端末の電源+通信回線+決済センターの三点セットで成立します。広域停電ではPOSレジや決済端末が起動しない、通信障害ではQR決済・ICのオンライン認証が失敗。復旧速度に差が出るため、現金だけが即時通用する時間帯が必ず生まれます。
2) 物流の乱れで“現金限定販売”が増える
初動は水・食料・電池・簡易医薬品の需要が急増。店舗側も釣銭の確保や伝票処理が限定的になり、小額紙幣・硬貨での簡易決済が受け入れられやすくなります。少額を素早く切る能力は、並び直しの回数や調達速度に直結します。
3) 自販機・公衆電話・現金精算が“最後の砦”
給水所開設までの間は自販機での飲料確保、公衆電話での安否連絡が命綱になります(多くが10円・100円硬貨対応)。鉄道・バスは臨時運行や現金精算に切り替わる場合があり、硬貨の有無が移動可否を分けることも。
4) 金融機関やATMの再開は“地域差”が出る
ATMは**電源・通信・補給(現金の装填)**が揃って稼働します。道路事情次第で補給が遅れ、並んでも引き出せない事態は珍しくありません。手元の現金が行動の確実性を高めます。
いくら用意する?(人数×期間×移動で決める)
目安の基本線
- 最小構成:5,000〜10,000円 … 1〜2日分の飲料・軽食・最低限の交通。
- 安心構成:20,000円前後 … 帰宅困難・宿泊・医療・衛生を含む3日想定。
- 家族世帯や出張・旅行時は上積みを前提に。
1人1日あたり“現金消費モデル”
| 科目 | 都市部の目安 | 郊外/地方の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 飲料・軽食 | 700〜1,200円 | 600〜1,000円 | 自販機・簡易食・温飲料等 |
| 交通 | 0〜2,000円 | 0〜1,500円 | 臨時運行・代替輸送・徒歩なら0円 |
| 通信 | 100〜300円 | 100〜300円 | 公衆電話硬貨・充電用コイン等 |
| 衛生・医療 | 200〜800円 | 200〜800円 | マスク・消毒・常備薬・絆創膏 |
| 雑費 | 200〜500円 | 200〜500円 | 雨具・手袋・使い捨て食器など |
概算:1人/日 1,200〜4,800円。移動・宿泊が発生すると一気に増えます。
ケース別の必要額(モデルケース)
| ケース | 期間 | 推奨額 | ポイント内訳 |
|---|---|---|---|
| 帰宅困難(徒歩帰宅) | 1日 | 5,000〜8,000円 | 飲料・軽食・タオル・小銭厚め |
| 避難所2泊 | 3日 | 15,000〜20,000円 | 衛生用品・交通・予備薬・コインロッカー |
| 乳幼児同伴 | 2〜3日 | 18,000〜25,000円 | ミルク・離乳食・オムツ・衛生・洗浄水 |
| 高齢者同伴 | 2〜3日 | 18,000〜25,000円 | 介護用品・医療・交通を厚めに |
| 車中泊(燃料あり) | 2日 | 10,000〜15,000円 | 食・衛生・コインランドリー・駐車代 |
| 出張先で被災(宿泊前提) | 1〜2泊 | 20,000〜30,000円 | 宿泊1泊最低10,000円+交通5,000円 |
人数・期間での早見表
| 世帯/期間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 想定内訳(例) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000〜20,000円 | 飲料・軽食・交通・予備薬 |
| 2人 | 8,000円 | 15,000円 | 20,000〜25,000円 | 飲食×2・交通×2・衛生 |
| 4人 | 12,000円 | 20,000円 | 30,000円前後 | 飲食×4・子ども用品・予備費 |
旅先・出張は宿泊1泊分(最低10,000円)+交通5,000〜10,000円を上乗せ。
札と硬貨の“勝てる内訳”と持ち方
紙幣:1,000円主軸で“崩し不要”に
災害時は釣銭不足が常態化。1,000円札を8割、5,000円札は1枚、10,000円札は非常時に1枚まで。これで小口決済の回転が速くなります。
硬貨:電話・自販機・コイン設備に効く
- 100円×20枚、10円×20枚、500円×4枚を基本。
- 公衆電話は10円・100円対応が多く、10円の刻みが重宝。
- 自販機・コインロッカー・駐輪・コインランドリー等、額面のバランスが有利。
内訳サンプル(合計20,000円)
| 額面 | 枚数 | 小計 |
|---|---|---|
| 1,000円札 | 14枚 | 14,000円 |
| 5,000円札 | 1枚 | 5,000円 |
| 10,000円札 | 0〜1枚 | 0〜10,000円(非常用) |
| 500円玉 | 4枚 | 2,000円 |
| 100円玉 | 20枚 | 2,000円 |
| 10円玉 | 20枚 | 200円 |
ポイント:“崩す”必要のない面構成が、行列や混雑で効きます。
支払いミスを減らす“渡し方ルール”
- 先に金額を口頭確認(「こちら1,300円ですか?」)。
- 小銭優先でピッタリに近づけ、最後に1,000円札で調整。
- 受け取り後はその場で枚数確認→すぐ封入。人混みでの数え直しは避ける。
どこに入れて、どう守る?(分散・防水・防火・防犯)
二重封入で“水と熱”から守る
- 防水チャック袋→耐水ケースの二重封入(薄い乾燥剤を同封)。
- 自宅保管は耐火ポーチや金属ケースで延焼・高温を回避。
- 夏場や雨天は汗・結露で紙幣が貼りつくため、半年ごとローテが安全。
分散保管で“紛失・盗難・水没”に備える
- 防災ポーチ本体/上着内ポケット/バッグ内ポケット/車載キットの4点分散。
- ダミー財布を表側に置き、本命は体側の見えない位置へ。
- 家族で1か所だけ取り出し場所を共有し、不在時もアクセス可能に。
表示と管理のコツ
- 封入袋の端に金額・作成日を極小でメモ。
- 使ったら即補充、半年ごとに硬貨の偏りを是正。
- 香り強い防虫剤は紙幣に匂いが移るので避ける。
分散保管の例(20,000円を4等分)
| 場所 | 金額 | 内訳(例) |
|---|---|---|
| 防災ポーチ | 8,000円 | 1,000円×6、500円×2、100円×10、10円×10 |
| 上着内ポケット | 4,000円 | 1,000円×3、100円×5、10円×5 |
| デイパック内側 | 4,000円 | 1,000円×2、500円×2、100円×10 |
| 車載キット | 4,000円 | 1,000円×2、100円×10、10円×10 |
現金以外も“多層化”しておく(復旧フェーズで効く)
予備カードと交通系ICは“別ブランド・別ポケット”
- クレジットカードはメインと別ブランドで1枚を追加。
- 交通系IC(Suica/PASMO等)は3,000円以上を事前チャージ。
- カードは別ポケット分散、暗証番号メモの携帯は不可。
プリペイド・QR決済は“可視化と役割分担”
- 最低限の残高を事前チャージし、家族で担当を分ける。
- 復旧初期に使える店舗が点在するため、選択肢が広がる。
身分確認と送金の準備
- 顔写真付き身分証のコピー・保険証の写しを薄く同封。
- 家族の合流地点・連絡先を紙で同封し、通信断に備える。
- 送金アプリや銀行の非常時手続きを事前に確認しておく。
季節・地域・同伴者で変わる“追加費用”
季節要因
- 夏:冷飲料・保冷・日除け・制汗・虫除け→飲料単価が増。
- 冬:カイロ・防寒具・温飲料・濡れ対策→衛生・暖取り費が増。
地域要因
- 都市部:宿泊費・交通費が高止まり。現金の単価上振れに注意。
- 郊外/地方:移動距離が長く、現金精算率が高い傾向。
同伴者別の上積み目安
| 同伴者 | 1日あたり上積み | 主な費目 |
|---|---|---|
| 乳幼児 | +1,000〜2,000円 | ミルク/離乳食/オムツ/衛生 |
| 高齢者 | +800〜1,500円 | 介護用品/医療/交通 |
| ペット | +500〜1,000円 | フード/簡易トイレ/衛生 |
10分でできる“現金セットアップ手順”
- 額を決める:最小5,000〜10,000円、安心20,000円。
- 両替する:1,000円中心に、100円・10円・500円を指定。
- 二重封入:防水袋+耐水ケース、薄い乾燥剤を同封。
- 分散:ポーチ・上着・バッグ・車に小口で分ける。
- ラベル:金額・作成日を極小で記入。
- 家族共有:保管場所と使い方ルールをメモで同封。
よくある失敗と回避策
- 高額紙幣ばかり → 1,000円主軸+硬貨で再構成。
- 硬貨が少なすぎる → 公衆電話・自販機・現金精算に詰まる。10円・100円を厚めに。
- 一箇所にまとめて保管 → 紛失・盗難・水没のリスク。4点分散へ。
- 防水不十分 → 汗・雨・結露で紙幣がダメージ。二重封入+半年点検。
- 使ったまま補充忘れ → ラベルに次回点検日を記し、カレンダーに登録。
職場・学校・地域での“現金レジリエンス”
- 職場:**小口現金(1,000円札×20、100円×50、10円×50)**を災害用に分離。保管責任者と取り出し手順を明文化。
- 学校:教職員室に小銭セット、公衆電話利用マニュアル、児童・生徒の安否連絡カードを整備。
- 自治会:避難所運営用に両替セットと会計記録用紙、領収証ブロックを常備。
早見表まとめ(コピペ保存用)
推奨金額
- 最小:5,000〜10,000円(1〜2日)
- 安心:20,000円(3日+宿泊・医療・衛生を含む)
紙幣
- 1,000円札中心(全体の約8割)+5,000円×1、10,000円×0〜1
硬貨
- 100円×20/10円×20/500円×4(公衆電話・自販機・コイン設備)
分散保管
- ポーチ/上着内/バッグ内/車載の4点、小口で分ける
保護
- 防水袋→耐水ケースの二重封入+半年ごと点検
代替手段
- 別ブランドの予備クレカ、交通系IC3,000円以上、身分証コピー
まとめ|“1,000円主軸+小銭厚め”を分散・防水で常備する
災害直後の決済は現金が最強です。目安は最小5,000〜10,000円/安心20,000円。1,000円札中心+100円・10円・500円の硬貨を厚めに組み、防水・防火の二重封入で4点分散。さらに予備カードと交通系ICを別ポケットで多層化し、半年ごとに点検・補充。この“小さな仕込み”が、非常時の移動・購入・連絡を確実にし、あなたと家族の行動力を守ります。