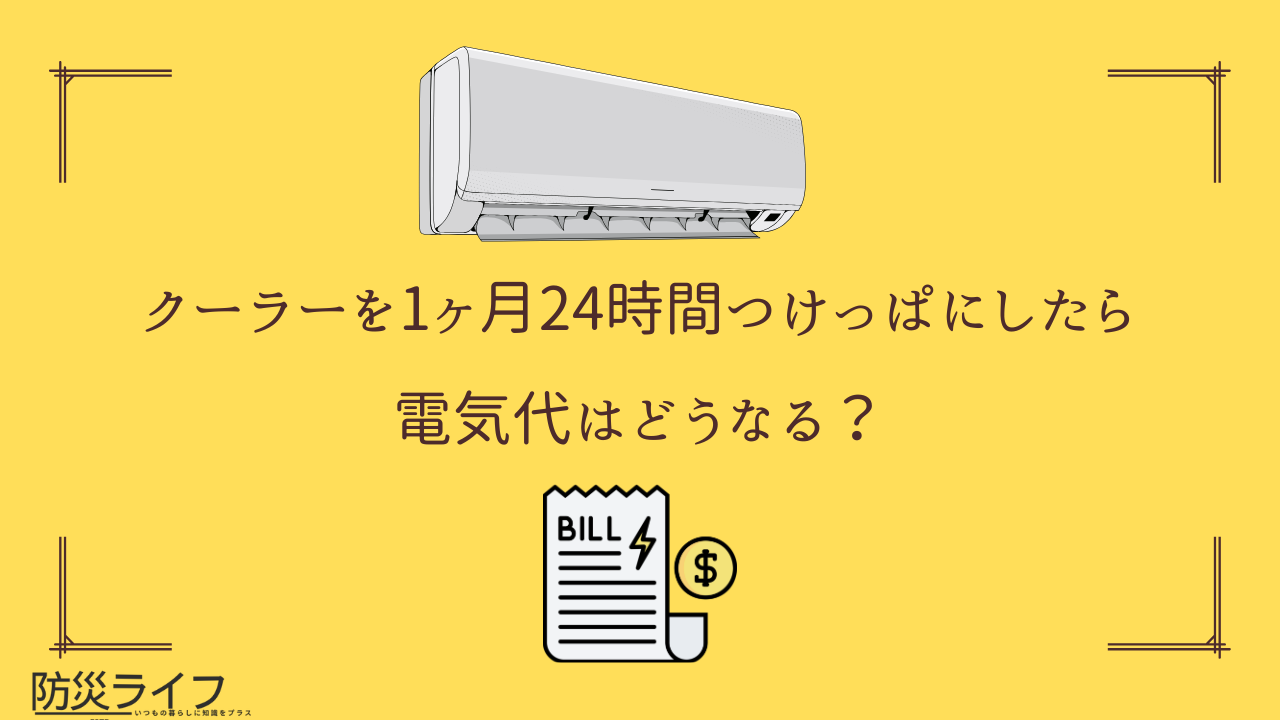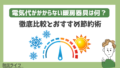はじめに。猛暑や熱帯夜が続く近年、「24時間つけっぱなし」という運用は珍しくありません。とはいえ、電気代はいくらかかるのか/本当に得なのかは気になるところ。
本記事では、仕組み→計算式→1か月の試算→環境差→節約術の順で、今日から使える数値と手順をまとめます。前提の電力単価は27円/kWh(例)で計算し、単価が変わる場合の感度表も用意。金額はあくまで目安で、機種・住まい・運転条件で上下します。
1.クーラーの電力消費はこう決まる(基礎)
1-1.「冷房能力」と「効率(COP)」の関係
家庭用エアコンの使う電力は、冷房能力(例:2.2kWクラス=6〜8畳目安)と、効率(COP=同じ電力でどれだけ冷やせるか)で概ね決まります。実際の入力電力は運転状況で変動し、2.2kW級でおおむね500〜900Wの範囲に収まることが多い一方、安定時はもっと低い平均になる例もあります。
1-2.外気温・日射・湿度・部屋の条件で大きく変わる
外が暑いほど、また西日や直射が強いほど消費は増えます。断熱・気密が高い家、内窓・遮熱カーテンありの部屋は有利。日本の夏は湿度が高く、除湿の負荷が電力に効きます。
1-3.起動直後と安定運転のちがい
立ち上がり(起動直後)は一時的に電力が増え、その後設定温度に近づくほど抑えめになります。ここが「こまめに切るか/つけっぱにするか」の損益分岐のポイントです(後述の簡易モデルで解説)。
1-4.部屋の形・高さ・吹き抜けの影響
同じ畳数でも天井が高い・吹き抜け・ロフトは空間が広く、必要能力が増えます。引き戸の開放や出入りの多さでも負荷は上下します。
2.24時間×1か月の電気代を丸ごと試算(モデル計算)
2-1.計算式(基本)
電気代(円)= 入力電力(kW)× 時間(h)× 単価(円/kWh)
例:0.7kWを24時間×30日、単価27円なら → 0.7×24×30×27=13,608円/月。
2-2.部屋の広さ別・月額の目安(24時間運転)
※入力電力は実運転の平均の想定。電力単価27円/kWh。
| 部屋の広さ(目安) | 入力電力の想定(平均) | 月の電気代(目安) |
|---|---|---|
| 6畳 | 0.50〜0.70 kW | 9,720〜13,608 円 |
| 8畳 | 0.70〜0.90 kW | 13,608〜17,496 円 |
| 10畳 | 0.90〜1.20 kW | 17,496〜23,328 円 |
| 14畳 | 1.20〜1.50 kW | 23,328〜29,160 円 |
実際は安定運転の時間が長いため、上表より2〜3割少なくなることも珍しくありません(断熱・日射・湿度・設定温度による)。
2-3.電力単価が違う場合の感度表(0.7kW想定)
1か月の消費電力量=0.7×24×30=504 kWh を前提。
| 単価(円/kWh) | 月の電気代(円) |
|---|---|
| 24 | 12,096 |
| 27 | 13,608 |
| 31 | 15,624 |
| 40 | 20,160 |
2-4.「つけっぱ」か「こまめにオフ」か:簡易モデルで比較
平均0.5kWで安定運転する部屋を仮定し、再起動の増分を0.9kWで20分(0.333h)と仮置きすると:
- 短い外出(1時間)で一度オフ:
- つけっぱ:0.5kW×1h=0.50kWh
- オフ→再起動:0.9kW×0.333h+0.5kW×0.667h=約0.633kWh
- → 差は約0.133kWh(約3.6円)で、短時間ならつけっぱの方が微有利という場面も。
- 長い外出(8時間)でオフ:
- つけっぱ:0.5kW×8h=4.0kWh
- オフ:0kWh(外出中)
- 再起動の増分を見込んでも、総量は大幅に減少。
目安:外出が1時間未満なら差は小さく、数時間以上なら切った方が通常は有利。体感や湿度、帰宅時の快適さも加味して選びましょう。
2-5.CO₂の目安(環境の視点)
排出係数を0.45 kg-CO₂/kWhとすると、0.7kW×24h×30日=504kWh/月 → 約227kg-CO₂/月。温度・湿度の適正化や断熱の強化は、家計と環境の両方に効きます(係数は地域・契約で変動)。
3.同じ「24時間」でも電気代が変わる要因(住まいと環境)
3-1.断熱・気密・築年数の差
内窓・断熱材・すきま風対策がある住まいは冷気が逃げにくいため、安定運転が長くなり電気代は抑えやすい。築年が進んだ木造はすきまに注意。目張り・隙間テープで改善します。
3-2.窓の方角・直射・カーテンの効き
南・西向きは日射が強く、昼の負荷が増えます。遮熱レース・遮光カーテン・断熱フィルムで室温上昇を抑えると、同じ設定温度でも電力が下がります。
3-3.湿度の高さと除湿の負荷
体感温度は湿度に大きく左右されます。弱冷房除湿は温度を下げつつ湿気を取る運転で、機種次第では冷房と同等〜やや高めの消費になることも。目標は湿度50〜60%前後(目安)。
3-4.室外機の設置環境
直射日光・ふさがった背面・吹き出し口の障害物は効率低下の原因。日よけ(風通し確保)と雑草・物の撤去で改善します。
4.電気代を抑える使い方(効果の大きい順)
4-1.設定温度と風の使い方
- 室温**28℃**を一つの目安に、風量は自動/やや強めで素早く均一化。
- 風向きは水平〜やや上。冷気は下にたまるため、天井付近へ送って循環させると効率が上がります。
4-2.扇風機・送風機で循環
**サーキュレーター(送風機)**や扇風機で空気を回すと、設定を1℃高めでも快適。冷気だまりと温度ムラを減らします。
4-3.フィルター掃除・熱交換器の汚れ対策
月1回のフィルター清掃で風量の低下を防止。年に一度は専門点検も安心です。室外機の吸い込み口のほこりも除去。
4-4.窓・直射対策(最小投資で大効果)
遮熱レース+遮光カーテン、断熱シート、すだれで日射をカット。床面への直射も避けると、体感が大きく変わります。
4-5.長時間不在時はオフ/短時間は設定を上げる
数時間以上の不在はオフ。短時間なら設定温度を上げる(例+2℃)+除湿優先で戻りの負担を軽くします。
4-6.寝室のコツ(睡眠の質を落とさない)
寝入りの1〜2時間はしっかり冷やし、その後は弱めに。扇風機の首振りと併用で冷えすぎ防止。体調に合わせてタイマー活用。
5.疑問をまとめて解決(Q&A)+用語の小辞典
5-1.Q&A(よくある質問)
Q1:24時間つけっぱなしで寿命は縮む?
A:頻繁なオンオフの方が負担が大きい場面も。適切な温度で安定運転なら過度に心配はいりません。ほこり対策は必須。
Q2:電気代を最優先で下げるなら?
A:まず日射対策と断熱→設定温度の適正化→送風機の併用→フィルター掃除。次に室外機まわりの風通しを確保。
Q3:除湿と冷房、どちらが得?
A:機種・方式によります。短時間で一気に下げたいなら冷房、長時間の湿気取りなら除湿が有利な場合も。**湿度50〜60%**を狙い、体感で調整。
Q4:夜間だけ強く冷やして日中は弱めは有効?
A:日射の時間帯に負荷が集中します。昼の直射対策と風の循環を組み合わせると、日中の電力を抑えやすいです。
Q5:ブレーカーを落とすのは?
A:長期不在なら有効ですが、短期はリモコンの電源オフで十分。設定がリセットされる機種もあるため注意。
Q6:電力単価が上がった。計算は?
A:**(kW)×(時間)×(単価)**で置き換えるだけ。例:0.7kW×720h×31円=15,624円/月。
Q7:子どもや高齢者がいる場合の優先順位は?
A:熱中症予防が最優先。室温と湿度の適正化、寝室の確実な冷房、こまめな水分補給を優先してください。
5-2.用語の小辞典(やさしい言い換え)
冷房能力(kW):どれだけ冷やせる力。部屋の広さの目安になる。
入力電力(kW):実際にコンセントから使う電力。電気代はここで決まる。
効率(COP):同じ電力でどれだけ冷やせるかの指標。大きいほど省エネ。
消費電力量(kWh):使った電気の総量。電気代=kWh×単価。
安定運転:設定温度に達して負荷が下がった状態。電力が抑えられる。
除湿:空気中の湿気を減らす運転。体感温度が下がりやすい。
5-3.家計メモに残す「計算の型」
- 月の電気代(円)= 入力電力(kW)×720×単価(1か月を30日と仮定)
- 日割(円)= 入力電力(kW)×24×単価
- 複数台はkWの合計で同じ式に当てはめればOK。
まとめ
24時間×1か月の冷房は、部屋と使い方次第で1万円台前半〜3万円前後が目安。断熱・日射対策・湿度管理・風の循環・こまめな清掃をそろえれば、同じ快適さでも電気代は確実に下げられます。外出時間に応じてオフ/設定上げを使い分けつつ、体調第一で上手に夏を乗り切りましょう。