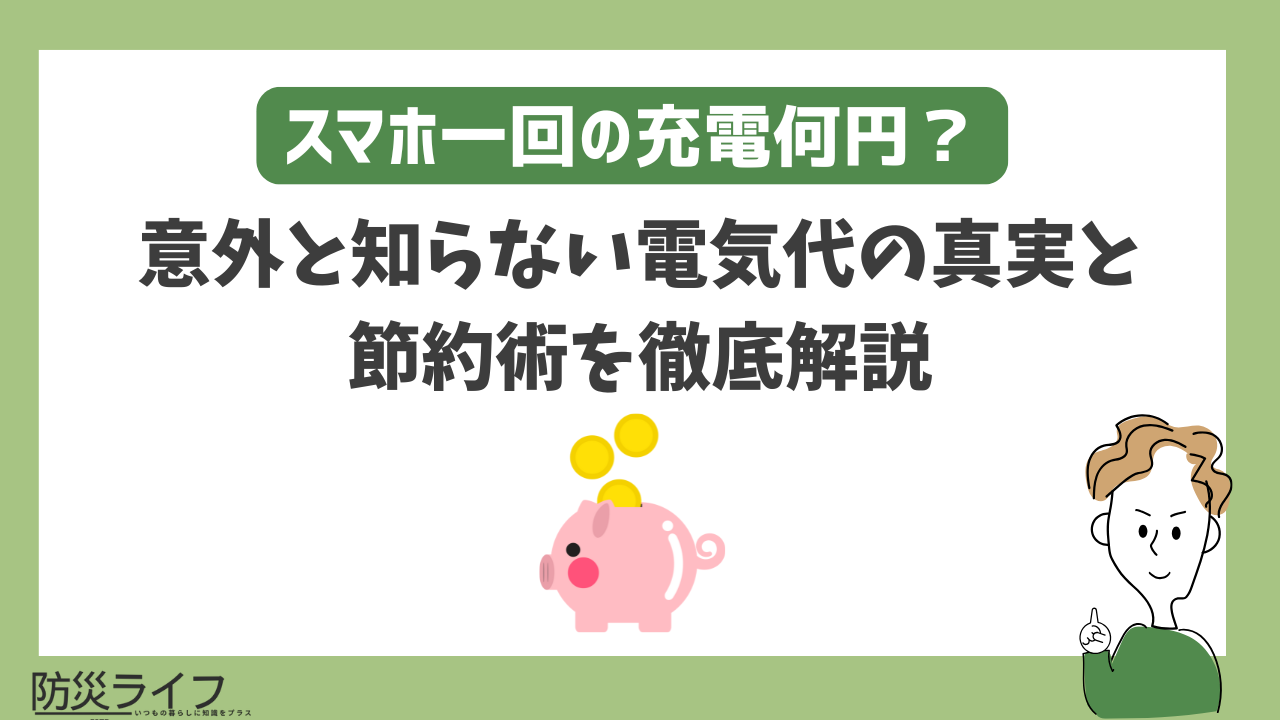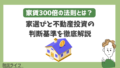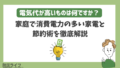毎日欠かさず行うスマホの“充電”。けれど実は、「一回いくら?」「家計への影響は?」を正確に説明できる人は多くありません。本記事では、数式に基づいた実額と、今日から実践できる節電と電池長持ち術を、できるだけむずかしい言葉を使わずに整理しました。家族分・複数端末・ワイヤレス充電・モバイル電源のロス、さらには時間帯別料金や太陽光の自家消費まで、日常で気になる論点を網羅します。
1.スマホ一回の充電にかかる電気代はいくら?(計算式・実例・応用)
1-1.バッテリー容量から電力量を求める(mAh → Wh)
スマホの電池容量は「mAh」で表記されています。電力量(Wh)に直すには、
電力量(Wh)= 容量(mAh) ÷ 1,000 × 電池電圧(V) を使います。多くのスマホは電池電圧が約3.7Vです。
- 3,000mAh → 3.0Ah × 3.7V ≒ 11.1Wh
- 5,000mAh → 5.0Ah × 3.7V ≒ 18.5Wh
- 8,000mAh(大型機・タブレット級)→ 8.0Ah × 3.7V ≒ 29.6Wh
部分充電のときは、入れた割合(ΔSOC)を掛け算します(例:20%→80%の充電=60%=0.6倍)。
1-2.基本式と“現実的”な効率を加味した計算
電気代の基本式は、
電気代(円)= 使用電力量(kWh) × 電力単価(円/kWh)
実際の充電では充電器やケーブルで少し熱として失われるため、ここでは有線充電の効率85%、ワイヤレス70%を目安にします(壁から取り出す電力量=電池に入る電力量÷効率)。
1-3.電力単価別シミュレーション(27円/31円/40円)
| 条件 | 壁からの電力量 | 27円/kWh | 31円/kWh | 40円/kWh |
|---|---|---|---|---|
| 3,000mAh(11.1Wh)/有線85% | 約13.1Wh(0.0131kWh) | 約0.35円 | 約0.40円 | 約0.52円 |
| 5,000mAh(18.5Wh)/有線85% | 約21.8Wh(0.0218kWh) | 約0.59円 | 約0.67円 | 約0.87円 |
| 8,000mAh(29.6Wh)/有線85% | 約34.8Wh(0.0348kWh) | 約0.94円 | 約1.08円 | 約1.39円 |
結論:有線充電なら、ほとんどの機種で1回あたり1円未満(大型機でも約1円前後)に収まります。
1-4.急速・通常・ワイヤレスで何が変わる?(効率と発熱)
急速充電は「速く入れる」だけで、使う電力量そのものは大きく変わりません。一方でワイヤレス充電は効率が下がりやすい(60~75%程度)ため、同じ満充電でも電気代がやや増えます。加えて、発熱が増えるほど電池寿命には不利です。
| 方式 | めやす効率 | 3,000mAhの目安(31円/kWh) | 5,000mAhの目安(31円/kWh) | 8,000mAhの目安(31円/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 有線(通常・急速) | 約85% | 約0.40円/回 | 約0.67円/回 | 約1.08円/回 |
| ワイヤレス(置くだけ) | 約70% | 約0.49円/回 | 約0.82円/回 | 約1.31円/回 |
1-5.部分充電の実額:20→80%だけでもOK
5,000mAh機を20%→80%(60%分)だけ満たすなら、18.5Wh×0.6÷0.85=約13.1Wh。単価31円/kWhで約0.41円です。小まめに継ぎ足しても家計インパクトは微小です。
1-6.時間帯別料金・太陽光の自家消費を使う
- 時間帯別料金:夜間の単価が安いプランなら、就寝前~早朝に充電を寄せるとさらに安くなります。
- 太陽光の自家消費:日中在宅なら、日射ピーク(昼~午後)に充電すると「買う電気」が減ります。
2.家計インパクトは?(月・年・家族・複数端末・在宅ワーク)
2-1.1台・毎日充電の月額/年額
5,000mAhを有線で毎日充電(31円/kWh)の場合:
0.67円 × 30回=約20円/月、×365日=約245円/年。家計全体では誤差に近い額です。
2-2.家族4人+タブレット+ウェアラブルのケース
- スマホ(5,000mAh)×4台:0.67円×30回×4=約80円/月
- タブレット(8,000mAh想定=29.6Wh/85%):1.08円×30回=約33円/月
- スマートウオッチ(350mAh=約1.3Wh/85%):1回約0.05円、毎日でも約1.5円/月
- ワイヤレスイヤホン(ケース600mAh=約2.2Wh/85%):1回約0.08円、週3回で約1円/月
合計でも月100~150円程度が目安。端末が増えても“塵も積もれば……止まり”です。
2-3.モバイル電源(モバイルバッテリー)経由はロス増
「コンセント→モバイル電源→スマホ」と二段階になるため、合計10~20%ほど余計に電気を使うことがあります。外出時は便利ですが、家では直接コンセント充電が経済的です。
2-4.在宅ワークで増えるのはスマホよりPC
ノートPCは1回の満充電で30~70Wh使う例が多く、スマホの2~4台分以上。仕事の電力コスト管理はPC中心で考えるのが合理的です。
3.他の家電と比べるとどのくらい?(省エネ度を相対評価)
3-1.冷蔵庫・テレビ・エアコン:主役は“常時”と“大出力”
電気代の主役は「常に動く」または「大出力で動く」家電です。スマホ充電はそのどちらにも当てはまりません。
3-2.ゲーム機・PC・調理家電:使うときだけでも大きい
据置ゲーム機・ノートPC・電子レンジ・電気ケトルは、短時間でも消費が大きめ。習慣の最適化が効きやすい領域です。
3-3.比較早見表(31円/kWhの例)
| 項目 | 消費電力量(目安) | 電気代(1回または月間) | 年間電気代(参考) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| スマホ充電(5,000mAh) | 約0.022kWh/回 | 約0.67円/回 | 約245円 | 家計への影響はごく小さい |
| 冷蔵庫(月間) | 約33kWh | 約1,020円/月 | 約12,000円 | 常時稼働の代表格 |
| テレビ(1日4時間・月間) | 約12kWh | 約370円/月 | 約4,400円 | サイズ・設定で変動 |
| エアコン(夏・1日8時間・月間) | 約120kWh | 約3,720円/月 | 設定で数千円の差 | 温度・風量が鍵 |
| 電気ケトル(1日2回・月間) | 約1.5kWh | 約46円/月 | 約550円 | 短時間だが出力大 |
| ノートPC満充電(1回) | 0.04~0.07kWh | 1.2~2.2円/回 | — | 機種差が大きい |
4.今日からできる節電&電池長持ち術(安全第一で)
4-1.待機電力を断つ・差しっぱなしをやめる
充電器を挿しっぱなしでもごくわずかに電気を使います(例:0.2Wとすると、年1.75kWh≒約54円/年)。まとめて切れるスイッチ付きタップや自動で切れるコンセントが便利です。
4-2.温度と充電の範囲を意識(20~80%運用)
電池は高温と満充電・空に弱い性質があります。ケースを外して充電、夏場の直射日光は避ける、20~80%の範囲を意識すると長持ちに効きます。機種の「最適化充電」をONにするのも有効です。
4-3.道具選び:安全マークと「規格対応」を確認
- PSEマークのある充電器・モバイル電源を選ぶ
- 太い導体のしっかりしたUSBケーブル(許容電流表示・Eマークの確認)
- 機種が対応する給電方式(例:PD・PPS)に合った充電器
見た目が同じでも中身の安全装置や発熱対策が違います。安さだけで選ばないのが、結局いちばんの節約です。
4-4.ワイヤレス充電のコツ(発熱とムダを抑える)
- コイルの位置合わせを丁寧に(ズレはロスと発熱の原因)
- 厚いケース・金属プレート・磁気カードは外す
- 夏場は卓上ファンで軽く送風すると熱ダレを防げる
4-5.“やってはいけない”チェック(安全版)
| NG行為 | なぜ危険? | 代わりにこうする |
|---|---|---|
| 布団やソファで充電器を覆う | 放熱できず発熱・劣化 | 硬く平らな場所で充電 |
| 破損したケーブルを使い続ける | ショート・発火リスク | 早めに新品へ交換 |
| 非対応の高出力充電器を無理に使用 | 過熱・誤作動の恐れ | 機種対応の規格を確認 |
5.よくある疑問と落とし穴(Q&A)
Q1.充電器のワット数が大きいほど電気代が高い?
いいえ。電気代は「入れた電力量」で決まります。大きな出力の充電器は時間を短くできるだけで、同じ満充電なら電気代はほぼ同じです(効率差はわずか)。
Q2.夜間充電は損?
単価が時間帯で変わる契約なら、安い時間に充電するとお得です。そうでなければ差はほぼありません。長時間の挿しっぱなしは発熱を招きやすいので、タイマー切りや朝方の仕上げ充電が安心です。
Q3.充電しながら使うとどうなる?
充電と放電を同時に行うため発熱しやすく、電池寿命には不利です。電気代の違いは小さいものの、長持ちを優先するなら避けましょう。
Q4.モバイル電源を経由すると高くなる?
変換の重ねがけで10~20%ほど余計に電気を使うことがあります。外では便利、家では直接充電が基本です。
Q5.ワイヤレス充電は電気代が高い?
効率が下がる分、1回あたり数割増になることがあります。便利さとの釣り合いで使い分けましょう。
Q6.待機電力はどれくらい?
充電器の種類次第ですが、たとえば0.2Wなら年1.75kWh、単価31円/kWhで約54円/年。小さいですが、まとめて切ると無駄を減らせます。
Q7.急速充電ばかりだと電池は早く劣化する?
高出力ほど発熱は増えがちで、寿命には不利です。日常は通常充電、急ぎのときだけ急速に切り替えるのが現実解です。
Q8.100%まで毎回充電しないと損?
いいえ。20~80%を維持する運用は寿命に有利です。必要なときだけ100%にすればOK。
Q9.電気代の高い月と安い月で、スマホ充電の差は大きい?
差はごく小さいです。月の基本料金や他家電の使用状況のほうが影響大。
Q10.車のUSBやPCから充電すると安い?
支払う先が「ガソリン代」「PCの電気」に変わるだけで、電力量は同程度。効率・発熱・速度の観点で家庭のUSB-C充電器がもっとも安定します。
用語の小辞典(やさしい言い換え)
- mAh(ミリアンペア時):電池にためられる量の目安。数が大きいほど長く使える。
- Wh(ワット時):実際に使う電気の量。電気代の計算の基本単位。
- kWh(キロワット時):Whの1,000倍。検針票に載る単位。
- 待機電力:使っていないのに機器が待機のために使うわずかな電力。
- 変換効率:コンセントの電気がどれだけムダなく電池に入るかの割合。
- 急速充電:短時間で多く充電する方法。便利だが発熱に注意。
- PD/PPS:機器と充電器が最適な電圧・電流をやり取りするための仕組み。
- SOC(充電率):電池の残量の割合。0~100%。
- サイクル:満充電1回分に相当する使用の単位(50%×2回=1サイクル)。
自分の機種で費用を出すミニ手順(保存版)
- 電池容量(mAh)を確認する。
- 電力量(Wh)= mAh÷1,000 × 3.7 を計算(電池電圧3.7V想定)。
- 有線なら÷0.85、ワイヤレスなら÷0.70で壁からの電力量を推定。
- kWhに直して(Wh÷1,000)、契約の単価(円/kWh)をかける。
- 部分充電なら、入れた割合(%)を最後に掛ける。
これで1回の電気代が出ます。月額は×30、年額は×365です。
例:5,000mAhを20→80%(60%分)だけ有線で:18.5Wh×0.6÷0.85=13.1Wh=0.0131kWh。単価31円/kWhで約0.41円。
チェックリスト(今日からのベストプラクティス)
- 有線充電が基本。ワイヤレスは便利なときだけ。
- 挿しっぱなしをやめる。スイッチ付きタップで一括オフ。
- 20~80%を目安。必要時のみ100%に。
- 高温を避ける。直射日光・布団の中・車内放置はNG。
- 対応規格の充電器・ケーブルを選ぶ(PSE・PD・PPS)。
まとめ
スマホ1回の充電はおおむね0.3~1.3円、月でも数十円。家計への影響はごく小さく、気にすべきはむしろ安全と電池寿命です。挿しっぱなしをやめる、温度に気をつける、有線を基本にする――この3点だけでもムダを抑え、長く快適に使えます。今日からできる小さな工夫で、ムリなく賢い節電を始めましょう。