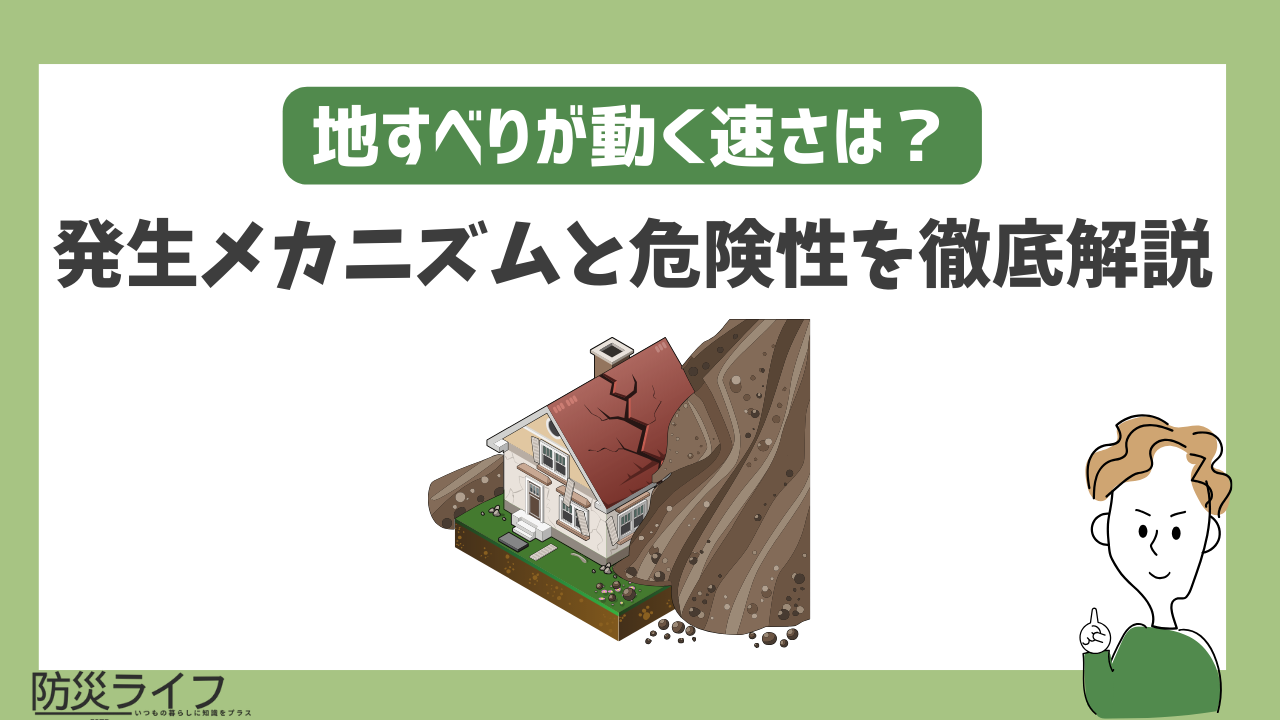地すべりは、斜面の一部が重力に引かれて“かたまり”で移動する現象です。速度は年間数センチのゆっくりした動き(クリープ)から、数秒〜数分で数百メートル到達する超高速な崩壊まで幅広く、速さ=被害の大きさと避難猶予を左右します。本稿では、速度の見方・加速条件・型式・実例・監視と避難の実務を、表とチェックリストで整理。今日から現場で使える具体策に落とし込みます。
1. 地すべりの基礎と「速さ」の考え方
1-1. 地すべりとは(基礎のき)
- 土砂や岩塊が“面”に沿って滑る現象。表層だけ動くことも、地下深部まで動くこともあります。
- 斜面内部にはすべり面(弱い層・面)が形成され、雨水・地下水・地震動・人工改変によって抵抗力<すべり力となると移動します。
- 速度の鍵は摩擦・粘着力・斜面角・間隙水圧のバランス。
1-2. 速度分類(目安・到達・避難猶予)
| 区分 | 速度の目安 | 到達スケール | 避難猶予 | 主な被害像 |
|---|---|---|---|---|
| 超遅速型 | 年間数cm〜数m | 数十m〜 | 長い(計画的対策) | 道路・農地の段差、家屋の微小変形 |
| 遅速型 | 数日〜数ヶ月で数十m | 数十〜数百m | 中(監視で回避可) | ライフラインの断続被害、建物の傾き |
| 急速型 | 数秒〜数分で数百m | 数百m〜1km | ほぼ無(即時避難) | 住宅地へ一気に到達、埋没・押圧 |
| 超高速型 | 秒速10m以上 | 1km以上 | 無 | 岩屑なだれ・泥流化、致命的破壊 |
要点:速いほど衝撃力・巻き込み量・到達距離が増し、避難時間は短縮します。
1-3. 速度はなぜ変わる?(安全率の直感)
- 斜面の安定度は安全率=抵抗力/すべり力で表せ、1を切ると加速します。
- 降雨・融雪→間隙水圧↑→有効応力↓→摩擦力↓で安全率が低下。
- 微小変位(クリープ)→加速段階→崩壊と段階的に速くなることがあります。
1-4. 用語の早見表(かんたん)
| ことば | いみ | 覚え方 |
|---|---|---|
| 震源ならぬすべり面 | すべる弱い面 | バターを塗ったパンの面 |
| 間隙水圧 | 土粒子のすき間の水の圧力 | スポンジに水を含ませた時の押し返し |
| 深層すべり | 地下深くまで動くタイプ | 地下のベルトコンベアが動く感じ |
2. 地すべりの速さを決める主因
2-1. 地質・地下水・間隙水圧
- 粘土質(膨潤性)が厚いとゆっくり滑る傾向だが、雨でじわじわ加速。
- 砂層・風化岩・節理が発達した岩盤はすべり面ができやすく、速い移動に移行しやすい。
- 地下水の滞留は間隙水圧↑→摩擦↓→加速。排水性がカギ。
2-2. 斜面角・地形・集水条件
- 急斜面ほど重力成分が大きい→急速化のリスク。
- 谷頭・段丘崖・崖錐は水が集まりやすい→飽和→不安定。
- 凹形の斜面は土砂や水がたまりやすく、流動化しやすい。
2-3. 外力:降雨・融雪・地震・人為
| 要因 | 速度への影響 | 典型トリガー | 実務ヒント |
|---|---|---|---|
| 豪雨 | 地下水位上昇→加速 | 線状降水帯・長雨 | 先行雨量で警戒強化、排水路清掃 |
| 融雪 | 長時間の供給継続 | 春先の高温・雨雪同時 | 集水桝・暗渠の維持 |
| 地震 | せん断強度低下→突然加速 | 強震動・余震 | 余震期の立入規制・巡視 |
| 人工改変 | 切土・過荷重・漏水で安定低下 | 法面掘削・ため池漏水 | 設計段階で安定解析+監視計画 |
2-4. 人の暮らしとの関係(リスク経路)
- 宅地造成・道路掘削で斜面形状が変化→安全率低下。
- 樹木伐採・農地転用で保水・根の補強が減る→表層移動増。
- 老朽排水施設の目詰まり→地下水滞留→加速。
3. 発生メカニズムと代表的タイプ
3-1. すべり面のつくられ方(型式)
- 円弧(回転)すべり:粘土・風化土で多い。地表の段差・クラックが前ぶれ。
- 平面すべり:層理面・断層粘土・不連続面に沿って一気に移動。
- 楔状・岩盤崩落:節理の交差がくさびとなり、高速で転落。
- トップリング:柱状節理などが前のめりに倒れる。
3-2. 表層すべり・深層すべり・流動化
- 表層すべり:厚さ数十cm〜数m。豪雨直後に多発。
- 深層すべり:地下数十mの古いすべり面が再活動。長期クリープ→閾値超過で急加速。
- 泥流・土石流化:含水比が高くなると流体のように動き、到達距離が長い。
3-3. 兆候・前ぶれ(見逃さないサイン)
| サイン | 何を意味? | 行動 |
|---|---|---|
| 亀裂・段差が増える | すべり面の拡大 | 立入禁止・計測強化 |
| 湧水量の急増・濁り | 地下水位上昇 | 排水確認・退避準備 |
| 樹木・電柱の傾き | 変位継続 | 避難判断の検討 |
| 扉・窓が開閉しづらい | 建物の変形 | 安全な場所へ移動 |
| 斜面からの異音(ミシ・ゴロ) | 破壊進行 | 即時退避・通報 |
3-4. 監視・計測の実務(見える化)
- 傾斜計・伸縮計・孔内水位計:閾値越えで警報。
- GNSS・トータルステーション:ミリ単位の変位追跡。
- ドローン・衛星(InSAR):広域の微小変位を面で把握。
- 雨量監視:時間雨量・累加雨量・先行雨量で段階対応。
閾値設定の例(考え方):
1)先行雨量が地域基準(例:数日合計)を超えたら巡視。
2)湧水急増+地表クラックが確認されたら高齢者等先行避難。
3)伸縮計・傾斜計が急変したら全員避難・立入禁止。
4. 事例で学ぶ:速度と被害のリアル
4-1. ペルー・ユンガイ(1970)
- 高山の氷河と岩盤が崩落し、極高速の岩屑なだれへ。短時間で広域を破壊。
- 雪氷との混合で流体化し、到達距離が長大に。
- 教訓:上流の崩壊が下流の市街に短時間で到達しうる。
4-2. 日本・広島の土砂災害(2014)
- 線状降水帯級の豪雨で、表層崩壊→土石流が同時多発。
- 夜間発生により感知と避難が遅延、住宅地へ瞬時到達。
- 教訓:夜間豪雨は明るい時間帯に先行避難が最善。
4-3. 中国・四川省の地震誘発地すべり(2008)
- 大地震で広域の斜面が不安定化し、**土砂ダム(堰止湖)**が形成。
- **二次災害(破堤洪水)**が潜在化。
- 教訓:地震後は“川の上流”の斜面崩壊も監視。下流域まで想定。
5. いますぐできる防災・減災アクション
5-1. エリア把握:ハザード・地形・土地履歴
- 地すべり危険区域・土砂災害警戒区域を地図で確認(自宅・学校・職場・通学路)。
- 段丘崖・旧谷筋・盛土造成地は優先チェック。
- 過去の災害履歴がある場所は再活動を常に想定。
5-2. ハード対策(斜面を安定させる)
| 対策 | ねらい | 効果のポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 集水ボーリング・横穴排水 | 間隙水圧低下 | 地下水の“抜き”で安定度↑ | 維持管理が命(詰まり対策) |
| 表面排水・側溝整備 | 表面水の速やかな排除 | 豪雨直後の加速を抑制 | ゴミ・落ち葉の目詰まり注意 |
| アンカー・杭・擁壁 | すべり抵抗の増強 | 地質・すべり面に適合設計 | 施工時の地盤弱化に配慮 |
| 法面保護・植生回復 | 表層侵食の抑制 | 根系で表土補強 | 樹種・維持の計画性 |
| 表層被覆(シート等) | 降雨浸透の抑制 | 緊急時の応急措置 | 長期は排水と併用 |
5-3. ソフト対策(監視・避難・家庭の備え)
- 雨量・変位・水位に段階閾値を設定(平常→注意→警戒→避難)。
- 高齢者・乳幼児・要配慮者の先行避難をルール化。
- 夜間豪雨は“暗くなる前に”移動を基本に。
行動早見表(住民用)
| きっかけ | 何をする? | 家での対策 |
|---|---|---|
| 大雨予報・注意報 | ハザード再確認・非常品点検 | 外の物片づけ・排水口清掃 |
| 警報・土砂災害警戒情報 | 高齢者等先行避難 | 停電に備えライト充電 |
| 斜面で異音・亀裂・湧水 | ただちに退避し通報 | ガス遮断・ブレーカー確認 |
家庭のミニ持ち出し(両手が空くリュック)
- ライト・予備電池・モバイルバッテリー
- 飲料水(500ml×人数分)・非常食
- 救急セット・常備薬・マスク・手袋
- ホイッスル・雨具・タオル・ポリ袋
5-4. 現場運用テンプレ(管理者・自治体向け)
- 監視計画:雨量・水位・変位の計器配置図+閾値表を整備。
- 連絡網:発報→判断→住民周知→避難所開設の時系列手順書。
- 巡視ポイント:クラック、湧水、法面変状、排水詰まり、倒木。
- 記録:雨量・観測・判断・広報・避難のタイムラインを残す。
5-5. 雨量基準の考え方(例示)
- 時間雨量・連続雨量・先行雨量の3点を見る。
- 地域基準があれば最優先。未整備時は過去の被害雨量を基準に安全側で設定。
- 閾値は季節・植生・工事状況で見直す(固定しない)。
まとめ|速度を知れば、命を守る判断も速くなる
地すべりの速度は年間数cmから時速100km超まで多様で、地質・地下水・斜面形状・降雨・地震・人工改変の重なりで決まります。兆候の“見える化”と段階閾値による前倒し行動、そして排水・安定化・監視を組み合わせることが、被害を減らす近道です。まずはハザードマップの確認、排水の清掃、家族の避難先と連絡方法の共有から始めましょう。