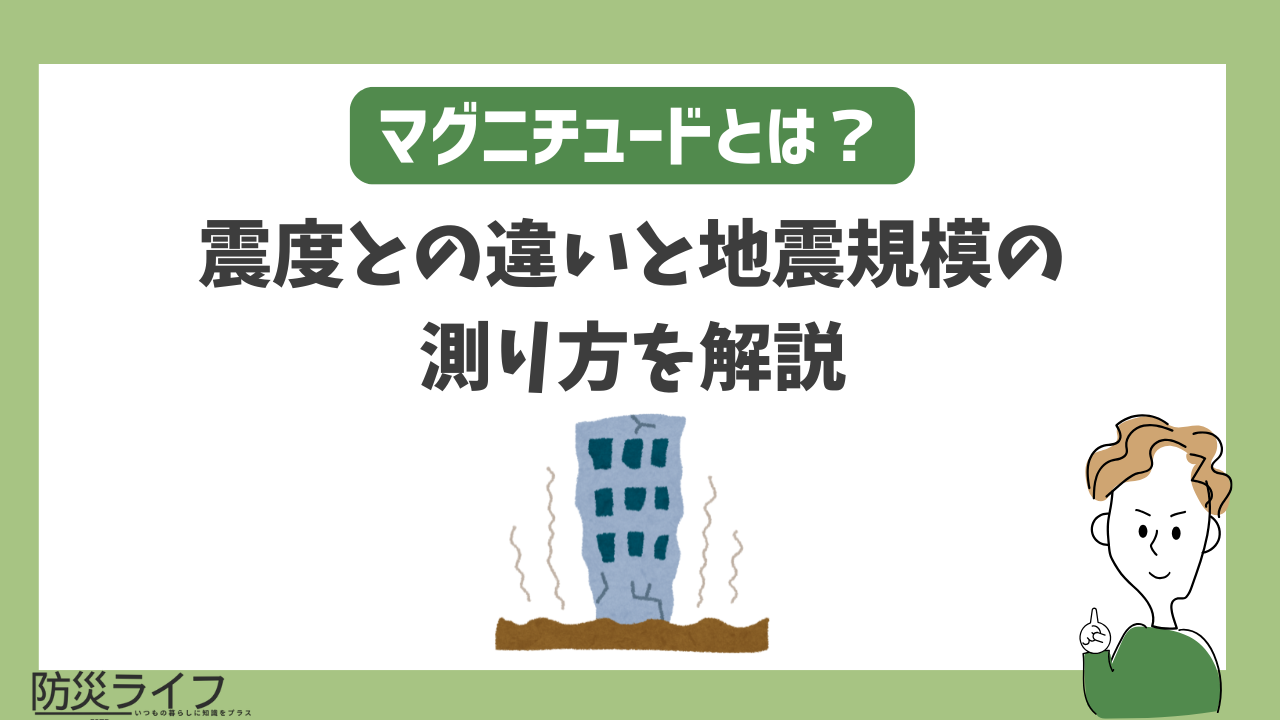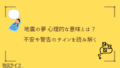ニュースで「**マグニチュード(M)◯◯**の地震」と聞くたびに、「被害の大きさ(震度)と同じ意味?」と迷う人は多いはず。結論から言うと、マグニチュードは“地震そのものの規模(エネルギー)”を表す指標、震度は“ある地点での揺れの強さ”です。本記事は、Mの定義・計測の仕組み・各スケールの違い・震度との関係・事例比較・速報の読み方・行動テンプレまで、初学者でも腹落ちするよう図解イメージ・表・具体例で徹底解説します。
マグニチュードの基礎知識|定義・意味・対数スケール
マグニチュードの定義と位置づけ
- 何を示す? 地震が放出したエネルギーの規模(地震そのものの“大きさ”)。
- どう決まる? 地震波の振幅や、断層がどれだけ**ずれたか(地震モーメント)**などから推定。
- どのくらい差がつく? 対数スケール。Mが1増えるとエネルギー約32倍、2増えると約1000倍。
震度との違い(混同しやすいポイントを整理)
| 指標 | 何を表す? | どこで決まる? | 値の特徴 | 典型の使いどころ |
|---|---|---|---|---|
| マグニチュード(M, Mw, Mj など) | 地震そのものの規模(放出エネルギー) | 震源で起きた断層運動 | 地震ごとに単一の値 | 地震の“規模”比較、津波規模の初期見積もり |
| 震度 | ある地点の揺れの強さ | 観測点(距離・地盤・建物に依存) | 地点ごとに異なる | 被害想定・現場の安全判断・緊急対応 |
要点:Mは“地震の強さの元(エネルギー)”、震度は“あなたのいる場所の揺れ”。
32倍ルールを体感する(直感のための例)
| 差 | エネルギー比 | イメージ |
|---|---|---|
| M4 → M5 | 約32倍 | 手持ち花火 → 焚き火(規模感の差) |
| M5 → M7 | 約1000倍 | 小型発電機 → 小規模発電所(放出量の桁違い) |
| M6.8 → M7.8 | 約32倍 | 同じ“強い地震”でも桁違いのエネルギー |
実際の被害は震源深さ・距離・地盤・建物で大きく変わります。Mだけで被害は決まりません。
マグニチュードの種類と算出法|リヒターからMwへ
主なスケールと用途の違い
| 記号 | 名称 | 仕組みの要点 | 長所 | 限界/注意 |
|---|---|---|---|---|
| M(リヒター) | 局地的マグニチュード | 地震計の振幅と震央距離で算出 | 浅く中規模の地震で有効 | 巨大地震で飽和、観測網の差を受けやすい |
| Mw | モーメント・マグニチュード | 地震モーメント M₀ = μ×S×Dに基づく | 巨大地震でも飽和しにくい世界標準 | 速報では参照データ確保まで時間が要る |
| Mj | 気象庁マグニチュード | 日本の観測網を用いた推定 | 日本域の速報で安定 | 海外値と若干の差が出ることあり |
計算式のイメージ(概念を掴む)
- リヒター:M=log10(A)+BM = \log_{10}(A) + B(A:振幅、B:距離補正)
- モーメント:Mw=23log10(M0)−CMw = \frac{2}{3}\log_{10}(M_0) – C(M0=μSDM_0=μSD、Cは定数)
- μ:岩盤の剛性、S:断層面積、D:すべり量
速報値・暫定値・確定値(値が“動く”理由)
- 速報値:発生直後。データが少なく誤差大。
- 暫定値:追加波形や広域観測を反映して更新。
- 確定値:断層モデル・長周期データまで加味して安定。
ニュースの「M◯◯→◯◯に更新」は普通。値が動く=解析が精緻化のサインです。
参考:規模と断層サイズの目安(概略)
| Mw | 断層長さ | 断層幅 | すべり量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10〜20 km | 数km | 数十cm | 直下型で強い揺れも |
| 7.0 | 40〜80 km | 10〜20 km | 1〜2 m | 広域で強震、余震活発 |
| 8.0 | 200 km級 | 数十km | 数m以上 | 海溝型で津波リスク大 |
| 9.0 | 500 km級 | 数十〜100 km | 数十m | 超巨大、長周期影響広域 |
※地質条件で大きく変動。あくまでイメージ。
マグニチュードと震度の関係|“同じMでも揺れが違う”のはなぜ?
震度が変わる主因(M以外の要素)
| 要素 | 影響 | 具体例 |
|---|---|---|
| 震源深さ | 浅いほど地表で強く、深いほど広域で中程度 | M6でも深さ10kmは強震、100kmは広域で震度3〜4 |
| 震源距離 | 近いほど大、遠いほど小 | 震央直下は震度6強、100km離れると震度3など |
| 地盤条件 | 軟弱地盤は増幅・長周期化 | 造成地・埋立地は長く大きく揺れやすい |
| 建物特性 | 高層は長周期に共振 | 同じ町内でも階・構造で体感が違う |
震度階級と影響の目安(簡易早見表)
| 震度 | 体感・屋内 | 屋外・構造 |
|---|---|---|
| 震度3 | 室内で揺れに気づく | つり下げ物が少し揺れる |
| 震度5弱 | 棚の物が落ちることがある | 家具の固定がないと移動 |
| 震度6弱 | 立っていられない | 壁にひび、ドア変形 |
| 震度7 | 多くの家具が転倒 | 木造の倒壊・インフラ被害 |
震度は地点ごとの観測値。同じ地震でも地図上で色分けされた“ばらつき”として表れます。
よくある誤解と正しい理解
- 誤「Mが1違うだけなら大差ない」→ 正:エネルギーは約32倍。
- 誤「Mが大きい=どこでも被害大」→ 正:被害は深さ・距離・地盤・建物で大きく変動。
- 誤「震度は全国一律で同じ」→ 正:地点ごとに大きく分布。同じ市内でも差が出る。
計測震度の仕組み(基礎)
- 加速度センサーで地表や建物1階の揺れを計測し、周波数成分を加味した演算で「計測震度」を算出。
- 人の感じ方だけでなく、揺れの速度・継続時間なども影響。だから同じMでも表示が異なるのは自然なことです。
過去の大地震で見るマグニチュードと影響
主要事例の比較(数値は代表値・概略)
| 年・地震 | マグニチュード | 最大震度 | 特徴(概要) |
|---|---|---|---|
| 1995 阪神・淡路 | M7.3 | 震度7 | 浅い直下型。都市直撃で強震域は狭いが被害甚大 |
| 2011 東日本 | M9.0 | 震度6強 | 極めて巨大な海溝型。津波と長周期影響が広域 |
| 2016 熊本 | M7.0(本震) | 震度7 | 活断層帯の連動。強い余震活動が長期化 |
| 2018 北海道胆振東部 | M6.7 | 震度7 | 斜面崩壊が多発。地盤条件の影響が顕著 |
学び:同じ“強震”でも、浅い直下型と巨大海溝型では被害の質が違う(倒壊/津波/長周期)。
Mが大きいほど起きやすい現象(傾向)
- M7台:広域で震度6前後、断水・停電などライフライン被害。
- M8台:津波リスクが高く、沿岸は高台避難が最優先。
- M9級:超長周期の揺れが広域に到達。高層・大型構造物で長い揺れ。
事例からの実務ポイント(型別対策)
- 直下型(内陸):家具固定と**初動(Drop/Cover/Hold on)**が生死を分ける。
- 海溝型(海域):揺れが収まったらただちに高台。情報待ちより先に動く。
- 長周期地震動:高層階はエレベータ停止・長揺れを想定。ヘルメットと靴を常備。
地震情報の読み解き方と備え|“数値→行動”に変える
速報・警報の見方(混乱しないために)
- 震度速報:まず自分の地点の震度を確認。余震に備える。
- マグニチュード速報:値は更新前提。Mの大小だけで避難判断しない。
- 津波情報:沿岸部は揺れが強く/長いとき迷わず高台へ。発表前でも先に動く。
家庭・職場の行動フロー(テンプレート)
| フェーズ | 家庭 | 職場 |
|---|---|---|
| 揺れの最中 | 頭を守る・低く・動かない | 机下退避・機械停止・火気確認 |
| 直後〜10分 | 出口確保・火元/ブレーカー確認 | 安否点呼・初期消火・設備点検 |
| 10分〜1時間 | 家族連絡・避難の要否判断 | 代替拠点/BCP切替・情報収集 |
| 1日以内 | 水・食・衛生の確保 | 業務優先度の再設定・シフト調整 |
今日からできる“数値に強い備え”
- ハザードマップで自宅・職場の地盤/津波/土砂のリスクを確認。
- 非常用:水(1人1日2〜3L×3日分)・ライト・モバイル電源・常用薬・衛生品。
- 住環境:家具固定・飛散防止・通路確保。寝室の足元に靴・手袋・ライト。
- 家族連絡:集合地点(近隣/広域)と定型文(安否/現在地/次の行動)を端末に保存。
60秒クイックフロー(印刷して玄関へ)
- 揺れ→ 頭を守る/低く/動かない
- 停止→ 火気・機械・エレベータの利用中止
- 確認→ 出口確保・落下物・ガス/ブレーカー
- 連絡→ 家族の安否と定型文送信
- 判断→ 津波/火災/倒壊リスク→避難の要否
よくある質問(FAQ)と誤解の修正
Q1. Mが大きいのに自宅はほとんど揺れなかったのは?
A. 震源から遠い/深い、地盤が固い、建物の固有周期と合わなかった等の要因。震度は地点差が大きいのが普通です。
Q2. 海外のMwと日本の速報値で数値が違う?
A. 演算手法・観測網・参照データの違いにより数値のブレが出ます。確定値で近づくことが多いです。
Q3. 「余震の方が大きくなる」ことはある?
A. まれに本震・余震の判定が入れ替わるケースはありますが、統計的には本震が最大です。いずれにせよ強い揺れに備える行動は同じ。
Q4. Mいくつで家は倒れる?
A. 倒壊はM」ではなく「あなたの地点の震度×建物条件で決まります。家具固定・耐震が最優先です。
まとめ|マグニチュードを正しく理解して行動へ
- マグニチュードは地震の規模(エネルギー)、震度は地点の揺れの強さ。
- M+1で約32倍のエネルギー差。ただし被害は深さ・距離・地盤・建物で変わる。
- 過去事例から、直下型/海溝型/長周期で対策が異なると理解する。
- 数値を見たら行動に翻訳:家具固定、持ち出し袋、家族ルール、避難経路の確認を今日やる。
数字の理解は“恐れを減らす力”。次に地震速報を見たら、「何を確認し、どう動くか」を1枚のメモにしておきましょう。