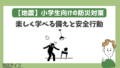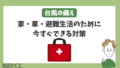地震は**「起きてから」ではなく「起きる前」の準備が命運を分けます。とくに家族は年齢・体力・役割がバラバラ。誰か一人の備えでは不十分です。この記事は、家の安全づくり、持ち出し袋と在宅備蓄、家族連絡と集合ルール、在宅避難・避難所生活の運用、復旧までの段取りを家族単位で総整理。実務で即使えるチェック表・早見表・テンプレ文例**を豊富に盛り込み、今日から動けるガイドに仕上げました。
1. 家族でできる地震の備え
家の中の安全対策(住まい別)
共通の原則
- 大型家具は必ず固定(L字金具+突っ張り棒+耐震ジェルの三点併用)。就寝スペース・出入口動線から倒れ物を遠ざける。
- 飛散対策:窓は飛散防止フィルム、食器棚は耐震ロック。観音扉・引き戸のロック忘れに注意。
- 安全ゾーンを決めて共有:テーブル下/柱際/座布団やヘルメットの位置を目を閉じても分かるように。
戸建ての場合
- 階段・吹き抜け周りに物を置かない。倒木・瓦の落下を想定し、玄関外側にも靴を1足配置。
- ガスメーター・ブレーカーの位置を家族で確認。外壁のヒビ・瓦・塀は定期点検。
マンションの場合
- 高層階は揺れが増幅。天井照明の落下対策(ワイヤー)と家具の前後揺れ対策を強化。
- エレベーター閉じ込めに備え、各階避難口を把握。共用部にヘルメット・担架の有無を確認。
10分でできるミニ点検
| 項目 | いまの状態 | 対応(期限) |
|---|---|---|
| 本棚・冷蔵庫の固定 | している/未実施 | 金具を購入し週末に設置 |
| ガラス飛散対策 | 済/未 | フィルムを今週中に貼付 |
| 枕元の安全セット | 懐中電灯・笛・靴 | 今日中に設置 |
| ガス/電気の遮断位置 | 家族が把握/不明 | 今夜の家族会議で共有 |
防災グッズの準備(持ち出し+在宅)
- 家族ごとに持ち出し袋(7~10kg目安)。共有品(テント・鍋・カセットコンロ・衛生大量備品)は家長バッグに集約。
- 水と食料は最低3日、理想7日。水は1人1日3L(飲用+調理/衛生)。
- 電源の複線化:モバイル電源+手回し発電+ソーラー。ケーブルはUSB-C/Lightning/USB-Aを2系統ずつ。
持ち出し袋チェック表(基本版)
| 区分 | アイテム | 目安・コツ |
|---|---|---|
| 水・食 | ペットボトル水、カロリーバー、アルファ米 | 3日分を個人袋へ。塩飴/経口補水粉末を少量追加 |
| 照明・通信 | LEDヘッドライト、ラジオ、モバイルバッテリー | ヘッドライト優先で両手を空ける |
| 衛生 | 簡易トイレ、ウェットティッシュ、消毒、マスク | トイレは1人/日3~5回×3日分 |
| 衣類・防寒 | 速乾下着、靴下、薄手ダウン、レインウェア | 圧縮袋で省スペース |
| 書類 | 身分証コピー、保険証写し、現金(小銭) | ジップ袋で防水 |
在宅備蓄の早見表(7日分)
| 人数 | 水(3L/日) | 主食(食/人) | 簡易トイレ(回/人) | 燃料(CB缶) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 21L | 21食 | 30~35 | 3~4 |
| 3人 | 63L | 63食 | 90~105 | 8~10 |
| 5人 | 105L | 105食 | 150~175 | 12~15 |
家族会議で決める3点(雛形付き)
- 集合場所:第1(近場の公園)/第2(避難所)/夜間代替(24h開放の施設)。
- 連絡手段の優先順位:家族LINE→SMS→災害用伝言ダイヤル171→避難所掲示板。
- 役割分担:初動(ガス/ブレーカー)/安否連絡/幼児・高齢者介助/ペット担当。
家族防災カード(メモ雛形)
- 氏名/血液型/持病・アレルギー/常用薬
- 連絡先(家族・親戚2名)/集合場所(第1・第2)
- 最寄り避難所名・住所/通学・通勤経路の退避ポイント
非常連絡テンプレ(SMS例)
00:00定時連絡/【氏名】無事/居場所:自宅前/次は01:00連絡/第1集合へ移動中
90日アクションプラン(平常時の訓練)
| 週 | 重点タスク |
|---|---|
| 1 | 家具固定・飛散フィルム・枕元セット |
| 2 | 持ち出し袋作成(個人)・共有品リスト化 |
| 3 | 在宅備蓄の購入(7日分) |
| 4 | 家族会議:集合場所/連絡/役割決定 |
| 5 | 避難ルート徒歩確認(昼/夜) |
| 6 | 171・Web171の試用練習 |
| 7 | 季節用品(防寒/暑熱)入替え |
| 8 | 近隣の安否確認ネットワーク作り |
| 9 | 総合ドリル:夜間想定で30分訓練 |
2. 地震発生時の行動
シーン別の初動
家の中
- まず身を守る:机の下で頭部を保護、揺れの最中は走らない。ガラス・食器棚から離れ、靴(厚底スリッパ可)を履く。
- 火の始末は揺れが収まってから。外出避難時はブレーカーを最後に落として通電火災予防。
就寝中
- 枕で頭を覆い、ベッド下や周囲の落下物を回避。足元の靴・ヘッドライト・笛を着用。
調理中
- 揺れたら火元から離れ、揺れ収束後に消火。油鍋はフタで覆って酸素遮断。
エレベーター内
- すべての階ボタンを押し、止まった階で降りる。閉じ込め時は非常ボタンで通報し、無理な脱出をしない。
屋外・ビル街
- 外壁・看板・ガラスから離れ、建物の陰にならない広い場所へ。バッグや上着で頭部保護。
津波警報エリア
- 強い揺れや長くゆっくりした揺れを感じたら、ためらわず高台へ。車は渋滞回避のため原則徒歩。
家族と離れた時の行動
- 事前に決めた集合場所へ自力移動。通信節約のため毎時00分の定時連絡を採用。
- 171/WEB171の操作を家族で年1回練習。
- 児童・高齢者には**「名前・集合場所・連絡先」を口頭で伝える練習**をさせる。
0~10分のタイムライン(目安)
| 時間 | 行動 |
|---|---|
| 0–1分 | 身の安全確保(頭部保護・退路確保) |
| 1–3分 | 出火確認・初期消火可否判断 |
| 3–5分 | 家族の安否呼びかけ・負傷確認 |
| 5–8分 | 情報収集(ラジオ/防災アプリ)・避難判断 |
| 8–10分 | ブレーカー処置→集合場所へ移動/在宅継続 |
行動フロー(文字版)
- 身の安全 → 2) 出火確認 → 3) 安否呼びかけ → 4) 情報収集 → 5) 避難or在宅判断 → 6) 集合・点呼
3. 避難の準備と持ち物
非常用持ち出し袋(実務版)
| カテゴリ | 必須 | あると強い | ひとことアドバイス |
|---|---|---|---|
| 水・食 | 水3L/日×3日、主食(米/パン/バー) | 経口補水、塩飴、ナッツ | 家族の嗜好1品で士気UP |
| 情報・電源 | 手回しラジオ、モバイル電源、ケーブル | ソーラーチャージャー | コードは2系統(USB-C/Lightning) |
| 衛生・トイレ | 簡易トイレ15回/人、マスク、除菌 | 速乾タオル、歯みがきシート | におい対策袋は必須 |
| 衣類 | 速乾下着×2、靴下×2、薄手ダウン | 雨具、手袋、ネックウォーマー | 季節替えを忘れずに |
| 医療 | 常用薬、絆創膏、鎮痛解熱、消毒 | 三角巾、テーピング | 持病メモは外ポケットに |
| 書類・現金 | 身分証コピー、保険証写し、現金1~3万円 | 小銭(公衆電話) | A6防水ポーチで一括管理 |
5分で持ち出す“ミニキット”
- 水500ml・栄養バー2本・簡易トイレ2回分・ヘッドライト・小型モバイル電源・現金小銭・マスク2枚・笛。
車載キット
- 給水タンク10L・ブースターケーブル・反射ベスト・アルミシート・作業手袋・タイヤチェーン/携帯スコップ(冬)。
避難所での運用
- 入所時に家族名簿(人数・年齢・持病)を提出すると支援がスムーズ。
- 貴重品は分散管理。就寝時は枕下、バッグは荷札+南京錠で識別。
- 感染症対策:マスク・手指衛生・こまめな換気。ゴミは臭気対策袋で密封。
在宅避難の運用
- **複合停止(電気・水・ガス)**に備える:カセットコンロ+CB缶6本、給水タンク、ポリ袋、ラップ、使い捨て食器。
- 冬は断熱カーテン・床ラグ・アルミシート、夏は遮光シート・電池/USB扇風機で温度管理。
- 室内の安全導線(玄関→トイレ→寝室)は段ボールで養生し、裸足禁止を家族合言葉に。
4. 家族ごとの防災対策(きめ細かく)
乳幼児・子どもがいる家庭
- ミルク・離乳食・オムツは多め(最低5日、可能なら7日)。液体ミルクは夜間・外出時に有効。
- 安心グッズ(ぬいぐるみ、ブランケット)を1つ。迷子札は氏名・保護者連絡先・アレルギーを明記。
- 学校・園ルートの安全ポイント(交番・店舗)を親子で歩いて確認。引き渡し訓練の日程も共有。
妊娠中・月経中の配慮
- 母子健康手帳・産科連絡先・マタニティマーク。腹部を圧迫しない衣類とカフェインレス飲料を確保。
- 生理用品は1週間分+消臭袋。下着は吸水ショーツなど洗濯簡便なものを。
高齢者・持病がある家族
- 常用薬2週間分+お薬手帳コピー。眼鏡・補聴器・電池の予備。
- 移動補助具は取り出しやすく。段差スロープと夜間足元灯を設置。
- CAPD・在宅酸素・CPAPなど電源依存機器は、ポータブル電源の出力・稼働時間を事前検証。
障害のある家族(視覚・聴覚・発達など)
- 触地図/点字メモや筆談ボードを用意。非常時のシンプル手順カードを色分けで提示。
- 過敏に配慮し、耳栓・ノイズキャンセル・サングラス・個室テント等で刺激を軽減。
ペットを飼っている家庭
- フード・水・トイレ砂は7日分。キャリー・リード・鑑札は玄関に吊るし即持出。
- 受入可否は自治体要綱を事前確認。同室不可の可能性を見越し、ケージカバー・静音毛布で鳴き対策。
- 迷子対策:名札・マイクロチップ登録、写真を印刷して持参。
5. 地震後の対応と復旧計画(総まとめ)
直後~72時間の行動タイムライン
| フェーズ | 目安 | 行動 |
|---|---|---|
| 超初動 | 0–10分 | 身の安全→出火確認→安否呼びかけ→情報収集→避難判断 |
| 初日 | 0–24h | 集合・点呼、負傷手当、断水/停電対策、トイレ運用開始、在宅or避難所を確定 |
| 2日目 | 24–48h | 物資の節度ある使用、携帯充電計画、近隣安否確認、家屋の一次点検 |
| 3日目 | 48–72h | 罹災証明用の写真・記録、保険連絡、後片付けのPPE装備、メンタルケア開始 |
家屋・ライフラインの安全確認
- ガス:臭気・メーター表示確認。異常時は復旧を専門業者に一任。
- 電気:冠水・漏水が疑われる場合は通電前に点検。ブレーカーは系統ごとに段階投入。
- 水道:濁り水は飲用禁止。生活用水は風呂水・給水所・雨水で区別管理。
片付けと衛生(NG→正解)
| よくあるNG | 正解 |
|---|---|
| 素手・布手袋だけで片付ける | 耐切創手袋+ゴーグル+マスクでPPE徹底 |
| 濡れた場所から無計画に作業 | 上→下、乾→湿の順で効率化 |
| 生ごみと汚物を同袋で保管 | 臭気遮断袋と二重袋で衛生管理 |
罹災証明・保険請求のコツ
- 被害箇所を広角→中景→接写の順で撮影(日時入り)。
- 家財は品目リスト化し、購入年月・概算額をメモ。領収書・保証書・シリアル写真を添付。
- 申請窓口・必要書類は自治体HPで確認。平時に下書きまで済ませておくと迅速。
心のケアと家族コミュニケーション
- **PFA(心理的応急処置)**の基本:安全の確保・落ち着き・つながり・実用的支援・希望。
- 子どもへは事実を短く・安心を長く伝える。「大丈夫、ここは安全。次は水を飲もう」など具体的行動を伴う声かけ。
- 睡眠・栄養・会話の三本柱で回復を支援。無理を感じたら休む合図を家族で決めておく。
家族で見直すチェックリスト
- 家具・家電の固定は完了している
- 持ち出し袋・在宅備蓄を7日分へ更新
- 連絡手段(LINE/SMS/171)の役割と時刻を統一
- 集合場所(第1・第2)と徒歩ルートを再確認
- 乳幼児・高齢者・ペットの専用物資を季節更新
- ポータブル電源と燃料の安全保管を確認
リカバリープランの要点
- 片付けは小さな成功を積む順番で(玄関→寝室→水回り)。
- 近隣と物資・情報の相互支援を約束。掲示板や回覧で可視化。
- ボランティア・炊き出し・相談支援を遠慮せず活用。家族の体力を温存するのも重要な戦略。
さいごに(今週末からの3ステップ)
- 決める:集合場所・連絡優先順位・役割分担を家族会議で確定。
- 揃える:持ち出し袋と在宅備蓄を7日分まで一気に底上げ。
- 練習する:夜間想定の避難ドリルと171訓練を実施。
準備は最大の安心です。この記事の表と雛形を活用し、今日から、家族全員の命を守る段取りを整えてください。