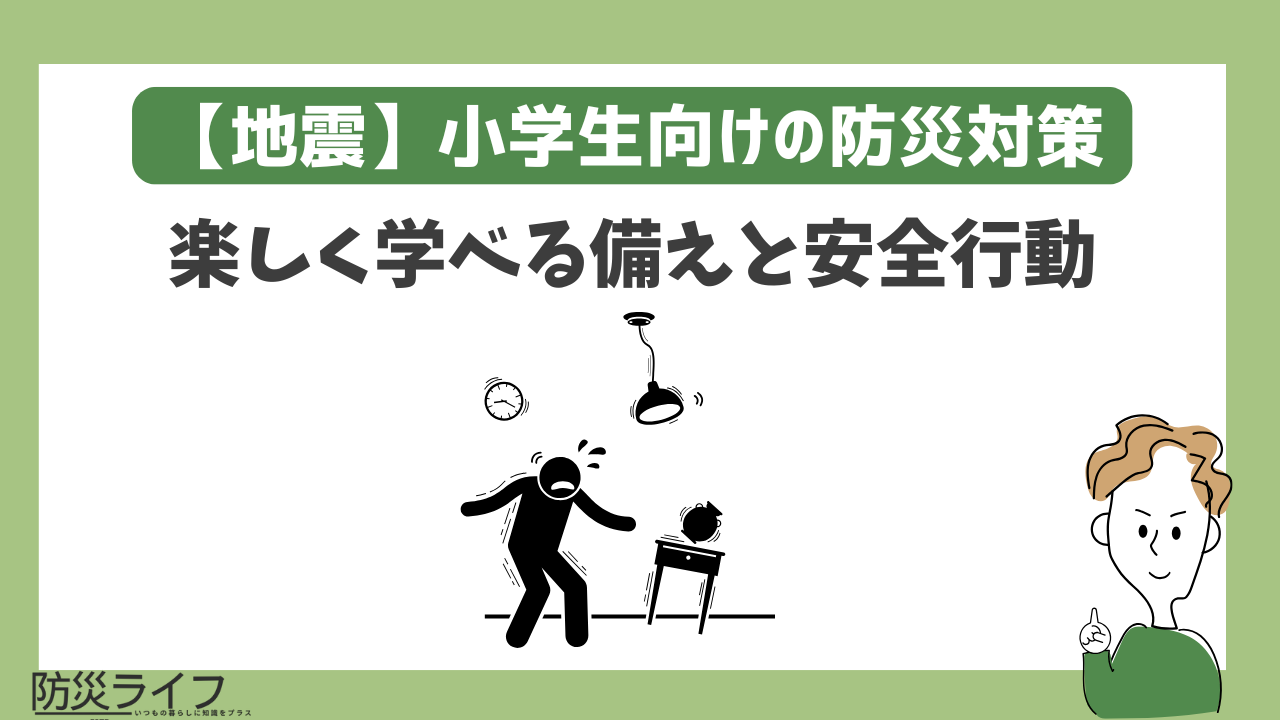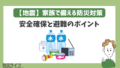はじめに|小学生もできる「地震の備え」
日本は地震が多い国です。いつ地震が起こっても安全に避難できるよう、小学生でも自分でできる防災対策を知っておくことが大切です。「地震が起こったらどうすればいいの?」「家族と離れていたら?」といった疑問に答えながら、楽しく学んで身につく方法を紹介します。
このガイドでは、小学生が自分でできる地震対策・避難方法・家族との話し合いポイントを、図解感覚でわかりやすくまとめました。家族みんなで読み、今日から練習しておきましょう。最後にチェックリストやゲーム、会話の例も付けています。
1. 小学生が地震の前に準備すること
家の中の“安全ゾーン”づくり
- 家具を固定し、本棚やタンスはL字金具・耐震ジェルで倒れにくくする。
- ガラスの飛散防止フィルムを窓や食器棚に貼ってケガを防ぐ。
- 倒れ物の少ない場所、**机の下・部屋の隅(柱の近く)**などを“安全ゾーン”として家族で確認。
- 夜用の安全:ベッドの横にスニーカー/ヘッドライト/手袋。ガラス片から足を守る。
- ペットがいる家は、ケージやリードの場所も決め、逃げ出さない工夫を家族で共有。
マイ防災リュックをつくる
- 水(500ml×1〜2本)・非常食(ビスケット/ゼリー/レトルト)。
- ライト(小型・頭につけるタイプが便利)・ホイッスル。
- 家族の連絡先カード、ティッシュ、タオル、常備薬、絆創膏、マスク。
- 予備のメガネやモバイルバッテリー(家の人用でもOK)。
- 重すぎないように体重の10〜15%を上限に。肩ひも・胸ベルトを調整して両手が空くように背負う。
家族との“約束カード”を作る
- **集合場所(第1・第2)**を決め、地図で印をつける。
- 電話が使えないときの**伝言方法(災害用伝言ダイヤル171/伝言板)**を確認。
- 帰宅ルートと避難所を親子で歩いてチェック。ブロック塀・古い看板・狭い路地などの危険も記録。
- **合言葉(パスワード)**を決め、見知らぬ人に声をかけられてもそれがない限りついていかない。
準備チェック表(印刷して貼ろう)
| 項目 | できたらチェック | メモ |
|---|---|---|
| 家具の固定を確認した | □ | 固定していない棚は? |
| 安全ゾーンを決めた | □ | どの部屋のどこ? |
| マイ防災リュックを用意 | □ | 重さ・背負いやすさOK? |
| 家族の約束カード作成 | □ | 集合場所2か所書いた? |
| 避難所まで歩いてみた | □ | 危ない場所は? |
| 靴・ライトを枕元に配置 | □ | 夜の備え完了? |
危険ポイント観察シート(家の周り)
| 場所 | 危険になりそうなもの | どう避ける? |
|---|---|---|
| ○○通り | 古いブロック塀 | 反対側の歩道を通る |
| ○○公園入口 | 大きいガラスの看板 | 離れて歩く・横断しない |
| 学校までの路地 | 電柱・配線が低い | 迂回ルートを決める |
2. 地震が起きた瞬間の“安全行動”
家の中にいるとき
- まず低く!頭を守る!動かない!(Drop・Cover・Hold on)
- 机の下に入り、片手で脚をつかみ、もう片手で頭を守る。
- 窓・家具・家電から離れる。揺れが収まるまであわてて動かない。
- ガス火は揺れが収まってから消す。火元に近づくときは落下物に注意。
学校や外にいるとき
- 学校では先生の指示に従う。廊下は壁側で頭を守る姿勢。
- 公園や広場では建物・看板・ガラス・電柱から離れる。
- 商業施設では案内放送に従い、エスカレーターやエレベーターを使わない。
- 海辺・川辺にいたらすぐに高い場所へ(津波の可能性を考える)。
家族と離れていたら
- 事前に決めた避難集合場所へ向かう。無理なら近くの大人や学校/交番へ。
- 見知らぬ人にはついていかない。困ったら大きな声で助けを呼ぶ。
- 171/ウェブ伝言板の使い方を家で練習しておく。
状況別 行動早見表
| いる場所 | まずやること | 次にすること |
|---|---|---|
| 家の中 | 机の下で頭を守る | ガス火の確認→落下物に注意して移動 |
| 学校 | 先生の指示に従い姿勢を低く | 指示で整列→避難経路へ |
| 外 | 建物・ガラス・電柱から離れる | 広い場所で待機→情報収集 |
| 夜間 | ライトで足元確認・靴を履く | 破片を避けて安全ゾーンへ |
| 雨の日 | 屋根や看板の下に近づかない | 水路・マンホールを避ける |
やってはいけないNG例
- 揺れている最中にむやみに外へ飛び出す。
- エレベーターに乗る/閉じこもる(最寄り階で降りる)。
- 裸足で移動(破片でけが)。
3. 避難のしかたと持ち物・マナー
小学生が“自分で持つ”最小アイテム
- 水(500ml)・非常食(飴/ビスケット)・タオル/ハンカチ。
- ホイッスル・小型ライト・家族連絡先カード。
- マスク・ティッシュ。ポーチ1つにまとめて常時携帯。
- 可能なら**小銭(硬貨)**を少量。公衆電話用に役立つことがある。
避難所での過ごし方(マナー)
- 順番を守る・大きな声で走らない・ゴミを持ち帰る。
- 体調が悪い人や小さな子を手伝う・ゆずる気持ちを大切に。
- 夜はライトは下向きに。周りが休めるよう静かに。
- 体調チェック:のどの渇き・頭痛・お腹の調子を大人に伝える。
服装と持ち物の工夫
- 歩きやすい靴、夜は反射材があると安全。
- 冬は防寒着/手袋/ニット帽、夏は帽子/汗拭き。
- 両手が空くリュックが基本。片手持ちは転倒リスク増。
持ち物ミニチェック(外出用ポーチ)
| アイテム | 用途 | 持った? |
|---|---|---|
| 水500ml | のどの渇き・熱中症対策 | □ |
| 飴・ビスケット | エネルギー補給 | □ |
| ホイッスル | 助けを呼ぶ | □ |
| 小型ライト | 夜間移動 | □ |
| 連絡先カード | 家族と連絡 | □ |
| マスク | ほこり・感染対策 | □ |
避難所での1日の過ごし方(例)
| 時間 | すること | ポイント |
|---|---|---|
| 朝 | 体調チェック・水を飲む | のどの渇きの前に補給 |
| 午前 | 勉強・本読み・お手伝い | 体を軽く動かす |
| 昼 | 食事・片付け | 手指を消毒する |
| 夕方 | ストレッチ・散歩 | 余震や情報に注意 |
| 夜 | 明日の準備・就寝 | ライトは下向きで静かに |
4. 家族で取り組む“楽しい防災訓練”
ゲーム感覚で身につける
- 「どこに隠れる?」ゲーム:家の各部屋で安全ゾーンを10秒で指さし。
- 「防災リュッククイズ」:10個の中から“本当に必要な5個”を選ぶ。
- 「避難ルート探検」:信号・ブロック塀・狭い道など危険ポイントを地図にメモ。
- 「暗闇歩き練習」:停電を想定し、懐中電灯で歩行練習(大人と一緒に)。
学校・地域の訓練を活用
- 年2回以上の避難訓練に必ず参加。
- 走らない・押さない・しゃべらない・戻らないを合言葉に。
- 集合場所・一時避難所・広域避難地のちがいも学ぶ。
- 地域のハザードマップを親子で確認し、水害や津波の危険も把握。
“わが家の防災ノート”を作る
- 家族の顔写真・連絡先・持病やアレルギーを1枚に。
- **合言葉(パスワード)**を決めて、受け渡し時の本人確認に活用。
- 月1回、中身の見直し日をカレンダーに設定。
- 連絡先リスト:学校・学童・塾・祖父母・近所の連絡先も記載。
家庭訓練のスケジュール例
| いつ | すること | 目安時間 |
|---|---|---|
| 毎月第1日曜 | リュック点検・電池交換 | 15分 |
| 学期はじめ | 避難ルート歩行・集合場所確認 | 30分 |
| 雨の日 | 室内で安全ゾーン確認ゲーム | 10分 |
| 長期休み前 | 祖父母の家の避難確認・伝言ダイヤル練習 | 20分 |
声かけ・会話の例(ロールプレイ)
- 親:「地震が来たらどうする?」
- 子:「まず低く、頭を守って、動かない!」
- 親:「家族と会えないときは?」
- 子:「集合場所1の公園。行けなければ近くの大人や学校に行って171で伝言!」
5. 地震後の“からだ・こころ・連絡”ケア
からだを守る基本
- 靴を履いて移動(ガラス片対策)。手袋があればさらに安全。
- 水分・甘いものでエネルギー補給。無理に動き続けない。
- 余震の間は落下物が少ない場所で待機。高い棚の近くは避ける。
- トイレが心配なときは早めに大人へ相談。長い列を避けるため時間をずらす。
こころを落ち着かせる
- ゆっくり深呼吸(4秒吸って6秒吐くを5回)。
- お気に入りのぬいぐるみ/本/音楽で安心感を取り戻す。
- 怖かったことは家族や先生に話す。言葉にすると楽になる。
- 日記やメモで嬉しかったことも1つ書くと、気持ちのバランスがとれる。
連絡の取り方(家族と会えないとき)
- 災害用伝言ダイヤル(171):親の番号に「1→録音」「2→再生」。
- ウェブ伝言板:文字で安否を書き込む。学校で練習しておく。
- 避難所で名前・学校名をスタッフに伝える。むやみに離れない。
連絡先カード 見本
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 名前 | 山田 はると |
| 学校・学年 | ○○小 3年 |
| 家族の電話 | 090-××××-×××× |
| 集合場所1 | ○○公園 時計台前 |
| 集合場所2 | ○○小 体育館入口 |
| アレルギー | そば・ピーナッツ |
| 合言葉 | あおいそら |
よくあるQ&A
- Q. 机が近くにないときは?
- A. ランドセルや腕で頭を守り、低くなる。落下物の少ない壁際へ。
- Q. 停電で真っ暗なときは?
- A. その場で動かず、ライトや大人を待つ。ガラス片に注意。
- Q. 家に1人のときに大地震が来たら?
- A. 身を守る→火の確認→連絡カードの順で。無理に外へ出ない。
6. 季節・時間帯で変わる対策
夏(熱中症に注意)
- 水・塩分・日陰の3点を意識。帽子・冷却タオルをリュックに。
- 避難所でもこまめに水分。スポーツドリンク粉末が便利。
冬(低体温症に注意)
- カイロ・手袋・厚手靴下をプラス。アルミブランケットは軽くて暖かい。
- 体を冷やさないよう、床にはマットや段ボールを敷く。
夜間・雨天
- 枕元ライト・反射材つきベスト。ぬれた路面での転倒に注意。
- マンホール・側溝に近づかない。水位が上がっている道は通らない。
7. みんなで助け合うために(配慮とルール)
小さな子・高齢の人への配慮
- 列で前をあけ、ゆっくり歩く。段差では声をかける。
- 体調が悪そうなら大人へ知らせる。無理に支えず周囲に協力を求める。
アレルギー・持病のある友だち
- 食べ物を分ける前に成分・アレルギーを確認。
- お薬や吸入器の置き場所を本人・家族と共有しておく。
情報の取り扱い
- 噂話は広めず、先生・保護者・自治体の情報を優先。
- SNSを見るときは公式発表を確認する(保護者と一緒に)。
まとめ|小学生でも“今日からできる”地震対策
地震は突然やってきます。事前の準備・その場の安全行動・家族との約束がそろえば、慌てずに行動できます。まずは家の安全ゾーン確認、防災リュックづくり、集合場所の共有、そしてゲーム感覚の訓練からスタートしましょう。続けるほど、自分と家族を守る力は確実に強くなります。
チェックリスト(今日から5つ)
- 家の安全ゾーンを家族で確認する。
- マイ防災リュックを“軽く・必要最小限”で整える。
- 集合場所と171の使い方をカードに書く。
- 月1回の“防災点検日”を決める。
- 避難ルートを一緒に歩き、危険ポイントを地図に記す。
合言葉:ひくく・まもる・うごかない → そのあとしらせる・あつまる。
備えは“できたら終わり”ではなく、続けるほど強くなる。今日から小さな一歩を積み重ねていきましょう。