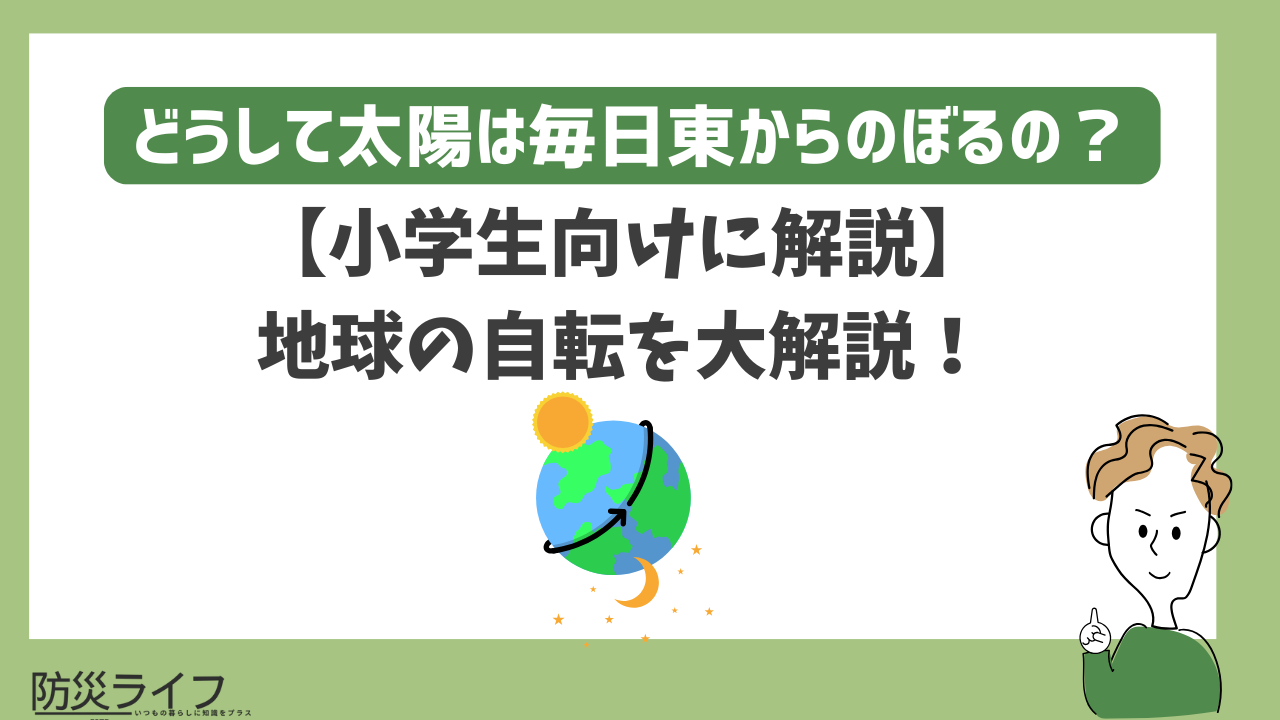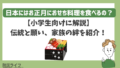「なぜ毎朝、太陽は東の空からのぼるの?」――答えは、地球が自分で回っている(自転)から。この記事では、東からのぼるしくみを中心に、朝・昼・夕・夜の移り変わり、季節や場所によるちがい、世界の時差、そして自由研究に使える観察・実験・工作まで、たっぷり&やさしく解説します。家でも学校でも使える表・ワークシート付き。安全に観察するコツもまとめました。
まずは3分でわかる!今日の超重要ポイント
- 地球は24時間で1回転(自転)。回る向きは西 → 東。
- そのため太陽は東からのぼり西にしずむように見える(※見かけの動き)。
- 地球の軸(地軸)は約23.4°かたむき、季節や日の出の位置・太陽の高さの変化を生む。
- 場所(緯度)と季節で、影の長さ・日照時間・空の色が大きく変わる。
- 標準時と時差のおかげで、世界の国々はそれぞれ違う「朝・昼・夜」。
- 観察のコツは**「同じ場所・同じ物・同じ時刻」、そして「太陽を直視しない」**!
合言葉:「地球が回る → 空が動くように見える」
地球の自転と太陽の見え方の基本
地球は24時間で1回転する
地球は“地軸(ちじく)”という見えない軸を中心に、24時間で1回転します。赤道では時速約1,670kmという超スピード。わたしたちも地面といっしょに動いているので、風のように感じないだけです。この回転が、朝 → 昼 → 夕方 → 夜という1日のリズムを作ります。
回る方向が「東からのぼる」を生む
地球は西から東へ回転。だから空では太陽が東からのぼり西にしずむように“見え”ます。もし地球が逆向きに回っていたら、毎朝「西」からのぼって見えたはず。本当に動いているのは地球のほうだと覚えよう。
地軸の傾きが季節のヒミツ
地軸は約23.4°かたむいています。この傾きと1年で太陽のまわりを1周する公転が合わさり、季節(春夏秋冬)・昼の長さ・太陽の高さ・日の出の方角の違いが生まれます。
「なぜ回っているのに目が回らないの?」(やさしい科学)
地球はとてもなめらかに一定の速さで回っているので、体は回転を感じにくいのです(電車に静かに乗っていると、動いていることをあまり感じないのと似ています)。
太陽が東からのぼる理由を模型で理解
「見かけの動き」を知ろう
空の太陽が動いているように見えるのは、観察する私たち(地球)が回っているから。電車の中から外を見ると景色が動くように見える“見かけの動き”と同じだよ。
家でできるライト&ボール実験
用意するもの: 懐中電灯(太陽役)/ボール(地球役)/丸シール(日本の位置)
- 部屋を少し暗くして、懐中電灯を机の上で固定する(太陽はその場にいる想定)。
- ボールに日本の位置にシールを貼る。
- ボールを西→東向きにゆっくり回す(自転)。
- シールの場所が暗い→うす明るい→まぶしい→また暗いと変化=夜→朝→昼→夜!
コツ:ボールをすこし傾けて回すと、季節で太陽の高さが変わる様子まで再現できます。
方角と太陽の動きを地図で確認
地図アプリや学校の地図帳で、自分の町の東西南北をチェック。山やビルに隠れて見える位置は変わっても、太陽自体は必ず「東」方向からのぼります(季節で少しずれます)。
一日の空の変化と影の観察(実践編)
時間帯と空・影の変化(早見表)
| 時間帯 | 地球の向き(あなたの場所) | 太陽の高さ | 空・光のようす | 影の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 朝 | 光が当たり始める | 低い | うす明るい、白っぽい青 | とても長い |
| 昼 | まっすぐ光を受ける | 高い | いちばん明るい青 | いちばん短い |
| 夕方 | 光が弱まる | 低い | オレンジ〜ピンクの夕焼け | また長くなる |
| 夜 | 光が当たらない | なし | 星が見える/月が出る | 影は出ない |
影で「時間の流れ」を感じよう
- 日本(北半球)では正午ごろ、影は北向き。
- 影の先は西→東の向きにゆっくり動く。
- 同じ場所・同じ棒(ノーム)で朝/正午/夕方の影を比べ、長さを定規で測ってみよう。
安全ポイント(ぜったい守る!)
- 太陽を直接見ない(目をいためます)。
- 観察は日かげや帽子を使い、水分補給も。
- 望遠鏡やカメラで太陽をのぞかない(専用の減光フィルターが必要)。
季節・地域・時差でどう変わる?
季節で変わる「日の出の位置」と時刻(北半球の例)
- 夏:日の出は北寄りの東、日の入りは北寄りの西。太陽の弧が高く、昼が長い。
- 冬:日の出は南寄りの東、日の入りは南寄りの西。太陽の弧が低く、昼が短い。
- 春分・秋分:ほぼ真東からのぼり真西にしずむ。
月ごとのイメージ(中緯度:日本の多くの地域)
| 月 | 日の出の方角 | 太陽の弧の高さ | 日照時間の感じ |
|---|---|---|---|
| 1〜2月 | 南東寄り | 低い | 短い/寒い |
| 3月 | ほぼ東 | 少し高く | 中くらい |
| 6〜7月 | 北東寄り | 高い | とても長い/暑い |
| 9月 | ほぼ東 | 少し低く | 中くらい |
| 11〜12月 | 南東寄り | 低い | 短い/寒い |
緯度(いど)による違い
- 赤道ちかく:太陽は高く上がり、正午の影がとても短い。昼の長さはほぼ一定。
- 高緯度:太陽は低く、冬は一日中低い位置。北極圏では白夜(太陽がしずまない)や極夜(のぼらない)が起こる。
世界の時差と「同時に朝と夜」
地球が回るため、世界は時間帯がズレています。日本が朝でも、地球の反対側は夜。国ごとに標準時を決め、時計をそろえています。太平洋には日付変更線があり、その線を超えると日付が1日進む/戻ることも!
ミニ実験:家族や友だちが別の国にいたら、ビデオ通話で同じ瞬間の空を見せ合おう。片方が朝日、もう片方が夜空かも。
もっと深く!方角の覚え方・太陽時計・地方時の不思議
東西南北をからだで覚える遊び
- 朝、太陽に顔を向ける→その方向が東。
- そのとき右手が南、左手が北、背中側が西。
- 校庭で「東にジャンプ!」「北にダッシュ!」ゲームにすると楽しく定着。
かんたん太陽時計(サンドダイアル)の作り方
- 紙皿の中心にストロー(または割りばし)を垂直に立て、テープで固定。
- 正午ごろ、影の先を「12」として印をつける。
- 1時間ごとに影の先に点を打ち、線でつないで目盛りを完成。
- 別の日も使い、季節で影の軌道が変わることを観察しよう。
「正午」「南中(なんちゅう)」って?
太陽がいちばん高くなる時刻が南中。日本ではそのころ太陽は南の空に見え(北半球)、影は北側にできるよ。
ちょっと上級:地方時と均時差(きんじさ)
- 同じ日本でも、東西の場所で太陽の南中時刻は少しずつズレます(地方時)。
- そして「均時差」という影響で、太陽南中と時計の12時は年間を通して数十分のズレが生じます。自由研究で年間グラフにすると面白い!
空と光のふしぎ(やさしい科学)
- 大気の屈折:太陽が地平線ちかくにあると、光が空気で曲がり、実際より少し高く見える→日の出が早く/日の入りが遅く感じる。
- 夕焼けが赤いわけ:太陽の光のうち青い光は散らばりやすい。夕方は光の通り道が長くなり、青が消えて赤やオレンジが残る。
- だるま太陽・蜃気楼:空気の温度差で太陽の形が下ぶくれに見えることがある。観察メモに「今日は丸/ゆがみあり」と書こう。
- なぜ昼の方が暑いのは午後? 地面や空気が温まるタイムラグで、気温のピークは正午より少し遅れる。
生活・防災に役立つ「太陽と方角」
- 家の中:朝日が入るのは東向きの部屋。午後暑くなるのは西向きの部屋(西日)。洗たく物の干し方や観葉植物の置き場所に生かそう。
- 外での安全:夏の午後は日差しが強い。日陰・帽子・水分で熱中症対策。
- 防災:太陽の位置でおおよその方角が分かる。地図と合わせて避難ルートを家族で確認しよう。
自由研究アイデア集(選んでやってみよう)
- 影の長さカレンダー:毎月同じ日・同じ時刻に、同じ棒の影を測って折れ線グラフ化。季節でどう変わる?
- 日の出方角マップ:春分・夏至・秋分・冬至の前後で、日の出位置をスケッチして比較。
- 校庭温度と日照:晴れ/くもりの日で地面の温度と影の長さの関係を調べる。
- 太陽時計の精度テスト:自作目盛りと腕時計を比べ、ズレの理由(地方時・均時差)を考察。
- 世界の時差リレー:海外の友だち・家族に連絡し、同じ瞬間の空のようすを写真交換。
- 山やビルの影響研究:高い建物のある場所と広場で、日の出時刻の違いを記録。
- 色と光の観察:青い紙/赤い紙に当たる光の見え方を記録して、夕焼けの色の理由にせまる。
観察ワークシート(印刷して使える)
| 観察日 | 時刻 | 天気 | 太陽の方角 | 太陽の高さ(低・中・高) | 影の長さ(cm) | 気づき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例:5/10 | 7:30 | 晴 | 東 | 低 | 120 | 涼しい・空が白っぽい |
| 12:00 | 晴 | 南 | 高 | 25 | まぶしい・影が短い | |
| 17:00 | 晴 | 西 | 低 | 110 | オレンジの夕焼け |
追加欄:風の向き/雲の量/気温(°C)/体感(暑い・寒い)も書くと研究の質が上がるよ。
よくある疑問Q&A
Q1. 太陽は本当に動かないの?
A. 太陽も宇宙の中で動いていますが、1日の見え方は地球の自転で決まります。日常の観察では「太陽はその場に見える」と考えてOK。
Q2. 山にかくれて朝日が遅いのはなぜ?
A. 地平線より高い山やビルがあると、太陽が顔を出すまで時間がかかるから。方角は東でも、見える時刻は土地条件で変わります。
Q3. なぜ昼がいちばん暑いのは午後?
A. 地面・建物・空気が温まる時間差のため、気温のピークは正午より少し後になります。
Q4. 東西南北がわからないときは?
A. 朝、太陽が出てくる方向=東。そこから右手が南、左手が北、後ろが西。方位磁石アプリも便利。
Q5. サマータイムってなに?
A. 夏だけ時計を1時間早める制度。太陽の動きは同じだけど、生活時間を少し前にずらして明るい時間を有効活用します。
Q6. 正午(12:00)=太陽がいちばん高い時?
A. ぴったり一致しない日が多いよ。場所の東西の違い(地方時)や均時差で数分〜数十分ずれることがあります。
Q7. 赤道では影はどうなるの?
A. 年に2回(春分・秋分のころ)正午の影がほぼゼロになる地域もあるよ。太陽が真上近くに来るから。
Q8. 北極や南極では日の出はどう見える?
A. 季節によって何週間〜何か月も太陽が沈まない(白夜)/**のぼらない(極夜)**ことがある特別な地域です。
Q9. 太陽を写真に撮っていい?
A. そのままは危険! 専用の減光フィルターが必要。まずは影や景色を撮って記録しよう。
Q10. 月や星も東からのぼるの?
A. だいたい東からのぼり西へしずむように見えるよ(地球の自転のため)。ただし見える時刻は天体によって変わります。
用語辞典(やさしいことばで覚える)
- 自転(じてん):地球が自分の軸を中心に1日で1回回る動き。
- 公転(こうてん):地球が太陽のまわりを1年で1周する動き。
- 地軸(ちじく):地球の北極と南極を結ぶ見えない軸。**約23.4°**傾いている。
- 日の出・日の入り:太陽が地平線から出る/しずむとき。時刻は季節と場所で変わる。
- 南中(なんちゅう):太陽がその日の空でいちばん高い位置に来ること。
- 見かけの動き:自分が動いているため、相手が動いて見えること。
- 緯度・経度:地球上の場所を表す数字。緯度は南北、経度は東西。
- 標準時/時差:国や地域が決めた共通の時刻/地域ごとの時刻のずれ。
- 日付変更線:カレンダーの日付が切り替わる国際的な線(太平洋上)。
- 均時差:太陽の南中時刻と時計の12時との年間のズレ。
追加のポイントまとめ表(配布プリント向け)
| ポイント | ひとことで | 生活でのヒント |
|---|---|---|
| 太陽が東からのぼる | 地球が西→東へ自転 | 朝の東・午後の西日で部屋の使い方を工夫 |
| 昼夜のしくみ | 明るい面=昼/影の面=夜 | 日なた・日かげで暑さが変わる |
| 季節のちがい | 地軸の傾き+公転 | 夏は日が長い/冬は短い |
| 地域のちがい | 緯度で太陽の高さが変化 | 影の長さで比べて学ぼう |
| 時差 | 世界は同時に朝と夜 | 連絡・配信時間の調整に便利 |
| 安全 | 太陽は直視しない | 帽子・水分・日かげで観察 |
先生・保護者向けミニメモ(活用アイデア)
- 教科横断:理科(天体)× 社会(地図・時差)× 算数(グラフ)× 図工(模型・工作)。
- 評価の視点:観察の継続性/記録の正確さ/因果の説明/安全配慮。
- インクルーシブ:まぶしさに配慮し、日陰観察・模型学習・写真記録を併用。
- 家庭学習:ベランダ観察や近所の公園での影測定、週間記録の提出などに。
観察ノートのつけ方(自由研究の型)
- 準備:方位磁石または地図、定規、ノート、(できれば)温度計。
- 方法:同じ場所で、朝・昼・夕の影の向きと長さ、空の色、雲、風、体感を記録。
- まとめ:表やグラフにして、**「なぜそうなった?」**を自分の言葉で説明。季節を変えて同じ観察をすると、日の出位置・影の長さの年間変化が分かるよ。
ミニクイズにちょうせん!(解説つき)
- 地球が回る向きはどっち? — A: 西→東(だから太陽は東からのぼるように見える)
- 正午ごろ、日本で影はどちらを向く? — A: 北(太陽が南の空に高く上がるため)
- 夏と冬、太陽が高いのはどっち? — A: 夏(地軸の傾きで太陽の弧が高くなる)
- 春分の日、太陽はどこからのぼる? — A: ほぼ真東(秋分も同じ)
- 太陽を直接見ていい? — A: ダメ!(目を守ろう。影や景色で観察)
- 世界で同じ時刻、みんな昼? — A: いいえ(時差があるから、同時に朝と夜がある)
地球と太陽の動き・まとめ総表
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 地球の自転 | 24時間で1回転。昼と夜のしくみを作る |
| 自転の方向 | 西→東へ回るため、太陽は東からのぼり西へしずむように見える |
| 公転 | 1年で太陽のまわりを1周。季節・日の出位置・太陽の高さを変える |
| 地軸の傾き | **23.4°**の傾きが季節の違いを作る重要ポイント |
| 緯度の影響 | 赤道ほど太陽が高く、極地ほど低い。昼の長さも大きく変化 |
| 時差と標準時 | 地球が回るから世界は時間がズレる。日付変更線もある |
| 観察の鉄則 | 同じ場所・物・時刻/太陽は直視しない/記録は表とグラフに |
さいごに
太陽が「東からのぼる」のは、地球が西から東へ自転している“宇宙のリズム”の証拠。明日の朝、方角と影に注目して登校してみよう。いつもの道も、地球という大きな乗り物の上の旅に見えてくるはず。空を見上げるたびに、新しい発見がきっと増えていくよ!