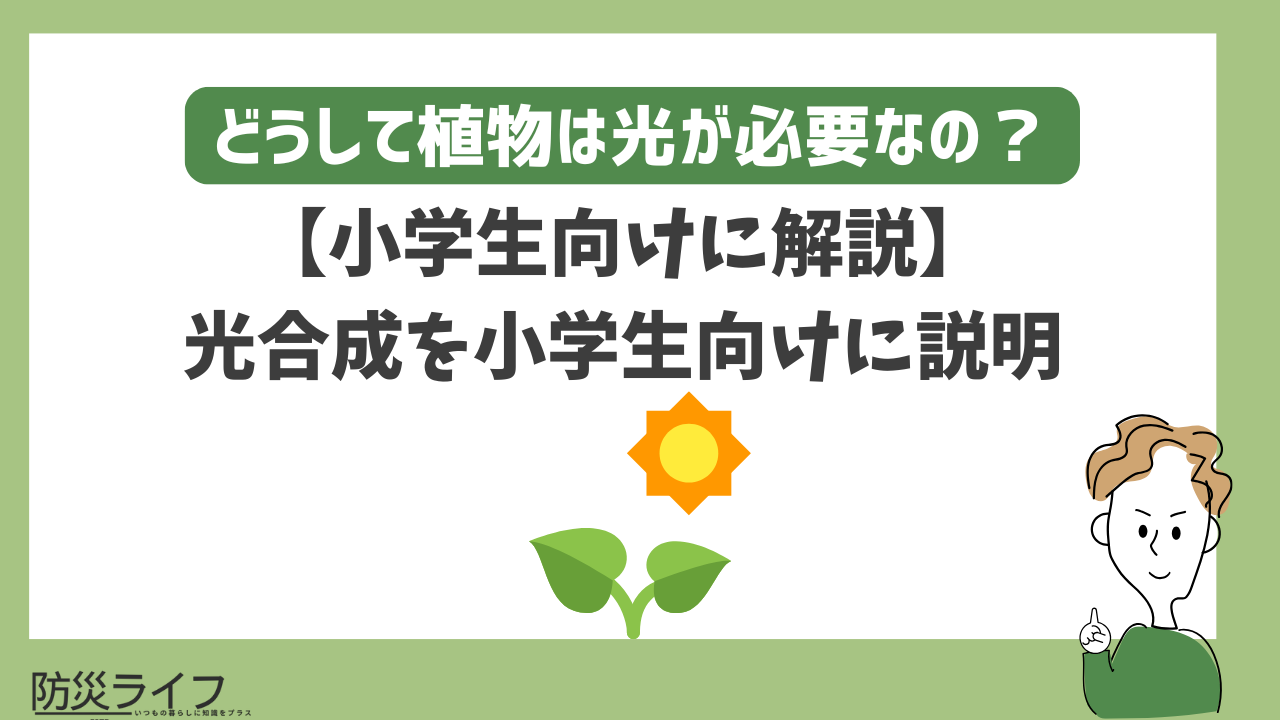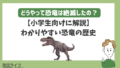植物は、太陽の光を使って自分の「ごはん」を作る特別な力——光合成(こうごうせい)——をもっています。この力のおかげで、植物は大きく育ち、花をさかせ、実をつけます。そして私たち人間や動物は、その実や葉を食べたり、光合成で作られた酸素を吸ったりして生きています。
この記事では、光がなぜ大切なのか、葉っぱの中で何が起きているのか、家でできる観察・実験、地球との関わり、さらには季節ごとの育て方の工夫や疑問解決、用語辞典まで、小学生にもわかりやすいことばでていねいに説明します。
光が必要な本当の理由——エネルギーと「体づくり」の出発点
植物は食べ物を食べないかわりに「光を食べる」
植物は動物のように口から食べ物を食べません。葉っぱにある葉緑体(ようりょくたい)が、太陽の光のエネルギーを受け取り、空気中の二酸化炭素と土から吸い上げた水を材料にして「でんぷん(糖)」を作ります。この「でんぷん」が植物のエネルギー源であり、体をつくる材料になります。だからこそ、光が足りないとエネルギー不足になり、育ちがにぶくなるのです。
光が足りないときに起きるサイン
長いあいだ暗い場所に置かれた植物は、葉の色が黄色っぽくなり、茎がひょろひょろと長くのび、花や実もつきにくくなります。これは、光合成が弱くなって「ごはん」が足りなくなるからです。反対に、十分な光を浴びた植物は葉が濃い緑になり、茎が太くしっかりしてきます。
さらに、光のあたり方で葉の向きが太陽のほうへ少しずつ変わることもあります。これは、よりたくさん光を受け取ろうとする植物の工夫です。
光・水・空気の三つ巴——そろうほど強くなる
光合成には、光・水・二酸化炭素の三つがそろうことが大切です。どれか一つでも不足すると力を発揮できません。下の表は、それぞれの役わりと観察のコツをまとめたものです。
| 材料 | どこから来る? | 何をする? | 足りないと… | 観察のコツ |
|---|---|---|---|---|
| 光 | 太陽の光、室内の照明 | 葉緑体がエネルギーとして使う | 葉が黄色くなり、成長がとまる | 日なた・日かげで葉色と背丈をくらべる |
| 水 | 雨・じょうろ・土の水分 | からだ中に運ばれて化学反応の材料になる | しおれて、葉が垂れ下がる | 指で土をさわり、乾き具合を記録する |
| 二酸化炭素 | 空気中(気こうから入る) | でんぷんの材料になる | 花や実がつきにくくなる | 風通しと葉の元気をメモに残す |
**光の量(明るさ)と時間(昼の長さ)は、光合成のスピードを大きく左右します。**春から初夏にかけては日が長くなり、植物は元気に育ちやすくなります。一方、冬は日が短く光も弱くなるため、成長はゆっくりになります。
葉っぱの中で起きていること——光合成のしくみをのぞいてみよう
葉緑体は「小さな工場」
葉っぱの細胞の中にある葉緑体は、緑色のつぶつぶで、ここが光合成をする工場です。光のエネルギーを受け取ると、葉緑体は水(みず)と二酸化炭素(にさんかたんそ)を使って、でんぷんと酸素(さんそ)を作り出します。
植物が緑色に見えるのは、葉緑体の中の色素が緑色の光をはね返し、赤や青の光を主に利用しているからです。
気こうは「出入り口」
葉の表面には気こうという小さな穴があり、ここから空気を取り入れたり、水分を出したりします。二酸化炭素は気こうから入り、できた酸素は気こうから外へ出ていきます。
暑い日や乾いた風の日には、水が出すぎないように気こうがとじ気味になることもあります。これは、体の水分を守るための大切なしくみです。
やさしい化学式で見る光合成
二酸化炭素+水+光のエネルギー → でんぷん(糖)+酸素。この流れが毎日くり返され、植物の成長をささえています。入ってくるものと出ていくものを整理すると、次のようになります。
| 入るもの | 使う場所 | 出るもの | 体の中での使われ方 |
|---|---|---|---|
| 光 | 葉緑体 | — | 反応を進めるエネルギーになる |
| 水 | 根→茎→葉 | 酸素 | 口や鼻から私たちが吸って生きるのに必要 |
| 二酸化炭素 | 気こう→葉緑体 | でんぷん | 植物の「ごはん」や体づくりの材料になる |
ポイント:植物は夜になると光がないため光合成は止まりますが、呼吸は昼も夜も続けています。呼吸では、でんぷんを使って少し酸素を吸い、二酸化炭素を出すはたらきがあります。昼は光合成の酸素づくりが呼吸を大きく上回るため、空気中の酸素がふえます。
光の「色」と植物の反応
光には赤・青・緑などの色(光の種類)があります。植物はとくに赤い光と青い光をよく使って光合成をします。室内照明でもあるていど育ちますが、太陽光に近い明るさと時間をあたえるとさらに元気になります。
家でできる観察・実験——安全に、たのしく、くり返して確かめる
日なたと日かげの比較実験
同じ種類・同じ大きさの植物を二つ用意して、一つは日なた、もう一つは日かげで育てます。水の量や鉢の大きさは同じにし、毎日同じ時間に葉の色、背の高さ、葉の枚数を文章で記録します。
1〜2週間たつと、光の量で成長の差がはっきりしてきます。実験が終わったら、観察ノートを読み返し、なぜ差が出たのかを自分のことばでまとめると、理解が深まります。
ヨウ素液で「でんぷんチェック」
理科でおなじみの方法です。葉っぱを熱湯で少しやわらかくしてから、うすいヨウ素液をたらすと、光が当たった部分は青むらさき色になります。これはでんぷんが作られた証拠です。
薬品を使うので、必ず大人や先生といっしょに、安全に注意して行います。火や刃物、熱湯の取り扱いにも十分注意しましょう。
観察ノートのつけ方
観察は同じ条件・同じ時刻でくり返すと、変化が見やすくなります。下の表のようなひな形を使うと、あとでまとめやすくなります。言葉だけでなく、簡単な絵をそえると、葉の形や色のちがいが伝わりやすくなります。
| 日付 | 天気 | 実験条件(例:日なた/日かげ) | 葉色(1=うすい〜5=こい) | 背丈(cm) | 気づいたこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | はれ | 日なた | 4 | 12.0 | 葉が厚くなってきた |
| 5/10 | はれ | 日かげ | 2 | 9.5 | 茎が細くのびている |
季節ごとの観察ポイント
春は新芽が出て光合成が活発になります。夏は光が強く水分が不足しやすいので、朝や夕方に水やりを。秋は日が短くなり、光合成の量が少し減るため、成長もゆっくりに。冬は光が弱く、室内の明るい場所に置くとよいでしょう。
光合成が支えるくらしと地球——食べ物と空気の「出発点」
たべものと空気の元は光合成
お米、小麦、野菜、果物——どれももとは光合成で作られた「でんぷん」やその仲間です。動物は植物やほかの動物を食べますから、食べ物の出発点は光合成といえます。さらに、私たちが吸う酸素の多くも、植物が光合成で作ったものです。海では、目に見えないほど小さな海の植物プランクトンが酸素づくりに大活やくしています。
森と温暖化の関係
光合成は二酸化炭素をへらし、酸素をふやすはたらきがあります。森や公園が多い地域は、空気がきれいで、気温の上がりすぎを防ぐ手助けにもなります。植物を大切にすることは、地球を守ることにつながるのです。学校や地域の緑をふやす活動に参加するのも、身近にできる地球のための行動です。
家や学校でできる小さな工夫
窓ぎわの明るい場所に鉢を置く、カーテンを開けて朝の光をしっかり取り入れる、観葉植物の鉢をときどき回して光が片方にかたよらないようにすると、どの葉にも光が届きやすくなります。水のあげすぎや根元の踏みつけを避けるなど、植物をいたわる習慣も大切です。
疑問解決&用語ミニ辞典——知るほど楽しく、もっと深く
Q&A(よくある質問)
Q1:光がなくても電気のあかりで育つの?
**A:**あるていど育てられますが、光の強さ・時間・色のちがいで結果が変わります。太陽光に近い明るさと時間をあたえると、より元気に育ちます。
Q2:葉っぱ以外でも光合成はできる?
**A:**若い緑色の茎でも少しは行われますが、主役は葉っぱです。根や茶色い部分では光合成はほとんどできません。
Q3:水をたくさんあげれば元気になる?
A:水は大切ですが、あげすぎは根ぐされの原因になります。土の表面が乾いたらあげる、受け皿の水はためない、などちょうどよい量を心がけます。
Q4:冬や雨の日でも光合成はできる?
**A:**できますが、光の強さや温度が低いとスピードがゆっくりになります。晴れた日より成長はゆっくりですが、反応は続いています。
Q5:どうしてヒマワリは太陽のほうを向くの?
A:成長するときに光の方向を感じて、より光を受けとりやすい向きに体を調整するからです。より多く光合成をするための工夫といえます。
Q6:夜、植物はなにをしているの?
A:夜は光がないので光合成は止まっていますが、呼吸はつづいています。からだの中のでんぷんを使って少し酸素を使い、二酸化炭素を出すはたらきがあります。
Q7:窓ガラスごしの光でも育つ?
**A:**育ちます。ただし、ガラスは光の一部を弱くすることがあります。ときどき鉢の向きを変えると、葉がかたよらず元気に育ちます。
Q8:葉に毛が生えていたり、白い粉がついているのはなぜ?
A:強い光や乾いた風から葉を守るための工夫です。葉の表面を守って、水分がにげすぎないようにしています。
Q9:土ではなく水だけでも育てられる?
A:育てられます(水耕)。ただし、栄養や光の量をうまく調整する必要があります。学校の理科でも行われる方法です。
Q10:植物は緑色なのに、どうして緑の光はあまり使わないの?
**A:**葉の色素は、赤や青の光を主に使い、緑の光は一部をはね返すからです。そのため、私たちの目には植物が緑に見えるのです。
用語ミニ辞典(やさしい言いかえつき)
| ことば | 意味 | やさしい言いかえ |
|---|---|---|
| 光合成 | 光のエネルギーで、二酸化炭素と水からでんぷんと酸素を作るはたらき | 光でごはん作り |
| 葉緑体 | 葉っぱの細胞の中にある、光合成をする緑のつぶ | ごはん工場 |
| 気こう | 葉の表面にある小さな出入り口。空気が出入りする | 空気のドア |
| でんぷん | 植物のエネルギーや体の材料になる栄養 | 植物のごはん |
| 二酸化炭素 | 空気の成分の一つで、光合成の材料 | ごはんの材料のガス |
| 酸素 | 光合成で作られ、私たちが呼吸に使う気体 | 生きるための空気 |
| 蒸散 | 葉から水分が出ていくはたらき | 体の熱をさます水のながれ |
| 葉脈 | 葉の中のすじ。水や栄養の通り道 | 水と栄養の道路 |
| 根毛 | 根の先にある細かい毛のような部分 | 水をすいとる細い手 |
| 導管・師管 | 水や栄養を運ぶ管(くだ) | 運ぶストロー |
| 呼吸 | 昼も夜も行う、体のエネルギー作りのはたらき | 体を動かすエンジン |
まとめ
**植物は、光・水・二酸化炭素がそろうと、葉っぱの中の葉緑体で光合成を行い、自分の「ごはん」と酸素を作ります。**この力があるから、私たちの食べ物と空気がうまれ、地球の環境も守られています。
家での観察や実験を通して、身近な草や木のすごさを感じ取り、植物を大切にする行動につなげていきましょう。季節や場所に合わせて光・水・風の条件を整えることが、植物といっしょにくらす第一歩です。