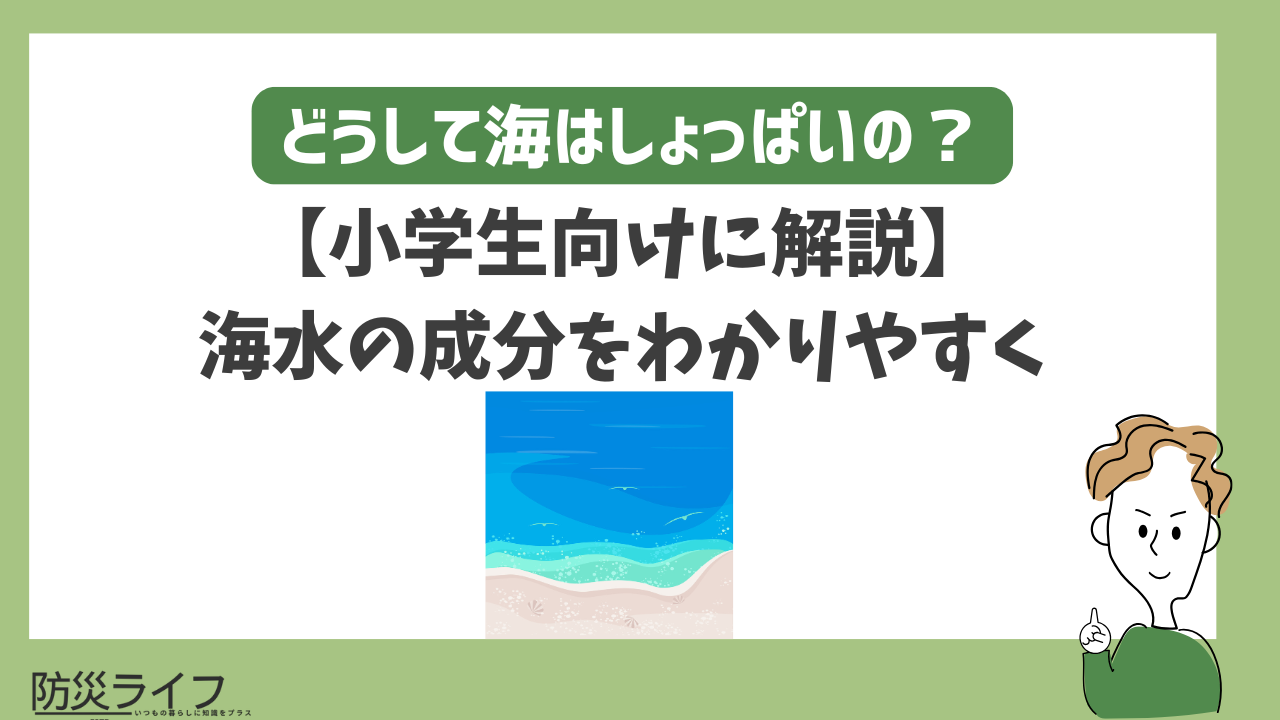海の水はなぜ「しょっぱい」のか。 川やプールはほとんど味がしないのに、海だけがしょっぱいのは、地球の長い時間と水のめぐり(サイクル)、そして岩石からとけ出したミネラルが関係しています。
この記事では、海のしょっぱさの正体から、海水にふくまれる成分、世界の海のちがい、生き物やわたしたちの生活とのつながり、自由研究に使える実験アイデアまで、小学生にも読みやすい言葉でていねいに解説します。読み終えたら、海のコップをひとくち味わうだけで、地球の歴史や自然のしくみが想像できるようになります。
1.海はなぜしょっぱい?――基本のしくみをやさしく
1-1.水の旅と「塩の行き先」
山や町にふった雨は川になり、道の途中で岩や土、落ち葉などにふくまれる塩分やミネラルをすこしずつとかして運びます。川の水はやがて海へ。こうして世界じゅうの川が長い時間をかけて運んだ成分が、海にたまりつづけたのです。川は流れが速く、すぐに新しい水に入れかわるため、塩分がたまる前に海へ出ていきます。
1-2.蒸発すると「塩は残る」――水のサイクル
海の水が太陽であたためられると、水だけが水蒸気になって空へ上がり、雲や雨になります。塩やミネラルは蒸発しないので海に残ります。だから海はだんだんしょっぱさがたまるのです。雨としてもどってきた水はふたたび川を流れ、また海へ。これが水のサイクルです。
1-3.海が「味つき」になるまでの時間
地球の歴史では何おく年という長い時間がながれています。火山の活動や岩石のくだけ方、雨の量などがくり返され、川から運ばれた塩分が海に少しずつたまって、いまの海水のしょっぱさ(塩分約3.5%)になりました。むかしの海は今よりうすかった時期もこくかった時期もあったと考えられています。
1-4.「うすまる力」と「たまる力」のせめぎ合い
海のしょっぱさは、雨や川でうすまる力と、蒸発や岩からのとけ出しでたまる力のつり合いで決まります。長い目で見ると大きくは変わりませんが、場所や季節では差が生まれます。
2.海水の成分をまるごと分解!――しょっぱさの正体
2-1.いちばん多いのは「塩化ナトリウム」
海水のしょっぱさの正体は塩化ナトリウム(食塩)。海水100gの中には約3.5gの塩が入っています(場所や季節で少し変わります)。
2-2.体と海の暮らしを支えるミネラル
食塩のほかにも、マグネシウム、カルシウム、カリウム、硫酸イオン、炭酸水素イオンなどがふくまれています。貝がらやサンゴの骨格はカルシウムででき、体の動きにはカリウム・マグネシウムが活やくします。海藻や小さな生き物(プランクトン)は、これらの成分を上手に使って育ちます。
2-3.ごく少量でも大切な成分
海水にはとても少ない量ですが、ヨウ素、鉄、ケイ素、フッ素、バナジウム、亜鉛などもふくまれています。こうした成分は海藻の育ちや貝類の成長にも役立ち、海の世界の栄養のバランスをささえています。
| 成分 | ふくまれる割合のめやす | どんな役わり? |
|---|---|---|
| 塩化ナトリウム(食塩) | 約2.7% | しょっぱさの主な正体/体の水分バランス |
| 塩化マグネシウム | 約0.3% | にがりの正体/体のはたらき |
| 硫酸マグネシウム | 約0.2% | 海のミネラル/苦味の一部 |
| 塩化カルシウム | 約0.1% | 貝がら・サンゴの材料 |
| カリウム塩 | 約0.04% | 体のはたらきを助ける |
| そのほか微量成分 | ごく微量 | 海藻・生き物の成長を助ける |
2-4.表面と深い海ではちがうの?
表面の海は雨や川の影響を受けやすく、うすまることがあります。深い海は温度が低く、塩分が安定している場所が多いです。場所によっては、表面と深さで塩分が大きく変わる塩の層(躍層)ができます。
2-5.河口は「まざり合いの教室」
川が海にそそぐ場所(河口)では、淡水と海水がまざって塩分がなだらかに変わるため、小魚やカニ、貝などが育ちやすい環境ができます。ここは生き物にとって大切なゆりかごです。
3.世界の海のしょっぱさをくらべよう
3-1.しょっぱさを決めるもの
太陽の強さ(蒸発)、雨の量、川からの水、海流、氷のとけ方などで海のしょっぱさは変わります。たとえば暑くて雨が少ない地域はよく蒸発し、しょっぱくなりやすいのです。
3-2.しょっぱい海・やさしい海の例
暑くて雨が少ない場所はよく蒸発するのでしょっぱくなり、寒い場所や川が多い場所はうすめられてしょっぱさが弱くなります。海流が出入りをさかんにしてくれると、しょっぱさはほどよく保たれます。
| 海・場所 | しょっぱさのめやす | 理由の例 |
|---|---|---|
| 紅海・地中海 | 高め(3.8〜4.0%前後) | 暑くて雨が少なく蒸発が多い |
| 太平洋の外洋 | ふつう(約3.4〜3.6%) | 広くてよくまざる |
| 日本近海 | ややふつう(約3.4〜3.5%) | 黒潮や親潮がまざり合う |
| バルト海 | 低め(2%以下の所も) | 川の水が多く入り、うすまる |
| 北極海・南極のそば | 低め | 氷がとけてうすまる |
3-3.湖のなかの「淡水」・「塩湖」
世界には淡水湖(ほとんどしょっぱくない)もあれば、塩湖(とても塩分が高い)もあります。死海では体がぷかぷか浮くほどです。これは水が出ていく道が少なく蒸発が多いため、塩がたまりやすいからです。逆に大きな川が流れ込む湖はうすく保たれます。
3-4.季節と雨のえいきょう
雨の多い季節や台風の後は、海面ちかくの塩分が一時的にうすくなることがあります。夏の強い日差しでは蒸発が進み、うすい海でも少しこくなることがあります。
4.生き物と人の暮らしを支える海水
4-1.生き物の体と海水のミネラル
海の生き物は体の中の塩分をうまく調整しながら生きています。海水魚は体の中の塩分が外より低くならないよう海水をのんで塩を出すはたらきが強く、淡水魚は反対に体から塩が出ていかないようにがんばります。カルシウムは貝がらやサンゴの骨、マグネシウム・カリウムは筋肉のはたらきや体内のバランスに大切です。海藻は海水の栄養を使って光合成を行います。
4-2.人の生活と海水――塩・にがり・ミネラル
海水からは塩が作られ、にがりは豆腐作りに使われます。ほかにもマグネシウム・カルシウム・ヨウ素などが取り出され、食べ物・入浴・工業材料として活やくしています。日本各地には塩田(えんでん)や釜でたく方法など、地域の気候に合った製塩の知恵が残っています。
4-3.天気と海のつながり
海は地球の70%以上をおおい、太陽の熱をためたりはなしたりして気温や天気を調整します。海でできた水蒸気は雲・雨・雪となり、やがて川を流れてまた海へ。水のサイクルが地球のいのちをささえています。海水は二酸化炭素をとりこむ力も持ち、地球の空気のバランスにも役立っています。
4-4.暮らしの中の「しょっぱさ」
海のしょっぱさは食文化にもいきています。漬物・干物・みそ・しょうゆなど、塩が味と保存に活躍。夏の海辺では体の水分と塩分がへりやすいので、水と少しの塩分を上手にとることも大切です。
5.やってみよう!――海のしょっぱさを体験する実験
5-1.ミニ塩田(えんでん)実験:塩を作ってみる
食塩水(海水のかわり)を浅い皿に入れて日なたに置くと、水が蒸発して白い結晶(けっしょう)ができます。これが塩です。日かげの皿と比べて、でき方の速さを記録しましょう。温度計や時間をメモすると、結果のちがいがよくわかります。
5-2.浮く?沈む?――卵・じゃがいもで浮沈テスト
水に塩を少しずつ入れると、卵やじゃがいもが浮く瞬間があります。これは水の重さ(密度)が大きくなったから。塩の量と浮き方を表にまとめましょう。砂糖水ともくらべると、成分によるちがいが見えてきます。
5-3.味と重さで塩分をくらべる
薄い食塩水・ふつうの食塩水・海水程度(約3.5%)の3種類を作り、味見は一口だけにして、水100gに何gの塩を入れたかを記録します。蒸発させて残った塩の重さもくらべると、塩分=しょっぱさが実感できます。
5-4.色水で作る「塩の層」モデル
うすい塩水(色A)とこい塩水(色B)をそっと重ねると、まざりにくい層ができます。これは海の塩の層(躍層)のモデルです。重ね方を工夫して、層ができる時間とくずれる時間を観察しましょう。
5-5.簡単「海の真水作り」実験
耐熱びんに塩水を入れ、ふたの内側に小皿をつけてあたためると、ふたに水滴(真水)がつきます。危険がないよう大人といっしょに行い、やけどに注意。蒸発しても塩は残ることを確かめましょう。
| 実験項目 | やり方 | 安全ポイント | 記録のコツ |
|---|---|---|---|
| ミニ塩田 | 浅い皿で蒸発 | 転倒に注意・屋外や窓辺 | 日なた/日かげ・時間・量を記録 |
| 浮沈テスト | 塩を少しずつ追加 | こぼれ注意・片付け徹底 | 入れた塩の重さと浮く瞬間 |
| 塩分比べ | 3種類の食塩水 | 飲みすぎない・口をゆすぐ | 濃度・味・重さの関係 |
| 塩の層モデル | 色のちがう塩水を重ねる | こぼさない・ゆっくり注ぐ | 層の厚さとくずれる時間 |
| 真水作り | ふたに水滴を集める | 火気とやけどに注意 | 集まった水の量と味 |
Q&A――海のしょっぱさの疑問をスッキリ解決
Q1:どうして川はしょっぱくならないの?
A:川は流れが速くて水が入れかわるので、塩分がたまらないからです。
Q2:海のしょっぱさはずっと同じ?
A:場所や季節で少し変わるけれど、広い海全体では大きくは変わりません。
Q3:雨がたくさんふると海はうすくなる?
A:一時的にはうすまることがあります。川のそそぐ河口ちかくはとくにそうです。
Q4:家の食塩はどうやって作るの?
A:海水を蒸発させたり、にがりを分けたりして作ります。天日塩・せんごう塩など方法はいくつかあります。
Q5:しょっぱい海のほうが体が浮くのはなぜ?
A:塩が多い水は重くなるので、体を強くおし上げる力(浮力)が大きくなるからです。
Q6:海のミネラルは体に必要?
A:はい。ナトリウム・カリウム・マグネシウム・カルシウムなどは体のはたらきに大切です。ただし食べすぎは禁物。
Q7:海の色はなぜ青いの?
A:水は光の色をえらんで吸収・反射するため、深い所ほど青く見えます。生き物やプランクトンでも色は変わります。
Q8:海のしょっぱさで天気は変わる?
A:しょっぱさそのものよりも、海の温度と水のめぐりが天気に大きく関係します。
Q9:海水はそのまま飲める?
A:塩分が高いのでそのまま飲むのは危険です。のどはうるおうように感じても、体の水分がうばわれてしまいます。
Q10:海水魚はなぜ塩辛い水でも平気?
A:体のしくみで塩や水分を調整しているからです。えらや皮ふ、腎臓のはたらきが関わります。
Q11:台所の塩と海の塩は同じ?
A:どちらも主な成分は塩化ナトリウムですが、にがりなどほかの成分の量がちがうことがあります。
Q12:塩分が高いと海はこおりにくい?
A:はい。塩がとけている水はこおる温度が下がるので、真水よりこおりにくくなります。
用語ミニ辞典(やさしい言いかえつき)
| ことば | 意味 | やさしい言いかえ |
|---|---|---|
| 塩分 | 海水などにとけている塩の量 | しょっぱさのもと |
| ミネラル | 体や生き物に大切な無機質 | からだを助ける栄養 |
| 水のサイクル | 蒸発→雲→雨→川→海のめぐり | 水のたび |
| 密度 | 同じ体積の重さのちがい | 水の重さのぎゅうぎゅう度 |
| 塩湖 | 塩分がとても高い湖 | しょっぱい湖 |
| にがり | 海水から塩をとったあとに残る液 | しょっぱ苦い液 |
| 躍層(やくそう) | 深さで塩分や温度が急に変わる層 | 急にかわる境目 |
| 河口 | 川が海にそそぐ場所 | 川と海の出会い |
まとめ――海のしょっぱさは地球からのメッセージ
海がしょっぱいのは、川が運んだ塩分が長い時間にわたって海にたまったから。 海水には多くのミネラルがとけ込み、生き物のくらしとわたしたちの生活を支えています。実験で塩が残る・浮く・結晶ができる・層ができることを体験すれば、教科書の言葉が自分の発見に変わります。
海と水のサイクルに注目して、自然のふしぎと地球のつながりを楽しく学びましょう。次に海へ行ったら、波の味の先にある長い時間の物語を思い浮かべてみてください。