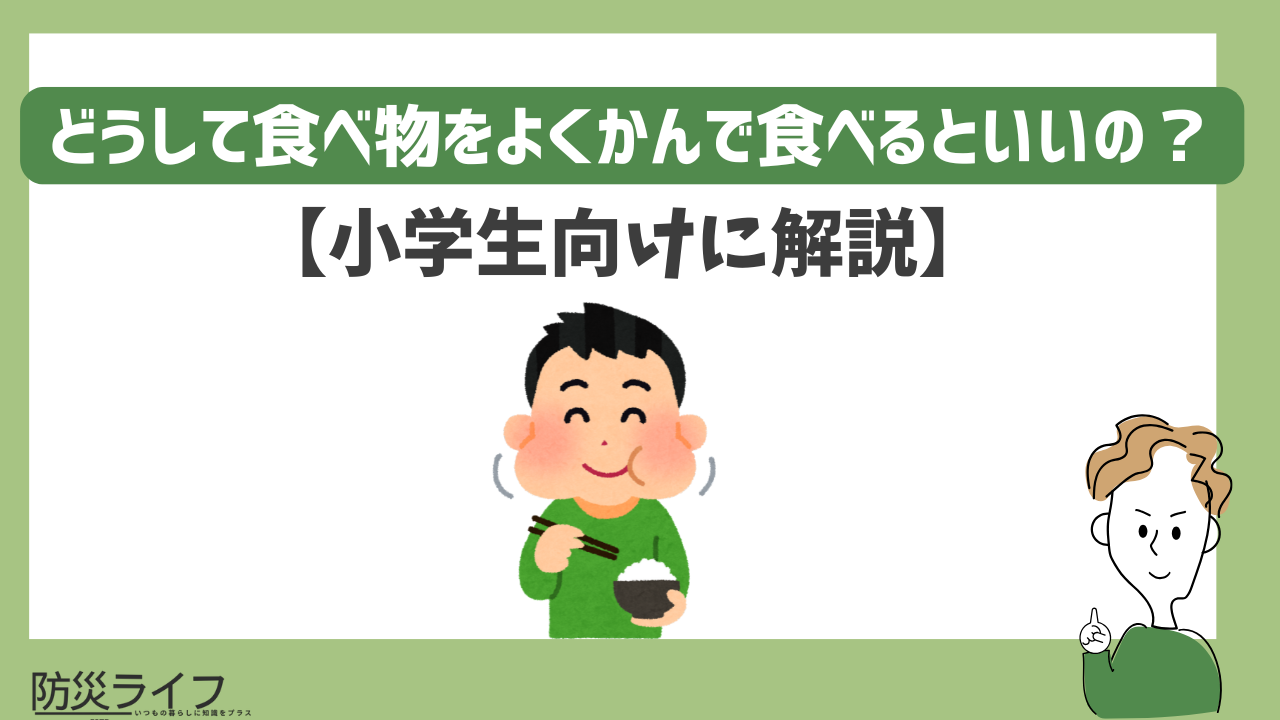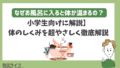毎日の給食やおうちのごはんで言われる「よくかんで食べよう」。ただの合言葉ではありません。よくかむこと(咀嚼〈そしゃく〉)は、消化、脳、歯やあご、姿勢や運動、心の安定、そして学習の力にまで広く関わる“すごい健康法”。
ここでは、小学生にもわかる言葉で、理由・しくみ・今日からできるコツ・自由研究アイデア・Q&A・用語辞典まで、たっぷり解説します。家族やクラスのみんなで挑戦できる記録シートやチェックリストも用意しました。
1.よくかむと何が起こる?—体と脳のしくみをやさしく解説
① だ液(だえき)と消化のエンジンが動き出す
・かむほどだ液がたっぷり出て、デンプンを分解する酵素(こうそ)が働き、消化が口の中からスタート。
・細かくくだけるほど表面積が増え、胃や小腸の仕事がラクになり、栄養がスムーズに吸収される。
・のみこみやすくなり、のどに詰まりにくく安全。高齢の家族とも“やわらかさ調整+よくかむ”で同じメニューを楽しめる。
② 脳が活性化—集中力・記憶力アップ
・かむ動きは“顔の運動”。あご周りの筋肉が動くと血流が増え、脳にも新鮮な血が届く。
・授業や読書、スポーツ前にしっかり朝ごはんをよくかむと、頭がスッキリして力が出やすい。
・左右バランスよくかむことで、姿勢や目の動きも安定し、黒板の文字が追いやすくなることも。
③ 口・歯の健康と免疫(めんえき)サポート
・だ液には口の中をきれいに保つ力があり、むし歯菌やばい菌を洗い流す〔自浄作用〕。
・だ液の成分が粘膜(ねんまく)を守って、のどの調子や声の出しやすさも保ちやすい。
・よくかむ子は、同じメニューでも“甘みやうまみ”を感じやすくなる=味わい上手に!
2.よくかむと起きるうれしい変化—毎日の“実感”を増やそう
① 食べすぎ防止と体重コントロール
・ゆっくりかむほど、脳の“満腹サイン”が早く届く。
・早食い・丸のみは食べすぎのもと。よくかめば適量で満足できるから、午後のだるさもへりやすい。
② あご・顔・姿勢(しせい)にも良い影響
・かむトレーニングは、あごの筋肉(咬筋〈こうきん〉)をきたえる。
・姿勢が整い、発音や表情もはっきり。音読・合唱・英語の発音にもプラス。
・片がみ(片方だけでかむクセ)をへらし、肩こり・首のこわばりも予防。
③ 気持ちが落ち着く“リラックス効果”
・かむ一定のリズムは呼吸を整え、イライラや不安がしずまりやすい。
・家族で会話しながら、ゆっくり味わう時間が心をほぐす“しあわせ時間”になる。
よくかむメリットとコツ【早見表】
| ポイント | からだ/こころへの効果 | 具体例・コツ |
|---|---|---|
| だ液アップ | 消化サポート・口内の自浄作用 | 一口30回、飲み物で流さず“かむ” |
| 満腹サイン | 食べすぎ防止・体重管理 | 箸をいったん置く・小さめひと口 |
| あごの筋トレ | 姿勢・発音・表情が安定 | かみごたえ食材を増やす |
| 口の清潔 | むし歯・口臭予防 | 食後の歯みがき+水でうがい |
| リラックス | 気分安定・集中力維持 | TVやスマホを消して味わう |
| 味わい力 | 野菜や苦手食材が食べやすく | “よくかむと甘い”体験を記録 |
3.今日からできる!「よくかむ」トレーニング&メニュー
① 一口30回“カムカム・チャレンジ”
・最初の一週間はカウントしながら。慣れたら“心の中でゆっくり”に切り替え。
・家族や友だちと記録し、達成シールでゲーム化すると続く。
・学年別の目安:低学年25~30回/中学年30回/高学年30~40回(固さで調整)。
② かみごたえのある食材を選ぶ
・野菜(れんこん・ごぼう・にんじん・キャベツ芯)、きのこ、海藻、豆・ナッツ、いか・たこ、こんにゃく、厚揚げ、するめ、干し芋、玄米や雑穀ごはん。
・ハンバーグやカレーは具を少し大きめに。サンドイッチは“耳付き”で、リンゴは薄切りより角切りに。
③ 食べ方の工夫で“早食い卒業”
・一口ごとに箸やスプーンをいったん置く。
・汁物→主菜→ごはんの順を固定せず、いろんな味をよくかんで行ったり来たり。
・飲み物で流し込まず、口の中でしっかり噛み砕く。水分は“合間にひと口”。
④ 季節の“かみごたえ”メニュー例
| 季節 | 主食 | 主菜 | 副菜・汁 | デザート |
|---|---|---|---|---|
| 春 | たけのこご飯 | 鶏の照り焼き | 新じゃがの味噌汁・菜の花おひたし | いちご |
| 夏 | 雑穀冷やし茶漬け | いかと枝豆の塩炒め | きゅうりとわかめの酢の物 | スイカ角切り |
| 秋 | 玄米きのこピラフ | さば塩焼き | れんこんきんぴら・豚汁 | 柿 |
| 冬 | もち麦ごはん | 厚揚げと大根の煮物 | ごぼう味噌汁・ひじき煮 | みかん |
4.観察・実験・自由研究アイデア—かむと体の“変化”を見つけよう
① かむ回数と満腹感の関係を調べる
・同じメニューで「早食い(10回以下)」と「よくかむ(30回)」を別日に比べ、満腹感・食べた量・食後の眠気を記録。
・グラフ化すると差が見えやすい。家族も参加して平均を出すとさらに◎。
② だ液と味わいの観察
・クラッカーやごはんをよくかむと、甘みを感じやすくなる変化をメモ。
・味覚(あまい・しょっぱい・すっぱい・にがい・うまみ)の感じ方を表にまとめ、好き嫌いの変化もチェック。
③ 家族で「カムカム週間」
・一週間、食事時間・かむ回数・気分・集中度(宿題のはかどり)を日記化。
・最終日に“マイ・ベストかみごたえメニュー”を発表。写真やスケッチでアルバム化。
④ かむ回数カウンターを手作り
・牛乳パックと紙クリップで“スライドカウンター”を製作。1口ごとに1目盛り動かす。
・自由研究の付録にして発表すると見やすい。
5.よくあるQ&A—疑問をすっきり解決!
Q1:やわらかい物ばかりでも大丈夫?
A:やわらかい物は食べやすいけれど、あごの筋肉がきたえにくい。毎食少しでいいので“かみごたえ”を足そう。スープにも角切り野菜をプラス。
Q2:ガムをかむのは効果がある?
A:食事以外に“かむ練習”としては○。ただし砂糖の少ないタイプを選び、長時間かみすぎはあごに負担なのでほどほどに。勉強前の5~10分が目安。
Q3:のどに詰まりやすい食材が心配…
A:小さめひと口にして、よくかんで少しずつ飲みこむ。水分もこまめに。高齢の家族とは固さを調整して一緒に楽しもう。
Q4:早食いのクセが直らない!
A:タイマーで“15〜20分は味わう”と決め、箸置きや一口休憩を活用。食卓でのながらスマホ・TVはオフに。ひと口ごとに深呼吸を一回。
Q5:スポーツの前後は?
A:前はよくかんで消化にやさしい物を。後はたんぱく質+炭水化物を“よくかんで”補給すると回復がスムーズ。
Q6:歯が生え変わり中でかみにくい…
A:噛む場所を左右で分散し、固さは段階調整。スティック生野菜→軽く蒸す→みじん切り、とステップを踏もう。
Q7:飲み物は先?あと?
A:基本は“食べ物をかんで飲みこむ→水分ひと口”。先にたくさん飲むと薄まって味わいにくくなることがあるよ。
6.用語ミニ辞典(やさしい解説つき)
・咀嚼(そしゃく):食べ物を歯でかみくだき、だ液とまぜること。
・だ液:口の中の液。洗い流す力と消化を助ける酵素をふくむ。
・酵素(こうそ):食べ物を体に取り入れやすい形に分解する“はたらき”。
・満腹中枢(まんぷくちゅうすう):おなかいっぱいの合図を出す脳のはたらき。
・咬筋(こうきん):かむ力を生む、ほほ〜あごの強い筋肉。
・消化:食べ物を小さく分け、体に吸収できるようにする過程。
・片がみ:左右どちらか一方だけでかむクセ。ゆがみやコリの原因に。
7.“よくかむ×栄養”—バランスごはんで効果を高めよう
① 三大栄養素と“かむ”のいい関係
| 栄養素 | からだでの主なはたらき | かむとどう良い? | 食材例 |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 筋肉・血・骨の材料 | しっかりかむと消化がスムーズ、筋づくりにプラス | 魚、肉、卵、豆、乳製品 |
| 炭水化物 | エネルギーのもと | だ液の酵素が分解スタート、勉強・運動の燃料に | ごはん、パン、麺、いも |
| 脂質 | 体温・ホルモンの材料 | よくかむと満足感UPで食べすぎ防止 | ナッツ、魚、植物油 |
② 色でそろえる「かみごたえ定食」
・茶(主食)+赤(主菜)+緑(野菜)+白(汁)+黄(果物)=見た目も楽しく、自然とかむ回数UP!
8.歴史と世界の食文化—“かむ”は昔からの知恵
① 昔の日本の食卓
・玄米や雑穀、干物、漬け物、根菜など“よくかむ”メニューが中心。自然と咀嚼回数が多かった。
② 世界の“よくかむ”料理
・フランスのハードパン、韓国のナムル、メキシコのトルティーヤ+豆、インドの豆カレーなど、かみごたえがあり栄養バランスも◎。
③ マナーと“味わう力”
・世界共通の合言葉は「ゆっくり・静かに・感謝して」。落ち着いてかむと会話もはずむ。
9.学校・家庭で続ける「カムカム計画」—実行プラン
① 学校で
・給食前に1分“かむストレッチ”(首回し→深呼吸→口角アップ)。
・クラス目標〔一口30回/タイム20分〕、週末にふり返りカードを提出。
② 家庭で
・“ながら食べ”をやめ、食卓のTV・スマホはオフ。
・週に1回は“かみごたえデー”(れんこん・ごぼう・きのこ祭り)。
③ 記録シート(例)
| 日付 | 料理 | かむ目標 | 実際の回数 | 気分・発見 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | カレー(具大きめ) | 30回 | 28回 | にんじんが甘い! |
| 火 | 焼き魚+雑穀 | 30回 | 32回 | 皮がパリパリで好き |
10.“よくかむ”をじゃまするクセ&リセット法
| クセ | 何が起きる? | リセット法 |
|---|---|---|
| 早食い | 満腹サインが届かない | 箸を置く・深呼吸・タイマー20分 |
| 片がみ | あごのゆがみ・肩こり | 左右交互に意識・一口ごとに反対側で |
| 流し飲み | 消化不良・味が薄い | 飲み物は“合間にひと口” |
| 猫背 | のみこみにくい | 足裏ペタッ・背中まっすぐ |
11.安全においしくかむための注意
・一口を小さめに。急がず、落ち着いて座る。
・固い食材は“下ごしらえ”で段階調整(生→蒸す→煮る)。
・アレルギーがある場合は医師の指示に従い、安全な代替食材で“かみごたえ”を。
・のどに詰まりやすい物(もち、ピーナッツ等)は要注意。小さく切って、よくかんで、ゆっくり飲みこむ。
12.チェックリスト:今日からはじめる10の習慣
- 最初の一口は30回かむ。
- 一口ごとに箸を置く。
- かみごたえ食材を一品追加。
- 飲み物で流し込まない。
- 食卓のTV・スマホはオフ。
- 姿勢を正して座る(足裏ぺたん)。
- 朝ごはんも“よくかむ”。
- 家族と会話して“ゆっくり時間”。
- 食後は歯みがき+水うがい。
- 一週間の記録をつけて見直す。
【まとめ】
「よくかむ」は、消化を助け、むし歯や口のトラブルを防ぎ、集中力や気持ちの安定、姿勢の安定、運動のキレまで底上げする“万能スキル”。
一口30回、かみごたえ食材、箸を置く——小さな工夫の積み重ねが、体と心をぐんぐん元気にします。家族や友だちと“カムカム習慣”を楽しく続け、毎日のごはん時間をもっとおいしく、もっと健康的に育てていきましょう!