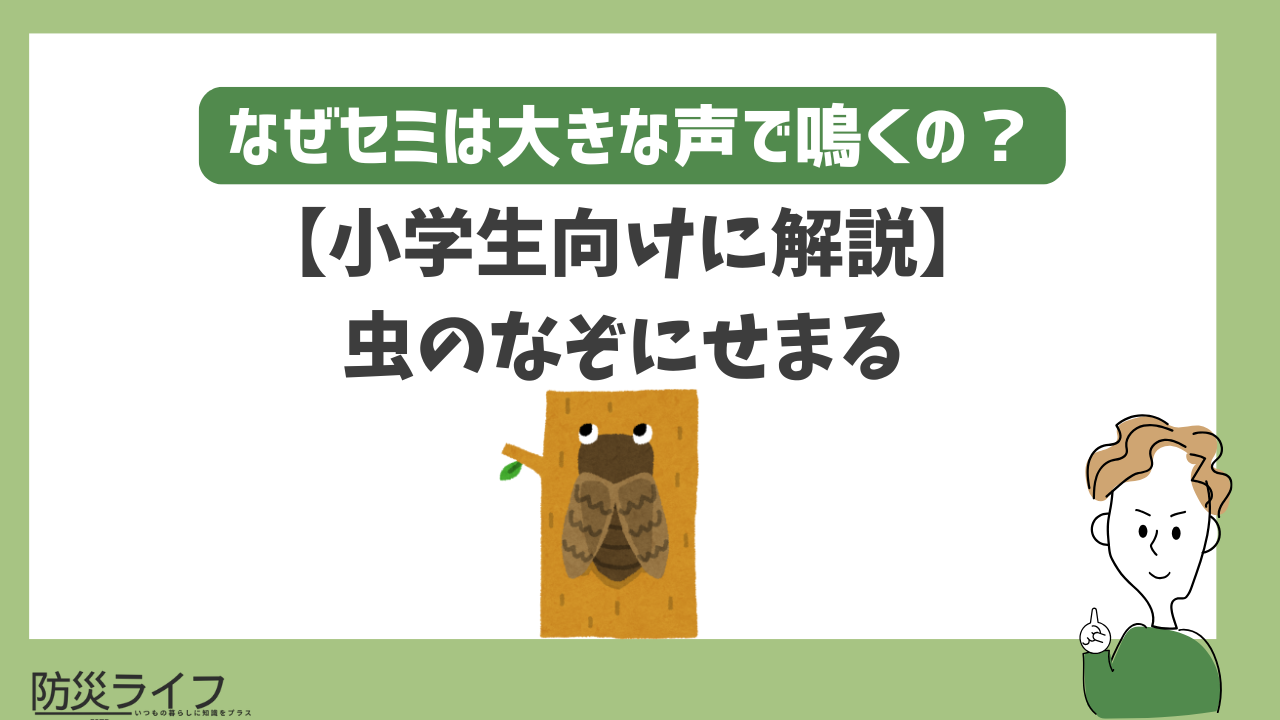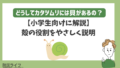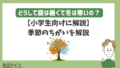夏になると木の上から聞こえる大合唱。「どうしてセミはあんなに大きな声で鳴くの?」というぎもんに、体のしくみ・鳴く理由・種類ごとの違い・観察のコツまで、やさしく徹底解説します。自由研究にも使える表とワークつき!このガイドでは、聞く・見る・記録するの3ステップで、セミの世界を深く楽しく学べます。
1.セミはなぜ大きな声で鳴くの?5つの理由
① メスへの合図と「ここにいるよ!」の知らせ
オスのセミが鳴く一番の目的は、木のあちこちにいるメスに自分の場所を知らせるためです。遠くのメスにも届くように、強い音で長く鳴き続けます。にぎやかな昼間でも聞き取ってもらえるよう、はっきりした音の高さやリズムになっています。鳴き声の“型(パターン)”は種類ごとに決まっていて、同じ種類のメスにだけ分かりやすい合図になっています。
② オス同士の競争とアピール合戦
同じ木に何匹もオスが集まると、より目立つ声・通りのよい声を出すオスが有利になります。鳴き声の強さ、続く時間、休みの取り方のちがいが、メスに選ばれる可能性につながります。いわば「恋のアピール合戦」。ときには**鳴く順番をずらす“鳴きかわし”**で、互いの声をじゃましないようリズムを工夫することもあります。
③ 季節・天気との関係(鳴くタイミングのわけ)
セミは温かくて湿度がほどよいときに元気に鳴きます。気温が下がったり雨がふりそうになると、いっせいに静かになることも。鳴き声は、夏の進み具合や天気の変化を教えてくれる自然のサインです。朝の涼しい時間や、風が弱い日ほど遠くまでよく届きます。
④ 外敵への警戒・身を守るため
強い音で外敵(鳥、カマキリ、ムクドリ、トカゲなど)をおどろかせる効果があります。敵の影を感じると一斉に鳴き止み、気配が去るとまた大合唱に戻る——この急なオン・オフも、身を守る作戦の一つです。
⑤ なわばりの主張・良い場所の確保
響きやすい枝先や高い位置は“人気の席”。そこをめぐってオス同士が鳴き合い、場所の取り合いが起きます。よく響く場所を確保できたオスほど、遠くのメスにアピールできます。
ワンポイント:耳をすませば、同じ木の中でも「高い所=よく響く強い声」「低い所=やや弱い声」などの音の段差が聞こえます。
2.大音量のひみつ:セミの体のしくみ(+ライフサイクル)
発音膜(はつおんまく)=音を作る「たいこ」
オスの腹部には、うすい板のような膜(発音膜)が左右にあり、筋肉で高速にふるわせて音を出します。この膜が「ジー」「ミーン」などの基本の音を作ります。ふるえる回数が増えるほど音は高く、回数が少ないほど低く聞こえます。
共鳴室(きょうめいしつ)=音を大きくする「からっぽの部屋」
腹部の中は空洞が多く、そこが共鳴室としてはたらきます。発音膜の音がこの空洞で反射して重なり、体の大きさからは想像できないほどの大音量に。体の向きや枝の形、木の幹の硬さでも響き方が変わります。
鳴きやすい姿勢・場所のえらび方
日当たりのよい枝先や、音が広がりやすい位置で鳴くことが多いです。風が弱い朝は音が遠くまで届きやすく、にぎやかな正午は、より強くはっきりと鳴いて目立とうとします。**木の“舞台効果”**を上手に使っているのです。
セミの一生(ライフサイクル)早わかり
| 段階 | どこで | どんなようす | 観察ポイント |
|---|---|---|---|
| 卵 | 木の枝の割れ目など | 秋に産みつけられる | 春〜初夏にふ化。産卵跡の筋(みぞ)を探してみよう |
| 幼虫(地中生活) | 地面の下 | 木の根から樹液を吸って数年過ごす | 雨のあとに小さな穴(羽化前の出口)が見つかることも |
| 地上へ(羽化直前) | 木の根元〜幹 | 夜、地上に出て登り始める | 夕方〜夜に観察。さわりすぎ注意 |
| 羽化(うか) | 幹・壁・柵など | 殻(ぬけがら)から成虫が出る | 白っぽい体→だんだん固く色づく様子を記録しよう |
| 成虫(鳴く) | 木の上 | オスが大合唱、メスをさがす | 朝・昼・夕方で鳴き方の変化を比べよう |
コラム:寿命のホント
セミは地上に出てからは1〜数週間で一生を終えることが多いですが、地中の幼虫期間は数年かけてじっくり育ちます。短い夏の成虫生活に全力をそそぐため、鳴き声も大きくなると考えられます。
3.種類別・鳴き声カタログ(聞き分け&観察のコツ)
身近な種類の鳴き声 早見表(拡充版)
| 種類 | 鳴き声の聞こえ方(例) | 鳴きやすい時間 | よくいる場所 | 音の大きさ | 観察メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| アブラゼミ | ジーーー…(濃く長い) | 昼 | 公園・街路樹 | 大きい | 幹にぴったり止まり、止まり木を変えながら鳴く |
| ミンミンゼミ | ミーンミンミン…(はっきり) | 朝〜昼 | 林・学校の木 | 中〜大 | 涼しい場所を好み、雲が出ると静かに |
| クマゼミ | シャーシャー…(連続・力強い) | 朝〜昼 | 都会の公園・海沿い | とても大きい | 太い街路樹で大合唱になりやすい |
| ツクツクボウシ | ツクツクボーシ…(しり上がり) | 夕方〜夏の終わり | 庭木・林 | 中 | 夏の終わりを知らせる代表選手 |
| ヒグラシ | カナカナカナ…(透明で物悲しい) | 早朝・夕方 | 山・里山 | 中 | 気温が下がるとよく鳴く。薄暗い時間帯に注目 |
| ニイニイゼミ | チー…チー…(小刻み) | 朝 | 低い木・藪 | 小〜中 | 初夏のはじまりに出会いやすい。小さくても負けない声 |
| エゾハルゼミ | ミョー…ミョミョ… | 初夏の朝 | 北国の森 | 中 | 早い季節に登場。地域の特色を感じる種 |
鳴く時間・場所のちがいを地図にしよう
種類ごとに「朝型」「昼型」「夕方型」があり、好む木の高さや太さも少しずつちがいます。同じ公園でも、エリアごとに聞こえる声が変わるので、地図にシールや色で書きこむと見比べやすくなります。
録音・聞き分けのコツ(家庭でできる)
- スマホやボイスレコーダーで10〜20秒ずつ録音し、音の高さ(低い・高い)とリズム(長い・短い・くり返し)をメモ。
- 2回目以降は録音を流しながら種類あてクイズ。家族や友だちと得点表を作ると盛り上がります。
- 風切り音が入らないよう、マイクにハンカチを軽くかぶせると録音がきれいになります。
ミニ実験:家のものを“共鳴室”にしてみよう
コップ・小箱・紙筒に録音した音を流してみると、入れ物の形で音の響きが変わることが体験できます。セミの体の共鳴室と同じ“仕組みのミニ版”です。
4.ほかの虫とのちがい(しくみ・時間・役わり)
「どこで音を出すか」のちがい
| 生き物 | 音の出し方 | 音の広がり |
|---|---|---|
| セミ | 腹部の発音膜をふるわせ、共鳴室で増幅 | 昼間のにぎやかな環境でも遠くへ届く大音量 |
| コオロギ・スズムシ | 左右の羽をこすり合わせて音 | 静かな夜に遠くまで通る細い音 |
| キリギリス | 羽のギザギザ(やすり)をこする | 高くパリッとした音色 |
鳴く時間・音の使い分け
セミは昼のにぎやかな時間帯に、遠くへ届く大きな声でアピール。コオロギやスズムシは夜に、静けさの中でよく通る細い音を使います。**環境に合わせた“鳴き分け”**と言えます。
観察・比べ方のポイント
同じ場所で昼と夜に観察して、鳴く虫の種類・時間・音の高さを表にまとめます。羽で鳴く虫は、鳴きながら体を左右にふるなど、しぐさも観察メモに残しましょう。
5.セミの声で読み解く自然のサイン&研究ワーク
季節の進みをよむ
初夏=ニイニイゼミ、盛夏=アブラゼミ・クマゼミ、晩夏〜初秋=ヒグラシ・ツクツクボウシ…というように、鳴き声の主役は入れかわります。耳で季節の物差しを作るつもりで**定点観測(同じ場所・同じ時間)**をしましょう。
天気の変化をよむ
晴れて気温が上がると合唱が強まり、雨や強風の前は静かになりがち。天気予報と照らし合わせて、「鳴き声指数」を自分でつくるとおもしろいです。(例:弱=0、ふつう=1、強=2)
観察ワーク(自由研究にそのまま使える)
- 地図作り:公園や学校の地図を用意し、聞こえた種類と時刻をピンで記録。
- 音の記録:同じ場所・同じ時刻で3〜7日連続録音し、音の長さや休みの間を数える。
- 気温との関係:気温・湿度を一緒にメモ。鳴く強さとあわせてグラフ化。
- 時間帯比較:朝・昼・夕で主役の交代を確認しよう。
観察チェック表(印刷して使える)
| 日付 | 場所 | 天気 | 気温 | 時刻 | 聞こえた種類 | 音の強さ(0/1/2) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例)7/25 | 学校のけやき並木 | 晴れ | 32℃ | 10:30 | アブラゼミ、クマゼミ | 2 | 日なたで合唱、風弱い |
| 例)8/28 | 裏山の杉林 | くもり | 26℃ | 17:45 | ヒグラシ | 1 | 夕方から一斉に鳴き出す |
観察マナー&安全チェック
- 木や幼虫・羽化中の個体をむやみにさわらない(羽が乾く前は特に弱い)。
- 私有地や住宅の庭には立ち入らない。人の迷惑にならない時間に観察。
- ゴミは持ち帰る。抜け殻(ぬけがら)は必要以上に集めすぎない。
6.地域と環境でかわるセミ(上級編)
住む場所と分布のちがい
都会の公園・街路樹ではアブラゼミやクマゼミ、山の多い地域ではヒグラシやミンミンゼミが目立つなど、場所によって主役が変わることがあります。樹木の種類(広葉樹・針葉樹)や水辺の有無も影響します。
都会と自然の“音の景色”
車の音が多い街中では、より強い・連続する声のクマゼミが目立つ場合も。静かな山では、ヒグラシの澄んだ声が遠くまで届きます。耳で“音の地図”を描いてみましょう。
環境の変化とセミ
植えかえや伐採、気温や降水のちがいで、見られる種類が年ごとに入れかわることもあります。毎年同じ場所を観察すると、小さな変化に気づけます。
まとめ・Q&A・用語辞典
まとめ(5行でおさらい)
1)オスのセミは、メスへの合図と競争のために大きな声で鳴く。
2)腹部の発音膜と共鳴室のおかげで、小さな体でも大音量。
3)鳴き声は季節や天気のサイン。定点観測で自然の変化が見える。
4)種類ごとに時間・場所・リズムがちがう。地図と録音で聞き分け上手に。
5)観察はマナーと安全第一。生きものと人にやさしい研究を。
よくある質問(Q&A)
Q1.メスのセミは鳴かないの?
A.鳴くのはオスだけ。メスには発音膜・共鳴室が発達していません。
Q2.同じ木で急に静かになるのはなぜ?
A.天敵(鳥・カマキリなど)を感じたり、急な日ざしや風の変化で警戒するからです。
Q3.家の近くにセミが増えた/減ったのは?
A.木の種類や太さ、植えかえ、気温・雨の量など環境の変化が影響します。
Q4.うるさく感じるときの対策は?
A.窓を閉める・厚手のカーテン・耳を休める時間を作る・朝の録音あそびに切り替えて聞こえ方を楽しむのも方法です。
Q5.抜け殻は集めてもいい?
A.少量ならOKですが、地域のきまりに合わせて。取りすぎず、屋外に戻すのがおすすめです。
Q6.羽化(うか)はいつ見られる?
A.夕方〜夜に始まることが多いです。明るいライトに集まる個体もいるので、ライトをまぶしすぎないよう注意して観察しましょう。
用語辞典
- 発音膜(はつおんまく):オスの腹部にある、音を作るうすい膜。
- 共鳴室(きょうめいしつ):体内の空洞。音を大きく響かせる部屋のはたらき。
- 警戒音:外敵に気づいたときなどに出す短い強い音や、急な沈黙。
- 羽化(うか):地中で育った幼虫が地上に出て、成虫になること。
- 鳴きかわし:近くのオス同士がリズムを合わせたり、ずらしたりして鳴くこと。
- 定点観測:同じ場所・同じ時間でくり返し観察し、変化をくらべる方法。
★ワンポイント:録音データは、日付・時刻・気温とセットで保存しよう。翌年に同じ場所でくらべると、季節の進み方のちがいが見えてきます。必要なら地図・音・気温の3つを1枚にまとめる“観察ポスター”にして発表しよう!