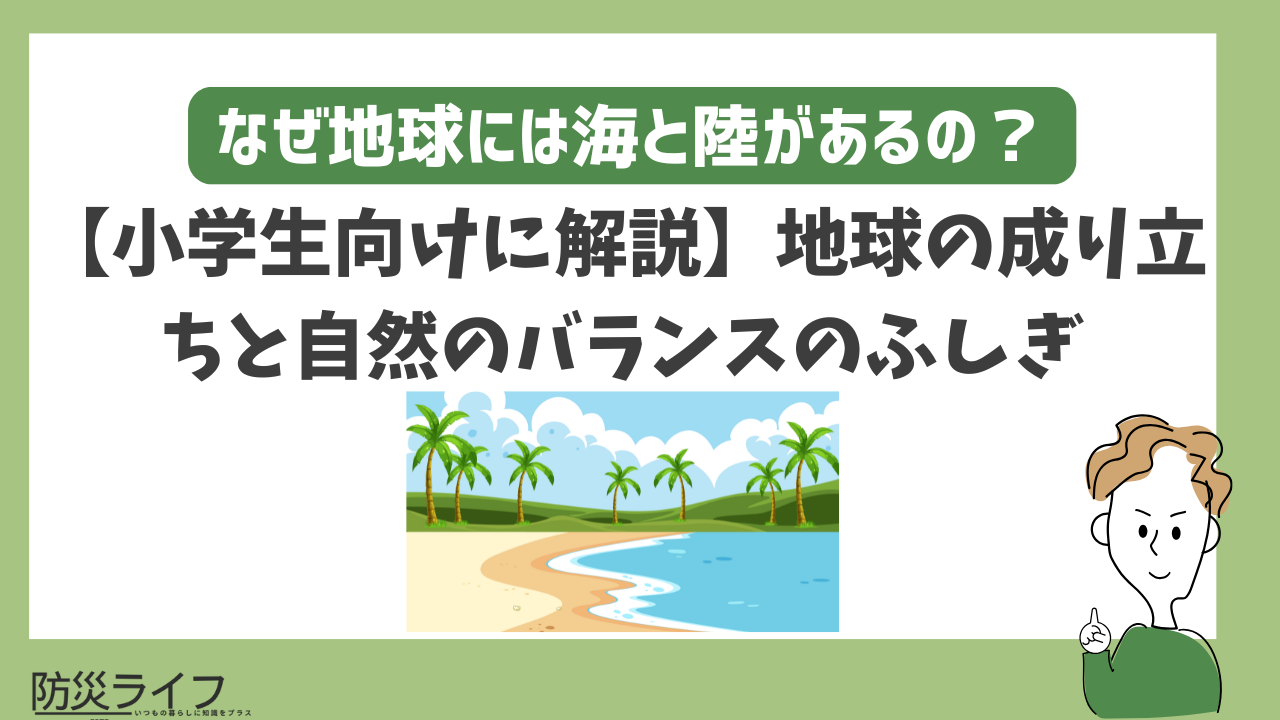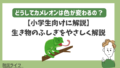地球には青い海と緑の陸があり、たくさんのいのちがくらしています。どうして海と陸はできたのか、そして今もその形がどうやって保たれているのか――46億年にわたる地球の物語を、やさしいことばでたどっていきます。読んだあとには、地図や身の回りの風景が今までよりもぐっと面白く見えてくるはずです。
地球ってどんな星?かたち・大きさ・動き
ちょっぴりつぶれた丸い星
地球は遠くから見ると丸いボールのようですが、実は上下が少しつぶれた形(回転だ円体)です。地球を包む大気(たいき:空気の層)と水(海・雲)は、いのちを守る二重の毛布の役目をしています。
自転と公転がつくる「昼と夜」「四季」
地球は1日で1回自転し、約1年で太陽のまわりを1回公転します。自転で昼と夜がうまれ、公転と地軸の傾きで春夏秋冬が生まれます。朝日や夕日の色のちがいも、太陽の光の当たり方のちがいから生まれます。
大きさと重力のイメージ
地球のまんなか(赤道)を一周すると約4万km。平均半径は約6371kmです。地球の大きな重さが生む**重力(じゅうりょく)**が、海の水も空気も、そして私たちも地面に引きつけています。
空気と水が守るしくみ
大気は酸素や二酸化炭素などをふくみ、気温をほどよく保ちます。海は太陽の熱をためたり運んだりして、地球の気候をやさしくならしてくれます。空気と水が力を合わせて、地球をいのちの星にしているのです。
海と陸はどうやって生まれた?46億年のながれ
① ちりが集まってできた熱い地球
46億年前、宇宙にただよう小さなちりや岩が少しずつ集まり原始の地球に。はじめの地球はとても熱く、どろどろ(マグマ)でした。火山があちこちでふん火し、空には水蒸気や二酸化炭素が広がりました。
② 地球が冷えて大雨がふり続ける
時間とともに地球が冷え、空の水蒸気が長いあいだ雨になってふり続き、地面のへこみに水がたまって最初の海(原始の海)ができました。同時に水の循環(のぼる→雲→雨→流れる)が始まり、今も続いています。
③ 山がもり上がり、陸が顔を出す
地球の下ではマントルがゆっくり流れ、上にあるプレート(大きな地面の板)を動かします。プレートどうしがぶつかったり、はなれたり、こすれ合ったりして山地や大陸が生まれ、火山のふん火で島もできて、陸地が広がりました。
④ 海がしょっぱくなったわけ
雨や川が岩や土をけずって塩分やミネラルを海へ運びます。海からは水だけが蒸発して塩は残るため、少しずつしょっぱい海になりました。
ミニコラム:月と潮の満ち引き
月の引力で海の水位が上がったり下がったり(潮汐:ちょうせき)します。満ち引きは海岸の生き物のくらしや砂浜の形をつくる力にもなっています。
今もつづく「海と陸」をつくりかえる力
プレートの動き(大地のゆっくりした大移動)
プレートは1年に数cmほど動きます。気づきにくい速さですが、何百万年たつと大陸の位置や海の広さが大きく変わります。日本列島も、こうした動きと火山活動で形づくられてきました。
プレート境界の3タイプと例
| 境界のタイプ | 何が起きる? | 例 | 海と陸への影響 |
|---|---|---|---|
| 沈み込み | 海のプレートが大陸の下にもぐる | 日本海溝 | 山地・火山・地震が多い |
| 広がる | プレートが左右に広がる | アイスランドの割れ目 | 新しい海底ができる |
| 横ずれ | プレートが横にながれてずれる | サンアンドレアス断層 | 大きな地震が起きやすい |
水・氷・風がけずるちから(侵食と運ぶちから)
川の水、海の波、風、そして氷河は、岩や土をけずって運びます。けずられた砂や泥は平野や砂浜をつくり、川口や海底にたい積します。けずる→運ぶ→たまる、という自然のそうじが、地形を少しずつ変えていきます。
けずれ方のちがい(やさしい言いかえ)
- くだける:氷や温度変化で岩がポロポロになる(物理)
- とかされる:雨や川の水に少しずつ溶ける(化学)
- こすられる:石と石がこすれ丸くなる(摩耗)
「つり合い」のしくみで高さがきまる
陸は軽い岩、海底は重い岩でできていることが多く、水の重さも加わって、地面はゆっくりたわみながらつり合いを保ちます。これにより、高い山や深い海ができても、長い時間で見れば全体のバランスがとられていきます。
ミニコラム:火山のめぐみ
火山灰は細かくて栄養をふくみ、畑の土を豊かにします。地下の温泉も火山の熱のプレゼントです。
地球の中身をのぞいてみよう(層のひみつ)
| 層の名前 | どこにある? | かたさ・ようす | ひみつの働き |
|---|---|---|---|
| 地殻(ちかく) | 一番外がわ。私たちが立っているところ | かたい岩の板(プレート) | 大陸や海底をつくる土台 |
| マントル | 地殻の下〜深いところ | 高温でゆっくり流れる | 流れがプレートを動かす力に |
| 外核 | さらに奥 | どろどろの金属 | 地球の磁石の力(磁場)をつくる |
| 内核 | いちばん中心 | かたい金属の球 | 地球の芯。とても熱い |
どうやって分かるの?(地震波の手がかり)
地震のときにひろがる波(地震波)は、通れる場所と通れない場所があります。波の伝わり方を調べることで、地球の中のようすが分かってきました。
海と陸のちがいをくらべよう(見た目・生き物・くらし)
| くらべる項目 | 陸(りく) | 海(うみ) |
|---|---|---|
| 広さ | 地表の約30% | 地表の約70% |
| 高さ・深さ | 山・台地・平野など高低差が大きい | 見た目は平らでもとても深い所も(1万m級) |
| 色・ようす | 緑(森)・茶(土)・白(雪)、四季で変化 | 青〜緑。光できらきら光る |
| 生き物 | 人・動物・植物・虫などすみかが多様 | 魚・イルカ・クラゲ・海草など水中の王国 |
| でき方 | プレートの動き・火山・けずる力 | 雨の水が集まり、へこみにたまり広がる |
| 人のくらし | 住む・育てる・つくる・学ぶ | 食べ物・資源・気候の調整の土台 |
海の色は場所で変わる?
| 海の場所 | 色の見え方 | 主なおもな理由 |
|---|---|---|
| 砂浜の近く(浅い) | 明るいみどり〜水色 | 砂地の反射、浅さ |
| サンゴの海 | うすい青みどり | 白いサンゴ、透明な水 |
| 外洋(沖) | 深い青 | 深さが深く赤色が吸収される |
陸の色も季節で変わる
春の若草、夏の深い緑、秋のもみじ、冬の雪――四季は陸の景色をいろどります。これも地球の自転・公転と、水や空気の流れがつくるリズムです。
もし片方だけだったら?
ぜんぶ海でもぜんぶ陸でも、今のような多様ないのちは生まれにくかったでしょう。海と陸のバランスが、地球をいのちあふれる星にしています。
海と陸があるから生まれる「いのちのバランス」
水の循環が気候をととのえる
海で水があたためられて水蒸気に→雲→雨や雪→川→海へ。これが水の循環。気温や雨のようすをととのえ、森や畑、町のくらしを支えます。
すみかの多様性(森・川・海・山)
山の森、川の流れ、海の浅瀬や深海――環境がちがうほど生き物の種類もふえるので、地球は豊かになります。小さな虫も大きなクジラも、それぞれの場所で役目を持っています。
炭素(たんそ)のやりとり(やさしい説明)
植物は光を受けて空気中の二酸化炭素を取りこみ(光合成)、体をつくります。海の中のプランクトンも同じ働きをし、空気と海のバランスを助けています。
人のくらしと資源
陸では食べ物を育て、住まいや道をつくり、海では魚や海草をいただき、運送やエネルギーの道にもなります。どちらも大切に使い、守ることで、未来へつながります。
46億年のハイライト年表(ざっくり)
| いつごろ | 地球で起きたこと | 海と陸への影響 |
|---|---|---|
| 約46億年前 | 地球のたん生(高温・どろどろ) | 海はまだない |
| 約43〜40億年前 | 地球が冷え、長い雨。海のはじまり | 海が広がる |
| 約35億年前 | 生命のはじまり(海の中) | 海が命のゆりかごに |
| 約25億年前 | 光合成する生き物がふえる | 空気に酸素がふえる |
| 約20億年前〜 | 大陸があつまったり離れたり | 陸の形が大きく変化 |
| 約7000万年前 | 日本のもとになる島々が動き出す | 島弧(とうこ)が形成 |
| 約260万年前〜 | 氷期とあたたかい時期のくり返し | 海面が上がったり下がったり |
| いま | プレートが動き、山や島が生まれ続ける | 海と陸のバランスが続く |
家や学校でできる「地球のしくみ」観察&実験
1. 地図で海と陸の境目をたどる
世界地図で大陸の形や海の広がりを観察。日本の周りの海溝(ふかいみぞ)や火山帯を見つけてみよう。標高や水深の色分け地図もおすすめです。
2. 盆地モデルで川の流れを体験
トレイに砂や土で小さな地形をつくり、上から水を流すと谷ができ、土が運ばれて広がるようすが見えます。けずる→運ぶ→たまる、の流れを実感!
3. しお水の蒸発実験
しお水を浅い皿に入れて日なたに置くと、水だけが蒸発してしおの結晶が残ります。海がしょっぱくなる理由の体験版です。
4. 真水としお水のかさね実験
透明コップに色つきのしお水と真水をそっと重ねると、重さの違いで層に分かれます。海と川が出会う**河口(かこう)**をイメージしてみよう。
5. 地球儀とライトで昼夜・季節を再現
地球儀にライト(太陽役)を当てて回してみよう。昼と夜、季節の仕組みが目で見て分かります。
安全ポイント:水や電気を使う実験は、かならず大人といっしょに行いましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1.どうして海はしょっぱいの?
A. 岩や土の成分が川で少しずつ海へ運ばれ、塩分がたまってしょっぱくなりました。海から水だけが蒸発して塩は残るので、しょっぱさが続きます。
Q2.海の色はなぜ青いの?
A. 水は光の色のうち赤い色を吸収しやすく、青い光が残って目に届くため青く見えます。空の色や海底、プランクトンの量でも色合いが変わります。
Q3.陸は動いているの?
A. はい。プレートが少しずつ動くので、大陸も島も長い時間で位置が変わります。地震や火山は、その動きの表れの一つです。
Q4.砂浜の砂はどこから来たの?
A. 山や岩が川でけずられて運ばれ、海岸で波にまるくされてできたもの。川と海の共同作業です。
Q5.海や陸の広さは変わるの?
A. 氷河の増減や海水温の変化、プレートの動きなどで少しずつ変化します。ただし、人間の一生ではわかりにくいとてもゆっくりした変化です。
Q6.日本に山や火山が多いのはなぜ?
A. 日本の下でプレートがぶつかり合っているから。山がもり上がり、火山が並ぶ火山帯になっています。
Q7.川はなぜ海へ流れるの?
A. 地球の重力で、高い所から低い所へ水が流れるから。山→川→海へとたどり着きます。
Q8.海は全部つながっているの?
A. はい。名前はちがっても、太平洋・大西洋・インド洋などは大きくつながった一つの海です。
Q9.陸はずっと同じ形?
A. 風や雨、波でけずられ、火山やたい積で作りなおされ、ゆっくり変わり続けています。
Q10.海の深さはどうやって調べるの?
A. 船から音を出して、海底から返ってくるまでの時間をはかる音波を使います。
用語辞典(やさしい言いかえつき)
- 大気(たいき):地球を包む空気の層。いのちの毛布。
- 自転(じてん):地球が自分でくるっと回ること。昼と夜のもと。
- 公転(こうてん):地球が太陽のまわりを回ること。四季のもと。
- 地殻(ちかく):いちばん外のかたい部分。私たちの足もと。
- マントル:地殻の下の高温の部分。ゆっくり流れてプレートを動かす。
- プレート:地殻の大きな板。海底と大陸の土台。
- マグマ:地中のどろどろに溶けた岩石。火山の材料。
- 侵食(しんしょく):水や風、氷が岩や土をけずること。
- たい積:けずられて運ばれた土や砂がたまること。
- 水の循環:海→水蒸気→雲→雨・雪→川→海、をくり返す流れ。
- 海溝(かいこう):海のとても深いみぞ。プレートがもぐりこむ場所。
- 磁場(じば):地球がつくる見えない磁石の力。太陽のつぶから地球を守る。
- 潮汐(ちょうせき):月や太陽の引力で海の水位が上がり下がりすること。
- 断層(だんそう):地面がずれてできたきずあと。地震の原因になることも。
- 大陸棚(たいりくたな):海にしずんだ浅い陸地。魚が豊かな場所。
まとめ:海と陸の「二つの舞台」で、いのちが育つ
海と陸は、46億年の時間が作った二つの舞台。
雨が海を育て、プレートの動きが陸をうみ、水の循環とけずる力が形をととのえ続けています。海と陸のちょうどよいバランスがあるから、地球はいろどり豊かな星になりました。
これからも自然を大切にしながら、足もと(陸)と水平線(海)の向こうに広がる地球の物語を学び続けましょう。