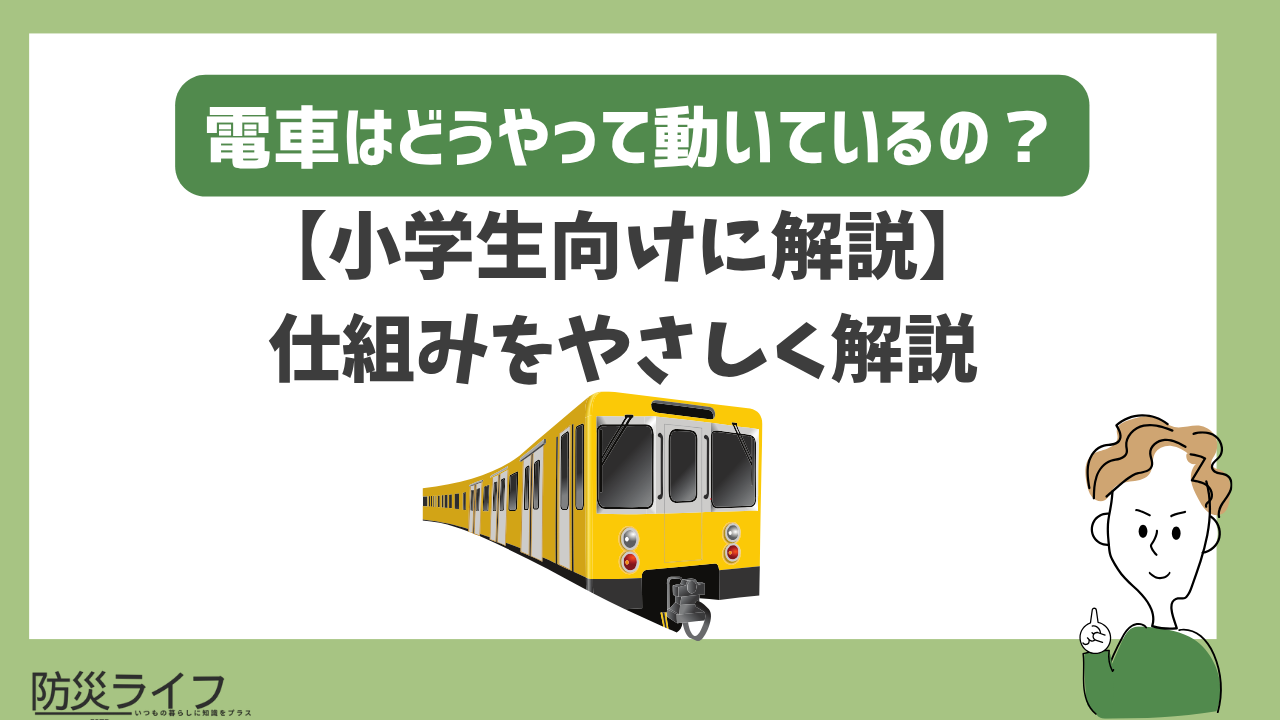毎日走っている電車。線路の上をまっすぐ速く、安全に走れるのは「電気の力」とたくさんの工夫があるからです。この記事では、電気とモーター、レールやブレーキ、駅や信号、運転士さん・車掌さんの仕事、変電所やダイヤのひみつ、そして新幹線・リニア・未来の電車まで、小学生でもスラスラ読める言葉でたっぷり解説します。自由研究のヒントや用語じてんも充実版!
電車は何で動く?電気とモーターの基本
電気の力がエンジンになる
多くの電車は電気の力で走ります。線路の上に張られた電線(架線)から、屋根のパンタグラフで電気を受け取り、車体の下にあるモーターへ送ります。電気はすばやく伝わるので、重い車体でも力強く、しかも静かに走らせることができます。
パンタグラフのはたらき
パンタグラフは、ばねとアームではね上がり、上向きに一定の力で電線にふれて電気を取り込みます。トンネルや橋の上など高さが変わっても、自動で高さを調整して安定して電気を受け取れるしくみです。停車中や車庫では、パンタグラフを下げて電気を切ります。パンタグラフの先についた黒色の**すり板(カーボン)**は、電線とこすれても壊れにくい素材です。
モーターが車輪を回すしくみ
モーターの中では、コイルと磁石が電気で引き合い・反発し、軸が回転します。この回転が歯車や直結軸を通って車輪へ伝わり、電車が動きます。電気の流れ方を変えると、前進も後進も思いのままです。最近の電車は、細かく力を調整できるインバーター制御で、なめらかに加速・減速します。
いろいろな電気の取り方(AC/DC/第三軌条)
日本の電車には、交流(AC)や直流(DC)など地域ごとの電気のちがいがあります。大都市の地下鉄の一部では、上の電線ではなく**レールの横にある“第三軌条”**から靴のような部品で電気を受け取る方式もあります。
蓄電池で走る電車も
近年は車体に蓄電池を積み、電線がない区間でもためた電気で走れる電車も登場。非常時の予備電源としても役立ち、環境にもやさしいのが特長です。
ここがポイント! 電車は「電気 → 回転 → 走る力」という流れで動く。電気はパンタグラフ(または第三軌条)から、走る力はモーターから生まれる。
電気はどこから?変電所と送電のひみつ
変電所(へんでんしょ)の役わり
沿線には変電所があり、発電所から送られてきた高い電圧を電車が使える電圧に変えて架線へ送ります。もし片方が停まっても、別ルートに切り替えられるように、何か所もの変電所が協力しています。
レールも“電気のかえり道”
電車に入った電気はモーターを回したあと、レールを通って変電所へ戻る仕組み。だからレールは電気的にも大切な役目を持っています。
回生電力のゆくえ
回生ブレーキで生まれた電気は、同じ線区の別の電車が使ったり、設備の電源に使われたりします。これで省エネが実現します。
ここがポイント! 変電所は“電車の電気ステーション”。レールは“電気の帰り道”。電車どうしで電気を上手に分け合う!
車体の下はこうなっている:台車・車輪・ブレーキ
台車(だいしゃ)と車輪の形
各車両の下には台車という大きな部品がついています。台車は車輪・軸・ばね・ダンパーをまとめた土台で、揺れをおさえ、カーブでもなめらかに走れるよう支えます。車輪の内側にはフランジという出っ張りがあり、これがレールから外れにくくする安全のつめになります。
連結器(れんけつき)と通路
車両どうしは連結器でつながっています。空気ブレーキのホースや電気のケーブルも一緒に接続され、何両でも同時に操作できるようになっています。中には貫通扉があって、車両間を安全に行き来できます。
ブレーキの種類と役わり
- 空気ブレーキ:空気の力でブレーキを押しつけ、確実に減速。
- 回生(かいせい)ブレーキ:止まるときにモーターを逆にはたらかせ、電気を作って線路側へ戻す。省エネに役立ちます。
- 磁気ブレーキ:磁石の力で強く減速。急勾配や高速運転で力を発揮。
ブレーキは電気の信号で細かく制御され、なめらかに停車できるよう工夫されています。雨や雪の日には、車輪がすべらないようすべり検知や砂まき装置が働くこともあります。
ドア・照明・空調も電気で動く
ドアの開閉、車内の明かり、冷房・暖房、放送もすべて電気で動きます。停車中に明かりを保つための補助電源装置も積んでいます。
ここがポイント! 台車が“足”、モーターが“筋肉”、ブレーキが“安全ベルト”。連結器は“手つなぎロープ”。力を合わせて静かに速く止まれる。
線路と駅のひみつ:レール・まくらぎ・ポイント
レールと道床(どうしょう)
レールは硬い鋼(はがね)ででき、まくらぎと呼ばれる板で等間隔に支えられ、下には砕石(さいせき)の層(道床)が敷かれています。これにより、重い電車の重さを広く分散し、雨でも安定して走れます。近年はコンクリートのスラブ軌道も増え、保守がしやすく静かです。
ポイント(分岐器)のしくみ
ポイントは、線路の進む方向を切りかえる装置。駅や車庫では欠かせません。運転指令や装置が連動していて、安全に切り替えられます。切り替え中は信号が進行を止めるので、ぶつかる心配がありません。
踏切と信号・ホームの安全
踏切では、電車が近づくと警報音と遮断機で人と車を止めます。ホームには案内表示やホームドアがあり、乗り降りを安全に。駅員さんが目視と放送で見守ります。線路脇には信号機や速度標識が並び、運転士が合図通りに走ります。
保守(ほしゅ)と見えない努力
夜間には保線員が、レールのゆがみやボルトのゆるみを点検・修理。架線を見守る電気係や、検査用の事業用車両も活躍しています。
ここがポイント! レールは“土台”づくりが命。ポイントと信号は“交通整理”。見えない夜の作業が昼間の安全を生む。
だれが電車を動かす?運転士・車掌・見えない支える人
運転士のしごと
先頭車両の運転台で、力行(りきこう)レバーとブレーキを操作。速度計・信号・時刻を確認し、滑らかな発車・停止を行います。非常時は非常ブレーキや連絡で安全最優先の判断をします。悪天候では速度をひかえ、安全余裕をとります。
車掌のしごと
ドア開閉、車内放送、ホームの安全確認を担当。運転士と合図や無線で連携し、定刻運行を支えます。体調不良の乗客がいれば救護や案内も行います。混雑時は乗降整理も大切な仕事です。
指令員・保線員・電気係のしごと
駅や線路全体を見渡す運行指令は、ダイヤの乱れに指示を出して回復を図ります。保線員はレール・まくらぎ・砕石の点検と補修、電気係は電線・信号・変電所の点検を行い、毎日安全を支えています。車両基地では検査員がブレーキやドア、車輪の**磨耗(まもう)**をチェック。
自動安全装置(ATS/ATC/ATO等)
決められた速度を超えたり、信号の見まちがいがあっても、自動でブレーキがかかる装置が働きます。ATOは運転士の指示で自動で発車・停車を支援。人の注意と機械の見張りで、安全を二重三重に確保します。
ここがポイント! 電車は“人の目”と“機械の目”が見守るチームプレー。前線だけでなく裏方の仕事が安全を作る。
ダイヤ(時間の約束)と駅のしくみ
ダイヤがあるから時間に強い
電車は秒単位の予定表(ダイヤ)で走ります。駅間の距離・信号・混雑を考えて作られ、運転士・車掌・指令が共通の時計で合わせます。だから時間に正確なのです。
駅のホームと案内
ホームは安全に乗り降りできるよう高さや幅が決められ、バリアフリーのエレベーターやスロープが整っています。発車メロディや案内表示は、乗客がまちがえないための工夫です。
車両基地(きち)
朝のラッシュの前に、車両基地からたくさんの列車が一斉に出てきます。夜は洗浄や給油、点検を受けて休み、翌日に備えます。
ここがポイント! 正確さの裏には綿密なダイヤと大きな車両基地。見えない準備が“時間どおり”を支える。
進化する電車:新幹線・リニア・未来の鉄道
新幹線の工夫
新幹線は流線形の先頭、軽くて強い車体、専用の線路、防音壁、地震時の自動停止など、速さと静かさ、安全を両立させています。ブレーキ時には回生電力も活用し、省エネにも貢献。雪国ではスノープラウ(除雪板)や融雪設備で安定運行します。
リニアのしくみ
磁石の力で車体を少し浮かせて走る方式。こすれる力(摩擦)が小さいので、とても速く走れます。トンネル内の空気の圧力も計算し、耳がキーンとしにくい工夫がされています。
世界の鉄道と環境
世界には二階建て列車や路面電車、ケーブルカーなど個性豊かな鉄道がたくさん。電車は人をたくさん運べて排出が少ないので、地球温暖化対策にも役立ちます。これからは省エネ車両、再生可能エネルギーとの連携、自動運転支援がさらに進みます。
ここがポイント! 「速く」「静かに」「安全に」「環境にやさしく」。鉄道の進化はこの4つを同時にねらう。
しくみ・部品 まとめ表(保存版)
| しくみ・部品 | どんな働き? | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 電線・パンタグラフ/第三軌条 | 電気を車両へ取り込む | ばねで上向きに接触、高さ自動調整/第三軌条は側面から受電 |
| モーター・インバーター | 車輪を回して前進・後退 | 磁石とコイルの力、細かな制御で静かになめらか |
| 台車・車輪・フランジ | 車体を支え、脱線を防ぐ | ばねとダンパーで揺れ吸収、カーブもなめらか |
| 連結器・貫通路 | 車両をつなぎ操作を共有 | 空気・電気も接続、乗務員やお客さんの行き来が可能 |
| ブレーキ(空気・回生・磁気) | 速度を落とし停止させる | 電気信号で制御、回生で省エネ、非常時は強力制動 |
| レール・まくらぎ・道床 | 重さを分散し安定走行 | 鋼レール+まくらぎ+砕石/スラブ軌道で静粛化 |
| ポイント・信号 | 進路と間隔を安全に管理 | 連動装置で誤作動を防止、切替中は進行禁止 |
| 踏切・ホームドア | 人と車を守る | 警報音・遮断機・案内表示、バリアフリー対応 |
| 変電所・帰線(レール) | 電圧を調整し電気を循環 | 多重ルートで停電対策、レールは電気の帰り道 |
| 運転士・車掌・駅員 | 運転・案内・安全確認 | 合図・無線で連携、非常時の対応も訓練済み |
| 指令・保線・電気係 | 見えない所で安全を維持 | ダイヤ整理、線路・電線の点検修繕 |
| 新幹線・リニア | 高速・高安全・省エネ | 流線形、回生電力、磁気浮上など先端技術 |
観察・自由研究のヒント
- パンタグラフを数えよう:何両目に付いている?上下する場面はいつ?図にして位置を記録。
- 車輪の音を聞く:カーブで「きしむ音」がするのはなぜ?直線との違いを書こう。駅ごとに比較。
- 踏切のしくみ調べ:警報が鳴ってから遮断機が下りきるまでの時間を計測。交通量との関係を考察。
- 停車のなめらかさ:最後の数メートルでの減速のしかたを観察し、グラフ化。回生ブレーキの有無を推測。
- 省エネさがし:車内表示やパンフレットから回生電力・省エネの取組みをまとめる。駅のLED照明もチェック。
- 駅のバリアフリー地図:エレベーター・スロープ・多機能トイレの位置を地図に描いて発表。
- ミニ工作:乾電池・モーター・輪ゴムで簡単な“走る台車”を作り、重さとスピードの関係を実験。
Q&A(よくある疑問)
Q1. 電車はなぜ線路の上をまっすぐ走れるの?
A. レールはまっすぐに敷設され、車輪のフランジがガイドの役目をします。さらに台車のばねが揺れを吸収し、まっすぐ走りやすくしています。
Q2. どうして雨の日でもすべらないの?
A. 車輪とレールは金属同士で、もともと接触力が強いです。雨の日は運転士が加速とブレーキを控えめにして安全に運転します。すべりを検知すると自動で調整する装置もあります。雪の場合はスノープラウや融雪器を使う路線もあります。
Q3. 電気が止まったらどうなるの?
A. 変電所は複数の経路で電気を送っているので、片方が止まってもすぐ切り替えられます。非常時は蓄電池やけん引で安全に移動します。駅間で止まったら、乗務員の指示で安全確保を最優先にします。
Q4. ブレーキの「回生」ってなに?
A. 止まるとき、モーターを発電機のように使って電気を作り、線路側(架線や設備)へ戻すしくみです。省エネに役立ち、発熱も少なくて部品が長持ちします。
Q5. 新幹線はなぜとても静かなの?
A. 車体を流線形にして空気の音を減らし、線路沿いに防音壁を設け、車輪・レールの加工も改良されています。トンネルの出入りで起きる空気の“ドン”という音も先頭形状で小さくします。
Q6. リニアはどうして浮くの?
A. 強い磁石の力で車体をわずかに浮かせ、こすれる力を小さくして速く走れるようにしています。浮いているので車輪が不要です。
Q7. ディーゼルの列車は電気を使わないの?
A. ディーゼルエンジンの力で発電してモーターを回すタイプが多く、実は電気の力も使っています。電線がない路線で活躍します。
Q8. 車内が暗くならないのはなぜ?
A. 走行中は架線からの電気、停車中は補助電源装置や蓄電池が電気を供給します。だから停車しても明かりや空調が保てます。
用語じてん
- パンタグラフ:屋根の上で電線にふれて電気を受け取る装置。先にすり板がつく。
- モーター:電気を回転の力に変える機械。インバーターで力加減を細かく調整。
- 台車(だいしゃ):車輪やばねをまとめた足回り。車体を支える土台。
- フランジ:車輪の内側にある出っ張り。レールから外れにくくする。
- 連結器(れんけつき):車両どうしをつなぐ部品。空気や電気の取り合いもできる。
- 回生ブレーキ:止まるときに電気を作って戻す省エネのブレーキ。
- ポイント(分岐器):線路の進む方向を切りかえる装置。
- ATS/ATC/ATO:自動で速度を管理・停止を助ける安全装置。ATOは自動運転支援。
- 道床(どうしょう):まくらぎの下の砕石の層。重さを分散し、雨水もぬけやすい。
- 変電所(へんでんしょ):電圧を変えて架線に電気を送る施設。停電対策も担当。
- 第三軌条(だいさんきじょう):地下鉄などで使う、レール横の電気を通す棒のこと。
まとめ
電車は、電気 → モーター → 車輪という流れで動き、レール・台車・ブレーキが走行を支え、信号・装置・人のチームが安全を守ります。変電所やダイヤ、車両基地など見えない仕組みも大活躍。新幹線やリニアなどの進化も、速さ・静かさ・安全・環境の4つを同時に高めるための工夫です。
次に電車に乗るときは、パンタグラフや台車、ポイントや信号、ホームドアに注目してみましょう。身近な鉄道が、きっともっと面白く見えてきます!