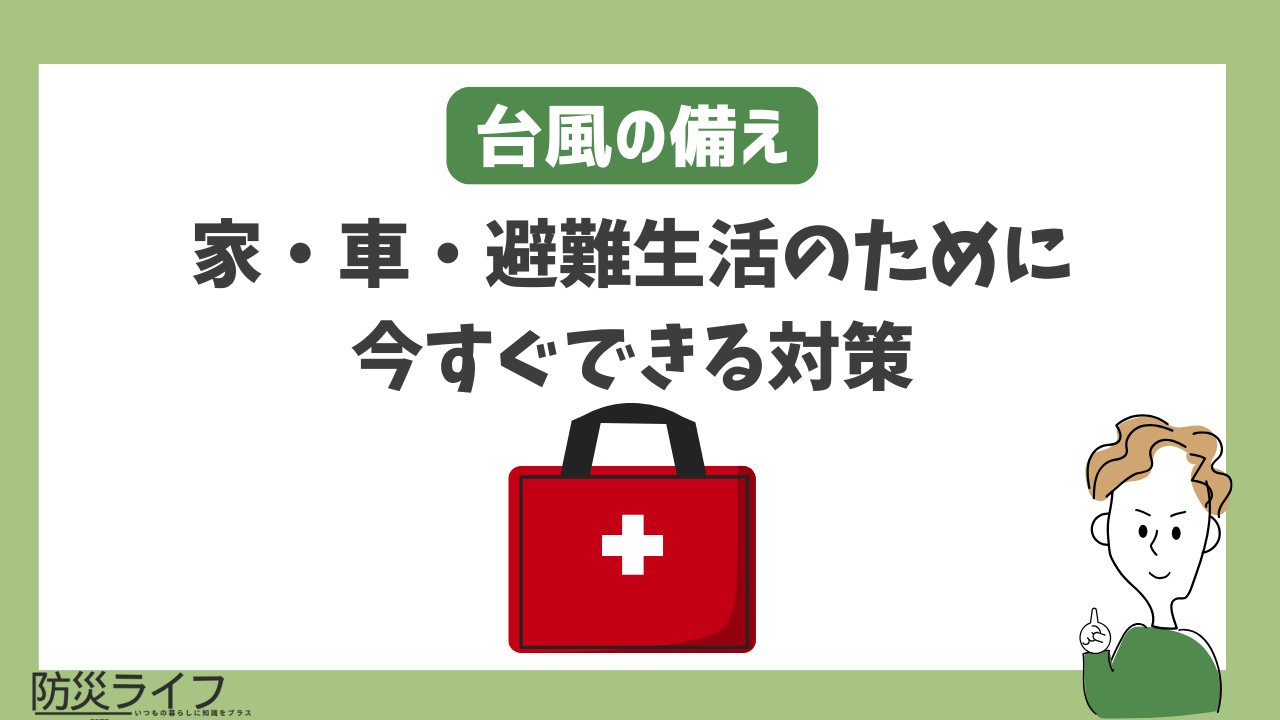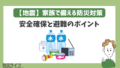台風は“来てから”ではなく“来る前”に勝敗が決まる災害です。 強風・大雨・高潮・土砂災害が同時多発し、停電・断水・浸水・交通寸断・通信障害が重なることで被害が長期化します。本稿は、台風前の下準備から接近時の判断、停電・断水の運用、車と車中避難の安全設計、通過後の復旧、そして次回に生かす検証までを数値と手順で落とし込み、今日から実践できる形にまとめました。家・職場・車・地域ごとに“いざ”の動きを標準化し、命と生活を守る現実的な選択肢を増やしましょう。
0. まずはTL;DR(要点メモ)
- 48時間前:備蓄の不足を埋め、ベランダ退避・排水掃除・車は高台へ。家族の集合場所と**連絡ルール(171・SNSグループ)**を再確認。
- 24時間前:雨戸・養生、浴槽満水、冷凍庫は氷と保冷剤で満たす。防災リュックは玄関へ、靴・雨具・防水バッグをまとめる。
- 接近中:公式情報を時系列で確認。無理な外出禁止、避難は明るいうちに前倒し。窓と背の高い家具の間に立たない。
- 停電・断水時:照明はLEDランタン、調理はカセットコンロ、トイレは携帯トイレ+凝固剤へ即切替。洗い物ゼロ運用。
- 通過後:感電・ガス漏れ最優先。被害は写真・動画で証跡化→罹災証明。うまくいった点/不足を改善リストに反映。
1. 台風シーズン前の下準備|家・備蓄・避難計画を「可視化」する
1-1 屋外の“飛ぶ・詰まる”を先に潰す
台風準備の鉄則は、飛散源の排除と水の行き場の確保。ベランダの植木鉢・物干し・簡易棚・サンシェードは固定または屋内退避。雨どい・集水桝・側溝は落ち葉や泥の詰まりを除去し、敷地内の水はけを改善。プロパンボンベは鎖で転倒防止、屋外コンセントは防水キャップで感電対策。車は冠水マップを確認して高台または立体駐車場へ移動します。
1-2 室内の“濡らさない・割らない・倒さない”
浸水可能性のある階では、冷蔵庫・洗濯機・PC・アルバム・重要書類を上段に退避。延長タップは床置き禁止、配線は結束して高所へ。窓際の家具は移動し、ガラスから1mの安全帯を確保。停電に備え、モバイルバッテリー/ポータブル電源は満充電、非常用ライトは家族が把握する定位置に。窓は飛散防止フィルム+カーテン二重、雨戸は可動確認と潤滑を済ませます。
1-3 情報・家族ルール・避難計画
洪水・土砂災害ハザードマップを家族で確認し、水平避難(安全な遠方へ)と垂直避難(上階へ)の判断基準を共有。避難所までの徒歩ルートを昼・夜・雨天で各1本用意し、集合場所を第3候補まで決めます。連絡は災害用伝言ダイヤル(171)と家族SNSグループを事前にテスト。ペット同伴可否は自治体情報で要確認。
1-4 台風カウントダウン・タイムライン
| 時点 | 家の外 | 家の中 | 情報・移動 |
|---|---|---|---|
| T-72h | 側溝・雨どい清掃/ベランダ整理 | 予備電池・ボンベ購入 | 最新進路とハザード再確認 |
| T-48h | 車を高台へ/飛散物退避 | 冷凍庫を氷で満たす | 171とSNS連絡テスト |
| T-24h | 雨戸閉鎖/屋外コンセント防水 | 浴槽満水・非常食前出し | 避難判断ラインの最終合意 |
| T-12h | 玄関に長靴・雨具・ヘルメット | リュック集約・就寝部屋変更 | 公式情報の定点監視開始 |
1-5 備蓄の“数値目安”早見表(最低ライン)
| 品目 | 1人×3日 | 1人×7日 | メモ |
|---|---|---|---|
| 飲料水 | 9L | 21L | 調理・歯磨き分で+3〜5L |
| 主食(米・パン・麺等) | 9食 | 21食 | 半分は加熱不要を確保 |
| おかず(缶・レトルト) | 6〜9品 | 14〜21品 | 高タンパク意識(魚・豆) |
| カセットボンベ | 3本 | 6本 | 中火60分/本が目安 |
| 簡易トイレ | 15回分 | 35回分 | 1人1日5回換算 |
| 乾電池(単3) | 8本 | 12本以上 | ランタン・ラジオ用 |
コラム|不足が出やすい物:防水バッグ、ゴム手袋、養生テープ、ブルーシート、結束バンド、軍手+薄手手袋の2枚重ね、替え靴下、現金(小銭)。
2. 台風接近〜通過時の行動|情報→判断→実行を“前倒し”する
2-1 公式情報を骨格に据える
気象庁の警報・注意報/線状降水帯予測/河川水位、自治体の避難情報(高齢者等避難・避難指示)を定点チェック。SNSは公式アカウント中心に参照し、拡散情報は一次ソースに戻って確認。
警戒レベルと行動イメージ
| レベル | 目安 | 行動 |
|---|---|---|
| 3(高齢者等避難) | 危険化前 | 準備完了・自発的避難を開始 |
| 4(避難指示) | 危険切迫 | 避難を完了(在宅安全なら垂直避難も) |
| 5(緊急安全確保) | すでに災害発生 | 命を守る最善策(屋内高所等) |
2-2 自宅待機の安全動作
雨戸/シャッター閉鎖+カーテン二重。浴槽に生活用水を満水にし、洗面器・バケツも充填。冷蔵庫は開閉最少、冷凍は保冷剤・ペットボトル氷で延命。窓と背の高い家具の間に立たない、就寝は窓から離れた内側の部屋へ。感電防止のため床に落ちた延長タップは外す。
2-3 避難を“夜になる前に”終える
浸水想定区域/がけ下・崖沿い/1階居室で高潮・増水・土砂のリスクが高い予報なら明るいうちの移動が鉄則。胸より深い水深・速い流れの道路は歩行・走行ともに禁止。避難所では受付→名簿→掲示板を確認し、家族到着の有無を把握。
直前チェック・ミニリスト
- スマホ・電源:100%充電/省電力ON/モバイル電源携行
- 断水:浴槽満水+給水袋/トイレ凝固剤・防臭袋
- 家財:ベランダ退避完了/施錠/ブレーカー位置確認
- 外装備:防水バッグ・長靴・雨具・ヘルメット/避難ルート最終確認
NG例:風雨が強い中での車移動、ロウソク使用、冠水道路への進入、窓辺での見物。
3. 停電・断水・トイレ問題への実装策|“やり切れる”仕組みを作る
3-1 停電:明かり・通信・冷蔵の3本柱
- 明かり:主役はLEDランタン。ヘッドライト併用で両手フリー。ロウソクは転倒火災リスクが高く原則回避。
- 通信:モバイルバッテリー(1万mAh/人)+手回し/ソーラーラジオ。ポータブル電源は**同時充電のルール化(誰が/いつ)**で枯渇を防ぐ。
- 冷蔵:クーラーボックス+保冷剤に早めに移し、冷蔵→冷凍の順で優先消費。IH宅はカセットコンロ必須、換気+一酸化炭素警報器をセット運用。
食品の“危険温度帯”早見表
| 保管温度 | 状態 | 運用 |
|---|---|---|
| 0〜5℃ | 安全域 | 冷蔵庫維持。開閉最少 |
| 5〜10℃ | 注意 | 早めに加熱して消費 |
| 10〜60℃ | 危険帯 | 常温放置NG、短時間で廃棄判断 |
3-2 断水:飲料・生活・衛生の流れを決める
- 飲料:1人1日3Lを厳守。粉末スポドリ・経口補水液で電解質補給。
- 生活用水:浴槽+給水袋で確保。トイレ洗浄は原則せず携帯トイレへ切替。
- 衛生:歯磨きは少量うがい+歯磨きシート、手指はアルコール+ウェット。食器はラップで覆い使い捨て、調理はポリ袋湯せんで洗い物ゼロ運用。
3-3 トイレ:最優先の衛生インフラ
水が止まれば最初にトイレ運用を切り替え。便器に防臭袋+凝固剤で“都度封緘”。就寝前にまとめて処理し、蓋付き保管箱で臭気管理。乳幼児・高齢者はポータブルトイレ、女性はサニタリー専用袋を別管理。
停電・断水ソリューション比較表
| 課題 | 最優先ツール | 代替案 | 運用のコツ |
|---|---|---|---|
| 照明 | LEDランタン | ヘッドライト | 目線の高さと足元の2系統配置 |
| 通信 | 大容量モバイル電源 | 手回し・ソーラー | 充電スケジュールを家族で共有 |
| 調理 | カセットコンロ | 固形燃料 | 1日1回“温食”で士気を維持 |
| 食器 | ラップ運用 | 使い捨て食器 | 水使用ゼロを徹底 |
| トイレ | 携帯トイレ | バケツ+袋+凝固剤 | 子どもも扱える手順書を同封 |
注意:屋内で発電機・BBQグリル・炭火を絶対に使用しない。一酸化炭素中毒は致命的です。
4. 車のリスク管理と車中避難の基礎|“動かす・置く・泊まる”の判断軸
4-1 台風前の車両準備
ガソリン満タン、ワイパー・タイヤ溝・バッテリー点検。車載USB・シガーインバーターで給電を多重化し、ブースターケーブル・牽引ロープ・エアポンプを常備。冠水常習エリアでの駐車は回避し、高台や立体駐車場へ移動。
4-2 運転は原則回避/やむを得ず走るなら
冠水道路・アンダーパスは全面立入禁止。高架・橋梁は横風リスクを見て回避。視界不良時はハザード+減速、吸気音や失火・電装異常を感じたら直ちに停車・退避。
冠水深と走行可否の目安
| 水深 | 歩行 | 乗用車 |
|---|---|---|
| くるぶし(〜10cm) | 可能だが注意 | 不可推奨 |
| ひざ(〜30cm) | 危険:転倒リスク | 不可:吸気・電装リスク |
| 腰(〜60cm) | 極めて危険 | 絶対不可 |
4-3 車中避難の“安全仕様”
駐車は建物の風影・風下を選び、排気ガス逆流防止に換気。シートアレンジ+マット+寝袋で体圧分散、2時間ごとに軽い運動でエコノミー症候群を予防。ブランケット・飲料水・携帯トイレは運転席背面に配置し、夜間も片手で取れる導線に。
車関連チェック表
| 項目 | 実施内容 | 頻度 |
|---|---|---|
| 燃料 | 満タン維持(7割切ったら給油) | 台風期は常時 |
| 駐車 | 高台・立駐へ移動/冠水マップ確認 | 接近48〜24時間前 |
| 装備 | 牽引・ブースター・ポンプ・空気入れ | 季節ごと点検 |
| 車中避難 | 寝具・水・トイレ・換気手段 | 出発前に再確認 |
5. 台風通過後の安全確認と復旧・次への改善|“終わらせ方”も備えの一部
5-1 まずは命の安全を最優先
感電・ガス漏れの危険排除を最優先。ブレーカーは濡れ・焦げ跡の有無を確認し、異常時は復電前に電力会社へ。屋根・外壁・雨どい・窓は双眼鏡や望遠で遠隔確認し、屋根に上らない。浸水時は長靴・厚手手袋・N95相当マスクで泥水・カビ対策を徹底。
5-2 片付け・乾燥・廃棄の手順
濡れた家具はまず乾燥、畳は撤去・乾燥の可否を自治体に確認。食品は水没・危険温度帯に入ったものは廃棄。写真・書類はキッチンペーパーで挟み風乾、家電は通電前に完全乾燥。作業は45分作業+15分休憩で熱中症と疲労を回避。
5-3 記録・申請・保険・再備蓄
被害は時系列の写真・動画で記録(外観→室内→設備→家財)。罹災証明は早めに申請、保険連絡は型番・購入年の分かる写真が有効。今回“足りなかった物”を改善リストにし、備蓄・配置・手順書を更新。家族会議でうまくいった点/改善点を共有し、次回の標準手順に落とし込みます。
通過後チェック&振り返り表
| フェーズ | チェック | 完了 |
|---|---|---|
| 安全確認 | ガス臭無/漏電痕無/倒木・瓦落下なし | □ |
| 片付け | 濡れ家具乾燥/腐敗食品廃棄/床・壁消毒 | □ |
| 手続き | 罹災証明申請/保険連絡/写真整理 | □ |
| 改善 | 不足品購入/備蓄更新/手順書改訂 | □ |
6. 近所・地域とつながる|“個の備え”を“面の備え”へ
- ご近所マップ:バルコニー側の避難はしご、消火栓、雨水桝、電柱番号を共有。
- 見守りリスト:高齢者・要支援者・乳幼児のいる家を平時に把握。LINE/掲示板で連絡網。
- 共用品:脚立・チェーンソー・ウェット&ドライ掃除機などは共同管理が効率的。
- 地域訓練:避難所の開設手順、名簿管理、物資受け入れ動線の実地訓練を年1回以上。
よくある落とし穴:避難所の“開いている扉=受け入れ開始”ではありません。受付が設置され、管理体制が整うまでは安全確保を最優先に行動を。
結論|台風対策は“前倒し・数値化・仕組み化”で強くなる
物を買うだけでは備えは完成しません。どこに置き、誰がいつ何をするかまで決めて初めて、再現性のある防災になります。以下の7日間アップデート計画で、今日から仕組み化を始めましょう。
7日間アップデート計画
- Day1:ハザードマップ確認/家族の連絡・集合ルール確定
- Day2:屋外清掃(側溝・雨どい)/ベランダ退避計画
- Day3:備蓄の棚卸し→不足品購入(表の数量を満たす)
- Day4:窓の飛散防止フィルム/雨戸メンテ
- Day5:非常用ライト配置と定位置マップ作成
- Day6:カセットコンロ運用訓練/ポリ袋湯せんテスト
- Day7:家族ミニ訓練(T-24hシミュレーション)→改善を手順書へ
この記事の表とチェックリストをそのまま家族会議に持ち込み、今日・明日・今週のタスクに落とし込んでください。準備を行動に変えれば、台風は**“対処可能なリスク”**へと姿を変えます。