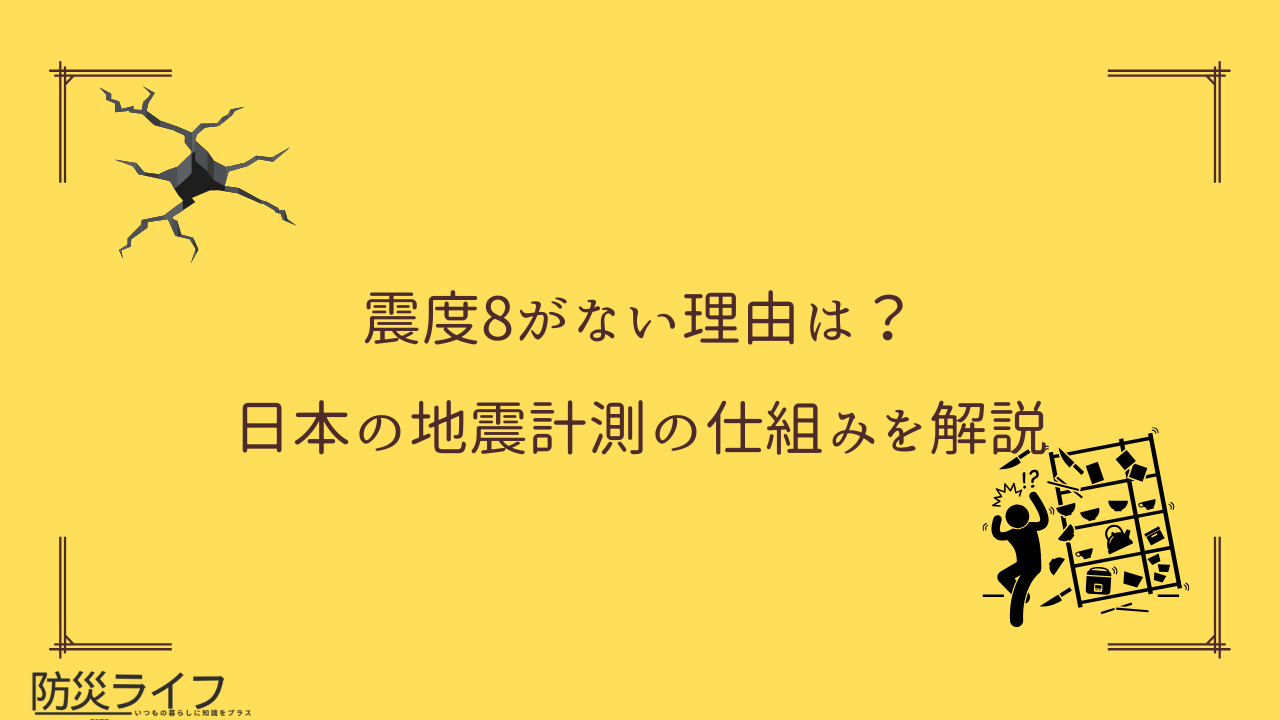日本に地震速報が流れるたびに耳にする「震度」は、その場所で人や建物が受けた揺れの強さを表す指標です。ところが、震度の上限は7であり、「震度8」は存在しません。
本記事では、震度とマグニチュードの違い、震度が0〜7に設計されている理由、震度7を記録した事例とそこで見えた課題、そして数字を行動に翻訳するための実務までを、段落中心で丁寧に解説します。さらに、震度の沿革や長周期地震動との違い、よくある誤解Q&A、家庭・学校・職場でそのまま使える行動表を追加し、“なぜ震度8がないのか”を暮らし目線で腹落ちできるように増補しました。
震度とは何か|“その場所の揺れ”を表す実務の指標
震度とマグニチュードは何が違う?
震度は観測点ごとに異なる局所の揺れの強さ、マグニチュード(M)は地震そのものが放出したエネルギーの大きさ(規模)です。同じ地震でも、震源からの距離・震源の深さ・地盤・建物の条件で、感じる揺れ=震度は大きく変わります。たとえばMが大きくても震源が遠ければ震度は小さく、Mが比較的小さくても都市直下なら震度は極めて大きくなり得ます。
日本の震度階級の構成(現在の10段階)
日本の震度は0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7という10段階で運用されています。5と6を弱・強で細分するのは、被害や行動の分かれ目が大きいため。日常生活の安全確保や行政判断において、どの行動に切り替えるかを素早く決めやすい設計です。
震度はどうやって決まる?(計測震度の考え方)
震度は全国の観測点に設置された地震計のデータから算出される計測震度(連続値)を、上の階級に割り当てて表現します。つまり、体感の申告ではなく機械計測に基づく客観値です。短周期〜長周期の揺れ方の違いも評価に反映されるため、同じ市内でも震度が違うことがあります。これは地盤増幅(表層地盤の性質)や建物の固有周期の差が影響するためです。
震度とマグニチュードの役割の違い(整理表)
| 指標 | 何を表す? | どこで決まる? | 実務での使い方 |
|---|---|---|---|
| 震度 | その場所での揺れの強さ | 観測点ごとの計測結果 | 避難・消防・鉄道の運転判断など |
| マグニチュード | 地震の規模(放出エネルギー) | 震源の性質・破壊の大きさ | 広域影響の推定、津波予測の初期値 |
震度階級と「体感・屋内・屋外・行動」の早見表
| 震度 | 体感の目安 | 屋内で起きやすいこと | 屋外・ライフライン | 推奨行動(要点) |
|---|---|---|---|---|
| 0〜3 | わずかな揺れ〜はっきり感じる | 吊り下げ物が揺れる | 影響小 | 落下物ゼロ化、避難靴を枕元へ |
| 4 | 多くの人が驚く | 棚の物が落ちることあり | エレベーター一時停止 | 通路確保、初期消火具確認 |
| 5弱〜5強 | 物が倒れる・不安定な家具が移動 | 食器・書籍が散乱 | 一部で停電・断水 | 頭部保護→出火確認→扉開放 |
| 6弱〜6強 | 立っていられない/固定家具でも動く | 家具の転倒多数・ガラス破片 | 広域で停電・ガス遮断 | 徒歩避難、近隣の声掛け、安否共有 |
| 7 | 大きな倒壊・非構造部材の落下 | 室内は大混乱 | 幹線の通行止め | 命を守る行動を最優先、車避難は避ける |
なぜ「震度8」がないのか|上限7に収める制度設計の合理性
理由1:行動と被害の観点では“7で十分に実務が回る”
震度階級は人命保護と初動判断を支えるための実務ツールです。震度7は建物の大きな倒壊や甚大な被害が生じ得る上限域として設計されており、それ以上をさらに分類しても、住民や行政の行動が変わりにくいのが現実です。**「避難・救助・消火・通行止め」**といった判断は、7を超えた“細かな差”よりも現場の状況に依存します。
理由2:観測・通信・周知のシステムをシンプルに保つため
震度情報は速報性が命。テレビ、ラジオ、スマホ、鉄道運行など多様なシステムが一斉に動くため、階級が増えるほど誤解や遅延のリスクが高まります。5弱/5強・6弱/6強で行動の分岐点は十分に表現でき、7の上を設ける運用上の必要性が低いのです。
理由3:工学・計測上、“7超の細分”は意味づけが難しい
観測値としての計測震度は連続的に変化しますが、7の上に実務的な閾値をもう一段設けても、対策が変わるだけの再現性ある差を示しにくい側面があります。地盤条件・建物の耐震性能・継続時間などの要因で被害は同じ“7”でも大きく変動し、“7強”“8弱”のような細分は誤解を誘うだけになりかねません。
理由4:国際的な整合と“多指標運用”の方針
世界には体感・被害ベースの強さ指標(例:修正メルカリ度やEMS)も存在しますが、日本は機械計測に基づく震度を中核に、津波警報・長周期地震動階級・土砂災害警戒情報などハザード別の指標を併用する方針です。一つの数値を増やすより、現象ごとに適切な警戒情報を重ねるほうが実務的です。
震度を“7止まり”にしている主な理由(早見表)
| 観点 | 要旨 | 現場での意味 |
|---|---|---|
| 行動 | 7で避難・救助などの判断は足りる | 区分を増やしても行動は変わりにくい |
| 速報 | システム簡素化で誤解・遅延を回避 | 伝達の確実性が最優先 |
| 工学 | 7超の再現性ある差を定義しにくい | 対策の優先順位に直結しにくい |
| 運用 | ハザード別指標と役割分担 | 情報の過多より“使える少数”を重視 |
震度の沿革と周辺指標|“7で打ち止め”の背景にある更新の歴史
沿革の要点
震度階級は時代の被害実態に合わせて見直しが行われてきました。大規模地震の経験を踏まえ、細分化(5弱/5強・6弱/6強)や計測震度の導入など、判断に使いやすい方向へとアップデートされてきました。結果として、上限は7に据えつつ、下位の閾値を精密化する道が選ばれています。
長周期地震動階級との違い
高層建物のゆっくり大きな揺れに対しては、長周期地震動階級(別指標)が運用されています。これは高層での揺れ方と被害リスクに着目したもので、地上付近の強い短周期の揺れを示す震度とは役割が異なる補完関係です。**“震度が低いのに高層で大きく揺れた”**という現象は、この違いで説明できます。
震度7の現実|歴史的な大地震とそこで見えた課題
阪神・淡路大震災(1995)|直下型が都市機能を直撃
都市の基盤施設(道路・鉄道・港湾)が損傷し、旧耐震の建物や家具の転倒が多数の犠牲を生みました。教訓は明快で、耐震改修・家具固定・救助ルートの確保が命の分かれ目になるということです。
東日本大震災(2011)|強震に津波と原子力災害が連鎖
広域の強い揺れに、巨大津波と長期の電力・物流障害が重なりました。ここで突きつけられたのは、「揺れ」だけで被害は語れないという事実。津波避難・在宅継続の装備・多重の事業継続計画が不可欠です。
熊本地震(2016)|短期間に震度7が複数回
連続する最大級の揺れが建物・人の判断に追い打ちをかけました。“一度片づけた室内が再び散乱”という二撃目の危険が顕在化し、突っ張り棒・L字金具・飛散防止など室内減災の徹底が必須だと再確認されました。
北海道胆振東部地震(2018)|広域停電と土砂災害の同時発生
強震により大規模な停電と土砂災害が重なりました。電力の冗長性や非常電源の確保、道路・通信の代替手段の重要性が浮き彫りになりました。
震度7相当の現場で起きやすいこと(整理表)
| 項目 | 起きやすい現象 | 先手の対策 |
|---|---|---|
| 建物 | 旧耐震の倒壊・非構造部材の落下 | 耐震改修・天井材/ガラスの飛散対策 |
| 室内 | 家具転倒・家電の移動・破片の散乱 | L字金具・耐震ジェル・飛散防止フィルム |
| ライフライン | 停電・断水・ガス遮断・通信障害 | モバ電・簡易トイレ・水の分散備蓄 |
| 生活 | 避難所混雑・在宅困難・交通遮断 | 徒歩避難ルートの身体化・近隣の声掛け |
震度よりも“どう守るか”|数値を行動に翻訳する実務
住まい:構造と室内の二段で“倒さない、落とさない”
建物の耐震診断・補強は土台。加えて寝室から先に、大型家具固定・ガラス飛散防止・通路確保を行います。夜間に停電しても動けるよう、枕元にヘッドライト・靴・手袋を常設し、扉の開放を合図に家族の集合動線を固定します。
在宅継続:水・衛生・電源・情報の“四本柱”
水(飲料・生活)、衛生(簡易トイレ・除菌)、電源(モバイル電源・燃料)、情報(ラジオ・充電・家族の合図)を最低3日、できれば1週間。冷蔵の優先消費表を作っておくと、停電時のロスが減ります。集合住宅は給水車受け入れ動線・エレベーター停止時の搬送も事前に決めておきます。
学校・職場:合図の固定と“徒歩優先”の徹底
車は渋滞と延焼で危険になりがち。徒歩・自転車で安全圏へ短距離で上がるルートを昼夜・晴雨で歩いて覚えます。「合流地点はA、公園の東側」「合図は“無事”の一言」のように言葉を固定し、迷いを排除します。職場は代替拠点・分散勤務・バックアップ電源を平時から回しておきます。
震度別・きょうのアクション早見表(家庭版)
| 想定震度 | きょう実施する準備 | 発災直後の行動 |
|---|---|---|
| 5弱〜5強 | 寝室の家具固定・ガラス対策/懐中電灯の常設 | 頭部保護→出火確認→扉開放 |
| 6弱〜6強 | 簡易トイレ・水・モバ電を1週間分 | 徒歩で近隣安全圏へ/近所に声掛け |
| 7 | 在宅と避難の判断レバーを文書化 | 家族の合図で即行動/危険物回避 |
家具固定・室内減災のチェックシート
- L字金具:本棚・食器棚を壁の柱位置に固定
- 耐震ジェル・ストッパー:家電・家具の前滑りを予防
- 飛散防止フィルム:窓・食器棚ガラスの飛散と二次被害を低減
- 通路確保:寝室→玄関の動線上に物を置かない
- 枕元セット:ヘッドライト・靴・手袋を常設、笛も有効
よくある誤解と最新事情|「7弱はある?」「速報の数値は?」
Q1:「震度7弱」や「7強」はありますか?
ありません。 震度5と6だけが弱・強に分かれ、7は一つだけです。メディア表現で「7弱」のように言うのは誤りです。
Q2:速報の“推計震度”と最終の“震度”は違う?
速報段階では限られた情報で推計震度が出ることがあります。観測データが集まり次第、最終的な震度に更新されるため、後から数値が変わることは珍しくありません。慌てず最新の確定情報を確認しましょう。
Q3:海外の“震度”と日本の震度は同じ?
国や地域で尺度も運用も異なります。日本の震度は機械計測に基づく階級で運用され、避難や運行判断など実務に直結する前提で整えられています。海外の尺度名が似ていても、同じ意味とは限りません。
Q4:震度は“最大加速度”だけで決まる?
いいえ。 揺れの持続や周波数特性(短周期・長周期)など体感と被害に効く要素も組み込んだ総合指標として設計されています。だからこそ、同じ最大加速度でも震度が違うことがあります。
Q5:震度が同じなら被害は同じ?
違います。 建物の耐震性能・築年・地盤条件・継続時間・火災の有無などで被害は大きく揺れます。**“震度=被害額”**ではありません。だからこそ、個別の対策が重要です。
Q6:高層で大きく揺れたのに震度が低いのはなぜ?
長周期地震動の影響です。高層の固有周期に合う揺れは長く大きく感じる一方、地上付近の短周期成分を重視する震度では数値が小さく出ることがあります。指標の役割が違うと理解してください。
まとめ|“震度8がない理由”は、命を守る設計思想にある
震度は0〜7で完結する実務の言語です。7を超える細分を作っても、行動や対策は変わりにくい——それが**「震度8がない理由」の核心です。過去の大地震は、耐震・室内減災・在宅継続・徒歩避難という普遍の基本を教えてくれました。数値に一喜一憂するより、生活導線に落とし込む。 きょう15分だけ**、寝室の安全化と家族の合図の固定を進めてください。準備を始めた瞬間から、あなたのリスクは確実に下がります。