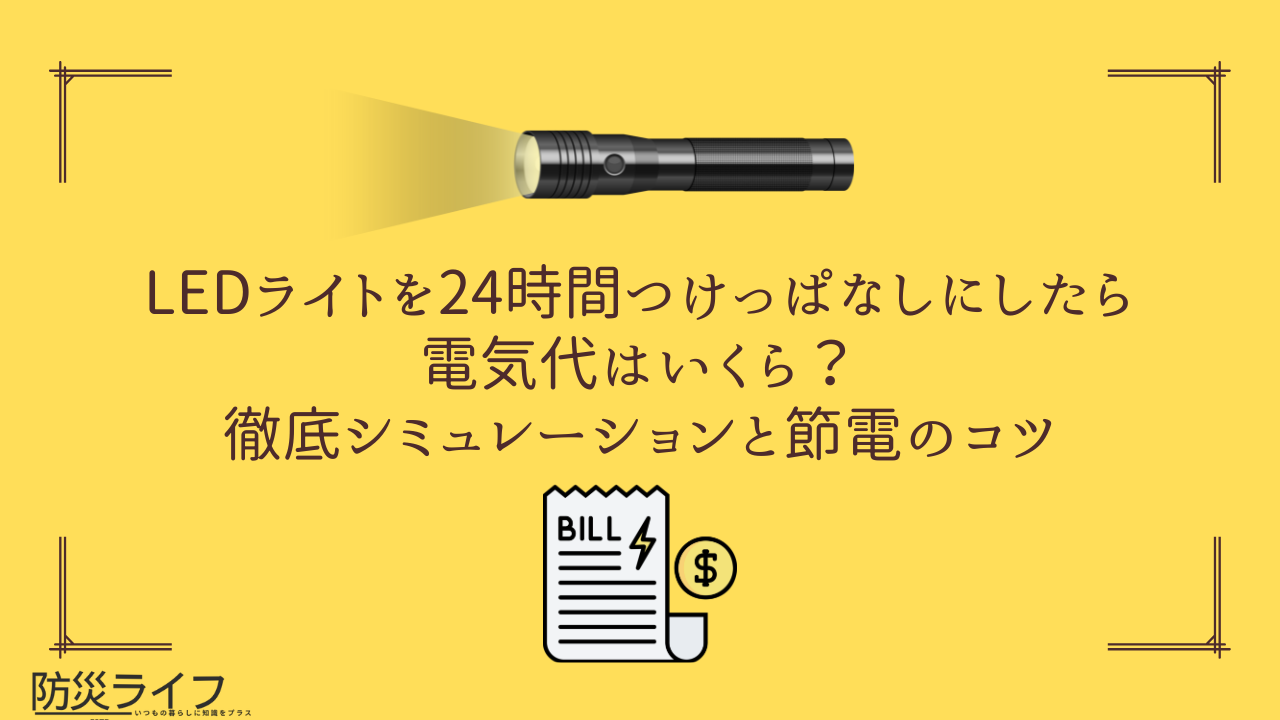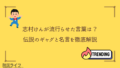はじめに、LEDライトは長寿命で省エネですが、「24時間つけっぱなしでも本当に安いのか?」は暮らしの実感として気になるところです。本記事では、家庭と小規模店舗でよく使う3〜30W帯を中心に、電気代の計算式→消費電力別の試算表→生活シーン別の目安→節電の実践→Q&Aと用語までを、そのまま使える数値で総整理します。
前提は電力単価27円/kWh(例)で試算し、単価が変わる場合の感度表や複数灯・待機電力、CO2排出量の概算も提示。金額は概算で、地域・契約・実測値で上下します。
1.LEDライトの電気代の基本(まずここから)
1-1.LED電球のワット数と明るさの目安
家庭用LEDは5〜15Wが主流(白熱40〜100W相当)。天井のシーリングやダウンライトは15〜30Wの器具も一般的です。たとえば10WのLEDは、白熱60W級の明るさに相当しながら、消費電力は約1/6に抑えられます。廊下や玄関は3〜7Wでも用途次第で十分なことが多く、必要な明るさに合わせてW数を下げるのが節電の第一歩です。
1-2.消費電力が電気代にどう効くか(比例関係)
電気代はワット数に比例します。倍のW数→電気代もほぼ倍。3W・5W・10Wの差は小さく見えても、24時間×365日積み上がると年間でははっきり差が出ます。複数灯が同時に点く空間(廊下・オフィス・店舗)では合算での管理が重要で、1灯のW数×灯数でまず年額を把握しましょう。
1-3.白熱・蛍光とのちがい(発光効率と熱)
白熱は電力の多くが熱になり非効率、蛍光は起動や部品の寿命差が出やすい。一方LEDは発光効率が高く、同じ明るさに必要な電力は白熱の約1/5以下、蛍光の約1/2〜1/3が目安。長時間点灯ほどLEDの優位は大きくなります。さらにLEDは瞬時点灯で、こまめな消灯と相性が良いのも利点です。
1-4.暗算の基本(覚えておくと便利)
1時間あたりの電気代= 消費電力(W)×0.027(円)
24時間あたりの電気代= 消費電力(W)×0.648(円)
※27円/kWh前提。例:15W×0.648=9.72円/日。
2.24時間つけっぱなしの電気代を徹底シミュレーション
2-1.計算式(シンプル)
電気代(円)= 消費電力(kW) × 使用時間(h) × 電力単価(円/kWh)
例:10W=0.01kW、24時間、27円/kWh → 0.01×24×27=6.48円/日。
2-2.単価の前提と丸め方(ブレの見方)
家庭向けの例として27円/kWhで算出(小数点は1日:小数第2位、年:10円単位目安で四捨五入)。実際は基本料金・燃料調整・時間帯別単価で変動します。深夜割安などのプランでは、夜間比率が高いほど年額が下がる可能性があります。
2-3.消費電力別の試算表(24時間点灯)
計算基準:電力単価27円/kWh、24時間点灯。
| 消費電力(W) | 1日あたり(円) | 年間(円) |
|---|---|---|
| 3 | 1.94 | 710 |
| 5 | 3.24 | 1,180 |
| 7 | 4.54 | 1,660 |
| 10 | 6.48 | 2,360 |
| 12 | 7.78 | 2,840 |
| 15 | 9.72 | 3,550 |
| 20 | 12.96 | 4,730 |
| 25 | 16.20 | 5,910 |
| 30 | 19.44 | 7,100 |
感度チェック(10Wのときの単価差)
| 単価(円/kWh) | 1日あたり(円) | 年間(円) |
|---|---|---|
| 24 | 5.76 | 2,100 |
| 27 | 6.48 | 2,360 |
| 31 | 7.44 | 2,720 |
| 35 | 8.40 | 3,070 |
| 40 | 9.60 | 3,500 |
2-4.複数灯・複数部屋の合算例(よくあるケース)
| 場所 | 灯数×W数 | 点灯時間/日 | 1日(円) | 年間(円) |
|---|---|---|---|---|
| 玄関・廊下(足元灯) | 2×5W | 12h | 3.24 | 1,180 |
| 廊下ダウンライト | 3×7W | 8h | 3.63 | 1,330 |
| リビング天井灯 | 1×24W | 6h | 3.89 | 1,420 |
| キッチン手元灯 | 1×10W | 4h | 1.08 | 400 |
| 子ども部屋常夜灯 | 1×3W | 10h | 0.81 | 300 |
| 合計 | 12.65 | 4,630 |
※27円/kWh。概算。
2-5.待機電力にも注意(スマート照明の常時通信)
Wi‑Fiや無線でつながるスマート電球は、消灯時でも0.2〜1W程度の待機電力が発生する場合があります。
| 待機電力(W) | 1日(円) | 年間(円) |
|---|---|---|
| 0.2 | 0.13 | 47 |
| 0.3 | 0.19 | 71 |
| 0.5 | 0.32 | 118 |
| 1.0 | 0.65 | 237 |
待機分は24時間×365日効いてくるため、台数が多い家庭・事務所では合計で数千円/年になることも。必要な場所だけスマート化するのが賢明です。
2-6.CO2排出の目安(環境の視点)
排出係数を仮に0.45kg-CO2/kWhとすると、10Wを24時間点灯で0.01kW×24h×0.45=0.108kg-CO2/日、年で約39kg-CO2。W数を下げる・点灯時間を短くするほど、家計と環境の両方に効果があります(係数は地域・契約で異なります)。
3.生活シーン別:24時間点灯が増えがちな場所と目安
3-1.玄関・廊下・足元灯(見守り・安全)
夜間は常時点灯にしがちな場所。3〜5Wの小型LEDなら、24時間でも日あたり1〜3円台。人感や明暗センサーと組み合わせると体感明るさは維持しつつ消費をさらに削減できます。乳白カバーや拡散型を選ぶと、低Wでもムラの少ない明るさになります。
3-2.寝室・子ども部屋の常夜灯(安心)
3W前後の常夜灯は、24時間でも年間700円前後(27円/kWh)。睡眠を妨げにくい電球色やまぶしさを抑えるカバーの採用で、低出力でも十分に感じます。夜間だけでよい場合は明暗センサーと併用を。
3-3.店舗看板・水槽・植物育成(業務・趣味)
看板は20〜30Wが複数灯になると年数万円に達するケースも。水槽・育成は15〜30Wで、24hではなく12〜16hの点灯管理が基本。タイマーで自動化すると、コストと品質を両立しやすくなります。屋外は明暗センサーで昼間の無駄点灯を防止しましょう。
3-4.浴室・洗面・トイレ(短時間の積み重ね)
在室時間は短くても回数が多い場所。人感センサーやゆっくり消える機能で、つけ忘れ・消し忘れを減らすと効果的。鏡まわりは拡散の良い器具に替えると、W数を上げずに見え方の満足を確保できます。
参考:よくある使い方の目安(24hでない日常パターン)
| シーン | 代表W数 | 点灯時間/日 | 1日(円) | 年間(円) |
|---|---|---|---|---|
| 玄関の足元灯 | 5W | 12h | 1.62 | 590 |
| 廊下ダウンライト | 7W×2灯 | 8h | 2.42 | 880 |
| リビング天井灯 | 24W | 6h | 3.89 | 1,420 |
| 看板(屋外) | 30W×4灯 | 12h | 38.88 | 14,200 |
| 水槽ライト | 20W | 12h | 6.48 | 2,360 |
※前提は27円/kWh。概算。
4.つけっぱなしでも電気代を抑える実践テクニック
4-1.自動制御:タイマー・人感・明暗センサー
点けるべき時だけ点ける仕組みが最強。廊下・トイレは人感、屋外は明暗、水槽・育成・看板はタイマー。夜間は照度を1段階下げる設定も効果的です。スマート照明は必要箇所だけ導入し、待機電力にも目配りしましょう。
4-2.明るさ設計と配光:必要十分にする
明るさはルーメン(光の量)で比較し、眩しさは配光・カバー・色温度で抑えます。過剰なW数を使わないことが、24時間運用の最大の節電です。壁や天井の汚れを拭き取るだけでも反射率が上がり、同じW数で明るく見えます。
4-3.製品見直しと契約:効率と単価を同時に下げる
古いLEDから高効率モデルへ更新すると10〜20%の省エネも。器具側の待機電力や常夜灯モードの有無も確認。電力契約は時間帯別・季節別のプランで実使用に合う単価を選ぶと効果が出ます。基本料金の見直しも年に一度チェックを。
4-4.安全と相性:長寿命のための下ごしらえ
密閉器具には対応製品を。高温環境・浴室では防湿・防滴の仕様を選びます。調光器(明るさ調節)対応のないLEDを調光器で使うとちらつき・故障の原因になります。パッケージの適合表示を必ず確認しましょう。
4-5.節電の優先順位づけ(効果の大きい順)
1)24時間点灯の見直し→2)W数の適正化→3)自動制御の導入→4)高効率モデルへの更新→5)契約単価の見直し。まず24時間点灯の灯りから手を付けるのが、最短で効果が見える順番です。
5.Q&A・用語辞典・計算のコツ(仕上げ)
5-1.Q&A(よくある疑問)
Q1:LEDを24時間点けっぱなしでも大丈夫?
A:器具の仕様温度・放熱が守られていれば問題ありません。密閉器具や高温になる場所は器具対応のLEDを選びましょう。ほこりの堆積は発熱の原因になるので、定期的に拭き取りを。
Q2:こまめに消すよりつけっぱなしが得?
A:LEDは点滅で寿命が大きく縮むタイプではないため、使わない時間は消す方が得です。人感・タイマーの併用がおすすめ。長時間の外出時は主電源からOFFが安心です。
Q3:色温度(電球色・昼白色)で電気代は変わる?
A:同じW数なら電気代は同じです。見え方の違いで必要明るさが変わることはあります。寝室は電球色の方が低Wでも落ち着いて感じやすいです。
Q4:電力単価が上がったらどう試算すればいい?
A:W÷1000×時間×単価で置き換えるだけ。10Wを24h、単価31円なら7.44円/日、約2,720円/年です。1時間あたりはW×0.031円で即算できます。
Q5:寿命の差は電気代に影響する?
A:消費電力が同じなら電気代は同じ。ただし交換頻度や手間、購入費はトータルコストに響きます。長寿命・高効率の両立製品を選ぶと安心です。
Q6:スマート照明の待機電力は気にすべき?
A:0.2〜1Wの待機が常時発生する場合があります。台数が多い家庭は合計で数千円/年になることも。必要な場所だけ採用する、ハブ型で集約するなどの工夫を。
Q7:調光器との相性が不安です。
A:調光対応の表示がない電球は避けましょう。相性が悪いとちらつき・発熱が起きます。試験的に1室だけで導入→問題なければ全室へ拡大が安全です。
Q8:昼間は自然光があるのにつけっぱなし…対策は?
A:明暗センサーや人感センサーを併用し、必要時だけ点灯に切り替えます。窓際は配光の見直しでW数を下げられることが多いです。
Q9:屋外配線の安全は?
A:屋外は防水コネクタ・防滴器具を使用。延長コードの屋外用表示や防雨カバーの有無を確認し、たわみや結露を防ぎます。
Q10:どこから節電を始めるべき?
A:24時間点灯の3か所(玄関足元・廊下・常夜灯)→待機電力(スマート照明)→店舗看板の順に点検すると、費用対効果が高い順で結果が出ます。
5-2.用語の小辞典(やさしい言い換え)
ワット(W):機器がどれだけ電気を使う速さ。
キロワット時(kWh):電気代の計算単位。1kWを1時間使うと1kWh。
ルーメン(lm):明るさ(光の量)の単位。
色温度:光の見え方の色味。電球色はあたたかい、昼白色は白っぽい。
人感センサー:人の動きに反応して点灯・消灯。
明暗センサー:周囲の明るさで自動点灯・消灯。
配光:光の広がり方。眩しさやムラに影響。
調光:明るさ調節。対応表示のない電球は不可。
5-3.計算の型(家計メモにそのまま)
- 1日あたり(円)= W×0.027×使用時間(h)
- 24時間の1日(円)= W×0.648
- 月(円)=(1日あたり)×30/年(円)=(1日あたり)×365
- 複数灯はW×灯数に置き換えて同じ式でOK。
まとめ
LEDは24時間点灯でも1灯あたり数円〜十数円/日と経済的。ただし複数灯・高W・長時間が重なると年単位の負担になります。まずは24時間点灯の見直し、ついでW数の適正化、自動制御の導入、高効率モデルへの更新、契約単価の見直しの順で整えましょう。W数の暗算(0.648)を手元に置き、今日からあなたの灯りの設計を最適化してください。