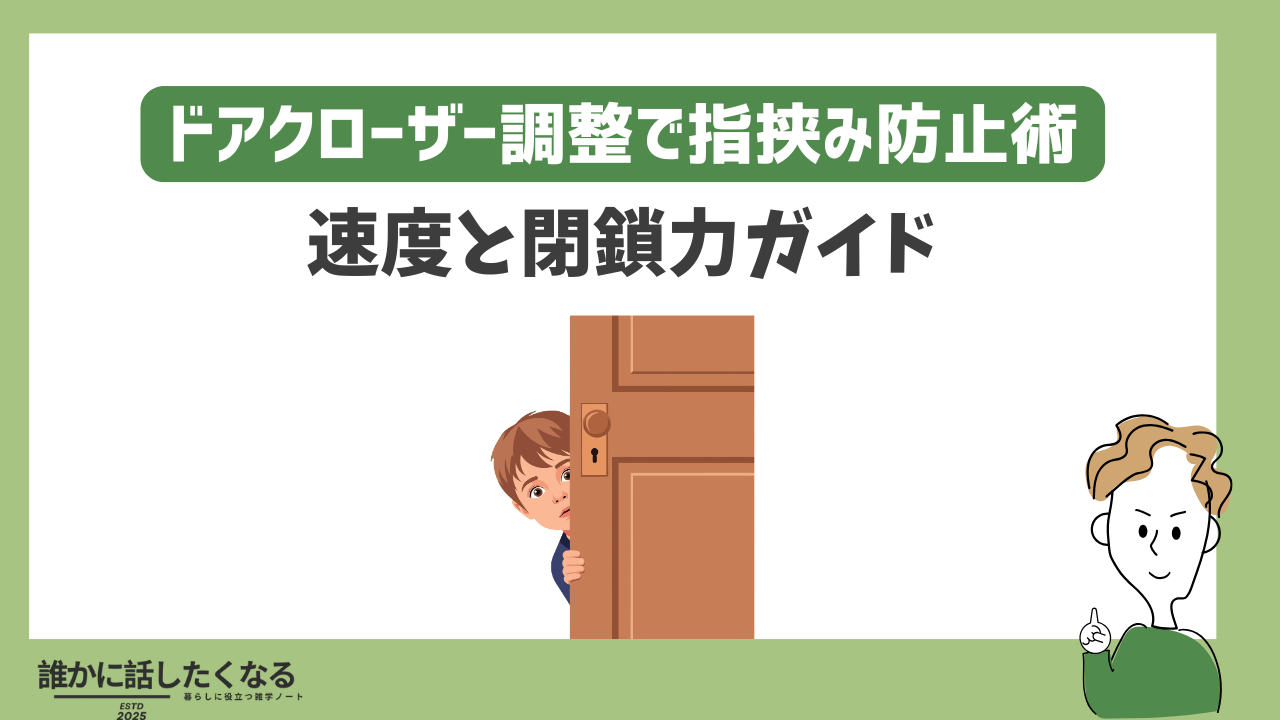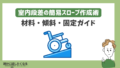「ゆっくり閉まる・最後は確実に閉じる・手をはさまない」。 ドアクローザーは速度と閉鎖力を数本の調整ねじで微調整するだけで、安全性・静かさ・閉まり切りを同時に高められる。
この記事は、基本構造の理解→安全準備→調整箇所の見分け→段階的な手順→点検と記録までを、家庭・事務所・店舗でそのまま使える実務手順に落とし込んだ。さらに季節差・気圧差・扉重量の影響、番手選定の目安、NG調整の見分け方、交換の合図まで踏み込み、表・チェックリスト・Q&A・用語辞典を添えて、初めての人でも迷わず仕上げられる内容にしている。
1.まず知る——ドアクローザーの働きと安全原則
1-1.三つの速度と一つの力(全体像)
ドアクローザーは一般に三つの速度域と一つの閉鎖力で考えると理解が早い。
- 開放域(バックチェック):大きく開けたときの急加速を吸収。壁・人・扉の破損を防ぐ安全装置。
- 中間域(スイープ):開放角からおおむね10〜15cm手前までの基準速度。ここが落ち着けば安心感が出る。
- 終端域(ラッチ):最後の10〜15cmで錠前(ラッチ)を押し込む速度。速すぎると指挟み、遅すぎると半ドア。
- 閉鎖力(バネ力):風・気圧差・気密材の抵抗に負けず閉まり切るための根本の力。強すぎると勢いが出やすい。
1-2.指挟みを防ぐ三原則(要点を先に)
1)終端域(ラッチ)の速度を弱める——最後は1.5〜2秒で静かに。
2)中間域(スイープ)をやや遅め——1秒で10〜15cmが目安。
3)閉鎖力は「最小限で確実に閉まる」——強すぎは事故の元、弱すぎは半ドア。
NG例:ラッチを速くして閉鎖力で押し切る設定。→指挟み・衝突音・金物摩耗の三重苦になる。
1-3.作業前の安全準備(最小セット)
- 保護手袋・脚立・養生テープ・+/−ドライバー、可能ならトルクをかけやすい短軸ドライバー。
- 戸当たり(扉止め)を下に入れて不意の閉鎖を防止。
- 調整ねじは1/8〜1/4回転ずつ。回しすぎ・抜きすぎ厳禁(油漏れ・故障の原因)。
- 記録:回す前に現状の位置をメモ(写真推奨)。元に戻す退路を確保。
2.見極め——調整ねじの位置と名称を理解する
2-1.外観で分かる主なねじ(一般例)
| 名称 | 役割 | 目安位置 | 調整方向の効き方 |
|---|---|---|---|
| スイープ速度ねじ | 中間域の速度を決める | 側面または前面 | 締める→遅く/緩める→速く |
| ラッチ速度ねじ | 終端(最後10〜15cm)の速度 | 側面の別穴 | 締める→ゆっくり/緩める→速く |
| バックチェックねじ | 大きく開いたときの急激な開きを抑える | 側面または上面 | 締める→強く効く |
| 閉鎖力(ばね)段階 | ばね力の総量 | 本体側面やアーム部の表示 | 強→弱の段階切替 |
※機種により名称・位置は異なるが、役割は共通のことが多い。カバーを外すタイプは落下防止に注意。
2-2.アーム位置と取り付け姿勢(効きの土台)
- アーム角度が初期動作を左右する。基準線(扉枠)とほぼ水平を目安に。
- パラレル型(枠側にアーム)は見た目すっきりだが効率はやや低め。スタンダード型(扉面にアーム)は効率高め。調整思想は同じ。
- 開き勝手(内開き/外開き)で風の受け方が変わる。外開きで風を受ける入口は閉鎖力をわずかに強め、ラッチはさらに遅めが安全。
2-3.不具合の初期診断(症状→原因→最初の一手)
| 症状 | よくある原因 | まず調整する箇所 |
|---|---|---|
| 最後でバタンと閉まる | ラッチ速度が速すぎ/閉鎖力が強すぎ | ラッチ速度ねじを締める→改善なければ閉鎖力を一段下げる |
| 半ドアになる | ラッチ遅すぎ/閉鎖力不足/錠のかみ合わせ不良 | ラッチ速度ねじを少し緩める→閉鎖力を一段上げる→受け金具を微調整 |
| 途中で止まる・戻る | スイープ遅すぎ/気圧差(換気扇)/丁番の抵抗 | スイープ速度を少し速く→換気停止→丁番注油 |
| 開けた瞬間に壁へ当たる | バックチェック弱い/開き角制限なし | バックチェックを締める/戸当たり設置 |
| ギイ音・がたつき | 丁番摩耗/固定ねじ緩み | 丁番へ注油・ねじ増し締め |
番手(サイズ)早見:扉幅900mm・重量30〜40kg→中位の番手。幅1,000mm超・重量40kg超→一段上を検討(ただし閉鎖力は最小で運用)。
3.実践——指挟みを防ぐための調整手順(標準)
3-1.基準化:いったん“中庸”にそろえる
1)スイープを中速(1秒で10〜15cm閉じる体感)に合わせる。
2)ラッチを遅め(最後10cmで1.5〜2秒)。ここが最重要。
3)閉鎖力は現状より一段弱くし、閉まり切るかを確認。閉まり切ればその強さが基準。
手順のコツ
- 各ねじは1/8回転ずつ、合計1/2回転以内で様子を見る。
- ねじを回す前に写真→回した方向と角度をメモ→10回テストで再現性を確認。
3-2.微調整:現場条件に合わせるプリセット
- 子ども・高齢者が通る家:ラッチ遅め・スイープ遅め・閉鎖力最小。丁番・受けの摩擦低減もセットで。
- 強風や気圧差のある入口:閉鎖力やや強め、ただしラッチは遅め。バックチェック強めで開け過ぎ防止。
- 防音重視のオフィス:スイープ遅め・バックチェック強めで静音、ラッチは静かに押し込む設定。
速度の目安(体感の物差し)
| 区分 | 目安 | 指挟みリスク |
|---|---|---|
| スイープ(中間) | 1秒で10〜15cm | 低〜中(手を離しやすい) |
| ラッチ(終端) | 最後10cmで1.5〜2秒 | 低(安全寄り) |
| 速すぎ | 最後10cmで0.5秒以下 | 高(要調整) |
3-3.確認:10回試験・温度差・運用テスト
- 連続10回、同じ角度から手を添えて閉め、終端速度・錠のかかりを確認。
- 夏冬・朝晩で油の粘りが変わる。寒い時期は遅く、暑い時期は速くなりがち。季節ごとに1/8回転を目安に見直す。
- 利用者テスト:子どもや高齢者に付き添い、手をかけたまま閉める動作が安全にできるかを観察。
4.仕上げ——静かで確実な閉まりをつくる細工
4-1.扉まわりの摩擦・気圧を整える(見落としがち)
- 戸当たりゴム・気密材が強すぎると半ドア。薄いものへ交換か当たりを削って微調整。
- 換気扇・空調の強運転は気圧差を生み閉まりにくい。給気口を開けるか運転を弱める。
- 敷居の段差・ドア下ブラシが擦ると速度が乱れる。干渉部の調整で解決。
4-2.丁番・ラッチ・受けの手入れ(半ドア対策の王道)
- 丁番の軸に少量の油を差すとギイ音・戻りが減る。緩みは増し締め。
- 錠前ラッチと受け金具は面で当てるのが理想。受けを0.5〜1mm範囲で調整し、角で引っかからないように。
- 油にじみ・オイル漏れが本体から出ていたら故障サイン。調整で直らないなら交換を検討。
4-3.表示・教育・点検(運用を仕上げる)
- 「手をかけたまま閉める」「小さな子は先に通す」など運用ルールを目線の高さへ掲示。
- 指は蝶番側に近づけないと明記。戸先側にも注意ピクトを。
- 月次点検で速度・音・がた・油にじみをチェックし、記録を残す。
周辺要因の点検表(仕上げ用)
| 項目 | 良好 | 要改善 |
|---|---|---|
| 気密材の押し返し | 軽い | 強くて半ドア |
| ラッチ受けの位置 | 面で当たる | 角で引っかかる |
| 丁番のがた | なし | 上下にがたつく |
| 敷居・ドア下の擦れ | なし | 擦って速度乱れ |
| 本体の油にじみ | なし | にじみ・漏れあり |
5.運用・Q&A・用語——長く安全に使うために
5-1.月次点検シート(貼って使える)
| 月 | スイープ | ラッチ | 閉鎖力 | 音・がた | 油にじみ | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ○/× | ○/× | ○/× | ○/× | ○/× | |
| 2月 | ○/× | ○/× | ○/× | ○/× | ○/× | |
| 3月 | ○/× | ○/× | ○/× | ○/× | ○/× | |
| … |
5-2.よくあるQ&A(実務に効く)
Q:最後だけ強く閉まって危ない。
A:ラッチ速度ねじを1/8〜1/4回転締めて終端をゆっくりに。それでも強いなら閉鎖力を一段下げる。受け金具の抵抗も確認。
Q:半ドアになる(気密住宅・強風時)。
A:ラッチをやや速くしつつ閉鎖力を一段上げ、給気口を開ける。気密材の当たりも見直す。
Q:寒い朝に急に遅くなる。
A:油の粘りが原因。スイープ・ラッチを各1/8回転だけ速めに。暖かい季節に元へ戻す。
Q:開けたとき壁へ当たる。
A:バックチェックを締め、戸当たりを壁側へ設置。開き角制限をつくる。
Q:重い扉で手をはさみそう。
A:閉鎖力を必要最小限へ下げ、ラッチを遅く。可能ならソフトクローズ寄りの機種へ更新。
Q:ねじを回しても効きが出ない。
A:回し切り/抜き過ぎの恐れ。元位置に戻す→少しずつやり直す。油漏れがあれば交換。
Q:防火戸(自動閉鎖が必要)での注意は?
A:自閉機能を阻害しないことが最優先。保持開(ストップ)は不可の場面がある。ラッチを遅くしつつ閉まり切る範囲で調整。
5-3.用語辞典(平易な言い換え)
スイープ速度:開放状態から途中までの閉まる速さ。
ラッチ速度:最後の10〜15cmの速さ。錠前を押し込む。
バックチェック:大きく開いたときの急加速を抑える機能。
閉鎖力(ばね力):閉まり切る力の強さ。段階調整あり。
半ドア:錠がかからずに中途で止まること。
戸当たり:扉や壁を守る当て金具やゴム。
受け金具(ストライク):ラッチがかみ合う側の金具。
番手:扉サイズ・重量に合わせたクローザーの大きさ区分。
パラレル/スタンダード:取付姿勢の違い(枠側/扉面)。
まとめ
指挟みを防ぐ鍵は、ラッチをゆっくり・スイープを落ち着かせ・閉鎖力は必要最小限という三点セット。さらに丁番・気密・錠前を整え、気圧差を味方につければ、静かで確実に閉まる扉が完成する。作業は1/8回転ずつ、10回試験で確かめ、季節ごとの見直しを続ける。今日の微調整が、明日のヒヤリをゼロに近づける。