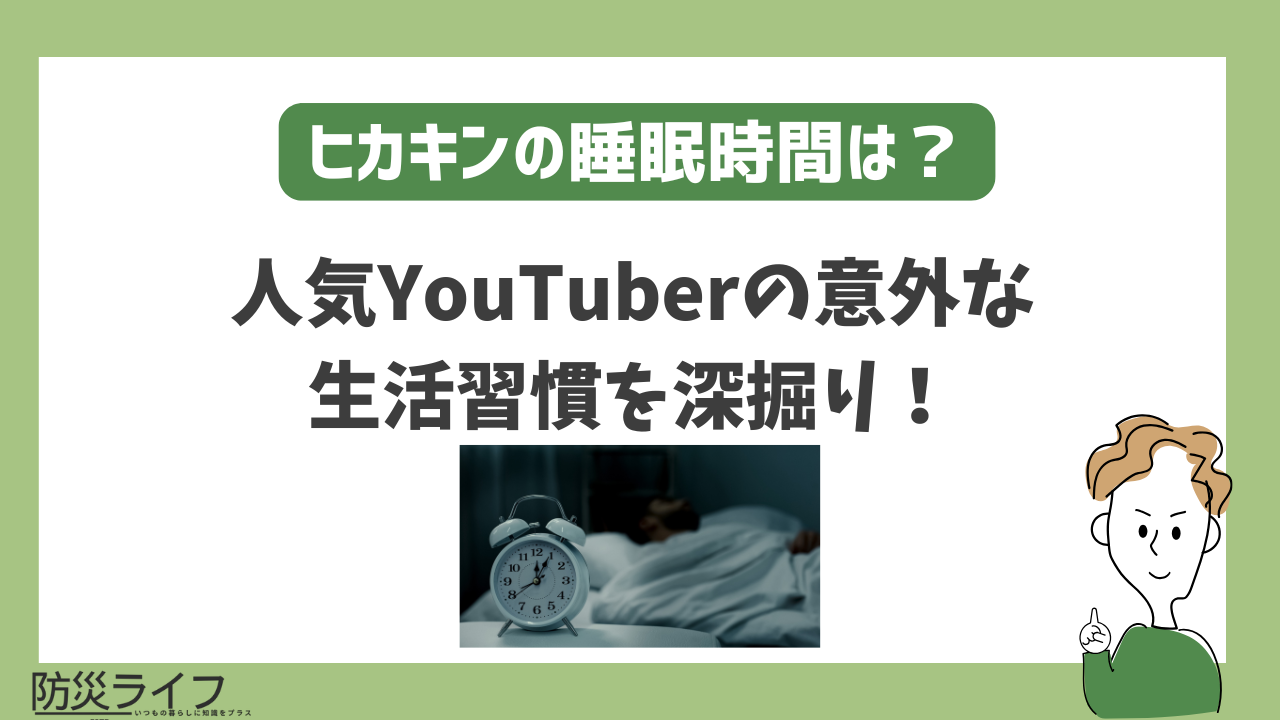ヒカキンさんは、動画づくり、企業からの依頼、テレビ出演や行事などを並行して進めるため、睡眠時間が短くなりやすい生活を送っていることで知られます。本記事では、平均的な睡眠の傾向、短くなりがちな理由、体を守る工夫、1日の流れと睡眠の取り方、食事や運動を含む整え方、道具の選び方、そして私たちがまねできる自己管理術までを、できるだけ分かりやすく丁寧にまとめます。医療行為の助言ではありませんが、今日から取り入れやすい具体策を多く盛り込みました。
1.ヒカキンの睡眠時間の傾向――短め・不規則・仮眠で補う
平均は4〜6時間前後になりやすい
動画の企画・撮影・編集・公開準備までを自分で確かめながら進めるため、まとまった睡眠を確保しづらい日が続く時期があります。平均すると4〜6時間前後にとどまる日が多く、記念回の制作前後はさらに短くなることもあります。短い時期が続いたあとは、まとめて眠る回復日を意図して作るのが定石です。
予定に左右されやすい夜型寄り
撮影場所や共演の都合で夜の作業が増え、就寝が深夜帯にずれ込むことがあります。翌日の撮影時間に合わせて起床を調整するため、睡眠時間が日ごとに変動しやすいのが実情です。眠れない日を責めず、翌日の計画に余白を入れることで無理の連鎖を止めます。
すき間の仮眠で体調を立て直す
まとまって眠れない日は、移動中や撮影の合間に10〜20分の仮眠を挟み、目の奥の重さや集中の切れを最小限に抑えます。短い休息でも、横になって目を閉じるだけで頭の疲れが和らぎます。夕方以降の長い仮眠は夜の入眠を妨げやすいため、昼すぎまでに収めます。
睡眠の取り方(概要)
| 項目 | 傾向 | 補い方 |
|---|---|---|
| 平均時間 | 4〜6時間 | すき間の仮眠で補う |
| 生活の型 | 夜型が中心 | 撮影予定に合わせて起床を調整 |
| 作業前後 | 記念回や大企画の前後は短縮 | 終了後に回復日を設ける |
| 気分の波 | 緊張期は浅くなりがち | 入浴・呼吸で落ち着かせる |
2.なぜ睡眠が短くなるのか――仕事の流れと責任の重さ
1本の動画に多くの工程を求める姿勢
ヒカキンさんは、題名の決め方、見せ場の並べ方、音や文字の出し方まで細部に手を入れることで有名です。一本あたりの総作業時間が長く、帰宅後も修正や確認が続くため、眠る時刻が遅くなりがちです。公開直前の**最終確認(音量・色・誤字)**が延びることも一因です。
1日の中に細かな用事が積み重なる
動画の撮影だけでなく、依頼先との打ち合わせ、練習、道具の準備と片づけ、写真撮影、告知文の作成など、こまごました作業が多数あります。予定が長引くと、その分だけ就寝が押されます。細かな用事を一か所に束ねる日を作ると、寝る時刻を守りやすくなります。
視聴者とのやりとりを大切にする
コメントやお知らせへの返答、近況の発信も欠かしません。人との約束を重んじる姿勢が、結果として就寝時刻の遅れに結びつくことがあります。やりとりの時間帯を日中に寄せる、夜は読むだけにする、といった線引きも有効です。
3.短い睡眠がもたらす負担と、体を守る工夫
体への負担を理解し、早めに手を打つ
短い睡眠が続くと、判断の遅れ、集中の落ち込み、胃腸の不調、風邪のひきやすさなどが現れやすくなります。無理を重ねないために、軽い頭痛や目の乾きなどの小さな信号の段階で、予定の入れ替えや仮眠を入れるなどの対処が大切です。
定期の検査と日々の記録で自分を知る
年ごとの健診だけでなく、血液検査や内科的な点検を重ねて体の変化を見逃さないようにします。また、就寝時刻・起床時刻・眠れた感覚を短い言葉で記しておくと、無理が続いた時期をふり返りやすくなります。季節の変わり目は鼻・喉・腸のケアを厚めにします。
短くても質を上げる寝室づくり
入眠の質を上げるため、遮光、静けさ、温度と湿度、寝具を整えます。寝る1〜2時間前の強い光や長い画面視聴を控え、ぬるめの入浴や軽い伸ばし運動で体温をゆっくり下げると眠りやすくなります。寝床では考えごとを書き出してから横になるのも有効です。
短時間睡眠時の守り(早見表)
| 状況 | 望ましい対処 | 補足 |
|---|---|---|
| 眠りが浅い | 就寝前の画面を短く/照明を温かい色へ | 30分前に通知を切る |
| 起きた後にだるい | 5〜10分の散歩と日光 | 朝の光で体内時計を整える |
| 日中の眠気 | 10〜20分の仮眠 | 夕方以降は長い仮眠を避ける |
| 締め切りで徹夜明け | 早めに横になり90分の回復睡眠 | 車の運転は避ける |
| 胃が重い | 温かい飲み物・消化にやさしい食事 | 冷たい油物は控える |
ここで述べる内容は一般的な心得です。強い不調が続く場合は、医療機関にご相談ください。
4.1日の流れと睡眠の取り方――夜型の仕事に合わせる工夫
夜に作業が伸びる前提で組み立てる
夜の撮影や編集が伸びる日は、翌朝の予定を軽めの用事に置き換え、昼の早い時間に20分ほど横になる時間を確保します。むやみに早起きして積み上げるより、夜の集中を活かすほうが効率的なことがあります。
4〜6時間+短い仮眠で山を越える
どうしても眠りが短くなる日は、4〜6時間の主寝+仮眠でしのぎ、山場が過ぎたら回復日を決めて長めに眠ります。無理が続いた後は消化のやさしい食事にして、胃腸の負担を減らします。
予定が変わることを前提に、余白を残す
撮影場所の変更や天候の影響で予定がずれるのは珍しくありません。1日のどこかに余白を作り、急な仕事が入っても睡眠を切り詰めすぎないようにします。
一日の例(夜型の日の目安)
| 時刻帯 | 主な動き | 睡眠の考え方 |
|---|---|---|
| 10:00前後 | 起床・軽い散歩・朝食 | 日光で体内時計を合わせる |
| 午前 | 打ち合わせ・台本づくり | 机に座り続けない |
| 昼 | 短い仮眠・昼食 | 10〜20分以内に留める |
| 午後 | 撮影・片づけ | こまめに水分をとる |
| 夕〜夜 | 編集・仕上げ・公開準備 | 2時間ごとに立ち上がる |
| 深夜 | 入浴・伸ばし運動・就寝 | ぬるめの湯で体をゆるめる |
5.食事・運動・光・音――短くても整う生活の土台
食事:眠りを浅くしない献立
就寝2〜3時間前は胃に負担の少ない献立にします。おかゆ、うどん、白身魚、湯豆腐、根菜の煮物、温かい味噌汁などが目安です。甘い飲み物・濃い味・油の多い品は眠りを浅くします。
夜の軽い献立(例)
| 主食 | 主菜 | 副菜 | 汁物 |
|---|---|---|---|
| おかゆ | 白身魚の蒸し物 | ほうれん草おひたし | わかめの味噌汁 |
| うどん | 湯豆腐 | 大根おろし | 野菜のすまし汁 |
運動:昼間の軽い動きで寝やすくする
日中に15〜30分の早歩き、階段の上り下り、軽い体操を取り入れます。寝る直前の激しい運動は避け、肩まわり・股関節の伸ばしで体をゆるめます。
就寝前の伸ばし(目安)
・肩甲骨まわしを前後10回ずつ
・もも裏の伸ばしを左右30秒ずつ
・深い腹式呼吸をゆっくり5回
光と音:寝室の刺激を減らす
寝室は暗く静かに。小さな明かりは足元だけにし、音は扇風機の弱い回転音など一定で小さな音にとどめます。耳せんや目隠しも役立ちます。
6.道具の選び方――少ない道具で効果を高める
眠りの質を上げる道具(手軽にそろうもの)
- 遮光できるカーテン:朝の光で目が覚めやすい人に有効です。
- 体に合う寝具:高すぎない枕、体圧を分散する敷物を選びます。
- 加湿・除湿の道具:季節で使い分け、喉の乾きや結露を防ぎます。
- 静かな目覚まし:大音量ではなく、光や小さな音で起きる習慣をつくります。
仕事と睡眠を両立する道具
- 簡易の目隠し:移動中の仮眠で光を遮ります。
- 携帯できる小枕:首の負担を減らします。
- 温かい飲み物の容器:寝る前は温かい番茶や白湯をゆっくり飲みます。
7.忙しい日の回復術――睡眠以外の“休む”を積み上げる
三つの回復(目・頭・体)
- 目:遠くをぼんやり眺める、まぶたの上から温める。
- 頭:思いつきを紙に書き出す。数分の黙想で呼吸を整える。
- 体:首・肩・腰をやさしく動かし、血のめぐりを戻す。
3分・15分・90分の回復法
| 時間 | できること | ねらい |
|---|---|---|
| 約3分 | 目を閉じて深呼吸、首の回し | すぐに整える |
| 約15分 | 横になって仮眠、温かい飲み物 | 小さな山を越える |
| 約90分 | 回復睡眠、ぬるめの入浴 | 大きな山の後に戻す |
8.睡眠と仕事の段取り――“やることの並べ替え”で眠りを守る
夜に向かない作業は昼へ移す
細かな入力、領収書整理、返信の定型文づくりなどは昼の明るい時間に寄せます。夜は創作の核に集中すると、作業の散らばりが減ります。
締め切り前の3段構え
1)最低限の完成形を早めに作る
2)見せ場の磨きに時間をかける
3)仕上げの点検を定時で切り上げる
9.注意したいサイン(一般的な目安)
以下が続く場合は、無理を強めず、休息を確保し、必要に応じて受診をご検討ください。
- 週の半分以上で入眠まで1時間以上かかる
- 朝の強いめまいや動悸が続く
- 日中の眠気で安全運転に不安が出る
- 気持ちが落ち込み楽しめることが減る
10.取り入れやすい実践集
週の計画表(書き込み用)
| 曜日 | 重点の仕事 | 仮眠予定(10〜20分) | 夜の入浴 | 就寝目安 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||
| 火 | ||||
| 水 | ||||
| 木 | ||||
| 金 | ||||
| 土 | ||||
| 日 |
就寝前の流れ(30分の型)
1)画面を閉じ、通知を切る
2)ぬるめの入浴で体を温める
3)軽い伸ばしで肩・腰をゆるめる
4)翌日の気がかりを紙に書く
5)部屋を暗くして横になる
11.ヒカキンから学べる自己管理術――短い睡眠でも折れない土台
成功は日々の整えの積み重ね
毎日の姿勢づくり・食事・軽い運動・感謝の言葉といった基本が、短い睡眠を補います。予定が詰まるほど、決まった型で一日の終わりを落ち着かせることが大切です。
自分に合う生活の形を見つける
人によって働く時間帯の合う・合わないは違います。朝型に無理に合わせるより、自分が集中できる時間帯を核に組み立て、無理のない改善を続けます。
睡眠は目に見えにくいが、成果の土台
眠りは声の張り、表情、判断の速さに直結します。数字には現れにくい土台ほど、崩れると一気に成果が下がります。短い睡眠の時期こそ、質の向上と回復の計画で支えます。
取り入れやすい工夫(まとめ)
| 分野 | きょうからできること | ねらい |
|---|---|---|
| 寝室 | 遮光・静けさ・寝具の見直し | 入眠の質を上げる |
| 夕方以降 | 甘い飲み物と画面を控える | 眠りを浅くしない |
| 夜 | ぬるめの入浴・伸ばし運動 | 体温をゆっくり下げる |
| 日中 | 10〜20分の仮眠 | 集中の落ち込みを防ぐ |
| 週の計画 | 山場の翌日に回復日を置く | 無理の連鎖を止める |
よくある質問(Q&A)
Q1:短い睡眠でも健康を保てますか。
A:個人差はありますが、短い時期が続くなら、質の向上とこまめな仮眠が助けになります。強い不調が続く場合は専門の受診をおすすめします。
Q2:仮眠はどれくらいが良いですか。
A:10〜20分が取り入れやすい長さです。30分を超えると夜の入眠が遅くなることがあります。
Q3:夜更かしが続いた後の回復法は。
A:90分以上の回復睡眠を一度確保し、消化のやさしい食事と軽い散歩で整えます。車の運転は控えめにしてください。
Q4:朝起きられない時の対処は。
A:目覚めてすぐに日光を浴び、水を飲み、深呼吸を数回行います。二度寝を避け、体を動かして体内時計を戻します。
Q5:寝る直前に小腹がすいたら?
A:温かい汁物や常温の牛乳、少量の果物など、消化にやさしいものを少なめにとります。辛い物や油の多い物は控えます。
Q6:寝具は高価である必要がありますか。
A:体に合う高さの枕、体圧が分散する敷物であれば十分です。まずは枕の高さと寝返りのしやすさを見直します。
Q7:短時間でも熟睡感を高めるコツは。
A:就寝前30分の静けさづくり、ぬるめの入浴、肩・腰の伸ばし、部屋の暗さの四つをそろえると、実感が変わりやすいです。
用語の小辞典
仮眠:昼間にとる短い眠り。10〜20分ほどが扱いやすい長さです。
入眠:寝つくまでの流れ。光や音、体温の影響を受けます。
回復睡眠:徹夜や多忙の後に意図して長めにとる眠り。体の負担を戻す目的があります。
就寝・起床:眠りにつく時刻・目覚める時刻。日光と食事の時間で整えやすくなります。
遮光:光をさえぎって暗くすること。朝の目覚めの時刻を整えやすくなります。
まとめ
ヒカキンさんの睡眠は短く不規則になりやすい一方で、仮眠・睡眠環境の整え・回復日の設定、食事と運動、光と音の調整、作業の並べ替えといった小さな工夫で、日々の働きを支えています。私たちも、自分に合う生活の形を見つけ、短い時期は質で補い、山場の後は回復日を置く――この基本だけでも、明日の動きはぐっと軽くなります。数字に表れにくい土台をていねいに守ることが、長く続く成功の近道です。