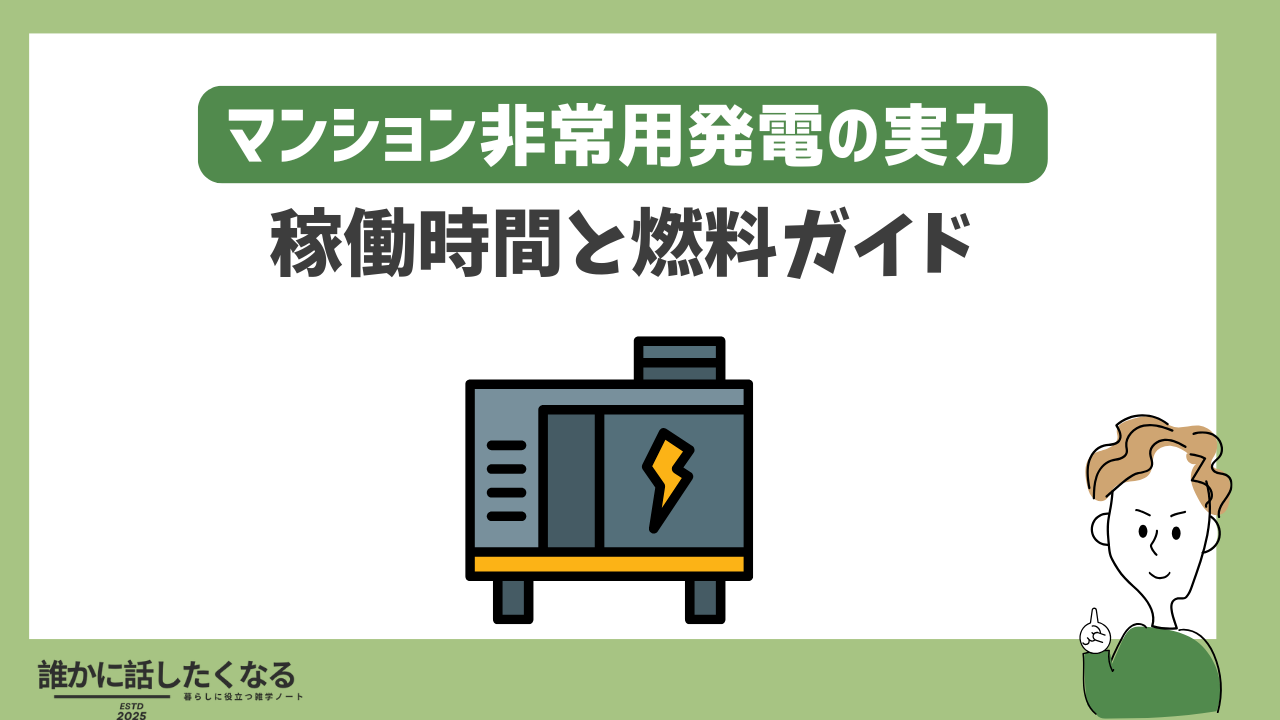非常用発電機は“建物の心臓の予備”。 停電時に命を守る設備を最低限でも動かし続けることが役目です。本稿では、マンションの非常用発電について、仕組み・稼働時間の読み方・燃料の扱い・住民運用・点検訓練・季節対応・騒音/排気配慮までをまとめました。
管理組合・管理会社・防火防災担当が同じ表と言葉で会話できるよう、計算手順と決めごとを具体化しています。
1.非常用発電の基礎:何を、どれだけ、いつまで動かすか
1-1.基本構成と起動の流れ
- 発電機本体(多くはディーゼル)+自動始動装置+自動切替盤(ATS)+専用分電盤で構成。
- 商用電源が途絶→ATSが停電を検知→自動始動→非常回路へ送電→復電で自動復帰。
- 併設の始動用蓄電池・燃料タンク・排気・吸気・冷却が正常であることが前提。
1-2.“何を守るか”の優先順位
- 必須(法令・安全):非常照明、誘導灯、屋内消火栓ポンプ、排煙機、非常用コンセント、消防受信機、非常用放送など。
- 重要(建物機能):給水ポンプ、排水ポンプ、共用部照明、通信設備(ONU/ルーター/監視)。
- 任意(余力があれば):エレベータ間引き運転、集会室、管理室空調、共用コンセントの拡張。
1-3.稼働時間の考え方(定格と実効)
- カタログ値は**“定格出力・定常温度”の目安。実際は外気温・経年・負荷変動**で消費燃料が変わる。
- 実効稼働時間(h)≒ 可用燃料量(L) ÷ 実負荷時燃料消費(L/h)。
- 安全在庫(タンク容量の10〜20%)を差し引いた残量で試算するのが現実的。
優先負荷の整理表(例)
| 優先 | 設備 | 目的 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防受信機・非常照明・放送 | 避難誘導 | 常時稼働 |
| 2 | 屋内消火栓ポンプ・排煙 | 消火・延焼防止 | 試運転で起動確認 |
| 3 | 給水ポンプ | 生活機能 | 間欠運転で節約 |
| 4 | 通信設備 | 情報確保 | ONU/ルーターは低負荷 |
| 5 | エレベータ | 垂直移動 | 間引き運行・時間制限 |
1-4.よくある誤解と対処
- 「全部の電気を賄える」→×:非常用は**“命を守る電気”**が前提。間引きが基本。
- 「燃料があれば何日でも」→×:油の劣化・補給導線・整備要員が制約。訓練で現実を把握。
- 「点検は年1回で十分」→×:週次の自動試運転で始動不良を早期発見。
2.稼働時間を見積もる:燃料と負荷の“足し算・引き算”
2-1.燃費の目安(ディーゼル発電機)
| 負荷率 | 燃料消費(L/h・概算) | メモ |
|---|---|---|
| 25% | 0.25〜0.35 × 定格kW | 低負荷は効率やや悪い |
| 50% | 0.18〜0.25 × 定格kW | 一般的な常用域 |
| 75% | 0.21〜0.28 × 定格kW | 高負荷で燃費上昇 |
| 100% | 0.24〜0.32 × 定格kW | 連続は避けたい |
例:**50kW機・負荷50%**なら 燃費 ≒ 50×0.2=10L/h 程度。
2-2.貯油量と“実効稼働時間”の算出
実効稼働時間(h)=(貯油量 − 安全在庫)÷ 実負荷燃費
安全在庫=貯油量の10〜20%(傾き・吸い込み残差・補給遅延に備える)。
計算例(モデルマンション)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 定格出力 | 50kW |
| 平均負荷 | 50%(=25kW) |
| 燃費 | 10L/h(上の例) |
| 貯油量 | 1000L |
| 安全在庫 | 15%(=150L) |
| 可用燃料 | 850L |
| 実効稼働時間 | 850 ÷ 10=85時間(約3.5日) |
2-3.負荷を削れば“時間が伸びる”具体策
- エレベータの間引き運行(1基のみ・時間帯限定)
- 給水ポンプの間欠運転(1〜2時間ごとに短時間加圧)
- 共用照明の間引き(避難・通路優先、装飾照明は停止)
- 管理室・集会室の空調停止(扇風機・自然換気に切替)
負荷削減シナリオ(例)
| 項目 | 通常時(kW) | 非常時(kW) | 削減率 |
|---|---|---|---|
| 給水ポンプ | 12 | 6(間欠) | 50% |
| エレベータ | 20(2基) | 10(1基) | 50% |
| 共用照明 | 5 | 2 | 60% |
| 通信・監視 | 2 | 2 | 0% |
| 計 | 39 | 20 | 49% |
39→20kWに落とせれば、稼働時間はほぼ約2倍に伸びる計算。
2-4.季節・温度による補正(冬・夏)
| 季節 | 影響 | 補正の考え方 |
|---|---|---|
| 冬(低温) | 始動性低下、油の粘り増加 | 余裕の燃費で見積(+5〜10%)・始動前の点検強化 |
| 夏(高温) | 冷却負荷増大、周波数不安定化 | 吸排気の通風確保・負荷の段階投入 |
| 梅雨 | 湿気×電装劣化 | 端子の清掃・結露対策 |
3.燃料の種類・保守・補給:止めないための現実対応
3-1.燃料の違い(軽油・都市ガス・LPガス・重油)
| 燃料 | 特徴 | 長所 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 軽油(ディーゼル) | 最も一般的 | 始動性・調達性が良い | 劣化・水分混入、菌汚れ対策が必要 |
| 都市ガス | 配管供給 | 保管不要・長時間運転 | ガス供給停止時は不可 |
| LPガス | ボンベ保管 | 災害に比較的強い | 保管スペース・残量管理 |
| 重油 | 大容量向け | 長時間運転に有利 | 低温時の流動性・保守が重い |
3-2.貯油管理(劣化と水分対策)
- 年1回以上の抜き取り確認:水抜き栓から水分・汚泥を排出。
- 防菌・防錆添加剤の採用(設備方針に沿って)。
- タンクの呼吸で水分が入るため、満タン管理を基本に。
- 通気口フィルタの清掃、結露防止の断熱シートなども有効。
3-3.補給の現実(停電時の段取り)
- 発注先の連絡網・受入時間帯・車両導線を平時に合意。
- 仮設受入(ドラム缶・移送ポンプ)の安全手順を文書化。
- 逆火・静電気対策と防火資機材(砂・吸油材)を設置。
- 受入時は消火器・誘導員・漏洩時の処置を事前割り当て。
3-4.燃料品質チェック表(例)
| 項目 | 頻度 | 許容目安 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 水分・汚泥 | 年1 | ほぼ無し | 水抜き・タンク清掃 |
| 変色・臭い | 半年 | 異常なし | 添加剤追加・入替検討 |
| 漏れ・錆 | 月1 | 無し | 補修・再塗装 |
4.住民と管理側の運用:72時間を乗り切る計画
4-1.エレベータと給水の“時間割”運用
- エレベータ:整列・介助優先、朝夕の集中帯だけ運行。医療・介護が必要な住民を優先。
- 給水:加圧を1〜2時間おきに短時間行い、各戸はタンク・浴槽で貯水。
- 排水:停電でも自然流下が基本。排水ポンプ系は残量監視、満水警報の伝達ルートを明確化。
4-2.照明・通信・監視の優先順位
- 避難経路照明・非常照明は常時、装飾照明は停止。
- 通信・監視(防犯カメラ・管理室通信)は止めない。
- 非常用コンセントは医療機器・携帯の充電を優先し、上限時間を掲示。
4-3.夜間静音と排気への配慮
- 発電機の防音扉・遮音パネルの閉鎖を徹底。
- 排気方向に人が滞留しない導線を設定。一酸化炭素に注意。
- 近隣へ運転掲示を出し、苦情窓口を一本化。深夜は最低負荷で運転。
4-4.72時間の運用スケジュール(例)
| 日/時間帯 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | エレベータ運行・給水加圧 | 照明間引き | 医療・通信充電 | 静音運転・警備強化 |
| 2日目 | 給水加圧・燃料残量点検 | 設備点検・清掃 | エレベータ限定運行 | 夜間は最低負荷のみ |
| 3日目 | 給水・排水点検 | 補給可否の確認 | 住民告知更新 | 予備燃料の再計算 |
4-5.掲示とアナウンスの雛形(短文)
- 充電は1人30分まで/医療機器優先
- エレベータは毎時00・30分に運行(救護優先)
- 給水加圧は2時間ごと/各戸浴槽で貯水を
5.点検・訓練・記録:止めない仕組みを回す
5-1.日常・定期点検のポイント
- 始動バッテリー電圧・電解液、ベルト張り・冷却水・潤滑油。
- 空気吸入・排気の通路に障害物がないか。
- 無負荷・負荷試験で所定電圧・周波数を確認、異音・振動を記録。
- ATS(自動切替)の動作を模擬停電で確認(年2回以上)。
5-2.訓練の型(年2回以上)
- 想定停電→自動始動→負荷切替→エレベータ間引き→給水間欠までを時刻表で訓練。
- 住民向け案内文(掲示・館内放送)の雛形を用意。
- 終了後、残燃料・稼働時間・異常を記録→共有。
5-3.記録・掲示・役割分担
| 書類 | 内容 | 保管先 |
|---|---|---|
| 点検記録 | 始動回数・電圧・油量・異音 | 管理室・デジタル台帳 |
| 燃料台帳 | 入出庫量・劣化対策・水抜き日 | 管理室・防火庫 |
| 運用計画 | 優先負荷・時間割・連絡網 | 管理室・掲示板 |
| 苦情対応表 | 騒音・排気の窓口・対応履歴 | 管理室 |
5-4.スペア・消耗品の目安
| 品目 | 保管量目安 | 交換・点検 |
|---|---|---|
| 始動用蓄電池 | 予備1セット | 3〜5年で更新目安 |
| エンジン油・冷却水 | 1回分 | 年1回点検・補充 |
| ベルト・フィルタ | 各1〜2本/個 | 年1回点検 |
| 漏斗・吸油材 | 必要数 | 補給時に使用 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.非常用発電は“全部の電気”をまかなえる?
A. いいえ。命を守る設備を優先し、その他は間引きが基本です。
Q2.ディーゼル燃料はどのくらいもつ?
A. 保管環境で差があります。水分・菌への対策(満タン管理・水抜き・添加剤)が鍵。年1回の確認を。
Q3.停電が長引き、燃料補給が間に合わない。
A. 負荷を半分に落とすだけで時間はおよそ2倍に。エレベータ・給水の時間割をすぐに実施。
Q4.都市ガス供給が止まったら?
A. ガス発電は停止。非常灯・消防関係のみ別電源(蓄電池等)で維持する計画が必要です。
Q5.騒音や排気で苦情が出る。
A. 運転時間を予告掲示し、夜間は最低負荷に。排気方向・防音対策を事前点検。
Q6.自動で始動しないことがある?
A. あります。始動バッテリー・燃料系・ATSの不良が主因。週次の自動試運転で発見を早めます。
Q7.太陽光や蓄電池と併用できる?
A. 可能な構成もありますが、系統の連系・切替の設計が必要。非常回路の分離が前提です。
Q8.エレベータを止める判断は誰が?
A. 管理員・理事長・防災担当の合議で、医療・介護の事情を優先して時間割を決めます。
用語辞典(やさしい言い換え)
ATS(自動切替盤):停電を検知し、商用電源↔非常用発電を自動で切り替える装置。
負荷率:発電機の定格出力に対する使い方の割合。
間欠運転:必要なときだけ短時間動かす方法。給水などに有効。
安全在庫:タンクにあえて残す燃料。吸い込み残差・傾き・遅延に備える。
無負荷/負荷試験:つながない/つないだ状態での試運転。性能を確かめる。
始動用蓄電池:発電機をかけ始めるための電池。弱ると自動始動しない。
周波数・電圧:電気のリズムと強さ。機器の安定運転に重要。
まとめ:数字で“伸ばし”、訓練で“守る”
非常用発電の実力は、燃料の量と使い方(負荷)で決まります。可用燃料と燃費から稼働時間を数字で把握し、優先負荷の時間割で“伸ばす”。
そして週次の試運転・年2回の訓練・台帳管理で“守る”。季節の補正・騒音/排気の配慮・掲示の徹底まで含めて準備すれば、停電は**“想定外”から“想定内”**へ。今日、貯油量と優先負荷表を更新し、掲示まで仕上げましょう。