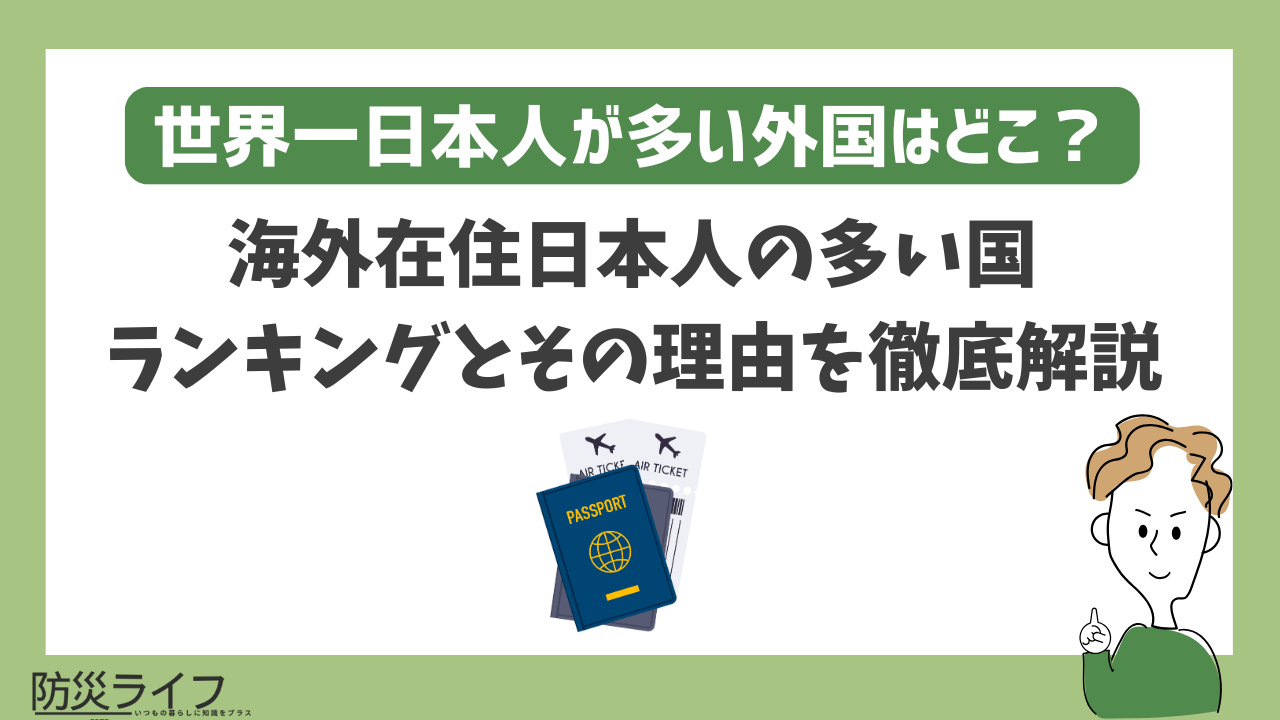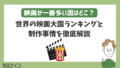はじめに。海外で暮らす日本人は、短期の滞在者から長期の定住者まで年々多様になっています。進学・就職・子育て・起業・退職後の移住など目的はさまざま。どの国に日本人が多く住み、なぜその国が選ばれるのかを知ることは、移住計画や海外展開の「現実的な判断材料」になります。
本記事では、在住日本人が多い国をランキングとともに示し、数字の読み方(推定の前提)、国別の暮らしやすさ、選び方の軸、準備の年次計画、費用感のモデル、最後にQ&Aと用語小辞典まで一気に解説します。
1.結論と集計の前提――いちばん多い国と、その見方
1-1.いちばん日本人が多い外国はどこか
結論から言えば、最も在住日本人が多い国はアメリカ合衆国です。次点には中国・オーストラリア・タイ・ブラジルなどが続きます。もっとも、国別の人数は届出状況・集計年・定義の差によって上下します。この記事では、各国の状況を**「推定の幅」**を明記しながら読み解きます。あわせて、駐在・現地採用・永住・留学・ロングステイの比率が国ごとに異なる点にも注意します。
1-2.何を「在住」とみなすか(定義の整理)
在住日本人には、長期滞在者・永住者・駐在員と家族・留学生・技能実習や専門職・自営やノマドなど多くの区分が含まれます。観光客や短期の出張者は含めません。海外で暮らす日本人の数は、**在外公館への届出(在留届)**の有無にも左右され、実数より少なく見える地域もあれば、二重計上の余地がある地域もあります。二重国籍・永住権のみ保有者の扱いでも差が出ます。
1-3.数字が毎年動く主因
人数は査証(ビザ)制度の改定、為替の変動、治安・医療の安心度、産業構造の変化、在宅勤務の広がり、学費・家賃の相場、地政学などで大きく動きます。たとえば学費や家賃の上昇で北米から他地域へ移るケース、製造拠点の移転で東南アジアに増えるケース、デジタルノマドビザ創設で欧州や中南米の一部に若年層が流入するケースなどが典型です。
1-4.読み間違いを減らす三原則
1)「幅」で見る(単年の点ではなく2〜3年の線で確認)。 2)区分で見る(駐在/現採/永住/留学)。 3)都市圏で見る(同じ国でも都市により体感が別物)。
2.ランキングと全体像――上位国の特徴を一望
2-1.在住日本人が多い国の概観(推定)
以下は概算レンジでの比較表です(届出率や二重国籍の扱い等で差が出ます)。
| 順位 | 国名 | 推定在住日本人数(幅) | 主な集中都市 | 主な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 40万〜45万人規模 | ロサンゼルス、ハワイ、ニューヨーク、サンフランシスコ湾岸、シアトル ほか | 教育・就労・永住、多様な産業と日本語生活基盤 |
| 2 | 中国 | 9万〜12万人規模 | 上海、北京、広州、深セン、天津 ほか | 駐在・事業展開、近距離・時差の利点 |
| 3 | オーストラリア | 9万〜10万人規模 | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト | 教育移住・自然環境・技術職、査証制度の選択肢 |
| 4 | タイ | 6万〜8万人規模 | バンコク、チョンブリー、チェンマイ、プーケット | 駐在・長期滞在(ロングステイ)、生活費と利便の均衡 |
| 5 | ブラジル | 5万〜6万人規模 | サンパウロ、パラナ、アマゾナス | 歴史的移民・大規模日系社会(多世代) |
| 6 | カナダ | 7万前後 | バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオール | 多文化共生・教育・移住政策の安定 |
| 7 | イギリス | 6万前後 | ロンドン、マンチェスター、エディンバラ | 金融・研究・文化産業、語学環境 |
| 8 | ドイツ | 4万〜5万 | デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン | 製造業・研究・家族帯同の安定 |
| 9 | シンガポール | 3万〜4万 | 全域(都市国家) | 事業拠点・教育・治安の良さ |
| 10 | フランス | 3万前後 | パリ、リヨン、トゥールーズ | 文化・芸術・研究、欧州内の拠点性 |
読み方の注意:上表はあくまで「幅」を持った目安です。届出率や重複、短期→長期の移行等で年々変動します。
2-2.地域ごとの偏りと動き
北米は教育・就労と永住志向で厚く、東アジア・東南アジアは駐在・事業拠点と長期滞在(物価・時差の利)が強み。南米は歴史的移民に根差す層が厚く、欧州は専門職・研究職が目立ちます。湾岸・中東はプロジェクト型の駐在比率が高めです。
2-3.数字の裏側――増減を左右する要素
家賃・学費・医療費の上昇、査証(ビザ)条件、通貨の強弱、国際情勢の変化、遠隔勤務の普及と税務の扱い、家族帯同のしやすさなどが、移住先選びと人数の増減に直結します。
2-4.年代別の傾向(ざっくり)
- 20代:留学・ワーホリ・現地採用スタート。英語圏とアジアが中心。
- 30代:駐在帯同・子育ての学区重視。北米・アジアの大都市。
- 40代:管理職駐在・起業・永住化。医療と教育のバランスを重視。
- 50〜60代:ロングステイ・二地域居住。医療アクセスと生活費の最適化。
3.国別プロファイル――暮らしの実感と選ばれる理由
3-1.アメリカ合衆国:多様な進路と生活基盤の厚さ
強みは、産業の幅広さ(IT、映画、金融、医療、研究、農業など)と日本語で受診できる医療・学校・商店の多さ。名門から州立まで選択肢が広い高等教育、郊外の暮らしやすさ、多様性を受け入れる土壌が魅力です。H/L/E系就労・投資・研究・家族と在留資格のルートも多彩。一方で、医療費・家賃の高さ、州ごとに異なる税や学校制度への理解が欠かせません。車社会か公共交通かでも生活コストが変わります。
代表都市の体感
- ロサンゼルス:文化産業・日系商業が厚い。車必須、家賃高。
- ハワイ:観光・医療・教育ニーズが交差。家賃・物価は高いが日本語環境は抜群。
- NY/NJ:金融・メディア・アート。公共交通は便利、教育費は高水準。
3-2.中国・タイ:事業の前線と暮らしやすさの両立
中国は製造・販売・技術の拠点として存在感が大きく、日系企業の駐在帯同が厚い層を形成。大都市では日本語対応の医療・教育・食材が整い、生活の便利さは高水準です。通信・キャッシュレスが進んでおり、生活のデジタル化に適応すれば快適度が上がります。タイは物価と利便性の均衡、日本食・日本語医療の普及、長期滞在制度(リタイアメント等)の選択肢が人気。近距離・小さな時差で日本とのやり取りが容易なのも強み。チェンマイはIT・クリエイティブ系の長期滞在者に人気です。
3-3.オーストラリア・ブラジル:学びの質と歴史の厚み
オーストラリアは治安と自然環境、教育の質、技術職や看護・介護等の人材需要が移住の追い風。気候が穏やかで家族連れに人気。都市はコンパクトで、医療・学校が生活圏にまとまっています。ブラジルは100年以上の移民史で大規模な日系社会が根づき、言語や文化をまたいだ**地域のつながり(コミュニティ)**が強固。多世代の日系人との交流は、仕事・教育・文化活動の厚みにつながり、日本文化行事が年間を通じて盛んです。
3-4.カナダ・イギリス・ドイツ・シンガポール・フランス(ダイジェスト)
- カナダ:多文化共生が進み、教育・医療が安定。永住ルートの透明性が高く、家族連れの満足度が高い。
- イギリス:金融・研究・アートの中心。EU離脱後もロンドンは国際都市。学術・クリエイティブ志向が集まる。
- ドイツ:製造業・研究・環境分野で強く、**家族政策(保育・教育)**が手厚い都市が多い。
- シンガポール:治安・教育・税制の読みやすさ。都市国家ゆえの移動負担の少なさが家族に好評。
- フランス:文化・芸術・食。研究機関も多く、欧州内移動の利便性が高い。
4.どう選ぶ?移住・長期滞在の判断軸と比較
4-1.生活費・税・医療を見比べる(ざっくり指標)
| 項目 | アメリカ | 中国 | オーストラリア | タイ | ブラジル |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃の目安(大都市中心) | 高い/地域差大 | 大都市は上昇中 | 高い(都市部) | 中程度(場所により差) | 中程度 |
| 税・社会保険 | 州により複雑 | 都市・所得で差 | 所得税・年金が整備 | 税率は適度 | 制度は地域差 |
| 医療の受けやすさ | 充実だが高額 | 大都市は充実 | 公私ともに整備 | 日本語医療あり | 大都市中心 |
| 査証(ビザ)の取りやすさ | 職種による | 雇用前提が多い | 職種・点数制等 | 長期滞在制度あり | 業務・家族等 |
| 日本語環境 | 広範囲にあり | 大都市に集中 | 都市部に点在 | 広く普及 | 歴史的に厚い |
目安は都市・時期で変わります。家賃・医療費・税の3点は下見や専門家相談で必ず現地確認を。
4-2.モデル家計(あくまで参考)
| 居住地・家族構成 | 家賃 | 食費 | 交通 | 教育・保育 | 医療保険 | 合計(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・夫婦+子1 | 3,200 | 1,000 | 250 | 1,000 | 600 | 6,050 |
| バンコク・夫婦+子1 | 1,200 | 700 | 120 | 700 | 180 | 2,900 |
| シドニー・夫婦+子1 | 2,800 | 1,000 | 220 | 900 | 350 | 5,270 |
| バンクーバー・単身 | 2,000 | 500 | 120 | – | 200 | 2,820 |
通貨・相場で大きく変動します。学校種別(現地校/国際校)と居住エリアで上下幅が最大。
4-3.子どもの学びと言葉の維持
現地校・国際校・補習校の三つの選択肢をどう組み合わせるかが鍵です。家庭内の日本語維持(読み書き・語彙)と、現地語・英語の習得バランスを学年ごとに見直す計画があると安定します。進学志向なら学区と通学の負担、放課後の学習支援、語学検定の受検機会も検討材料。
4-4.働き方の現実と手続き
就労は雇用主による就労許可が一般的で、起業(新規事業)や投資、研究・芸術など複数ルートがあります。近年は遠隔勤務や複業の相談も増加。税務・社会保険・在留資格の条件を事前に専門家へ確認することで、後のトラブルを避けられます。社会保障の通算協定の有無も老後の基礎を左右します。
4-5.準備の年次計画(12か月の目安)
- T-12〜9か月:目的の明確化(教育/仕事/生活費)。渡航先の気候・治安・医療の調査。
- T-9〜6か月:資金計画(初期費用+半年の生活費)。語学対策と履歴書の現地仕様化。
- T-6〜3か月:査証申請・学校出願・予防接種・賃貸市場の下見。現地SIM・銀行の手配検討。
- T-3〜0か月:保険加入・賃貸契約・引越し物流・在留届準備。緊急連絡網と持病の翻訳診断書。
4-6.チェックリスト(印刷推奨)
- パスポート残存/査証書類/戸籍・婚姻証明/予防接種記録
- 学校成績・推薦状/職務経歴・資格証明/ポートフォリオ
- 海外送金・現地口座・クレジット/携行薬・慢性疾患英文リスト
- 海外旅行・医療保険/家財保険/運転免許の国際化
- 在外日本人会・ママ友ネット・同業コミュニティの連絡先
5.よくある質問(Q&A)と用語小辞典
5-1.Q&A――疑問にまとめて答える
Q:結局、初めての海外移住ならどの国が無難?
A:言葉・医療・治安・仕事の4点がそろうアメリカ・カナダ・オーストラリア・タイは候補になりやすいです。ただし家賃や学費が高い都市も多いため、予算と目的を先に固め、現地の**下見(1〜3か月)**で生活感を確認するのが安全です。
Q:子育てと教育費が不安。どこが現実的?
A:公教育の質と学区の影響が大きい北米・オセアニアは情報が得やすい反面、費用が高め。タイやマレーシアは国際校の選択肢が多く、日本語医療も整っていて費用のバランスが取りやすい傾向です。
Q:仕事はどう探す?現地採用と駐在の違いは?
A:駐在は給与・住居・教育の補助が大きく、任期が終わると帰任が基本。現地採用は現地水準の給与での雇用が中心ですが、自由度や転職機会は広がります。いずれも在留資格の条件と税務の確認が最優先です。
Q:治安や医療に不安がある。どう備える?
**A:**住む地域の選び方と保険加入でリスクは大きく縮みます。日本語対応の医療機関の位置、通学・通勤ルートの明るさ、夜間の外出ルールなど、家族で事前に合意しておきましょう。
Q:IT・クリエイティブ系のノマドに向く国は?
A:通信・コワーキング・時差・税の4点を満たすタイ(チェンマイ)/マレーシア/ポルトガルなどが定番。デジタルノマドビザや滞在日数と課税の関係は事前確認を。
Q:永住権は取るべき?
**A:**家族の教育・医療・就労の自由度が上がる一方、納税・義務はその国の制度に従います。二重国籍の可否、年金通算協定、帰国後の再挑戦のしやすさも併せて判断を。
Q:住まい探しの落とし穴は?
A:入居審査の書類(収入証明・在留資格)と保証金、学区境界、通勤時間帯の渋滞。内見は昼と夜の二回が理想です。
5-2.用語小辞典(やさしい言い換え)
- 査証(ビザ):その国に入国・滞在・就労してよいという許可。種類や条件は国ごとに異なります。
- 永住権:期限のない滞在許可。取得後も税や義務は国の制度に従います。
- 在外公館:大使館・総領事館など。在留届は安全情報の受け取りや緊急時連絡のために重要。
- 補習授業校:海外で日本の学習指導要領の一部を補う学校(週末中心)。
- 地域のつながり(コミュニティ):同じ地域で支え合う人の輪。情報・子育て・防犯で力を発揮します。
- 社会保障協定:年金などを二重負担にしないための国際取り決め。老後の受給に影響。
- デジタルノマドビザ:リモート就労者向けの中長期滞在許可。税・保険の取り扱いは国ごとに差。
5-3.情報収集のすすめ(失敗を減らす三手)
1)現地の下見:市場(食料品価格)、学校見学、医療機関、交通の混み具合を自分の目で。
2)費用の見える化:家賃・光熱・学費・保険・車の維持費を月額と年額で試算。
3)専門家と二段構え:法律・税務・教育はプロに確認し、同時に生活者の声(地域の日本人会や先輩)で現実を補強。
まとめ
世界で日本人が最も多く住む国はアメリカ。そのほか中国・オーストラリア・タイ・ブラジルなどが続きます。数字は年ごとに変わりますが、共通する選ばれる理由は、仕事の機会・教育の選択肢・医療の安心・生活費と利便のバランスです。移住は情報戦。
定義と前提を理解して数字を読み, 現地下見と費用設計、査証・税務の確認を丁寧に進めることで、後悔の少ない選択になります。あなたの目的(学び、働き方、家族の安心)に合う国を、冷静に選び取りましょう。