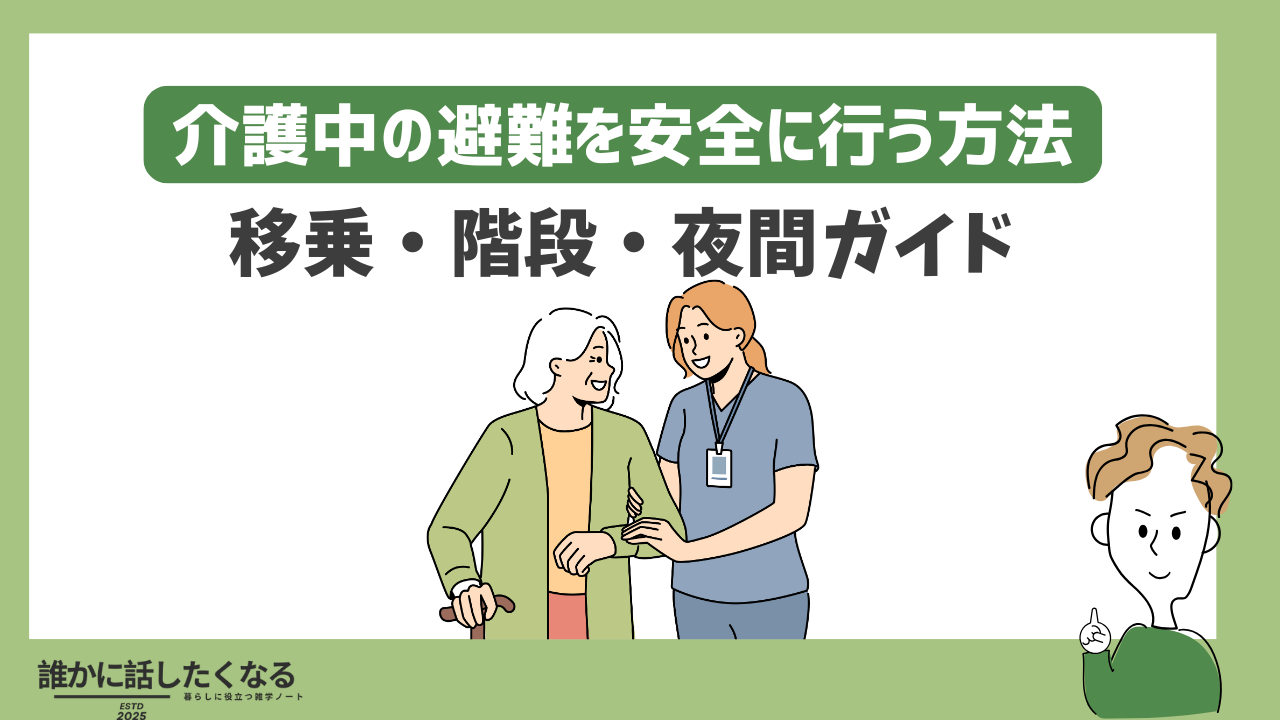要介護の家族と避難する状況では、1回の移乗・1段の段差・1本の手すりが生死を分けます。焦りは禁物ですが、段取りさえ整っていれば動きは驚くほど軽くなります。
本記事は、在宅介護・通所前後・夜間の見守りといった日常の延長で、いざという時に“そのまま実行できる”避難手順を、移乗・階段・夜間の3本柱に、役割分担・医療への配慮・持ち出しを加えて体系化。数値の目安・声かけの型・導線設計・道具配置までまとめました。
まず押さえる安全原則:倒れない・詰まらない・迷わない
介助の基本姿勢と合図(体を守る)
- 重心は低く・広く:足は前後に開き、膝・股関節を曲げて腰をそらさない。
- 持ち上げない・ねじらない・引っ張らない:滑らせて移すが基本。
- 合図は短文1語×2回:「立ちます→立ちます」「回ります→回ります」。
- 触る場所は骨に近い部位(肩甲骨・骨盤)を広い面で支える。
動線の事前設計(詰まらない)
- 寝室→廊下→玄関→屋外の直線を優先。角の家具・マットは撤去。
- ドアは避難方向へ開く/引き戸は戸車の潤滑を確認。
- 回転スペースは直径150cmが理想。最低でも130cm確保。
視覚と合図(迷わない)
- 足元灯・蓄光テープで段差・角を可視化。矢印は床と腰高の二重。
- 笛・合図ライトを寝室入口・玄関に常備。夜間は声+光+触覚で。
初動10分のタイムライン(家族2名想定)
1)0〜2分:安否確認・合図統一(短文二度)。
2)2〜4分:動線の障害物を撤去、足元灯点灯。
3)4〜7分:ベッド→車いすへ移乗(または玄関椅子へ)。
4)7〜10分:玄関で上着・ケープ・連絡カードを装着、外へ。
避難原則の早見表
| 項目 | 最低目安 | 推奨値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 回転スペース | 130cm | 150cm | 車いす・介助で切返し不要 |
| 通路幅 | 80cm | 90cm | すれ違いは180cm |
| 手すり高さ | 75cm | 80cm前後 | 連続・端部丸め |
| スロープ勾配(屋内) | 1/12 | 1/15 | 上下端に50cm水平部 |
| スロープ勾配(屋外) | 1/15 | 1/20 | 雨・霜で緩める |
| 合図 | 短文1語×2回 | 人ごとに固定 | 例:立ちます/止まります |
移乗を安全に:ベッド⇄車いす⇄玄関椅子の“最短導線”
ベッドからの立ち上がり(合図と重心移動)
1)合図:「起き上がります→起き上がります」。
2)側臥位→端座位:肩甲骨と骨盤を同時に支え、足は床へ。
3)体前傾→立ち上がり:鼻が足先より前へ。膝に手を置かせると踏ん張りやすい。
スライドボード移乗(段差ゼロ・摩擦を減らす)
- 高さ合わせ:ベッド座面=車いす座面±2cm以内。
- ボード角度はやや下りに設定して滑走補助。
- 骨盤を先に移す→肩をついてくるの順で、頭は最後。
車いすのセッティング(“近く・斜め・ブレーキ”)
- **ベッドに斜め30°**で近づけ、フットレストは跳ね上げ。
- ブレーキ→肘掛外す→足位置の順。膝が当たる障害物を先に除去。
非立位での移乗(立てない・痛みが強い時)
- 回転クッションやすべり布を活用し、骨盤→肩→頭の順に横移動。
- 腰ベルトで体幹を保ち、ねじらずに水平移動を徹底。
移乗のチェックリスト(印刷用)
| 工程 | できた | メモ |
|---|---|---|
| 合図の確認(短文二度) | ||
| 座面の高さ合わせ(±2cm) | ||
| ブレーキ・フットレスト処理 | ||
| 骨盤→肩→頭の順 | ||
| 体前傾(鼻>つま先) | ||
| すべり布・回転具の準備 |
よくある失敗と対処
| 失敗例 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 途中で腰が落ちる | 座面差・摩擦が大 | 高さ±2cmに調整、滑り材追加 |
| 膝が当たって痛がる | 車いすの角度不良 | **斜め30°**へ調整、クッション配置 |
| 肘掛が邪魔 | 事前処理不足 | 外す→固定の順で準備 |
階段・段差の越え方:1段ずつ、落ちない仕組みで
上り:前向き・三点支持・短い合図
- 合図:「上がります→上がります」。
- 手すり+杖+足の三点支持。一段一呼吸で脈と息を合わせる。
- 介助者は半段下の位置で骨盤帯を支える。
下り:後ろ向き・二人介助・腰ベルト
- 原則は二人。要介護者は前向き、介助者は背後から骨盤・胸郭を支える。
- 腰ベルト(移乗ベルト)ですべり落ちを封じる。
- 一段ごと停止し、合図→足位置→体幹の順。
車いすでの小段差越え(玄関の敷居など)
- 前輪を軽く上げてから押し、後輪で押し切る。
- 足置きは跳ね上げ、つま先の挟みを防ぐ。
- 声かけ:「段差です→行きます」。
スロープ・仮設板の使い分け
- 段差10cmで長さ120cm(1/12)が目安。屋外は1/15〜1/20に。
- 縁の立ち上がり5cmで脱輪を防止。上下端各50cmの水平部を。
段差越えの早見表
| 方法 | 強み | 注意点 | 向く場面 |
|---|---|---|---|
| 手すり+杖 | 設備が少なく即実行 | 体力負担あり | 室内の小段差 |
| 二人介助 | 安定・安全 | 人手が必要 | 階段の下り |
| スロープ | 連続移動が容易 | 距離・設置場所 | 玄関・屋外 |
| 仮設板 | すぐ用意できる | たわみ・滑り | 一時的な通路 |
夜間・停電・悪天候:見える・聞こえる・冷えない
足元灯と合図の二重化(光+音)
- 停電点灯タイプの足元灯を寝室・廊下・玄関に。
- ヘッドライトは両手を空けるため必須。笛は3回で緊急の合図に統一。
- スマホのライトは予備。主役は頭に付く光。
防寒・保温(低体温の回避)
- 避難用ケープやひざ掛けを玄関椅子に常備。
- 銀色の保温シートは肩から腰を先に包む。
- 濡れを拭く→新しい靴下の順で足から温める。
- 飲み物は常温の甘い物が体にやさしい。
雨・雪の日の足元(滑らない)
- 滑り止め付きサンダルを玄関内側に。
- 玄関スロープは縦溝ゴムマット。
- 車いすのタイヤ水切りを玄関外で実施。
夜間持ち出しセット(玄関椅子に吊る)
| 品目 | 理由 | 備考 |
|---|---|---|
| ヘッドライト | 両手が空く | 予備電池も同封 |
| 笛 | 声が出にくい時に | 合図は3回=緊急 |
| 薬・連絡先カード | 命に直結 | ラミネート保護 |
| ひざ掛け・ケープ | 冷え対策 | 圧縮袋に収納 |
| ポケットラジオ | 情報収集 | 予備電池同封 |
役割分担・動線・持ち物:時間で切ると混乱しない
役割分担(主・副・予備)
- 主介助:移乗・段差越えの主担当。
- 副介助:ドア・荷物・照明・足元の安全。
- 予備:連絡・合図・近所への声かけ。
「主は手を離さない/副は先行」を合言葉に。
動線の固定(日常から同じ動きに)
- 寝室→廊下→玄関→屋外は毎日同じ順路で。
- 玄関椅子を設置し、小休止→靴→ケープの順を習慣化。
- 障害物ゼロの割れ物ゼロゾーンを通路に設定。
持ち物の最小セット(両手は空ける)
- ショルダーポーチに薬・連絡先・小銭・身分証。
- 手袋(滑り止め)・マスクを玄関内側に常備。
- 延長コードとモバイル電源は車いすユーザーに有効。
- 介護保険証の写し・お薬手帳の写真をスマホに保存。
介護避難の準備表(家庭用)
| 項目 | 配置場所 | 点検頻度 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 玄関椅子・ケープ | 玄関 | 月1 | 副 |
| スロープ・手すり | 玄関・屋外 | 半年 | 主 |
| 夜間セット | 玄関椅子下 | 月1 | 予備 |
| 連絡先カード | 寝室入口 | 月1 | 副 |
| 予備電池・モバイル電源 | 玄関棚 | 月1 | 副 |
医療・服薬・衛生:中断させない工夫
服薬の継続
- 1回分ずつ小袋に分け、日付と時間を大きく記入。
- 急な中断で困る薬(てんかん・心臓など)は最優先で持ち出し。
医療機器の扱い(在宅酸素・ストマなど)
- 在宅酸素:予備ボンベの位置を家族全員で共有。転倒防止ベルトで固定。
- ストマ・カテーテル:交換セット一式を密閉袋に。
- 血糖測定・インスリン:保冷袋と予備針をまとめる。
衛生の基本
- 手指消毒はこすり時間20秒を合言葉に。
- 使い捨て手袋は介助前後で交換。
- 口腔ケアは柔らか歯ブラシと口腔湿潤剤を小分け。
認知症・見当識のゆらぎへの配慮
声かけの型
- 名前→場所→行動の順で短く。例:「田中さん、寝室から玄関へ、ゆっくり行きます」。
- 選択肢は二択:「右手の手すりを持つ・持たない、どちらにしますか」。
不安・興奮への対応
- 音・光・人を最小に。一人が主に話し、他は補助。
- 手をつなぐ・肩に手など触覚で安心感を出す。
迷子防止
- 名札・連絡カードを胸元に。
- 玄関・廊下の矢印表示を大きくし、戻る方向も明確に。
ケーススタディ:3世帯の実践
例1:片麻痺・杖使用(戸建・段差10cm)
ベッド高さを座面±5cmに調整し、スライドボードで玄関椅子へ。玄関スロープ120cm(1/12)+縁5cmで脱輪防止。主が移乗、副がドアと荷物。在室→玄関→外まで7分で完了。
例2:電動車いす(マンション・停電)
ヘッドライト・笛・連絡カードを寝室入口に。水平避難を優先し、同一階の共用バルコニーへ移動。延長コードで共用電源へ仮接続し、予備が近隣へ連絡。
例3:夜間・大雨・二人介助(狭い廊下)
副が先行して足元灯を配置、主は腰ベルトで後ろ支え。ドアストッパーで開放、滑り止めサンダルを履いて退避。合図は短文で統一して混乱を防止。
Q&A(よくある疑問)
Q1. 一人介助しかいない時、階段は?
A. 原則は避ける。可能なら水平避難、やむを得ない場合は段差板と腰ベルトで一段ずつ停止。
Q2. 体が重くて持ち上がらない。
A. 持ち上げないのが原則。スライド・回転で骨盤→肩→頭の順に移す。
Q3. 玄関が狭くて回れない。
A. 玄関椅子を外に出し、屋外で方向転換。傘立て・収納を移設して90cm幅を確保。
Q4. 夜間で声が出ない。
A. 笛とヘッドライト点滅で合図。合図3回=緊急を家族で共有。
Q5. 雨でスロープが滑る。
A. 縦溝ゴムシート・砂入り塗装に変更。上下端に50cm水平部を入れて再施工。
Q6. 認知症で不安が強い。
A. 一人の声かけに統一し、短い言葉と触覚を使う。選択は二択に絞る。
Q7. 在宅酸素やストマがある。
A. 予備ボンベ・交換セットを玄関椅子下に常備し、連絡カードにも明記。
用語辞典(やさしい言い換え)
移乗(いじょう):人をある場所から別の場所へ移すこと。
水平避難:階段を使わず同じ階の安全な場所へ移ること。
スライドボード:すべりやすい板。座面間をすべらせて移す道具。
腰ベルト(移乗ベルト):介助者が腰を支える帯。すべり落ちを防ぐ。
1/12・1/15:高さ1に対し長さ12・15の勾配のこと。
回転スペース:方向転換に必要な円の広さ。
まとめ:段取りが介助者と家族を守る
避難の安全は段取りでつくれます。移乗は持ち上げずに滑らせる/階段は二人で一段ずつ/夜間は光と音の二重化。そして主・副・予備の役割を平時から決めておけば、非常時も同じ手順で動けます。今日、玄関椅子・夜間セット・連絡カードの3点から整え、初動10分のタイムラインを家族で共有しましょう。