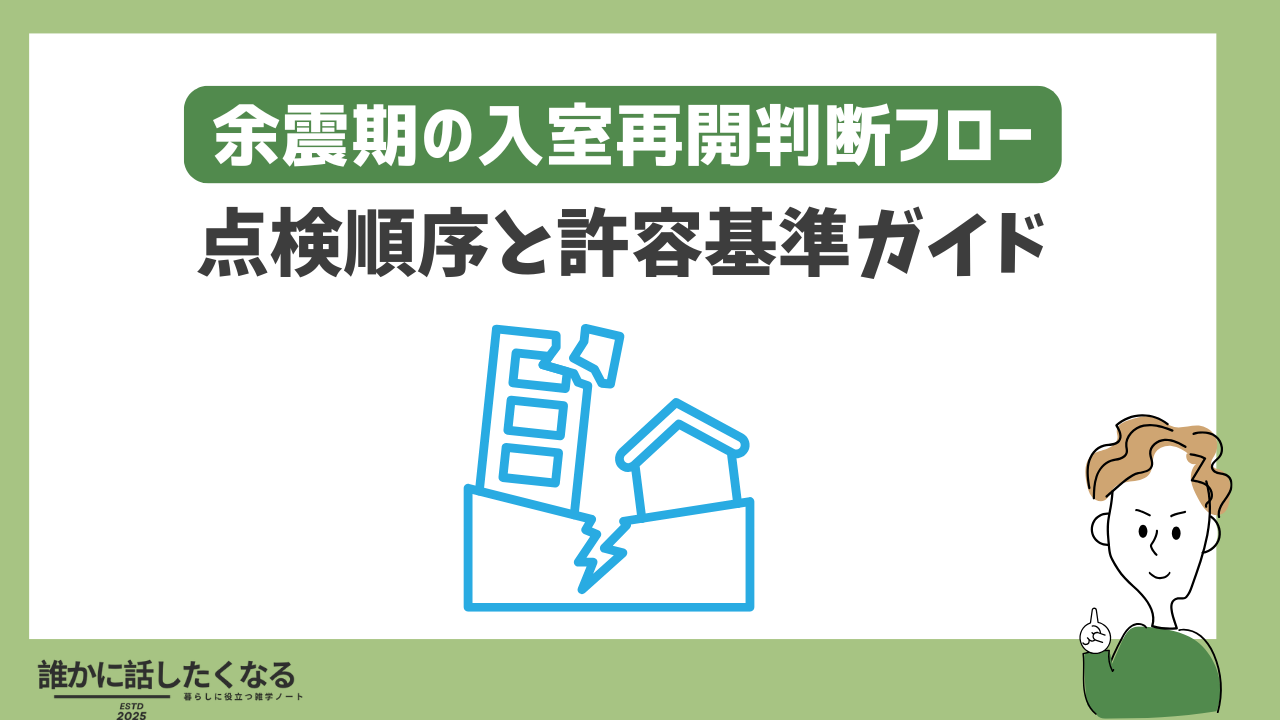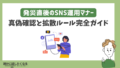強い揺れの直後は、建物がまだ揺れる前提で動くのが安全です。焦って室内に戻るより、外で状況をそろえ、順序と基準を先に決めてから点検すれば、二次被害を大きく減らせます。
本記事は、家庭・小規模事業所・集合住宅の管理者が、誰でも同じ判断に近づけるための入室再開フローと許容基準を、表・チェックリスト・実例で具体化した実践ガイドです。時間目安や撮影方法、再開後の巡回までを網羅し、**迷ったら立ち止まる“しきい値”**も明確に示します。
結論サマリー:先に外、次に設備、最後に室内
1. 先に外まわりを確認(倒壊・落下の芽をつぶす)
屋根・外壁・塀・バルコニー・配管・電線・樹木の傾きや落下物を外から一周で点検。危険が1つでも“赤”なら、入室再開は見送ります。外周は2〜5分の短時間で良いので、とにかく全周を切らさず見るのがコツです。
2. 次に設備(ガス・電気・水・下水)を遮断→個別確認
止めてから見るが原則。におい・音・濁り・漏れ・メーターの異常回転など、**設備ごとの“黄色サイン”**が消えるまで再開しません。止め方→見方→戻し方の順で、記録しながら進めます。
3. 最後に室内(落下・転倒・破片・有害物)を片付けてから再開
天井・壁・家具・ガラス・家電・薬品・電池を上→中→下の順で確認。避難経路を先に確保し、出入口がいつでも開くことを最後にもう一度確認します。初回の在室は**短時間(目安15分)**から。
入室再開の三条件(満たせなければ見送り)
1)逃げ道が常に開いている(通路・ドアの確保)
2)火気・漏電・ガス・液体の危険がゼロ
3)天井からの落下/壁のはらみがない(上を見て音も確認)
3色タグでの全体判断(自主管理用)
| 色 | 総合判断 | 再開の可否 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 緑 | 軽微 | 条件付きで可(短時間→段階的) | ひび極小、設備異常なし、落下なし |
| 黄 | 注意 | 要監視・在室者を最少に | ひび小・一部転倒、設備は復旧済み |
| 赤 | 危険 | 入室禁止・要専門点検 | 大きな割れ・傾き・におい・漏れ |
フロー全体図:5段階で“立ち止まるポイント”を作る
段階0 初動整え(1〜2分)
- 人数確認(二人一組が基本)。
- 防護具(手袋・マスク・保護めがね・ヘッドライト)。
- 連絡役の決定(外に一人残し、見張り+連絡)。
段階1 外周一周(2〜5分)
- 外壁・基礎:貫通ひび、斜めの大割れ、モルタル剥落。
- 屋根:棟板金の浮き、瓦のずれ・落下、雨どい外れ。
- 塀・フェンス:ぐらつき、控えの不足、基礎の割れ。
- バルコニー・庇:手すり緩み、床の段差、吊り金物の脱落。
- 周囲の落下物:ガラス・看板・瓦片の散乱。
段階2 設備安全化(遮断→点検)
- ガス:元栓閉→におい・シュー音・メーター異常回転。
- 電気:主幹ブレーカーOFF→浸水・焼け跡・こげ臭。系統ごとに復帰。
- 水道:濁り・赤水→少量排水で確認、漏れを点検。
- 下水:逆流・悪臭・床排水のあふれ、封水切れ。
- 給湯器・ボンベ:固定バンドの緩み、配管の折れ・にじみ。
段階3 室内上部→中段→足元
- 上部:天井板のたわみ、照明の外れ、吊戸棚の開放、梁の割れ。
- 中段:食器棚・本棚の固定、耐震金具、引き戸の外れ/かみ合い不良。
- 足元:ガラス破片・液体こぼれ・電池の散乱、床のふわつき。
- 開口部:ドア・サッシが閉まったまま固着していないか。
段階4 重要室の重点確認
- キッチン:こんろの変形、ゴム管のひび、油のこぼれ。
- 浴室・トイレ:タンクの割れ、床防水のふくれ、配管のにじみ。
- 寝室:避難経路の直線化、頭上落下のゼロ化、割れ物撤去。
- 子ども部屋・高齢者部屋:段差・コード・敷物のつまずき源除去。
段階5 条件付き再開と監視
- 短時間から再開(黄は在室者を最少に)。
- 監視項目を紙に書いて貼る(ひび、におい、音、湿り)。
- 赤に変化したら即退避し、フローを段階1からやり直し。
許容基準(外周・構造・設備・室内):“線引き”の例
外周・構造:見た目の兆候と線引き
| 兆候 | 緑(許容) | 黄(要注意) | 赤(危険) |
|---|---|---|---|
| 外壁のひび | **髪の毛程度(〜0.3mm)**で伸びなし | 0.3〜1mm、斜めに連続 | 1mm超、貫通、窓角から斜め |
| 基礎の割れ | 表面の細筋のみ | 幅0.5mm前後で短い | 幅1mm超、段差、鉄筋露出 |
| 柱・梁の欠け | 塗装欠けのみ | 角の小欠損 | 木口・鉄骨が見える |
| 屋根のずれ | 目視で不明瞭 | 一部ずれ・浮き | 瓦落下・棟外れ |
| 塀の傾き | 目測で垂直 | 軽い傾き・ぐらつき | 明確な傾斜・ひび連続 |
| サッシのかみ合い | 開閉に支障なし | こすれる・ずれる | 閉鎖不能/枠の変形 |
| 床の傾き | ビー玉が止まる | ゆっくり転がる | はっきり転がる/沈む |
注:黄判定は短時間の入室のみ。赤は入室禁止、専門点検が前提。
傾き・ひびの簡易測定
- ひびの幅:名刺/紙片を当てて写真撮影。
- 傾き:ビー玉や水の入ったコップで確認。
- 再確認:同じ場所・角度・距離で撮り、変化を見る。
設備(ガス・電気・水・下水):止め方→見方→戻し方
| 設備 | 止め方 | 見方(異常) | 戻し方(正常時) |
|---|---|---|---|
| ガス | 元栓・メーター弁を閉 | におい、シュー音、メーター回り続け | 窓開→においゼロ→各機器OFF→メーター復帰→元栓開 |
| 電気 | 主幹OFF | 焦げ臭、濡れ・浸水、焼損 | 乾燥→系統ごとにON(重要→一般) |
| 水道 | 止水栓閉 | 赤水、濁り、漏れ | 透明まで少量放水→止水栓開 |
| 下水 | 一時停止 | 逆流、悪臭、床排水あふれ | 封水回復(水を張る)→再開 |
| 給湯器 | 電源OFF/ガス閉 | 配管にじみ、固定緩み | 固定確認→試運転は最後 |
| LPボンベ | バルブ閉 | 転倒/バンド外れ | 直立固定→配管点検後に開栓 |
室内:落下・破片・有害物の線引き
| 兆候 | 緑 | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 家具の固定 | 全固定・移動なし | 1点外れ・10cm以内の移動 | 転倒・扉破損 |
| ガラス破片 | 片付け済み | 細片が点在 | 広範囲散乱・足元危険 |
| 液体こぼれ | 水・飲料 | 洗剤・油少量 | 薬品・灯油・不明液 |
| 天井・照明 | 異常なし | カバー外れ | たわみ・落下の恐れ |
| 壁面 | 表面のこすれ | 石こうの粉落ち | ふくらみ/剥離が拡大 |
| 匂い | なし | 弱いこげ/下水 | 強いガス/こげで即退避 |
点検の実践:順序・道具・記録のコツ
点検順序は「危険が落ちてくる方向」から
上→中→下。次に出入口→通路→居室。避難口の確保を最優先し、重い家具は後回しでも通路を開けます。片付けは小さい物から外へが基本です。
点検道具:最小でもこれだけ
- 手袋(厚手)・踏み抜き防止インソール
- ヘッドライト(両手を空ける)
- マスク・保護めがね
- 養生テープ・布ガム(ひびの仮押さえ、ガラスの補強)
- ビニール袋・ほうき・ちりとり・雑巾
- 紙と油性ペン(記録)・印をつける付箋
写真記録の「5同」
同じ場所・同角度・同距離・同明るさ・同サイズで撮り、前後比較をしやすくします。黄判定は監視項目として次の余震後に再撮影。撮影前に名刺/紙片を当てて幅の目印を残すと正確です。
点検記録シート(配布用)
| 場所 | 兆候 | 色 | 時刻 | 追記 |
|---|---|---|---|---|
| 北外壁 | 窓角から斜め0.7mm | 黄 | 10:20 | 次の余震後再確認 |
| 台所 | こんろゴム管細かいひび | 黄 | 10:30 | 交換予定 |
| 玄関 | ガラス破片片付け済 | 緑 | 10:40 | —— |
再開後の監視:いつ退避に戻すかの“しきい値”
時間軸での巡回(目安)
- 0〜2時間:30分ごとにひび・におい・音を確認。
- 2〜6時間:1時間ごと。水回りのにじみと電源まわりの温度に注意。
- 24時間:朝夕の外周一周を復活し、写真を更新。
退避に戻す条件
- 余震が明確(立って歩けない・物が落ちる)→即退避、段階1から。
- ひびが伸びる・にじむ・音がする→黄→赤に格上げ、入室禁止。
- におい・こげ臭・湿り・しみの再発→設備完全停止、換気→外へ。
監視項目の早見表
| 区分 | 具体例 | 対応 |
|---|---|---|
| ひびの変化 | 長さ・幅・段差の増加 | 退避→外周点検に戻る |
| 音 | ミシミシ・パキ | 退避→専門点検へ |
| におい | ガス臭・こげ臭・下水臭 | 設備停止→換気→退避 |
| 水 | 天井しみ・壁の湿り | 範囲拡大で退避 |
ケーススタディ(3例)
例1:木造戸建(築25年)
外周で屋根のずれ小、外壁に0.4mmの斜めひび。設備は問題なし。黄判定とし、在室を15分以内に制限。翌朝の外周一周で変化なし→緑に降格し、通常再開。
例2:RCマンション5階(角部屋)
外周は異常なし。室内で食器棚の移動10cm、サッシのこすれ。黄判定で監視項目にサッシを追加。夕方の余震でこすれ悪化→赤判定、入室停止し専門点検へ。
例3:小規模店舗(路面)
看板の金具緩み、店内にガラス細片。赤水が一時発生。電気は主幹OFFのまま片付け、赤水解消後に水回り再開。看板撤去後に緑判定で短時間営業から復帰。
Q&A(よくある疑問)
Q1. ひびの幅はどう測る?
A. 名刺や紙片で比較し、写真に重ねて記録。同じ場所・角度で再撮影します。
Q2. ガスのにおいが微かにする。入っていい?
A. 入室禁止。元栓を閉じ、窓は屋外から開放。火気厳禁で専門点検へ。
Q3. 電気はいつ戻す?
A. 主幹OFF→各系統ごとにON。濡れ・焼け跡・こげ臭があれば復旧延期。
Q4. 赤水が出る。飲んで大丈夫?
A. 飲用不可。透明になるまで排水し、必要なら煮沸。長引く場合は給水を利用。
Q5. 家具転倒で通路がふさがれている。
A. 出口側から小さい物を動かし、通路を先に開ける。重い物は後回し。
Q6. 子ども・高齢者・ペットがいる。どう再開する?
A. 黄判定の部屋は入れない。安全な一室を先に整えて短時間利用に留めます。
Q7. 夜間で暗い。点検はどうする?
A. ヘッドライトと足元灯で上→中→下を確認。写真は朝に撮り直し。
Q8. 一人暮らしで二人一組が難しい。
A. 隣家と声かけし、外に見張りを置く。連絡先を紙に書いて玄関内側に掲示。
用語辞典(やさしい言い換え)
貫通ひび:壁の裏まで届く割れ。雨や風が通る。
主幹ブレーカー:家全体の電気を一度に止めるスイッチ。
封水:排水口の水のふた。下水のにおいをせき止める水。
段差ひび:片側が上下にずれる割れ。動きが大きいサイン。
赤水:管のさびが混じって赤くなる水。
かみ合い不良:戸や窓が枠に合わずこすれる状態。
まとめ:順序と基準が“焦り”を止める
余震期の入室は、外→設備→室内の順序と、緑・黄・赤の基準があれば、迷いが減ります。危険は後回しにせず“立ち止まる”。初回は短時間から再開し、監視項目を決めて次の余震ごとに再点検。ルールを紙1枚に落とし、家族・職場で共有しておきましょう。