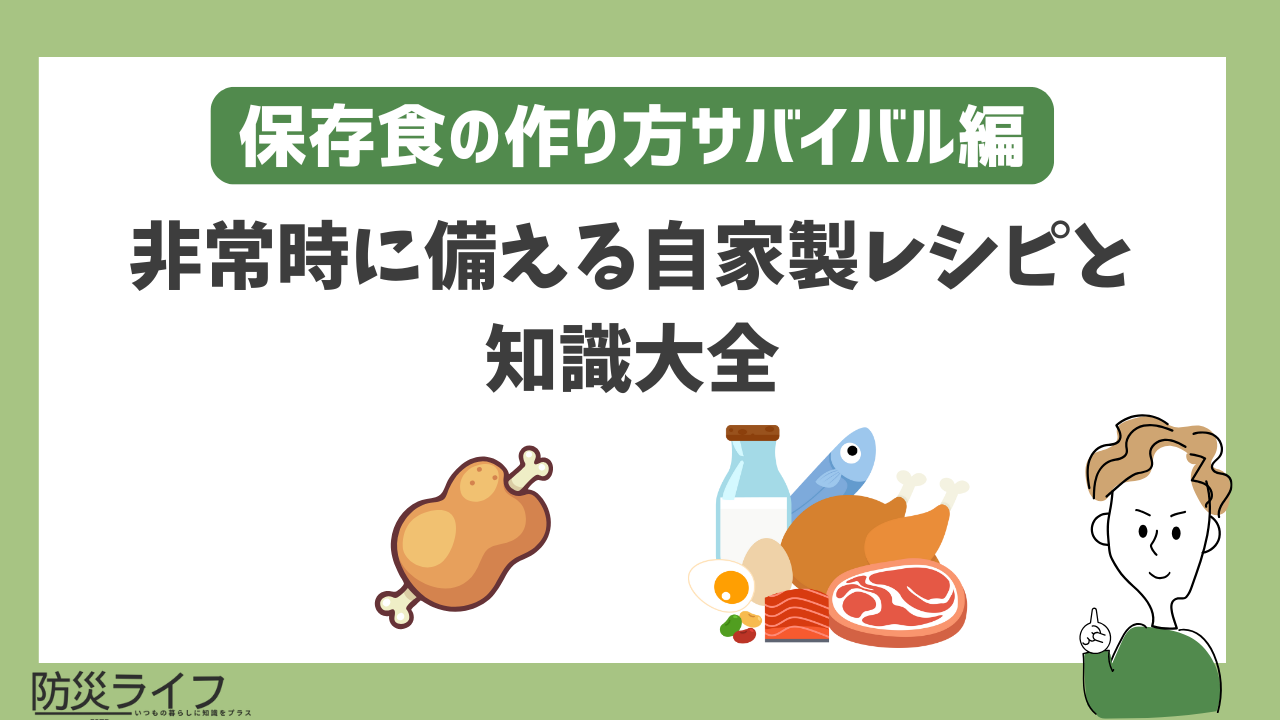台所で作れる保存食は、ふだんの節約と健康管理に役立つだけでなく、地震・台風・大雪・感染症流行・経済混乱・戦時の物流停止のような非常時に、家族のいのちを支える最後の砦になります。
本稿では、サバイバルの視点でなぜ保存食が必要かを整理し、家庭で再現できる保存技術(乾燥・塩漬け・発酵・瓶詰・粉末化)、長持ちの理屈と衛生、持ち運べる携帯食の工夫、回しながら増やす備蓄術、72時間〜1週間の運用と献立、年齢や体質に合わせた配慮までを、実践向けに詳しくまとめました。手順・分量・保存条件を明記し、安全上の注意を随所に添えています。
サバイバルにおける保存食の基本と重要性
“買えない”を前提に組み立てる(仮定づくり)
大規模災害や社会混乱では、店が開かない、開いても棚が空、道路寸断や燃料不足で配送が止まることがあります。買い足せない前提で「家にあるもので72時間→1週間→30日」と段階的に自立できる計画を立てると、必要量と優先順位が明確になります。
熱量・三大栄養・水分(体を動かす土台)
人は一日におよそ1500〜2600kcalを必要とします。主食(米・粉・芋)で熱量を確保し、豆・魚・肉・卵・乳でたんぱく質、油で持続力を足します。食物繊維・ミネラル・塩分・水も欠かせません。とくに水は**1人1日3L(飲用2L+調理1L)**を目安にします。
一日分の熱量と主食・水の目安(成人)
| 体格・活動 | 目安熱量 | 主食の例(いずれか) | たんぱくの例 | 水の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 小柄・軽作業 | 1500〜1800kcal | 米2合弱 / うどん2.5玉 / オート麦120g | 魚缶1、豆150g、卵1 | 2.5〜3L |
| 標準・中程度 | 1800〜2200kcal | 米2合 / パスタ300g / 芋大2本 | 鶏胸150g、卵2 | 3L |
| 体格大・重作業 | 2200〜2600kcal | 米2.5合 / パン6枚+α | 豚200g、豆200g、卵2 | 3〜3.5L |
ポイント:暑熱時・発汗時・授乳中は水と塩を増やし、寒冷時は油と糖を増やすと体が楽になります。
心の安全にも効く(“食べ慣れた味”の力)
非常時は不安と緊張で食が細くなります。いつもの味が一口でもあれば落ち着きが戻り、判断力も上がります。保存食は胃袋と心の装備。平時から食卓に混ぜ、味の調整と好みを掴んでおきましょう。
年齢・体質別の配慮(目安)
| 区分 | 重点 | 具体の工夫 |
|---|---|---|
| 幼児 | 噛みやすさ・薄味 | やわらか飯・汁物・刻み干し野菜 |
| 高齢 | たんぱく・水分 | 魚缶・豆・粉末スープ、こまめな水分 |
| 妊産婦 | 鉄・葉酸・水分 | 鶏レバー缶・豆・乾燥野菜、薄味 |
| 食物アレルギー | 原材料の明示 | ラベル保管・在庫表に記載 |
家で作れる基本の保存食(乾燥・漬け・瓶詰・粉末化)
干し野菜(乾かして軽く甘く、燃料も節約)
材料:にんじん・大根・しいたけ・ピーマン など/厚さ2〜5mmに切る。
手順:①日陰で風通しの良い場所に重ならないよう並べる → ②2〜3日乾かし、折るとパキッと割れる硬さまで → ③厚手袋+乾燥剤で密封。
使い方:水で戻して味噌汁・炊き込み・炒め物。皮や芯も刻んで干せばくずなく使い切り。
コツ:梅雨どきや湿潤日は電子レンジ短時間+扇風で補助乾燥。天日直射は色が抜けやすいので日陰干しが基本。
塩蔵・味噌漬け(発酵の力で長もち)
塩蔵:野菜に塩2〜3%を均一にまぶし、落としぶた+重しで水を出す。表面の浮き・泡は除去。
味噌漬け:水けをふき、味噌で包んで密封。
保存:涼所で数週間〜。酸味や香りが強くなりすぎる前に食べきり→作り直し。
注意:容器・手指は清潔最優先。塩分が気になる場合は食べる直前の塩ぬきで調整。
干し肉・干し魚(たんぱくを軽く確保)
材料:鶏胸・豚もも・白身魚・小魚。
下ごしらえ:薄塩(1〜1.5%)に短時間漬け、水けを完全にふく。
乾燥:網+風で日陰干し。仕上げに低温オーブン(60〜70℃)で水分を飛ばすと安全度が上がる。
注意:十分な乾燥ができない天候では無理をせず加熱後に冷蔵。油分が多い部位は酸化が早いので短期消費を。
瓶詰(熱と密封で安定、冷暗所で短期)
手順の概略:びん・ふたを煮沸消毒→具を熱々のうちに詰める→隙間を少なく→ふたを閉めて追加加熱→冷暗所。
注意:肉・魚など酸の少ない食品は、家庭設備では長期常温保存を前提にしないのが安全。中心まで十分な加熱ができない場合は、冷蔵の短期保存に切り替える。
粉末化(軽くて早い調理)
干したねぎ・しいたけ・人参、煎ったごま・大豆を粉にし、小袋で小分け。湯で即席汁やふりかけに。粉は空気に触れると劣化しやすいので厚手袋+乾燥剤で保管。
保存法の比較(家庭で再現しやすい四法)
| 方法 | 長所 | 注意点 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 乾燥 | 軽い・燃料いらず・味がのる | 湿気・天候に左右 | 野菜・きのこ・果物・一部肉魚 |
| 塩・味噌漬け | 道具が少ない・発酵で栄養増 | 清潔・塩分管理 | 野菜・魚 |
| 瓶詰 | すぐ食べられる・味がなじむ | 加熱不足は厳禁・容器管理 | 肉・魚・豆・煮物 |
| 粉末化 | 軽量・湯だけで食べられる | 酸化しやすい | 香味・汁物・滋養 |
保存性を高める工夫と保管の要点
清潔の徹底(器具・手・場)
成功の半分は清潔で決まると言っても過言ではありません。まな板・包丁・ざる・瓶は熱湯か食品用アルコールで処理。手は石けんで30秒以上。生と加熱済みの道具の使い分け、台ふきの乾拭き仕上げも徹底します。
容器の選び方(空気・湿気・光を断つ)
厚手袋・密封びん・金属缶を使い分け、食品により乾燥剤・脱酸素剤を組み合わせます。透明容器は光劣化を防ぐため紙や布で覆う。穀物・粉は防虫板や唐辛子のさやを入れて虫害を抑えます(強い香りは苦手)。
温度・湿度・光の管理(冷暗と通風)
直射日光を避けた冷暗所が基本。押し入れ最下段・キッチンの熱源近くは不適。北側の物置が安定しやすい。梅雨時は乾燥剤の入れ替えを早め、夏は高温になる天袋を避けます。
穀物・豆の長期保管(主食の土台)
白米は無洗米+密封で使いやすく、玄米は冷所で。豆は虫の混入の有無をふるいで確認し、密封びんで保管。粉は小分けして酸化を遅らせます。
容器と保管の組み合わせ例
| 食品 | 容器 | 追加資材 | 場所 | 目安保存 |
|---|---|---|---|---|
| 干し野菜 | 厚手袋 | 乾燥剤 | 冷暗所 | 3〜6か月 |
| 味噌漬け | 陶器・密封箱 | 落としぶた | 涼所 | 1〜3か月 |
| 肉の瓶詰 | 密封びん | 清潔布 | 冷暗所 | 1〜数か月(開封後冷蔵) |
| 穀物 | 密閉びん | 防虫板 | 涼所 | 6か月〜 |
| 粉末品 | 厚手袋 | 乾燥剤 | 冷暗所 | 1〜3か月 |
持ち運べる携帯保存食(軽く・高密度・手早く)
穀物ぎゅっと棒(焼いて切るだけの高密度食)
押し麦・砕いた木の実・干しぶどうをはちみつと練りごまでまとめ、薄板に広げて焼き、冷めたら棒状に切ります。1本200〜250kcalを目標に配合。包丁に油を薄く塗ると切りやすい。
脱気密封のおにぎり(炊いて包んで冷凍)
炊き込み・わかめ飯を小さく握り、空気を抜いて密封し冷凍。非常時は常温戻し→袋のまま湯せんで衛生的に温食。手に塩水をつけて握ると日持ちが延びます。
粉の汁物・乾燥おかず(湯だけで温まる)
粉みそ、乾燥ねぎ、わかめ、高野豆腐、切り干し大根の小袋セットを作っておくと、湯だけで塩分・水分・たんぱくを素早く補給可能。
乾肉・小魚・海藻(歩きながら噛める)
小魚の干物や焼きのりは軽く、割って携行袋に。乾肉は薄切り・低温加熱乾燥で噛みやすく仕上げる。塩飴・黒砂糖は即効の糖として役立ちます。
携帯食の重さあたりの熱量めやす
| 食品 | 100gあたりの熱量 | 強み |
|---|---|---|
| 木の実(くるみ等) | 650〜700kcal | 高密度・噛む満足感 |
| 穀物ぎゅっと棒 | 450〜550kcal | 自作で配合自在 |
| 干し芋 | 約300kcal | やさしい甘み・食物繊維 |
| 黒砂糖 | 約380kcal | 即効の補給 |
備蓄を続ける仕組み(回しながら増やす)
回転保存(食べて補充する)
「買って積むだけ」は賞味期限切れの近道。普段の献立に保存食を組み込み、食べたら同じ物を買い足す方式に切り替えます。先入れ先出しの棚づくりで迷いをなくす。
在庫表・表示ルール(誰が見ても分かる)
在庫表に品名・個数・賞味期限・保管場所を記し、入れ替え日に○印。透明容器には日付ラベル。アレルギーや宗教上の制限は太字で明記します。
家族別・用途別に分ける(取り出しやすさ)
家族の数だけ小分け袋を作っておくと配布が速い。**台所用(調理)/持ち出し用(即食)/寝室用(夜間)**など場所別に分けると実戦的。
三日分×家族3人の例(目安)
| 品目 | 1日あたり | 3日合計 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主食(米・麺・餅) | 2合相当 | 6合相当 | 無洗米が便利 |
| たんぱく(魚缶・豆) | 1〜2缶 | 3〜6缶 | 卵粉・粉乳も有効 |
| 油脂(ごま油等) | 大さじ2 | 大さじ6 | 小瓶で小分け |
| 野菜(乾物) | ひとつかみ | 3つかみ | みそ・乾燥わかめ等 |
| 水 | 1人1日3L | 27L | 生活用水は別途 |
いざという時の運用術(72時間〜1週間の食と衛生)
48時間前〜直後(ある物で回す段取り)
警報・予報で2日前から準備。冷蔵庫の消費優先表を作り、停電時に先に食べる物を前面へ。直後は火を使わず食べられる物から出し、調理は湯だけで済ませる。水は飲用を最優先、洗い物は拭き取りで代替。
小さな熱源の連携(燃料節約)
卓上こんろ・固形燃料は風よけを使うと燃費が伸びる。湯を保温容器に移し二次利用、鍋はふた必須。袋ごと湯せんの**“袋調理”**は衛生的で洗い物が少ない。
衛生とごみの管理(病気を防ぐ)
生ごみは密封、汁気は紙で吸わせて捨てる。食器は熱湯・食品用アルコールで拭き、使い捨て敷き紙で洗い物を減らす。手洗いが難しいときは消毒液を活用。
72時間ミニ献立(例)
| 時間帯 | 1日目 | 2日目 | 3日目 |
|---|---|---|---|
| 朝 | 米飯+乾燥汁 | 米飯+干し野菜卵とじ | 米飯+みそ汁+海苔 |
| 昼 | 魚缶丼+漬物 | おにぎり+粉の汁物 | うどん+乾燥ねぎ |
| 夜 | 肉の瓶詰と芋 | 豆とさばの煮込み | 炊き込みご飯 |
1週間の回し方(温かい汁を軸に)
汁物+主食+たんぱく一品を基本形に、乾物と缶詰を日替わりで回す。温かい一杯が体温と気力を支えます。
特別な配慮:子ども・高齢・持病・季節
子ども(噛む力・栄養バランス)
やわらか飯・おじや・粉末だしを活用。甘みは干し芋・甘納豆で自然に。誤嚥しやすい硬い木の実は刻む。
高齢(たんぱくと水分を欠かさない)
魚缶・豆・卵粉でたんぱくを確保。こまめな水分と温かい汁で負担を軽く。塩分は食前の塩ぬきで調整。
持病(アレルギー・減塩・糖)
在庫表に食べられない原材料を明記。減塩が必要な方は無塩の乾物+香味で満足感を。糖を制限する方は油とたんぱくで腹持ちを図ります。
季節(暑さ・寒さ)
暑熱時は水・塩・酸味(梅・酢)で体を守る。寒冷時は油・糖で発熱を助け、温かい飲み物を増やす。
よくある疑問と答え(安全のために)
乾燥が足りないとどうなる?
水けが残るとかび・異臭・粘り。折ってぱきっと割れるのが乾燥の目安。迷ったら短時間再乾燥。
瓶詰はどのくらい持つ?
家庭設備では長期常温保存を前提にしないのが安全。冷暗所で数週間〜数か月、開封後は冷蔵で早めに。中心までの十分加熱ができない場合は冷蔵短期へ。
塩分が気になる場合は?
下漬けは薄塩、食べる直前に塩ぬき。香辛料・酢・昆布だし・柑橘で塩味以外の満足を作る。
乾物はそのまま食べてもいい?
噛み砕ける物は可。ただし水なしで大量摂取は消化に負担。湯で戻すと安全で量も増えます。
まとめ:平時の工夫が非常時を救う
保存食づくりは、むずかしい技ではなく下ごしらえの延長です。乾かす・漬ける・熱して密封・粉にするという四つの柱を、清潔・密封・冷暗の三条件で支えれば、家は小さな倉(くら)になります。普段の食卓に少しずつ取り入れ、食べて補充する回し方で備えを育てましょう。味のなじんだ保存食と湯の一杯は、いざという時に心身を支える最強の道具です。今晩、干し野菜をひと皿仕込む——その小さな一歩が、家族の大きな安全につながります。