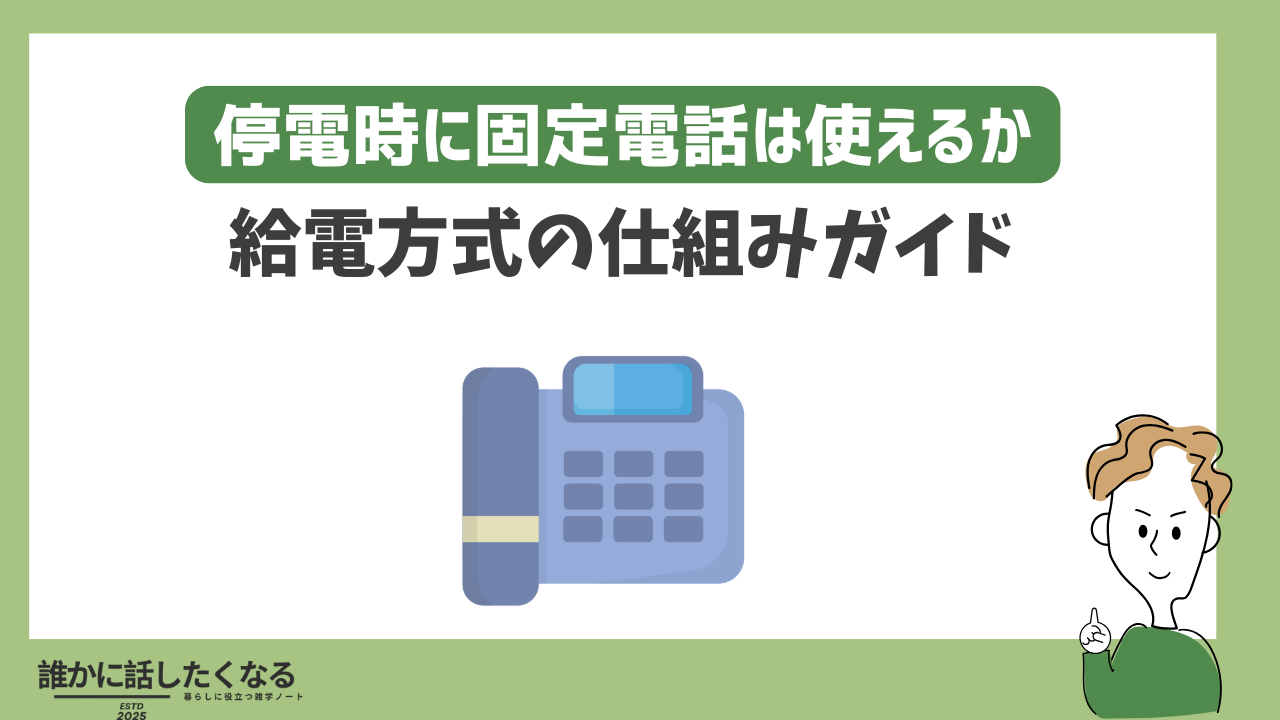結論から先に:固定電話が停電でも使えるかは、回線の種類と給電の仕組みで決まります。アナログ(メタル)回線は電話局からの線路給電で電源不要の受話器なら通話可能。
一方、光・ケーブル・IP電話は宅内機器への電気が止まると発着信不可になります。本稿は、家庭の配線図に落とし込めるよう、仕組み→可否早見→電源確保→通話運用→点検・訓練→復旧の順で、具体的手順・表・計算例まで掘り下げて解説します。
要点先取り(まずここだけ)
- 回線の型で可否が決まる:
- アナログ回線+電源不要受話器=停電に強い。
- 光・ケーブル・IP=宅内装置への給電が止まれば不通。外部電源で延命。
- 最小構成の電源を守る:ONU・通話装置・親機の合計Wから必要Whを逆算。200Whで約9時間、500Whで約24時間が目安(17W構成)。
- 混雑回避は通話の短文化:「無事/場所/次の連絡」の30秒定型+家族代表一本化。
- 準備は紙と配線の見える化:回線の種類・配線図・非常時の手順をA4で1枚にまとめ、装置の棚へ貼る。
1.固定電話の給電方式を理解する(仕組みの地図)
1-1.アナログ(メタル)回線:電話局からの線路給電
- 電話線(2芯)に待機の直流と呼出用の交流が重畳され、電源不要の受話器は家庭側のコンセントが無くても通話できる。
- ただし親機がAC依存(コードレス・留守録・FAX一体など)の場合は停電で不通。受話器直結型を1台備えると強い。
1-2.光回線(ひかり電話等):宅内機器が命綱
- ONU(回線終端装置)と通話装置(ホームゲートウェイ)が家庭のコンセントで動作。
- 停電時はONU/HGWが停止し発着信不可。無停電電源装置(UPS)やポータブル電源で一定時間の継続は可能。
1-3.ケーブル電話(同軸)・IP電話(インターネット)
- ケーブルモデム(通話対応)や宅内ルーターが家庭電源に依存。
- 一部に内蔵電池搭載機もあるが数時間規模。長期停電では外部電源が必要。
1-4.ISDN・PBX・宅内交換機の注意
- ISDNはTA(終端装置)が必要でAC停止=不通。
- 事務所・集合住宅の小型交換機(PBX)も本体電源が落ちれば全台不通。
1-5.屋内配線の型(単独・分岐)と影響
- 単独配線:壁のモジュラーに受話器を直挿し。切替が簡単で停電時の確認がしやすい。
- 分岐配線:家中に複数の差し口。親機の故障や混線が起きやすく、停電時の切り分けに時間がかかる。
2.停電シナリオ別「使える/使えない」早見表
2-1.可否早見(家庭側の停電/地域停電/設備障害)
| 回線方式 | 家庭のみ停電 | 地域が停電 | 事業者設備障害 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アナログ(メタル) | 可(シンプル電話のみ) | 条件付き可(局舎の非常電源次第) | 不可 | 親機AC依存型は不可 |
| 光(ひかり電話等) | 不可(UPS等で可) | 条件付き不可(局側OKでも宅内機器が停電) | 不可 | ONU/HGWに電源必須 |
| ケーブル電話 | 不可(装置内電池で数時間可) | 条件付き不可 | 不可 | 事業者側電源が鍵 |
| IP電話(ネット) | 不可 | 不可 | 不可 | ルーター・網双方の電源が必要 |
ポイント:“親機が電源不要”דアナログ回線”の組み合わせだけが停電に強い。
2-2.親機タイプ別の停電耐性
| 親機タイプ | アナログ線 | 光・ケーブル・IP |
|---|---|---|
| 受話器直結型(電源不要) | 強い | 宅内機器が止まるため不可 |
| コードレス親機(子機) | 不可 | 不可 |
| 留守番電話・FAX一体 | 不可(AC必要) | 不可 |
2-3.集合住宅での留意点(MDF・共用設備)
| 項目 | ありがちな仕様 | 停電時の影響 | 対処 |
|---|---|---|---|
| 共用設備 | PBX/光収容 | 本体電源停止で全戸不通 | 発電・UPS対象に含める |
| MDF室 | 施錠・入室制限 | 復旧作業が遅延 | 連絡経路・鍵管理を明確化 |
| 監視・通報 | 電源依存 | 停電で通報不可 | 代替巡回・掲示で補完 |
2-4.停電の長期化と通信の混雑
- 大規模停電では電話局・中継設備は非常電源で持続するが、呼量集中でつながりにくい。
- 短い通話・定刻連絡・発信先の絞り込みで回線占有を避ける。
3.家側でできる停電対策:最小電力で“通話をつなぐ”
3-1.最小構成の電源確保(持続時間の算出)
- 公式:持続時間(h)= 電源容量(Wh) × 0.8 ÷ 合計W(0.8は変換ロスの目安)。
例:光回線の一式(家庭)
| 機器 | 消費電力の目安 |
|---|---|
| ONU | 6W |
| ホームゲートウェイ | 8W |
| 通話親機(AC必要) | 3W |
| 合計 | 17W |
- 200Wh → 200×0.8÷17 ≒ 9.4時間
- 500Wh → 約23.5時間
- 1000Wh → 約47時間(2日弱)
必要容量を逆算する早見
| 目標運用時間 | 合計17Wの場合の必要Wh(目安) |
|---|---|
| 6時間 | 約130Wh |
| 12時間 | 約255Wh |
| 24時間 | 約510Wh |
| 48時間 | 約1020Wh |
迷ったら**「24時間×一式」**を基準に。家族構成と昼夜で見直す。
3-2.配線と置き場所の工夫
- ONU・HGW・親機を同じ棚に集約し、一括でUPSにつなぐ。
- ケーブルを短めに整理し、抜け止めタップで不意の抜けを防ぐ。
- 熱こもり防止(通風・埃対策)と掃除のしやすさを優先。
3-3.“停電に強い電話機”を1台用意
- アナログ線を契約中なら、電源不要のシンプル受話器を壁のモジュラーに直挿しで運用。
- コードレスしかない家庭は、親機が停電すると子機も不可。直結受話器を予備で備える。
- 光のみ契約の場合はUPS/ポータブル電源の整備が実質必須。
3-4.非常用の発電・給電の選び方(簡易)
| 電源 | 特徴 | 向き |
|---|---|---|
| 無停電電源装置(UPS) | 瞬断に強い・自動切替 | 短時間停電が多い地域 |
| ポータブル電源 | 大容量・屋内安全 | 長時間停電に備える家庭 |
| 車の給電 | シガー口や外部電源で補う | 駐車場が近い・ガソリン余裕 |
3-5.USB電源・小型照明との組み合わせ
- USB給電ランタンを壁に向けて照らせば少電力で広く明るい。
- 充電は昼間にまとめて行い、夜間は通信・照明のみに絞る。
4.非常時の通話運用:回線を“占有しない”知恵
4-1.発信先の優先順位と“短く・決め文句”
- 順位例:119/110/災害対策本部 → 家族代表 → 近隣支援。
- 定型文:「無事/けが/場所/次の連絡時刻」。30秒以内を目標に、同じ内容を繰り返さない。
4-2.代替連絡手段の併用
- 公衆電話(非常時は優先的に通じやすい)。
- 災害伝言ダイヤル・災害用伝言板を家族で訓練。
- 集合住宅は掲示板・回覧・掲示テンプレ、**小型無線機(特定小電力)**の活用も検討。
4-3.FAX・通報機器・見守り機器の注意
- FAX・火災報知連動通報・見守り装置は電源と回線の両方が必要。
- 停電時に停止する前提で、**代替(巡回・掲示・隣戸確認)**を準備。
4-4.短文テンプレ(そのまま使える)
- 家族へ:「こちら無事。住所○○。次は19時に同番号へ。—名前」
- 近隣へ:「○号室、けが無し。明朝8時に再確認します。」
5.点検・訓練・復旧:止めない仕組みを作る
5-1.停電前のチェックリスト(年2回)
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 回線の種類 | アナログ/光/ケーブルの別を把握 |
| 親機の電源 | 電源不要受話器を1台用意 |
| 配線図 | ONU・HGW・親機の位置と接続を図示(A4) |
| 電源 | UPS/ポータブル電源の容量・動作試験 |
| 連絡計画 | 家族代表・連絡時刻・短文テンプレ |
| 公衆電話 | 最寄り位置を紙地図に書き込み |
5-2.停電発生時の初動
1)家だけか地域全体かを確認(夜景・近隣に聞く)。
2)UPSの稼働と残容量を確認、持続時間を家族で共有。
3)30秒の短文連絡で状況共有、通話回数を減らす。
4)直結受話器がある場合は試験発信で状態確認。
5-3.復電後の復旧手順
- ONU→HGW→親機の順に電源を入れ直す(1台ずつ数分待つ)。
- ダイヤル音・発着信をテスト。
- 留守電・FAXの時刻、子機の再登録を確認。
5-4.よくあるトラブルと対処
| 症状 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 発信できない | ONU/HGWの固着 | 再起動・配線差し直し |
| 子機だけ通話不可 | 親機AC停止 | 親機の電源復帰・直結受話器で代替 |
| 雑音・断続 | 線路の劣化・接触不良 | モジュラー差し直し・親機交換で切り分け |
| 留守電が動かない | 時刻ずれ・設定消失 | 時刻合わせ・設定復元 |
5-5.訓練の流れ(所要15分×年2回)
1)ブレーカーOFF模擬→ONU/HGWの停止を確認。
2)UPSへ切替→通話可否を確認。
3)短文連絡テンプレで家族代表へ発信。
4)復電手順(ONU→HGW→親機)を実演し、手順書に追記。
6.運用設計の実例:24時間つなぐ“ミニ計画”
6-1.家庭(光回線・3人家族)の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標 | 24時間固定番号を維持 |
| 機器 | ONU 6W/HGW 8W/親機 3W(合計17W) |
| 電源 | ポータブル電源 600Wh(余裕を見て) |
| 配置 | 一つの棚に集約、UPS→電源→機器の順 |
| 連絡 | 12:00/19:00の定刻短文、公衆電話の位置共有 |
6-2.集合住宅(管理室・掲示)の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 回線 | 管理室の回線は種別を掲示(アナログ/光) |
| 電源 | UPS対象に管理用回線・放送・監視を含める |
| 掲示 | 「通話は30秒/定刻/医療優先」の掲示を作成 |
| 鍵 | MDF室・機械室の鍵管理と立会い手順を文書化 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.電話機に電池が入っているが、停電でも使える?
A. それは親機の機能用で、回線装置の電源とは別です。アナログ回線+電源不要受話器でなければ通話できません。
Q2.光回線で停電中、携帯の“テザリング”でIP電話は?
A. ルーターが動き、IP電話アプリが使えれば可能ですが、回線混雑・電池消耗の面で長時間運用には不向きです。
Q3.集合住宅の管理室にある電話は強い?
A. アナログ直通なら強い場合がありますが、PBXや光収容だと機器電源が必須。掲示で種類を明示しましょう。
Q4.ひかり電話のためにUPSを入れる価値は?
A. 短〜中時間の停電で固定番号を維持できる利点があります。医療・見守りの連絡先を固定にしている家庭は有効です。
Q5.公衆電話はいつでも動く?
A. 優先的に復旧・接続されやすいですが、設備障害・浸水・断線で使えないことも。最寄り位置を紙地図に記入を。
Q6.災害時、通話はどれくらいに抑えるべき?
A. 目安は30秒以内。無事/場所/次連絡時刻の3点で十分です。
Q7.コードレス子機だけ残したい。方法は?
A. 親機が動かないと子機は不可。親機+子機+UPSでまとめて給電するか、直結受話器を別に用意。
Q8.FAXは停電時に送受信できる?
A. ほとんどのFAXはAC必須。アナログ線で電源不要の受話器があれば音声通話は可能ですが、FAX機能は使えません。
Q9.IP電話の番号だけは維持したい。
A. UPS+ポータブル電源でONU/HGWへ給電すれば維持可能。長期停電では発電・車給電も選択肢。
Q10.高齢の親に最小の備えを一つだけ勧めるなら?
A. アナログ回線+電源不要受話器の常備。無ければ公衆電話の位置を紙に、短文連絡の練習を。
用語辞典(やさしい言い換え)
線路給電:電話局側から電話線に電気を流すこと。
ONU:光回線の終端装置。光を電気の信号に変える箱。
ホームゲートウェイ(HGW):通話や通信をまとめる箱。
ケーブルモデム:同軸ケーブルの通話・通信の変換器。
PBX:建物内の小さな電話交換機。
UPS(無停電電源装置):停電でも短時間は電気を出せる装置。
災害伝言ダイヤル:災害時に音声で安否を残す・聞く仕組み。
MDF室:集合住宅の回線の分岐室。
まとめ:回線の“型”と“電源”で決まる
停電時の固定電話は、回線の型(アナログか、光/ケーブルか)と宅内・局側の電源で可否が決まります。アナログ+電源不要受話器は強く、光・ケーブルはUPS等で電源を付けて守る。
連絡は短く・定刻・優先順位で。今日、自宅の回線方式と配線図を紙に描き、非常時の給電手順を棚に貼っておきましょう。必要容量は合計Wから逆算、24時間運用を基準に用意すれば安心です。