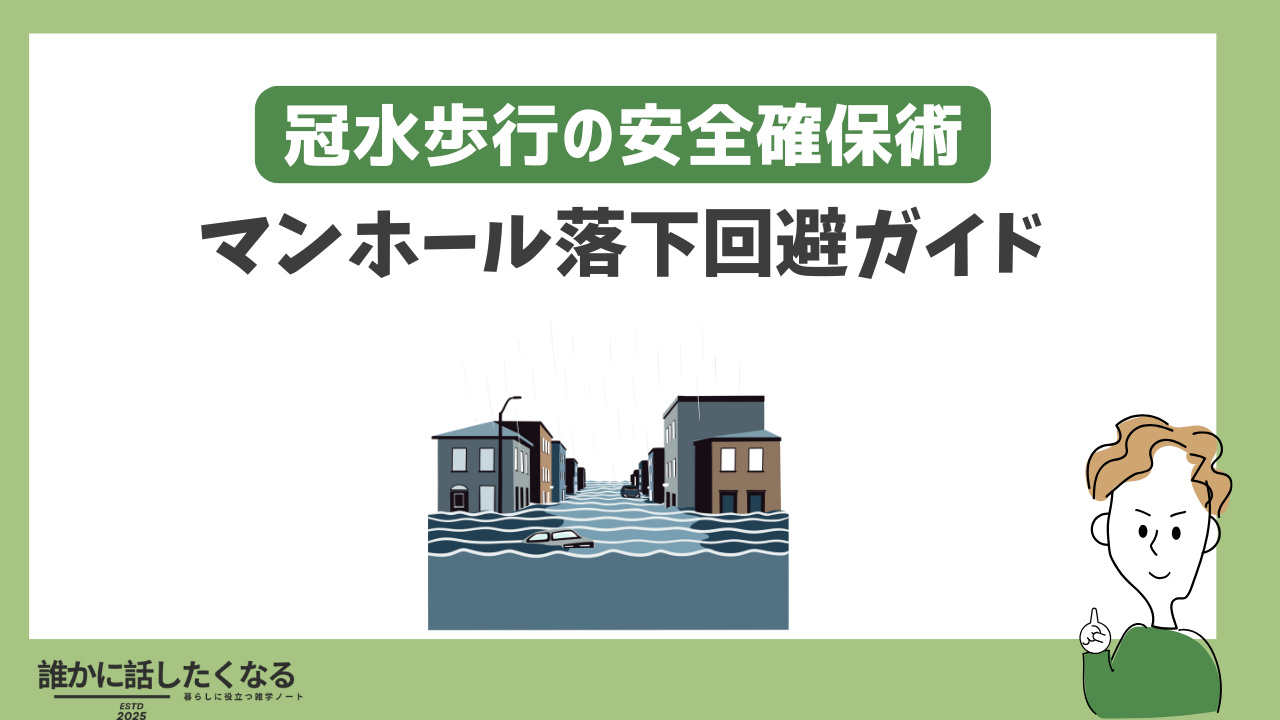増水や内水氾濫の現場では、見えている水だけが敵ではありません。ふたが外れたマンホールや外れてずれた側溝の格子、浮き上がった舗装、逆流する排水口など、**足元の“見えない穴”と横からの“見えない流れ”**が命取りになります。
本稿は、少人数から家族連れ、職場の帰宅隊列までを想定し、装備→地形の読み方→歩行フォーム→隊列→救助・衛生の順で、現場でそのまま使える運用に落とし込みました。表とチェックリストを添え、夜間・強風・泥濘・低体温のリスクにも対応します。また、撤退基準・連絡テンプレ・帰宅後の衛生まで網羅し、判断に迷わない“実行用マニュアル”としてまとめました。
1.冠水下の歩行“基本原則”と必須装備
1-1.三禁の原則(走らない・踏み込まない・逆らわない)
冠水路では走ることで水圧と滑りが増し、視界の情報処理も粗くなります。見えない段差や穴へ勢いよく踏み込むと落下や捻挫を誘発し、濁流に逆らう進路取りは転倒と流出を招きます。走らず、見えない場所へ深く踏み込まず、腰から下を押す横流れには逆らわない。これが三禁の原則です。
1-2.最低限の装備(家にあるもので整える)
長靴は流れを受けると脱げやすく、水が入ると重くなります。運動靴に厚手靴下が基本で、足首をテーピングで固定すると捻挫予防に役立ちます。上半身は雨具上下の分離型で風をはらみにくくし、両手が空くヘッドライトと軍手または作業用手袋を備えます。先端に反射テープを巻いた**棒(120〜150cm)**を一本持てば、水深や段差、穴の有無を前方で探れます。笛は緊急合図用に首から下げ、携帯用カイロは低体温対策に有効です。
1-3.出発前30秒の自己点検
靴ひもやベルト、リュックの胸・腰ベルト、ライトの電池、スマホの防水袋、笛の位置、身分証と連絡先メモの携行を確認します。濡れても困らない小銭と千円札を防水袋に入れて胸ポケットへ。荷重は背中の高い位置へ寄せ、両手と膝が自由に動く姿勢を確保します。雨具の裾は膝が上がる長さに調整し、足裁きを邪魔させないことが転倒防止の第一歩です。
1-4.ルート選定と“撤退基準”を先に決める
徒歩開始前に高所の退避先(立体駐車場・高台・堅固な建物の2階以上)を地図で決め、到達時刻の目安を設定します。水深がすね超え・流速が足首を押す力に達したら撤退、視界が10m未満になったら待機など、事前に基準を言語化しておくと現場で迷いません。
1-5.装備の最小・推奨・代用品
| 区分 | 最小セット | 推奨セット | 代用品の例 |
|---|---|---|---|
| 足元 | 運動靴+厚手靴下 | 運動靴+ネオプレン靴下 | ごみ袋で足首二重巻き |
| 手 | 軍手 | すべり止め手袋 | 皿洗い用ゴム手袋 |
| 照明 | 小型ライト | ヘッドライト+予備電池 | 自転車ライトを帽子に固定 |
| 探り棒 | 竹・アルミ棒 | 伸縮ポール+反射テープ | ほうき・スキー用ストック |
| 合図 | 笛 | 笛+反射タスキ | ペットボトルを叩いて合図 |
水深・流速別の危険度早見表
| 条件 | 人の体感 | 代表リスク | 判断・行動 |
|---|---|---|---|
| くるぶし未満(〜10cm) | 冷え・砂利で不安定 | 小さな段差・排水口の吸い込み | 棒で前方確認、歩幅を半分に |
| すね(10〜20cm) | 押し流され始める | 側溝蓋のずれ・冠水マンホール | 隊列で進む。片足三点支持 |
| 膝(20〜40cm) | 強い水圧で足が浮く | 横流れ・見えない穴 | 退避を優先。無理な横断は中止 |
| 太もも以上(40cm〜) | 歩行困難 | 転倒・流出 | 徒歩移動をやめて高所で待避 |
2.地形とインフラの“危ない場所”を読む
2-1.マンホール・側溝・集水桝の見分け方
冠水時はふたの縁にできる白い泡の円や水の回転、わずかな沈みで位置を推測します。側溝の格子は流木や泥で持ち上がりやすく、縁の線が波打って見える場所は極力避けます。棒で前方を左右に扇形に探り、かすかな落ち込みや空を切る感触に気づいたら進路を変えます。
2-2.交差点・カーブ・坂の下は横流れに注意
交差点は四方から水が集まり、マンホールや桝が多く配置されています。坂の下や地形のくぼみは横からの押し流しが強く、足がすくわれます。建物の壁沿いを選ぶと流れが弱まりやすい一方、はね返りで渦が立つ場所も生じるため、足元を棒で確認しながら壁から半歩離れたラインを保ちます。
2-3.商業地・住宅地・河川近傍での違い
商業地は地下設備の出入口が多く、地下室や駐車場への吸い込みが発生しやすい区域です。住宅地は宅地の乗り入れ口に段差や溝が隠れ、河川近傍は堤外地のわずかな下りで流速が増します。地域の浸水想定図で低地の帯を把握し、通り抜けよりも短い距離で高所へ逃げる進路取りが安全です。
2-4.視界不良(夜間・濁水・豪雨)での判断
光の反射が均一に見える水面は深さ変化が大きいことがあります。ヘッドライトは広角+手元を同時に照らす設定にし、棒が硬さの違いを返す場所(舗装→芝→土)では歩幅をさらに短く。雷鳴が3秒以内に聞こえる距離なら高所で一時待機へ切替。
2-5.橋・高架・地下へのアプローチ
橋のたもとは渦と横流れが強く、欄干付近には吸い寄せが生じます。橋の下の通路や地下出入口は短時間で水位が上がるため、近づかないが鉄則。やむを得ず橋を渡る場合も路肩を避け中央寄りを選び、欄干や金属柵をつかんだまま歩かない(雷と感電の回避)。
危ない場所の特徴と回避のコツ(現地メモ)
| 場所 | 兆候 | 何が危険か | 回避策 |
|---|---|---|---|
| マンホール | 泡の円・渦・沈み | ふた外れ・落下 | 扇形に探って大きく迂回 |
| 側溝格子 | たわみ・浮き | 片足落下・転倒 | 壁から半歩離れ、棒で縁確認 |
| 坂の底 | 横流れが強い | 体が流される | 斜め上へ逃げ高所で待機 |
| 地下入口 | 吸い込み音 | 吸い込まれる | 近づかず反対側へ移動 |
| 橋のたもと | 渦巻き・巻き返し | 横流れ・吸着 | 中央寄りで短時間通過 |
3.安全な歩き方と隊列:一列・三点・声掛け
3-1.一歩の作り方(三点支持と短い歩幅)
足を前へ置く前に棒でその地点を一度突き、硬さと深さを確かめます。足裏全体を静かに置き、かかとから親指へ重心を移すことで滑りを減らし、もう片方の足が離れるまで棒と脚の三点支持を保ちます。歩幅は普段の半分、ピッチは一定にします。上半身はやや前傾で、膝は柔らかく保つと突発の流れに耐えやすくなります。
3-2.隊列の組み方(先導・中核・しんがり)
先導は棒とライトを持ち、中核は子どもや体力の弱い人を両側から支え、しんがりは後方の車や自転車に注意を払いながら進みます。狭い歩道は一列、広い車道は二人一組の縦二列で、互いの肘やリュックのストラップを軽く持つと安定します。声掛けの約束(止まる・戻る・右・左・危険)が共通言語です。笛は3回が緊急と統一します。
3-3.夜間・強風・雷の追加対策
夜間はヘッドライトに拡散カバーを付けて手元と足元の陰を減らし、反射材を胸・腕・足に付けます。強風時は横風に対して体を半身にし、風上の足を先に置くと安定します。雷が近い場合は電柱や樹木から離れ、金属柵に触れない。水面での携帯電話の通話は短時間にとどめます。
3-4.渡渉(どうしても横断が必要なとき)
一人ずつ、斜め下流へ進むと水の力を逃がせます。胸より高い荷物は先導が受け取り、両手を自由に。流れが速い・膝以上の深さ・渦が見えるのいずれかがあれば中止。ロープを体に固定しての渡渉は原則禁止(引きずられる危険)。
3-5.休憩・低体温・熱疲労の管理
休憩は風の当たらない建物の陰で3〜5分。水分と甘味を少量ずつ摂り、靴と靴下の水を絞るだけでも体感が大きく変わります。歯のガチガチ・手の震え・返事が遅いは低体温の初期サイン。アルミ保温シート+カイロで体幹を温め、無理をやめる判断を。
隊列・合図・役割の早見表
| 位置 | 役割 | 装備 | 合図 |
|---|---|---|---|
| 先導 | 棒で探る・進路決定 | ヘッドライト、笛、棒 | 笛1回=停止 |
| 中核 | 体力が弱い人のサポート | リュック、予備ライト | 笛2回=集合 |
| しんがり | 後方警戒・離脱合図 | ライト、反射ベスト | 笛3回=緊急 |
4.子ども・高齢者・妊婦・ペットの配慮
4-1.子どもを守る動線と合言葉
子どもは水に近づきたがるため、大人と同じ数で動くという合言葉を徹底します。背負いひもは親の前が見えにくくなるため、可能なら手をつないで歩くか抱える位置を高くします。服は体温を奪いにくい長袖長ズボンで、予備の靴下をビニールに入れて持たせます。
4-2.高齢者・妊婦の歩き方
高齢者には杖先用の滑り止めを付け、歩幅をさらに狭めて三点支持を長く保ちます。妊婦は腹帯で体幹を安定させ、横風に身体を預けないよう半身で進みます。いずれも疲労が急に出るため100mごとに立ち止まり、膝の突っ張りやふくらはぎの冷えを確認します。
4-3.ペットの安全
ペットは短いリードと胴輪で抱え上げやすい姿勢を作り、足裏の冷えや傷を防ぐため靴の代わりに靴下型カバーを使用します。濁水は飲ませず、口周りを拭くタオルを別に用意し、迷子札と最近の写真を携行します。
4-4.補助具の工夫(杖・ベビーカー・車いす)
杖は四点タイプの先ゴムで安定性が上がります。ベビーカーは車輪が細いほど埋まりやすいため、抱えて移動を基本に。車いすは前輪を浮かせる姿勢を作り、二人以上で支えながら短距離で高所へ。
4-5.同行が難しい場合の待避と所在共有
どうしても同行できない場合、高い階・屋根に近い場所へ移動し、窓からの目印(布・ライト)と連絡先メモを外へ掲示。位置情報の共有と連絡の時刻を紙に残すことで救助に結びつきやすくなります。
体力別・支援の目安
| 対象 | 歩幅 | 休憩目安 | 追加装備 |
|---|---|---|---|
| 子ども | 1/3〜1/2 | 50〜100m | 予備靴下、甘味、笛 |
| 高齢者 | 1/3 | 50m | 杖滑り止め、ひざ掛け |
| 妊婦 | 1/2 | 100m | 腹帯、飲料 |
| ペット | 抱き上げ中心 | 随時 | 胴輪、タオル |
5.もしもの時の対処と帰宅後の衛生
5-1.落下・転倒・吸い込みの初期対応
マンホールや側溝へ片足が落ちた場合、無理に引き抜かずまず体を水の流れに合わせて倒し、足を縦に回して抜きます。流れに巻き込まれた人を助けるときは、必ず棒やベルト、ロープを介し、人が人をつかみに行かないのが鉄則です。救急要請時は場所・人数・状態を短く伝えます。
5-2.低体温とけがの手当て
濡れた衣服はすぐに脱がせ、乾いた衣服→アルミ保温シート→雨具の順に重ねます。出血は清潔な布で圧迫し、泥が付いた創部は清水で軽く流すだけに留め、消毒は帰宅後に行います。頭部打撲・胸の痛み・息苦しさがあれば迷わず受診を。
5-3.帰宅後の衛生・消毒
足と手を石けんで十分に洗い、爪の間と足指の間の泥を落とします。小さな擦過傷は流水→石けん→清潔な布→消毒の順で処置し、破傷風ワクチンの履歴に不安があれば医療機関に相談します。衣類は泥を外で払い落としてから洗濯し、靴は中敷きを外して風通しの良い場所で乾かします。
5-4.通報・連絡テンプレ(口頭で一息)
- 場所:○○市○○区○○通り、交差点から北へ50m。
- 状況:大人3人、子ども1人。1人が片足落下、歩行可。水深はすね、横流れあり。
- 必要:救急車不要、高所への案内と警戒を希望。
5-5.靴・衣類・携行品の乾燥と再使用
靴は新聞紙を詰めて30分ごとに交換。インソールと靴ひもを外して別乾燥。ライトは電池を抜いて接点を拭く。笛や反射材は泥を落として乾燥、次回に備えて定位置へ戻す。
応急・衛生の手順表
| 状況 | 最初の行動 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 片足落下 | 体を流れに合わせて倒す | 足を縦に回して抜く |
| 全身転倒 | 頭部打撲有無を確認 | 体温保持、休ませる |
| 出血 | 清潔布で圧迫 | 医療機関へ |
| 帰宅後 | 手足の洗浄 | 小傷の消毒・衣類乾燥 |
Q&A(よくある疑問)
Q1. 長靴と運動靴、どちらが安全?
長靴は水が入ると脱げやすく重くなります。冠水下の歩行は運動靴+厚手靴下が基本で、靴の口からの浸水を最小限にできます。
Q2. 棒がないときはどうする?
ほうき、スキー用ストック、折りたたみ傘などまっすぐで強度がある物で代用できます。先端に反射テープや白い布を巻くと視認性が上がります。
Q3. どうしても横断が必要な道路がある。
水の最も浅い場所を斜めに選び、三点支持で一人ずつ渡ります。腰まで水がある、流速が強い、渦が見える場合は中止して高所で待機します。
Q4. 片側だけ深い場所の見分け方は?
水面の色が急に暗く見える場所や泡が集まる溝は急深の兆候です。棒が空を切る感触があれば迂回してください。
Q5. 子どもが怖がって進めない。
数十メートルごとに目標を設定し、合言葉と小休止を重ねます。抱える際は胸より高く持ち、足元は先導者が確認します。
Q6. 自転車で進むのはあり?
不可。 視界と制動が奪われ、側溝や穴に前輪が落ちる危険が高い。押して歩くか、高所で待機を。
Q7. 胸まで水が来たら泳げばいい?
やめましょう。 目に見えない障害物や鉄柵で負傷の恐れ。建物・高所へ退避が最善です。
Q8. 低い車で送迎してもらうのは?
危険。 吸気・排気が水をかぶり停止します。高所で待機→徒歩で短距離退避が原則。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 内水氾濫:雨が多すぎて町の中の排水が間に合わず、道や敷地が水びたしになること。
- 三点支持:棒と両足、または手と足で常に3点が地面に触れている状態で支える歩き方。
- しんがり:列のいちばん後ろで全員の安全を見守る役割。
- 吸い込み:地下や側溝に向かって水が流れ込む勢い。近づくと足を取られる。
- 斜め横断:横断よりも上流から下流へ斜めに進んで水の力を流す渡り方。
- 巻き返し:壁や段差に当たって水が戻る流れ。足元をすくう原因。
まとめ:見えない穴と横流れを“言語化”して避ける
冠水下の事故は、目に見えない穴と腰から下を押す横流れで起こります。棒で前を探り、歩幅を半分にし、一列隊形と声掛けで進むだけで、落下・転倒・流出の確率は大きく下がります。
子どもや高齢者、妊婦、ペットには距離の短い高所ルートを選び、無理な横断は中止。帰宅後は洗浄・保温・消毒を徹底し、次に備える準備を静かに整えましょう。