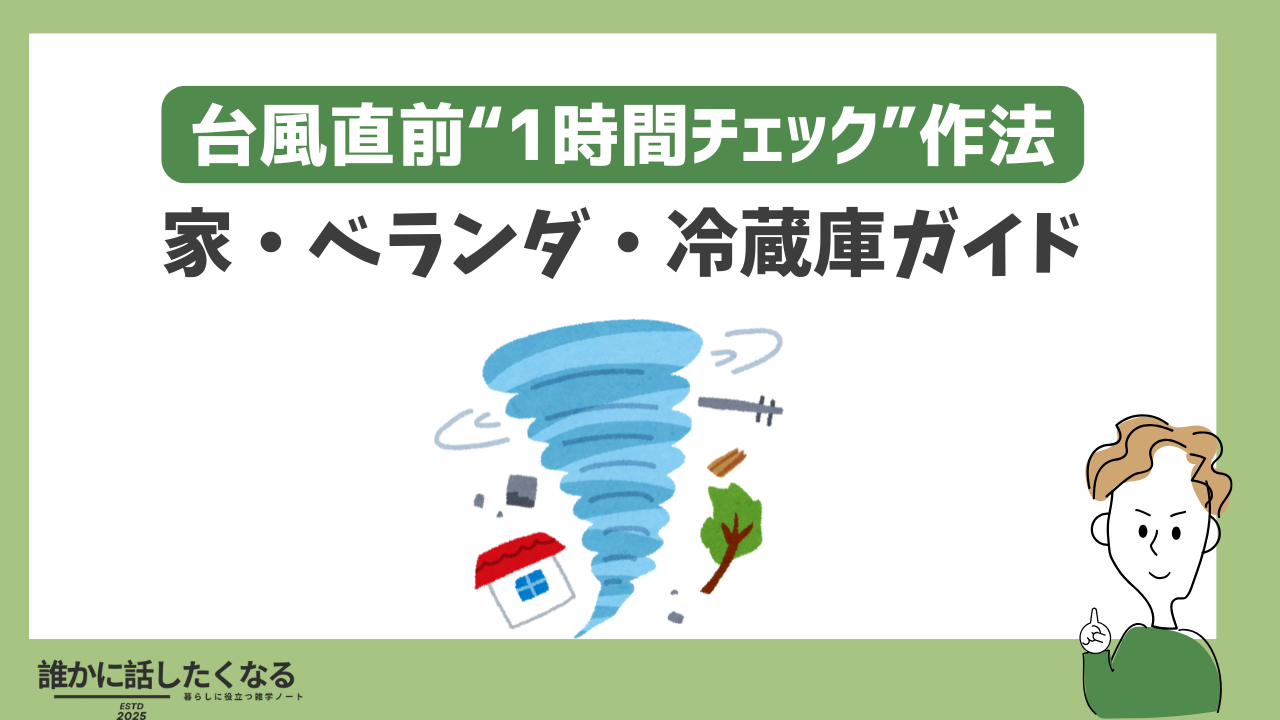台風接近の最後の1時間は、家の被害を最小にし、停電と断水に備える最終確認の黄金タイムだ。やることは多そうに見えても、順番と型があれば迷わない。
本稿は、玄関→窓→ベランダ→冷蔵庫→停電まわりの5ブロックを5分単位の動線に落とし、役割分担表・チェック表・配置表・Q&A・用語辞典まで揃えた。家族で読み合わせれば、そのまま実行台本になる。
先に決める三本柱:外回りは飛ぶ物をなくす/窓は割らせない・人を離す/冷蔵庫は中身を守る。そして停電しても生活を回す導線を確保する。
1.玄関・外回りの最短整頓|5分で終える飛散ゼロ化
1-1.置き物と掲示の撤収
- 傘立て・表札飾り・置物・宅配ボックスの上物は室内へ退避。新聞受けのチラシ束も回収。
- 自転車は横倒しでフレーム2か所をフェンスに結束。サドルカバー・前かごの布物は外して室内へ。
- プロパンボンベ・物置の扉は鎖またはベルトで固定。転倒の恐れがあるゴミ箱は空にして屋内へ。
1-2.ドア・ポストの雨対策
- ポストの投函口に簡易防水テープを上向き気味に貼る(下向きだと水だまりになりやすい)。
- 玄関ドア下のすき間テープを内側に追加し、水はねの浸入を軽減。敷きマットは屋内側へ退避。
- 表札灯・インターホンの直下に滴受け(布切れやキッチンペーパー)を設置して浸水跡を見える化。
1-3.排水の一手
- 玄関前・駐車スペースの排水口・側溝の落ち葉を手ばさみでかき出す。5分であふれ率は大きく下がる。
- マンホールの段差上の泥をほうきで脇へ。水の道を作るのが目的。
- 雨量が増える前に砂袋・段ボールで一時止水。排水をふさがない配置に。
1-4.外回り“飛ぶ物ゼロ”リスト(チェック用)
| 物品 | 場所 | 対応 | 済 |
|---|---|---|---|
| 傘立て/傘 | 玄関前 | 室内へ | □ |
| 表札飾り・置物 | 玄関前 | 室内へ | □ |
| 宅配ボックス上物 | 玄関前 | 室内へ | □ |
| 自転車 | 駐輪場 | 横倒し+2点結束 | □ |
| ゴミ袋・段ボール | 収集所 | 屋内/ベランダ内へ | □ |
| プロパンボンベ | 戸外 | 鎖/ベルト固定 | □ |
| ゴミ箱・コンテナ | 戸外 | 空にして屋内 | □ |
2.窓・雨戸・カーテンの守り方|割らせない三段構え
2-1.窓ガラスの一次防御(外側の風対策)
- 雨戸/シャッターは全閉、鍵まで確実に。ない窓は厚手カーテン+飛散防止フィルム。
- 窓枠の水抜き穴を爪楊枝で確認し、詰まりを除去。ここが詰まると室内側へ逆流する。
- 網戸は室内側へ寄せてロック。外れやすいタイプは外して室内保管。
2-2.室内側の二次防御(割れてもけがをしない)
- 養生テープは米印ではなく縁取りが基本。ガラス端の応力集中を抑える。
- ローテーブル・ベッド・ベビー布団は窓から30cm以上離す。寝床の頭は窓と反対へ。
- 子ども・ペットが触れる窓には、厚手カーテン+古毛布を内側から洗濯ばさみで仮固定。
2-3.窓際の三次防御(漏水の道を作らない)
- サッシレールにタオル2枚重ね、洗面器を水たまり位置にセット。ビニール手袋・雑巾を近くに置く。
- カーテン下端が水を吸い上げないようクリップで持ち上げ、床との間に空間を作る。
- 延長コード・タップは窓際から離し、床から高い位置へ退避。
2-4.窓まわりの優先順位表
| 状態 | やること | 目安時間 |
|---|---|---|
| 雨戸あり | 全閉+施錠 | 2分/窓 |
| 雨戸なし | カーテン厚手+縁取りテープ | 3分/窓 |
| 漏水あり | タオル堤防+洗面器 | 2分/窓 |
迷ったら人を窓から離す。物よりけが防止を優先。
3.ベランダ・排水の通り道|詰まりを取るだけで勝てる
3-1.飛散源の撤去
- 植木鉢は室内へ。重い鉢は受け皿を外し、紐で手すりに固定して低く置く。受け皿は風受けになるので外す。
- 物干し竿は外して床へ。可能なら室内干しに切替。ピンチハンガーも室内へ。
- すだれ・簡易目隠しは固定具を増し締め。外れる恐れがあれば一旦室内へ。
3-2.排水口のクリアリング
- ベランダ排水口の落ち葉・砂を片手ですくえるだけ取り除く。網目のゴミも忘れずに。
- 排水の出口側(共用管の目視できる穴)も確認。詰まりが強い場合は割りばしでほぐす。
- エアコンの室外機は吸排気を塞がない位置に。前面と背面20cmを確保し、ブロックで仮押さえ。
3-3.風の通り道を意識する
- 仕切り板(共用部とのパーテーション)は破損時の避難路。物を立てかけない。
- 隣室側へ風が抜ける線を想定し、軽い物はその線から外す。
- ベランダ内の高い物→低い物の順に処理すると時間短縮。
3-4.ベランダ“2分整備”表
| 作業 | 道具 | 時間 |
|---|---|---|
| 鉢の室内退避/固定 | 軍手・紐 | 2分 |
| 物干し竿の床置き | なし | 1分 |
| 排水口のゴミ取り | ちりとり | 2分 |
| 室外機の確保 | なし(ブロック等) | 1分 |
4.冷蔵庫・冷凍庫の“停電耐久”設定|中身を守る手順
4-1.温度・中身の下ごしらえ
- 冷蔵/冷凍を最強(強め)に設定。ドア開閉は最少に。メモを貼りむやみに開けない宣言。
- 凍らせた保冷剤・ペットボトルをすき間に詰め、冷気の塊を作る。ペットボトルは7〜8分目で凍らせると膨張余地ができる。
- 消費順ラベルを容器に貼る(今日→明日→明後日)。
4-2.停電時の優先消費
- 常温→冷蔵→冷凍の順に食べ切る。
- 卵・牛乳・惣菜は先に。冷凍は扉を開けないほど持つ。
- ガスや固形燃料で調理する場合は短時間で火が通る献立(麺、雑炊、薄切り肉)を優先。
4-3.氷と水の確保
- 製氷皿・ペットボトルで氷を満杯に。保冷バッグに数本はあらかじめ移動。
- 電源復旧後も異臭/ぬるさがあれば廃棄判断を優先。疑わしいものは口にしない。
- 冷凍庫は空間を減らすほど保ちやすい。新聞紙で隙間を埋めるのも手。
4-4.“停電耐久”の目安
| 状態 | 冷蔵 | 冷凍 |
|---|---|---|
| ドア開閉ほぼなし | 6〜8時間 | 24〜36時間 |
| 開閉が多い | 2〜4時間 | 12〜18時間 |
目安。庫内充填率・断熱性能で変動。開けない勇気が一番の延命策。
5.最後の10分:停電・避難の備え|人を守る段取り
5-1.灯り・通信・ラジオ
- 懐中電灯は1人1本、足元用は玄関に置き点検。頭に付けるライトがあると作業がはかどる。
- モバイル電源と充電ケーブルをマグネットつきトレーにまとめ、居間の定位置へ。
- 手回し/電池ラジオの周波数をNHK/地域局に合わせ、音量は最小から。
5-2.安全導線の確保
- スリッパ・長靴を玄関に並べる。夜間の破片対策として厚底を手前に。
- 避難バッグは肩に掛けるところまで準備。雨具・飲料・常用薬は外ポケットへ。
- ブレーカー位置を家族で共有。停電復帰時に家電が一斉起動しないよう、個別スイッチを一段下げておく。
5-3.安否と近所
- 家族の集合場所(建物の陰・高台・公園の高所)を地図で再確認。
- 近所の高齢者・子どもへ声かけ——ドア1回ノックの習慣で無理なく。
- 非常時連絡カード(氏名・電話・血液型・持病)を財布と玄関に常備。
5-4.“最後の10分”行動表
| 時刻 | 行動 | 確認 |
|---|---|---|
| −10分 | 灯り・通信の最終点検 | 予備電池・ケーブル |
| −7分 | 玄関の靴・スリッパ整列 | 長靴の位置 |
| −5分 | 避難バッグ肩掛け | 飲料・薬・雨具 |
| −3分 | ブレーカー位置共有 | 懐中電灯の置き場 |
| −1分 | 施錠・窓カーテン確認 | 漏水タオル・洗面器 |
5-5.家族の役割分担(30秒で決める)
| 役割 | 担当 | 作業 |
|---|---|---|
| 大人A | 玄関・外回り | 飛散物撤収・排水確認 |
| 大人B | 窓・ベランダ | 雨戸・テープ・排水口 |
| 子ども/高齢者 | 屋内 | 懐中電灯・ラジオ・飲料準備 |
60分カウントダウン台本(5分刻み)
| 残り時間 | 動く人 | やること |
|---|---|---|
| 60〜55分 | 大人A | 玄関前の撤収・自転車固定 |
| 60〜55分 | 大人B | 雨戸全閉・網戸ロック |
| 55〜50分 | 大人A | 排水口・側溝の落ち葉取り |
| 55〜50分 | 大人B | 窓の縁取りテープ・家具移動 |
| 50〜45分 | 大人A | 植木鉢退避・物干し竿床置き |
| 50〜45分 | 大人B | ベランダ排水口クリア・室外機確保 |
| 45〜40分 | 大人A | 冷蔵庫設定強め・保冷剤配置 |
| 45〜40分 | 大人B | 冷凍庫の隙間埋め・消費順ラベル |
| 40〜30分 | 全員 | 懐中電灯点検・ラジオ周波数合わせ |
| 30〜20分 | 全員 | 飲料・薬を避難バッグへ |
| 20〜10分 | 全員 | 室内の延長コード退避・漏水対策配置 |
| 10〜0分 | 全員 | ブレーカー共有・施錠・最終見回り |
Q&A|よくある疑問を一気に解決
Q1.窓に米印テープは有効?
端の縁取りが基本。米印は割れ方を鋭くさせることがある。
Q2.ベランダの鉢は全部室内?
大物は受け皿を外し、低く固定すれば可。落下経路に置かない。
Q3.冷蔵庫の中身が心配。何を先に食べる?
卵・乳製品・惣菜→肉→冷凍の順。開けない時間が命を伸ばす。
Q4.室外機をカバーで包む?
吸排気を塞がないことが最優先。前後20cmの空間を確保。
Q5.停電時のブレーカーは?
復旧時に家電が一斉起動しないよう、個別ブレーカーを一段下げておき、順に上げる。
Q6.窓の内側に段ボールを貼るのは?
飛散防止と断熱には有効だが、漏水経路をふさがない貼り方で。下端は浮かせる。
Q7.停電が長引く時の食事は?
短時間で火が通る麺・雑炊・薄切り肉を優先。水分と塩分も確保。
Q8.断水の可能性はいつ見極める?
水圧の弱まりや濁りがサイン。浴槽に早めにためる。
Q9.車はどうする?
立体駐車場・高台へ。無理ならフロントを上向きに止める。冠水路は走らない。
Q10.ペットの対策は?
キャリー・ペットシーツ・飲水を玄関に。鳴き声対策に毛布も1枚。
用語辞典(やさしい言い換え)
飛散:風で物が飛んで当たること。
縁取りテープ:窓ガラスの周りを囲って貼るテープ。割れの広がりを抑える。
排水口:雨水を外へ流す穴。詰まると室内に逆流する。
停電耐久:電源が切れても冷えを保てる時間の目安。
仕切り板:ベランダの隣室との板。避難路になることがある。
一時止水:段ボールや砂袋で水の入り道を一時的にふさぐこと。
消費順ラベル:食べる順を記した紙。迷いを減らす工夫。
まとめ|順番・道具・10分の余白
台風直前の最後の1時間は、順番どおりに手を動かすだけで家の守りが整う。外回り→窓→ベランダ→冷蔵庫→停電の5ブロックを5分単位の型にしておけば、焦りは減り、最後の10分で人を守る段取りまで整えられる。今日のうちにチェック表を印刷し、玄関と冷蔵庫に貼る——それだけで明日への安心が変わる。