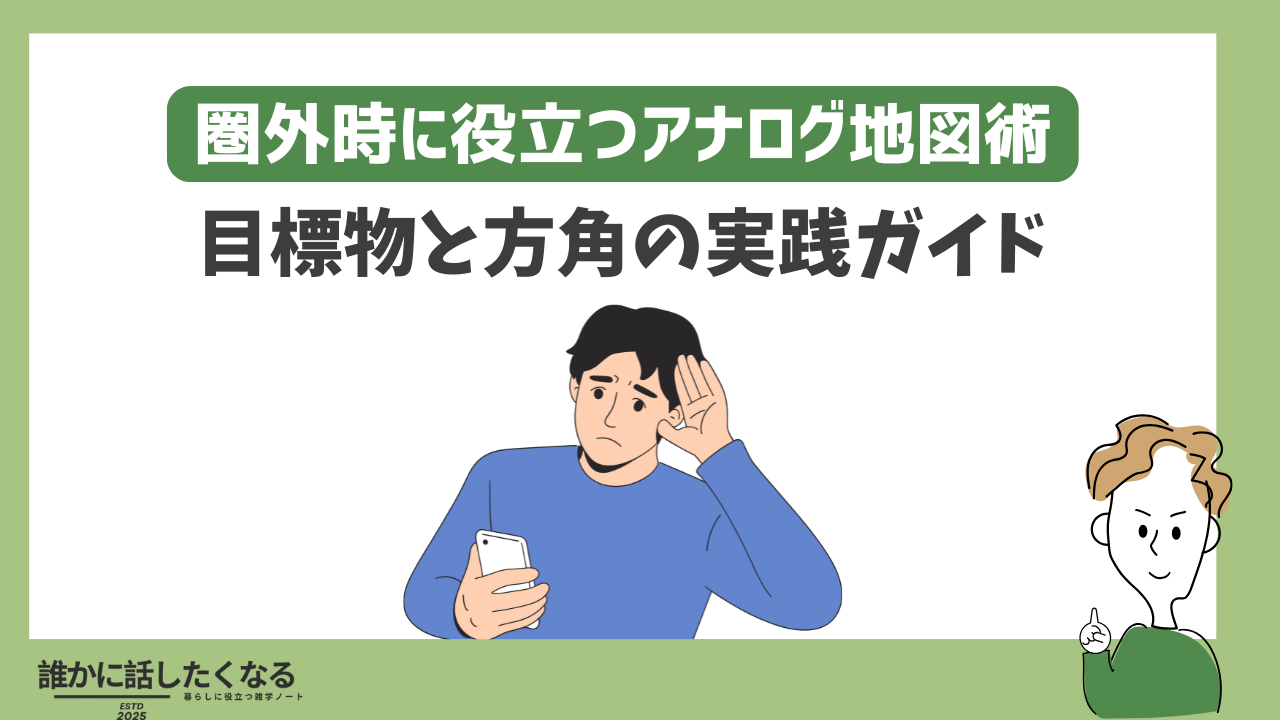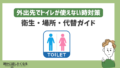電波が無くても、道は読める。 通信が途絶えた都市・里・山・海辺で、紙地図と身の回りの目印だけで現在地を確かめ、確実に前進するための実践ガイドです。
コンパスが無くてもできる方角の作り方、二つの目印で場所を絞る簡易三角測量、歩数と時間で距離を測る方法に加え、地図の折り方・防水・書き込み法、雨雪・夕暮れ・強風の補正までを網羅。現場でそのまま使える表・手順・短文テンプレを充実させました。印刷して携行すれば、“圏外”は“焦らず考える時間”へ変わります。
1.紙地図の読み解き:縮尺・等高線・目標物で現在地を絞る
1-1.縮尺と距離感(1cm=?m を体で覚える)
- 縮尺の式:1:25,000なら地図1cm=実距離250m、1:10,000なら1cm=100m。1:50,000は1cm=500m。
- 指の物差し:親指爪の幅=約1cm、手の幅=約8〜9cm(人差)。地図上の直線距離を指で素早く当てる癖を付ける。
- 歩行速度の目安:平地=分速80〜100m、登り=分速50〜70m、下り=分速80〜120m。荷物・天候で±20%変動。
- 暗算のコツ:25,000図は4cm=1km、10,000図は10cm=1kmと覚える。
1-2.等高線と地形(登らずとも読みで避ける)
- 線が詰む=急坂/崖、広い=なだらか。谷はU字が上流へ、尾根はV字が下流へ尖る。
- トラバース(斜め横断):等高線にほぼ平行に進むと登り下りを減らせる。崩落・雪庇・落石帯は回避。
- 人工地形:造成地・切土/盛土・堤防は等高線が直線的。段差や法面に注意。
1-3.目標物の三種(固定・線状・面)
- 固定物:神社・塔・給水塔・鉄塔・校舎・交番・煙突。遠方からも形で識別しやすい。
- 線状物:鉄道・川・幹線道路・送電線・堤防。横切る/沿うで迷いを減らす。
- 面の境界:公園・湖・広い駐車場・工場敷地。端をなぞると位置合わせが簡単。
縮尺・速度・地形 早見表
| 要素 | 目安 | 現地でのコツ |
|---|---|---|
| 縮尺1:25,000 | 1cm=250m | 親指爪で1cm測る |
| 平地速度 | 80〜100m/分 | 15分で1.2〜1.5km |
| 登り速度 | 50〜70m/分 | 休憩を細かく入れる |
| 等高線密集 | 急坂/崖 | 斜めトラバースで回避 |
| 送電線 | 高い鉄塔列 | 鉄塔番号が手掛かり |
持ち歩きの地図術(折り・防水・書き込み)
- 折り:目的地周辺が中央に来る観音折りで、北を上に出せる形に。片手で出し入れできるサイズへ。
- 防水:透明袋に入れ、袋の口を下向きに。消せるペンと油性ペンを併用(雨は油性が強い)。
- 書き込み:背骨の道・合流点・危険箇所を色を変えて記す。終わったら日付を書き足し次回に活かす。
2.コンパスなしで方角を作る:太陽・時計・地物の影
2-1.腕時計法(アナログ文字盤を使う)
- 北半球の日中:短針を太陽へ向け、短針と12の中間が南。デジタルは紙に円を描き短針を書いて代用。
- 注意:季節・緯度で誤差が生じるため**±15°程度の幅で扱う。サマータイムは1時間補正**。
- 応用:地図の上(北)を作った南北に合わせる→大通りや川の向きと矛盾が無いかを確認。
2-2.影と棒の方法(棒1本で東西を読む)
- 地面に棒を垂直に立て影の先端に石。10〜20分後に新しい先端へ石。最初→次の石が東向き。
- 東西線ができたら直角が南北。地図の北と合わせ、目標物の方向を読み取る。
- 弱点:平坦でない地面・濡れ地・強風は誤差が出る。石の位置を大きめに印し再測で補正。
2-3.都市の地物を方位として使う
- 大通りの走向(例:〇〇通りはおおむね東西)。街路樹の並びで風向や道の流れも読める。
- 河川の流向(上流→下流)。橋の銘板・河口方向の案内板に東西南北の手掛かりがある。
- 鉄道の方向(駅間の直線性)。駅の案内表示は方角を明記。高架の影は時間帯で向きが変わる点に注意。
方角作成のミニ手順表
| 手段 | 所要 | 精度 | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| 腕時計法 | 30秒 | 中 | 日中の大まか方位 |
| 影と棒 | 10〜20分 | 高 | 停滞時の基準作り |
| 地物の方向 | 即時 | 中 | 都市・里の補助 |
3.現在地の絞り込み:三角測量の簡易版と歩数カウント
3-1.簡易三角測量(「見える物×2」で場所を決める)
- 地図上で識別できる固定物を2つ選ぶ(例:給水塔と高層ビル、鉄塔と寺社の塔)。
- 現地でおおよその方角を取り、地図へ方向線を引く。2線の交点付近=現在地の候補。
- 誤差三角形ができたら、三角の中心を当面の現在地とし、**線状物(川・道路)**で確かめる。
3-2.歩数と時間で距離を測る(ペースカウント)
- 事前に100mの歩数を平地で測る(例:100m=120歩)。現地では心のカウンタで数える。
- 上り下り補正:登り**+10〜30%、下り−10〜20%**を目安。段差・雪・向かい風でさらに誤差増。
- 時間クロス:分速80〜100mの目安と時計で二重確認し、思い込みを潰す。
3-3.交差確認(線状物を使って正誤判定)
- 推定位置から川・線路・送電線がどの方向にどの距離か、地図と現地の見え方を照合。
- 一致が2つ以上で現在地確度が高い。合わなければ方向線を引き直し、歩数・時間を再計算。
位置絞り込み 早見表
| 手順 | 使うもの | できること | 失敗の芽 |
|---|---|---|---|
| 固定物×2 | ビル・塔 | 交点で現在地推定 | 似た建物の取り違え |
| ペースカウント | 自分の歩数 | 距離の裏付け | 上り下りで狂う |
| 線状物クロス | 川・線路 | 誤差の検出 | 立入不可で遠回り |
誤差の原因と対策
| 原因 | 典型例 | 対策 |
|---|---|---|
| 目印の誤認 | 似た塔・給水塔 | 番号・色・周囲の建物で再確認 |
| 方角の取り違え | 影が薄い・高架の影 | 腕時計法+地物で二重取り |
| 歩数の誤差 | 段差・群衆で乱れる | 時間クロス、休憩後に再カウント |
4.都市・里・山でのルート作成:安全と合流を崩さない
4-1.都市(明るい幹線・正面口・交番前)
- 明るい大通りを背骨にし、裏道の近道は捨てる。横断は信号交差点のみ、高架下は見通し優先。
- 合流点は駅の正面口→交番前→明るい店の前の順番で固定。同じ言葉で伝える。
- 短文テンプレ:「圏外。〇〇通りを北上、駅正面に向かう。返信不要。」
4-2.里(送電線・寺社・水路を“線”に)
- 送電線に沿うと高台から集落へ導かれる。鉄塔番号は地図の手掛かり。
- 寺社・学校は広い道が集まる結節点。行事掲示板で集落名を確認できることも。
- 水路は下りが下流。橋の間隔と曲がり角で位置を推定。
4-3.山(尾根と谷、等高線で“避ける”)
- 尾根道は迷いにくいが風、谷道は水と崩落。等高線の詰みやガレ場は回避。
- 鞍部・峠は風が抜け目印が少ない。方角線で抜ける方向を事前に確認。
- 海辺や河口近くでは堤防・砂州・導流堤が線状の目印。潮位で通行可否が変わる点に注意。
地域別 ルート設計表
| 地域 | 背骨 | 禁じ手 | 合流 |
|---|---|---|---|
| 都市 | 明るい幹線 | 裏道ショートカット | 駅正面→交番→店 |
| 里 | 送電線・寺社 | 田の畦の横断 | 神社前・学校前 |
| 山 | 尾根筋 | 等高線密集へ突入 | 鞍部・峠 |
| 海辺 | 堤防・遊歩道 | 砂州横断の無計画 | 漁港入口・避難階段 |
5.天候・時間帯・非常時の補正:判断を鈍らせない型
5-1.雨・雪・強風(視界・足元・体温)
- 白線・金属板は滑る。歩幅短く・足裏フラット。橋の上・日陰のタイルは要注意。
- 風下の壁を選び、体温は首・手首・腰で守る。濡れたら一枚脱いで拭く→重ね直す。
- 視程が落ちる日は線状物に沿う(川・堤防・幹線)。
5-2.夕暮れ・夜間(光と反射を増やす)
- 胸のライトは下向き、反射材は腕・足へ。黒服には白いタオルを外側へ。
- 星の北:北極星(北斗七星のひしゃく後端を5倍伸ばした先)。雲・街明かりで見えないこともあるため補助扱い。
- 夜間の歩数誤差を見越し、時間クロスを強めに使う。
5-3.体調・同行(止まる→寄る→知らせる)
- 不安を感じたら明るい店・交番へ寄る。戻る/走るより寄るが安全。
- 短文合流テンプレ:「正面口で合流、10分待つ。来なければ交番前。」
- 子ども・高齢者は段差回避・休憩刻みを徹底。合図は同じ言葉で繰り返す。
補正ポイント表
| 状況 | 重点 | 具体策 |
|---|---|---|
| 雨・雪 | 足元 | 白線回避・歩幅短く |
| 夕暮れ | 視認 | ライト下向き・反射二重 |
| 強風 | 体温 | 風下・壁沿い・橋上回避 |
| 不安 | 回避 | 明るい店/交番へ寄る |
Q&A(よくある疑問)
Q1.地図と景色が一致しない。どうする?
A. 線状物(川・鉄道・堤防)を探し交差角で合わせる。固定物×2の方向線で交点を作り直し、誤差三角形の中心を暫定位置に。
Q2.コンパスがない。方角は正確に出せる?
A. 腕時計法+地物の方向で実用十分。棒と影で東西線を作れれば精度は一段上がる。
Q3.山で迷ったら上へ?下へ?
A. 等高線の緩い方向(尾根側)を選ぶ。谷底は増水・崩落がある。尾根に乗ってから方角線で建て直す。
Q4.距離感がずれる。
A. ペースカウント(100m歩数)を事前に測り、時間×分速と二重確認。上り下り補正を忘れない。
Q5.夜間の北の見つけ方は?
A. 北極星(北斗七星のひしゃく端2星→5倍延長)を補助に。ただし雲・街明かりで見えない場合は地物方位+腕時計法へ切替。
Q6.紙地図は何を持つ?
A. 1:25,000の地形図と周辺拡大(1:10,000)。裏面に連絡先・合流順をメモし、透明袋で防水。
Q7.目印が少ない高原や造成地では?
A. 送電線・用水路・風車列など線状物を拾う。遠景の山並みを輪郭で照合するのも有効。
Q8.海辺での注意は?
A. 堤防・導流堤・避難階段を線状物・固定物として使う。潮位・高潮で通行可否が変わるため無理はしない。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 縮尺:地図の1cmが現地で何mかの比率。
- 等高線:同じ高さを結ぶ線。詰む=急、広い=緩。
- 固定物:遠くから見ても形が変わらない目印(塔・給水塔など)。
- 線状物:細長く続く目印(川・鉄道・幹線道路・送電線・堤防)。
- ペースカウント:一定距離の歩数を数えて距離を推定する方法。
- 簡易三角測量:二つの目標物の方向線の交点で現在地を絞るやり方。
- 誤差三角形:二本の方向線が完全に交わらずできる小さな三角。中心を暫定位置にする。
- 背骨の道:明るく広い幹線をつないだ迷いにくい徒歩道。
まとめ:目印×方角×距離の“三点合わせ”で迷いは減る
見える物(固定・線状・面)で手掛かりを作り、太陽や影で方角を決め、歩数と時間で距離を裏付ける。これだけで、圏外の不安は計画的な前進へ変わります。地図の北を自分の北に合わせる—この基本を軸に、背骨の道→合流点→安全確保の順で行動を組み立て、確かな一歩を重ねましょう。