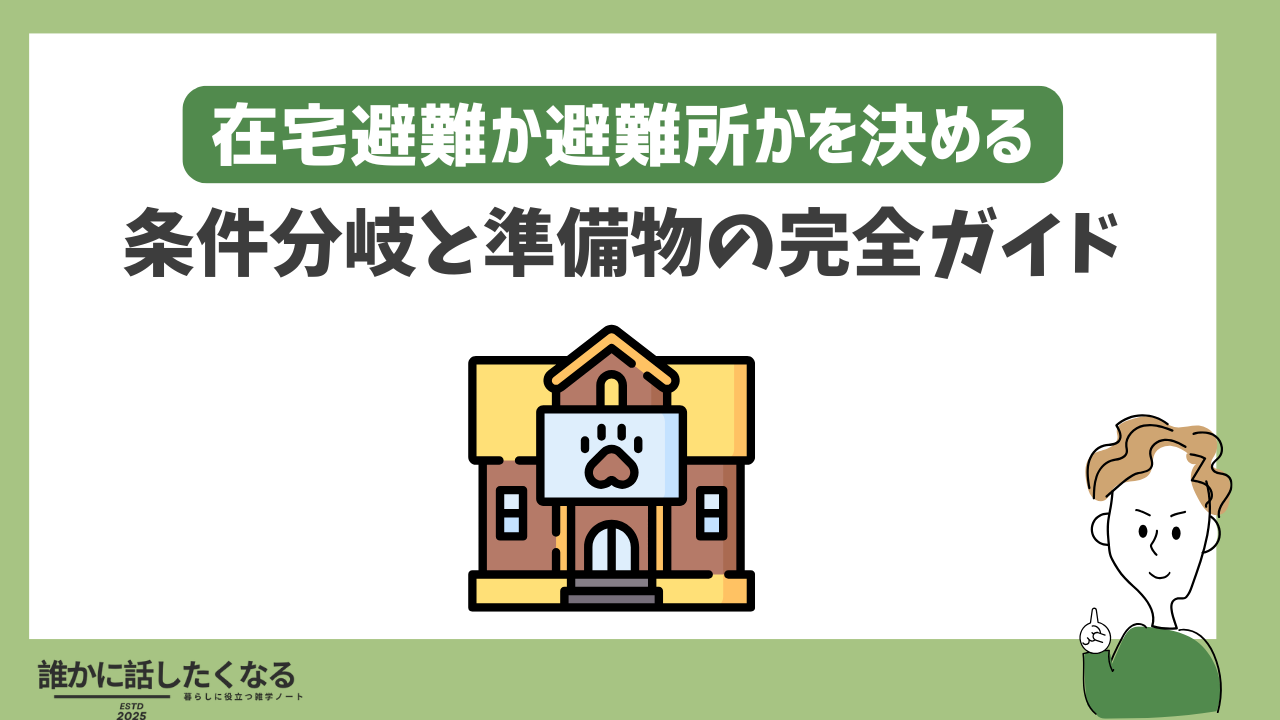大きな災害でまず問われるのは、「自宅にとどまる(在宅避難)」か「避難所へ行く」か。最善の選択は、災害種別・自宅の安全性・家族構成・季節・ライフラインの有無で変わります。本ガイドは、条件分岐で即判断できるフローと、どちらを選んでも困らない準備物を表とチェックリストで具体化。
高齢者・乳幼児・障害当事者・持病のある方・ペット同伴の観点も織り込み、実行手順をそのままコピペ運用できるようにしました。さらに、10分判断プロトコル、72時間タイムライン、集合住宅/戸建ての違い、車中泊の可否、夜間・雨天の移動基準まで踏み込み、迷いを削ぎ落とします。
1.まず決める:在宅か避難所かの条件分岐フロー
1-1.建物・立地の安全確認(最優先)
災害直後は命に関わる要素から切り分けます。外壁の大きなひび・傾き、屋根瓦やタイルの落下、室内の建具の開閉異常は構造の歪みのサインです。集合住宅では共用階段・外廊下の亀裂、エレベーター停止と非常用発電の有無を確認。浸水はくるぶし(10cm)で家電・床下、ひざ(30cm)で車・転倒、腰(60cm)で歩行困難の目安。斜面直下・河川沿い・海岸は、警戒情報に関わらず夜間は避難所寄りで判断します。
1-2.ライフラインと居住性の判定(在宅の可否)
電気・水・ガスのうち2系統以上が途絶し、なおかつ室温が極端(夏30℃超/冬10℃未満)なら避難所へ。1系統停止でも代替(蓄電池・給水袋・カセットコンロ)で72時間回せるなら在宅可。トイレが流れない/逆流は在宅不可の赤信号。集合住宅は受水槽・加圧ポンプ停止で高層階が断水しやすい点に留意。窓・出入口の施錠が保てない場合は防犯上の観点からも避難所を検討します。
1-3.家族要件と支援の有無(脆弱性の評価)
医療的ケア・透析・要介護など外部支援が止まると致命的な場合は早期に避難所/医療救護所。乳幼児・妊婦・発達特性・不安が強い家族は、静音・清潔・温度を保てるなら在宅優先が負担軽減。単身・遠方家族は合流場所と時間(例:公民館前11:00/17:00)を事前設定。ペットは受入可否と同室/別室の方針で選ぶ避難所が変わります。
条件分岐サマリー表(自宅掲示用)
| 観点 | 在宅でよい | 避難所へ | 追加メモ |
|---|---|---|---|
| 建物 | 主要構造に損傷なし/浸水なし | 傾き/大破/浸水継続/土砂・火災接近 | 夜間は無理をしない |
| 立地 | 浸水想定外/斜面から離れている | 氾濫危険・津波・急斜面直下 | 駐車場の冠水にも注意 |
| ライフライン | 1系統停止まで/代替あり | 2系統以上停止/トイレ不可 | 室温の維持可否を同時評価 |
| 家族 | ケア可能/支援あり | 医療・介護支援途絶/体調悪化 | 薬・機器の電源確保必須 |
| 情報 | 通信確保/地域支援あり | 情報遮断/孤立懸念 | ラジオ+紙連絡網を併用 |
誤判断あるある:情報が少ない早期に感情で決める/トイレ不可を軽視/夜間移動で足元の危険。→ 10分判断プロトコルに沿って落ち着いて判断。
10分判断プロトコル(印刷推奨)
- 3分:建物・外周を目視(傾き・落下・水位)。
- 3分:ライフライン確認(電・水・ガス・トイレ)。
- 2分:家族の体調・薬・電源依存の有無を確認。
- 2分:在宅/避難所の仮決定→連絡テンプレ送信。
2.在宅避難の実践:家を“避難所化”する
2-1.最優先は水・トイレ・温度(生命線の3本柱)
水は1人1日3L×3日分を最低ライン。風呂水は生活用水として温存。給湯器タンクや洗濯機の残水も活用可。トイレはダブル袋+凝固剤を1人1日5回×3日で算定し、黒袋で目隠し・臭い漏れを抑える。集合住宅は排水立て管の状況が不明なら絶対に流さない。温度管理は夏:遮光・対角換気・保冷剤、冬:段ボール+銀マットで床断熱・重ね着。体温低下や熱中症の兆候(悪寒/頭痛/めまい)を家族で共有。
2-2.食・衛生・睡眠の整え方(3日間の回し方)
食は主食・たんぱく・野菜を常温3日分。例:パックご飯/乾麺、ツナ缶/豆、野菜ジュース/乾燥野菜。1日目は冷蔵品の消費→2〜3日目は常温に切替。衛生はウェット・手指消毒・簡易シャワー袋で最小水量に。洗濯はビニール揉みで代替。睡眠は段ボールベッド+マットで底冷え回避、耳栓・アイマスクで睡眠確保。子の退屈対策に折り紙・トランプ・塗り絵を1袋にまとめておくと雰囲気が安定します。
2-3.情報・連絡・見守り(孤立しない仕組み)
ラジオ+モバイル電源の2系統を基本に、紙の連絡網と非常時連絡カード(氏名・連絡先・持病・服薬)を玄関に掲示。通信障害時は固定/公衆電話・近隣宅を代替に。見守りは朝夕の声かけ、ドアノブに色札(緑=無事/黄=要支援/赤=緊急)で可視化。防犯は窓の補助錠・玄関の二重施錠・夜間照明。ペットはケージ・餌・水・トイレ砂を3日分、迷子札と写真を用意。
在宅避難・装備チェック表(数量の目安)
| 分類 | 必要量のめやす | 例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 水 | 3L×人数×3日 | ペットボトル、給水袋 | 調理・手洗い別に+1L/人/日あると安心 |
| 食 | 3食×3日 | ご飯パック、乾麺、缶詰、ナッツ | 1日目は冷蔵庫消費 |
| トイレ | 5回/人/日×3日 | 凝固剤、黒袋、ペーパー | 消臭材・新聞紙で吸湿 |
| 衛生 | 1式 | ウェット、消毒、簡易シャワー | 生理用品・おむつを人数分 |
| 電源 | 300〜500Wh | モバイル電源、手回し、ソーラー | 懐中電灯は家族分+予備電池 |
| 情報 | 2系統 | 手回しラジオ+スマホ | 紙の連絡網・筆記具 |
3日メニュー例:
- 1日目:冷蔵のパン・サラダ・作り置き→夜はパックご飯+レトルト。
- 2日目:乾麺+ツナ+乾燥わかめ、豆乳、果物缶。
- 3日目:クラッカー+ナッツ+スープ、パックご飯+缶詰野菜。
3.避難所を選ぶ・移動する:時間とルートの設計
3-1.避難所の選定と到着前の準備(48時間自立)
最寄+第2候補を地図にマークし、開設情報・ペット可否・バリアフリーを事前確認。到着後すぐ使う物は取り出しやすいポーチへ(保険証コピー・常備薬・モバイル電源・ライト)。家族グループと近隣代表に到着連絡テンプレを送る。受付で要配慮(乳幼児・妊婦・持病・障害・高齢)を伝えると適切な区画や電源の情報が得やすい。
3-2.移動の安全と代替(歩行優先・夜間回避)
避難は徒歩が基本。水が動いて見える路面は10cmでも転倒の恐れ。マンホール周りや側溝ふたは浮き上がりに注意。夜間・強風・増水は延期または在宅継続を優先。車移動は冠水・立体交差・河川沿いを避け、満タン/満充電で出発。同乗者に水分補給と足首回しを指示。要支援者は台車・車いす・歩行器を活用し、階段補助具(布スリング・毛布搬送)を用意。
3-3.避難所での過ごし方(休息・感染・防犯)
ゾーニング(一般/要配慮/感染)を守り、掲示板・放送・班長から1日2回は情報確認。睡眠衛生は段ボールベッド・耳栓・アイマスク・首元保温。貴重品は身につける。清掃や仕分けのボランティアは心の安定にもつながる。子どもは静かな遊びセット、高齢者は足首回し・深呼吸でエコノミー症候群予防。
避難所持ち物・優先度表(48h自立)
| 優先 | 品目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高 | 水・主食・常備薬・保険証コピー | 2日分 | 服薬時刻メモ添付 |
| 中 | 防寒/雨具・衛生・ライト・電源 | 個人1式 | 延長コードは役立つ |
| 中 | イヤホン・アイマスク・耳栓 | 1セット | 休息の質を上げる |
| 低 | 娯楽・学用品・追加食材 | 余力で | 子ども用おもちゃ少量 |
4.家族構成別・災害種別の最適解
4-1.乳幼児・妊婦のいる家庭(静音・清潔・温度)
在宅優先が基本。授乳・おむつ替え・昼寝のリズムが守りやすい。ミルク/離乳食/おむつは3日分、抱っこ紐・授乳ケープ・大判タオルを準備。避難が必要な場合は最短滞在で、静かな区画を早めに相談。
4-2.高齢者・持病・障害当事者(電源・段差・薬)
薬・手帳・処方内容のコピーを1袋に。電源依存機器(酸素・吸引・CPAP等)はモバイル電源と充電スポットを確保。段差回避ルートとエレベーター停止時の代替を事前に。嚥下に配慮した食材(ゼリー飲料等)も忘れずに。
4-3.災害種別の違い(地震・台風/豪雨・土砂)
地震:建物損傷と余震が続く間は避難所寄り。ガス漏れ・通電火災に注意。台風/豪雨:水害ハザードに従い事前避難。風最盛期は外出しない。土砂:急斜面・沢筋は即退避、夜間は絶対に近づかない。
4-4.集合住宅/戸建ての違い(設備と意思決定)
集合住宅は受水槽・加圧ポンプの停止で高層階が断水しやすい。管理組合の掲示を確認し、共用部の損傷(ガラス・外壁)に注意。戸建ては屋根・外壁・基礎の点検が早期に必要。井戸・雨水タンクがある家は在宅の強み。
4-5.車中泊の可否(短期限定)
短期の仮避難としては有効だが、換気・姿勢・防犯に配慮し、足の運動・こまめな水分を徹底。アイドリング長時間は避け、一酸化炭素に注意。可能なら避難所の駐車区画を活用。
家族×災害×推奨判断の早見表
| 家族/災害 | 地震 | 台風・豪雨 | 土砂 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 乳幼児あり | 在宅優先/損傷時は避難 | 事前避難 | 即退避 | 静音・清潔重視 |
| 高齢者あり | 支援あれば在宅 | 事前避難 | 即退避 | 段差・薬・電源 |
| 単身 | 状況に応じ在宅 | 事前避難または在宅 | 退避 | 連絡の定時化 |
| 医療機器依存 | 電源確保不可なら避難 | 早期避難 | 早期避難 | 充電計画が鍵 |
5.準備物の標準パックと運用:在宅・避難所の両立
5-1.在宅パック(家置き)と回転管理
水・主食・トイレ・衛生・電源を3日分、棚1段まるごと防災に集約。ラベル管理(日付・人数・残量)で先入れ先出しを徹底。季節モジュール(夏:冷感・虫よけ/冬:カイロ・ブランケット)を入替。
5-2.持ち出しパック(肩掛け+背負い)の役割分担
肩掛けには貴重品・薬・水500ml×2・行動食・ライト・小型電源・ティッシュ。背負いには雨具・防寒・トイレ・衛生・タオル・薄手寝具。家族で役割分担(大人:共用品、子:軽い個人品)。ペットバッグはケージ・リード・餌・シーツを基本に。
5-3.情報・連絡テンプレと72時間タイムライン
到着連絡:「◯◯小学校体育館に到着。大人2・子1、体調良好。明日9時に再連絡。」/在宅継続:「自宅在宅、電○水×ガス○。トイレ運用可。朝夕に状況送信。」。
72時間タイムライン
- 0〜6時間:安否確認、負傷対応、在宅/避難所判断、水・トイレ確保。
- 6〜24時間:食事の切替(冷蔵→常温)、睡眠環境の整備、連絡の定時化。
- 24〜72時間:在宅は清掃・衛生ルーチン、避難所は情報収集と役割参加、物資の追加調達計画。
在宅・避難所の両刀運用チェック表
| 項目 | 在宅 | 避難所 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 水/食 | 家置き3日分 | 到着48h分持参 | □ |
| トイレ | 凝固剤・袋で運用 | 共用+自前簡易 | □ |
| 休息 | 段ボールベッド | 毛布/マット | □ |
| 連絡 | ラジオ/スマホ/紙網 | 掲示板/放送/スマホ | □ |
| ペット | ケージ・餌3日分 | 受入可否を確認 | □ |
| 防犯 | 補助錠・照明 | 貴重品携行 | □ |
Q&A(よくある疑問)
Q1. 迷ったら在宅と避難所、どちらが安全?
A. **水害・土砂・火災の可能性が少しでもあれば避難所へ。**建物健全・水回り可・情報確保なら在宅も選択肢。夜間は無理せず明朝判断も可。
Q2. 避難所が満員だったら?
A. 第2候補へ。親戚・車中はエコノミー症候群対策(足運動・水分・横になれる体制)を必ず。翌朝の再開設も確認。
Q3. 車で避難してよい?
A. 冠水・土砂・強風時は避ける。走るなら満タン・夜間回避・河川沿い回避。止むを得ず停車する場合は排気口の浸水に注意。
Q4. 在宅で一人暮らし。連絡が不安。
A. 1日2回の定時連絡と連絡が取れない時の見回り依頼を、近隣・会社と事前に取り決め。紙の連絡カードをポスト内側に。
Q5. ペット同伴は?
A. 受入可否・ゾーニングは自治体次第。ケージ・餌・シーツは自前、迷子札と写真を必ず。在宅優先も検討。
Q6. トイレが流れない場合は?
A. 逆流の恐れがあれば絶対流さない。簡易トイレ運用に切替。マンションは排水立て管の情報が出るまで様子見。
Q7. 電気だけ止まった。在宅でいい?
A. 日中は在宅で可。ただし冷蔵庫の管理と夜間の寒暑に注意。蓄電300〜500Whが安心。
Q8. 小学生と高齢者が同居。どちらを優先?
A. 安全確保で共通。移動が危険なら在宅、水害・土砂の恐れがあれば避難所。役割分担で負担を分散。
Q9. 避難所での感染対策は?
A. 手指消毒・マスク・距離。換気と睡眠の確保が免疫維持に有効。発熱時の連絡先を確認。
Q10. 在宅で不審者が怖い。
A. 補助錠・窓の養生・夜間照明、見守り声かけのネットワークを作る。貴重品は分散して保管。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 在宅避難:自宅にとどまり生活を続ける避難のしかた。
- 指定避難所:自治体が災害時に開く学校や公民館など。
- ハザードマップ:災害ごとの危険範囲を示す地図。
- ゾーニング:避難所で、一般・要配慮・感染など区画分けすること。
- エコノミー症候群:長時間同じ姿勢で血の流れが悪くなる状態。足の運動・水分で予防。
- 受水槽/加圧ポンプ:集合住宅で水を各階に送る設備。停止で断水が起きる。
- 排水立て管:各階の汚水を下へ流す太い管。状況不明時は流さないが基本。
まとめ:基準を決めて、同じ手順で動く
在宅と避難所の選択に絶対の正解はありません。だからこそ、建物・立地・ライフライン・家族要件の4条件を同じ順序で評価し、在宅の整備と避難所の準備を同時に持つことが大切です。10分判断プロトコルと72時間タイムラインを家族で共有し、チェック表を印刷して貼っておけば、次の災害でも迷わず・素早く・安全に動けます。