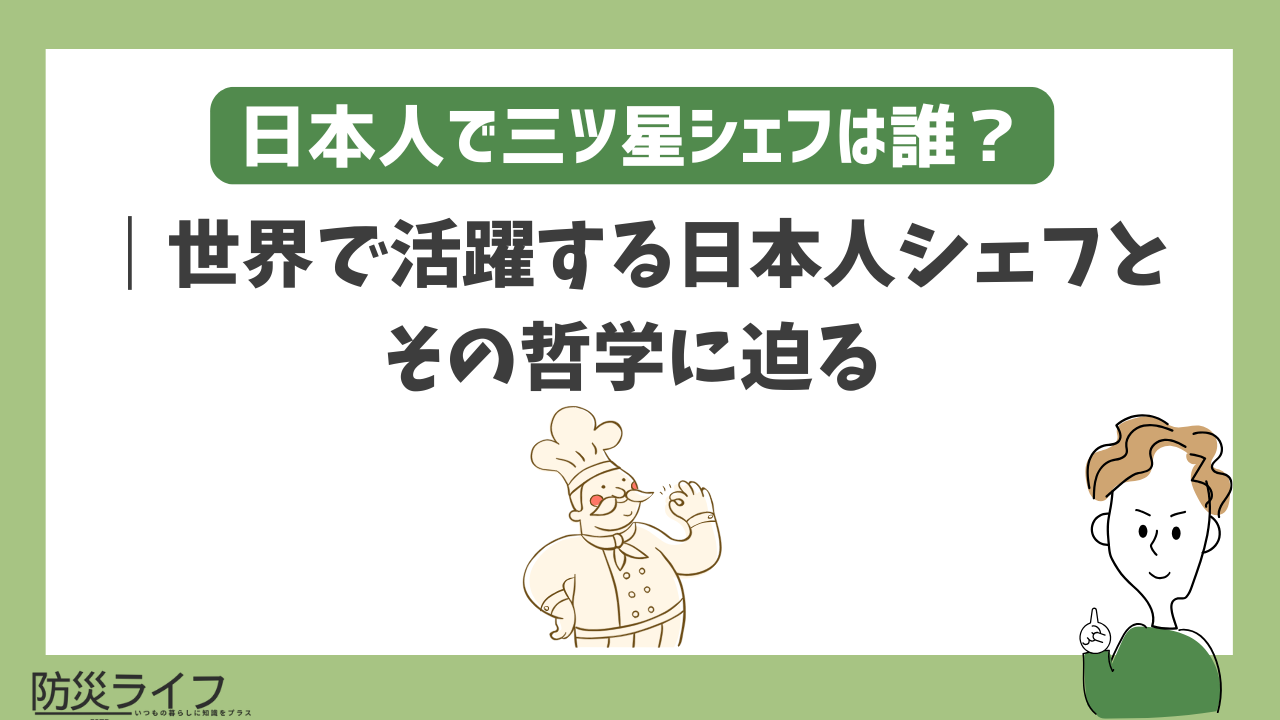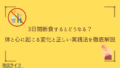「三ツ星」とは、味・技・一貫性にくわえ、体験の完成度まで問われる最高位の評価です。ここでは2025年時点で三ツ星を率いる日本人シェフを中心に、その歩みと哲学、海外で活躍する顔ぶれ、次代の流れまでを一気に整理。リストや表を用いて、読みながら“比較・理解”できる構成にしました。なお、ミシュランの星は年度ごとに見直しが行われ、評価の単位は店です(料理長交代や営業形態の変更で星の数が変わる場合があります)。
日本人で三ツ星シェフは誰?最新リスト(2025年)
まずは現在の顔ぶれを地域別に一覧化。店名は公式表記、料理ジャンルはわかりやすく記載しています。各店の紹介は一般的な特徴に留め、詳細は訪問時の体験を大切にしてください。
東京|三ツ星を率いる日本人シェフ
| シェフ名 | 店名 | 料理 | 初三ツ星年 | 特徴・要点 |
|---|---|---|---|---|
| 神田 裕行 | かんだ(Kanda) | 日本料理 | 2008 | 私邸のような静けさと、細部まで行き届くだしの世界。季節感の出し方が端正。 |
| 岸田 周三 | カンテサンス(Quintessence) | フランス料理 | 2008 | 火入れ・塩味・酸味の“精度”を突き詰める。おまかせ一本で一貫性を体現。 |
| 山本 征治 | 日本料理 龍吟(RyuGin) | 日本料理 | 2012 | 伝統と現代性の調和。温度や香りの制御で“旬の最高潮”を皿にのせる名手。 |
| 生江 史伸 | レフェルヴェソンス(L’Effervescence) | フランス料理 | 2021 | 自然と向き合う料理観。食材のいのちを尊ぶ表現と、行き届いたもてなし。 |
| 川田 智也 | 茶禅華(Sazenka) | 中国料理 | 2021 | 日本人が磨いた中国料理。だし・炭火・茶の文化を重ねる唯一無二の世界。 |
| 高橋 治匡 | はるたか(Harutaka) | 寿司 | 2024 | 研ぎ澄まされた江戸前。米と魚の“温度差”を読む握りで芯の通った旨さ。 |
| 小泉 功二 | 虎白(Kohaku) | 日本料理 | 2016 | 素材の組み合わせの妙。余白を生かしつつ、新しさが自然に立ち上がる。 |
| 石川 秀樹 | 神楽坂 石かわ(Kagurazaka Ishikawa) | 日本料理 | 2009 | きめ細かな一客一亭。引き算の品格と、寄り添うもてなしで名高い。 |
※ 東京の三ツ星にはこのほか「L’OSIER」「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」「SÉZANNE」などもありますが、いずれも料理長は外国籍のため本稿では“日本人シェフ”の名鑑からは割愛しています。
東京の三ツ星に共通すること(要点)
- おまかせ制が多く、季節や天候で献立が微調整される。
- 器・しつらえへの配慮が行き届き、提供温度や香りの立ち上がりまで設計。
- カウンター主体の店では**間合い(会話・手元の見せ方)**が体験の核になる。
京都|磨き抜かれた伝統と革新
| シェフ名 | 店名 | 料理 | 初三ツ星年 | 特徴・要点 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 吉弘 | 菊乃井 本店(Kikunoi Honten) | 日本料理 | 2010 | 懐石文化を世界へ。しつらえ・器・だしの三位一体で季の物語を描く。 |
| 高橋 義弘 | 瓢亭(Hyotei) | 日本料理 | 2010 | 400年の系譜。玉子サンドに象徴される“素直な旨さ”を極める老舗。 |
| 中村 元計 | 一子相伝 なかむら(Isshisoden Nakamura) | 日本料理 | 2011 | 代々受け継ぐ味を現代に。だしの切れと香りの調和が秀逸。 |
| 佐々木 浩 | 祇園 さゝ木(Gion Sasaki) | 日本料理 | 2020 | 遊び心と技量の同居。五感を揺さぶる構成力で京都の今を牽引。 |
| 石原 仁司 | 未在(Mizai) | 日本料理 | 2014 | 圧倒的な一体感。座付から甘味まで“間”を計算した流麗な進行で魅せる。 |
京都の三ツ星に共通すること(要点)
- 出汁文化と季節の移ろいの表現が中核。
- 庭・床の間・器など空間全体で“静と動”を演出。
- 茶の湯や和歌の心を映した名前の付け方・献立の流れが印象を深める。
大阪ほか|関西の個性が光る星
| シェフ名 | 店名 | 料理 | 初三ツ星年 | 特徴・要点 |
|---|---|---|---|---|
| 米田 肇 | HAJIME(大阪) | 革新料理 | 2008(再昇格2017) | 宇宙観を映す一皿。自然科学の視点と美意識で“世界観のある食”を提示。 |
| 松尾 英明 | 柏屋 大阪 千里山(Osaka Senriyama) | 日本料理 | 2011 | たおやかな旨さ。席毎に寄り添う懐石で四季の情趣を表す。 |
| 髙畑 均 | 太庵(Taian) | 日本料理 | 2011 | 素地の良さを生かす火入れ。肩肘張らずに本質へ迫る“凜とした旨さ”。 |
関西エリアの特徴(要点)
- だしの濃淡と温度の妙で品の良い旨さを追求。
- 客の間合いを読むサービスが巧みで、会話の“余白”が心地よい。
海外で三ツ星を獲得した日本人シェフ
日本の外でも三ツ星をつかんだ日本人は少なくありません。代表例をおさえておきましょう。海外での成功は、単なる“逆輸入人気”ではなく、現地の食文化と誠実に向き合い、日本の精度を重ねることで生まれています。
フランス|小林 圭(Restaurant Kei/パリ)
- 要点:日本人としてフランスで初の三ツ星。フランス料理の文脈に“間”と“陰影”を持ち込み、盛り付けに端正な美を宿す。
- 魅力:香りの重ね方、酸の切れ味、余白の取り方。細部の統率が皿の上で凛然と完結。
- 学び:素材の組み合わせを“削る勇気”。足すより引くことで、中心がくっきりと立ち上がる。
アメリカ|高山 雅義(Masa/ニューヨーク)
- 要点:米国で長年三ツ星を守る鮨職人。米と魚の温度・圧の設計が徹底され、無駄のない所作に緊張感が漂う。
- 魅力:器・間合い・沈黙までが演出。“食べる儀式”としての江戸前を世界に伝える。
- 学び:温度差と圧の設計が味わいを決める。家庭でも“ごはんは温かく、具は程よく冷やす”だけで別物になる。
英国ほか|歴代で三ツ星経験のある日本人
- 荒木 水都弘(The Araki/ロンドン):渡英後に三ツ星へ。のちに帰国し、店体制の変化で評価も推移。星は“店の現状”に付与されることの象徴的な例。
- 香港・欧州の鮨:日本人が率いる鮨店が三ツ星に到達する事例が複数。現地の魚介・文化を取り込みながら江戸前の芯を貫く姿勢が共通項。
海外成功の共通点:①産地との対話 ②現地客の文化理解 ③言葉と所作の丁寧さ ④“日本の精度”の持ち込み ⑤チームの多国籍化。
なぜ日本人シェフは三ツ星に選ばれるのか――文化と哲学
細部に宿る美学:道具・火入れ・余白
料理は“工程の連続”。包丁の入れ方、火の回し方、盛り付けの線まで、細部の統制が味の芯をつくります。日本の職人文化はこの微差の積み上げを得意とします。
素材を生かす「引き算」
派手さを抑え、素材の声を聞く。だしや塩の使い方、温度差の設計、香りの足し引き……。余計なものを足さない勇気が皿の透明感を生みます。
一貫性と進化の両立
三ツ星に必要なのは“毎日同じ高さで旨いこと”。同時に、季節や産地の変化に合わせ、昨日より少し良くする更新を止めないこと。日本の四季は、その更新を自然に促します。
表:日本的な料理観と三ツ星評価の接点
| 日本的価値観 | 厨房の実践 | 体験としての効果 |
|---|---|---|
| 端正・清潔 | まな板・布巾・包丁の管理が徹底 | 雑味がなく、香りが立つ |
| 季節の移ろい | 旬の食材・器・設えの統一 | 物語性が生まれ記憶に残る |
| 引き算 | 味の重ねを最小限に | 透明感と余韻が出る |
| 間合い | 提供タイミング・間の演出 | 皿ごとの集中力が高まる |
三ツ星の舞台裏:頂に至るまでの道筋
長い修業と学び直し
十数年規模の現場経験は当たり前。国内外の名店で基本の徹底→再解釈を繰り返し、土台を厚くします。修業は“終わり”ではなく学び直しの始まりでもあります。
体験設計は“料理の外側”まで
照明、器、香り、音、サービスの所作……。総体としての心地よさが、味の感じ方を底上げします。たとえば、同じ料理でも器の質感や提供温度次第で印象は大きく変わります。
チームと仕組み
料理長一人では三ツ星は続きません。育成・分業・再現手順を整え、誰が仕上げても“店の味”になる仕組みを作ります。予約の受け方、食材の検品、仕込みの段取り、提供の流れまでが設計図として共有されています。
三ツ星に近づくためのチェック表(要点)
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 基本技術の精度 | 火入れ・塩味・酸味の再現性、だしの切れ |
| 体験の一体感 | 提供温度、器の選定、香り・音・照明の設計 |
| 産地との信頼 | 生産者との往来、訪問頻度、相互の改善提案 |
| 継続力 | 定休日・人員配置・教育の仕組み化 |
| 記録と改善 | サービス後の振り返り、レシピの更新履歴 |
厨房での1日の流れ(概略)
- 朝の検品:温度記録・鮮度確認・下処理の共有。
- 仕込み:火入れの基準、味の基準を“見本皿”で確認。
- 賄い・休憩:集中力のための体調管理。
- 営業前ブリーフィング:席図・アレルギー・記念日の共有。
- サービス:提供のタイミング管理、温度と香りの揺らぎを監視。
- 片付け・振り返り:良かった点と改善点を記録。
次世代の芽吹き:いま注目の潮流
分野横断の広がり
日本人が手掛ける中国料理・フランス料理・革新料理が三ツ星に並びました。固定観念を超え、和の感性を他ジャンルに溶かす動きが加速しています。
サステナブルの深化
森・海・土への配慮は“味の土台”。環境とおいしさの両立に本気で取り組む店ほど、結果として評価が高まる傾向にあります。無駄のない仕込み、地のものの活用、食品ロスの抑制などは、家庭でも活かせる視点です。
海外拠点と往来
パリ、ニューヨーク、ロンドン、香港……。現地を深く知り、日本の精度を持ち込む往復運動が、次の三ツ星を生みます。海外で経験を積み、国内で開花するケースも増えています。
家庭で取り入れられる“プロの視点”
- 旬を押さえる:季節の主役を一つ決め、献立は脇役で支える。
- 温度管理:温かい料理は温かい器、冷たい料理は冷たい器へ。
- 塩の基準:まずは控えめに、最後に一つまみで輪郭を出す。
- 器と余白:盛り込みすぎず、器の地を見せる。
よくある質問(Q&A)
Q1. 三ツ星は“料理人”ではなく“店”につくの?
A. はい。評価の単位は基本的に店です。料理長の交代や営業形態の変更があると、星の数が見直されることがあります。
Q2. 予約困難店はガイドから外れることがある?
A. 一般客が予約できない体制になれば、掲載対象外となる場合があります。品質評価そのものとは別の運用上の基準です。
Q3. 三ツ星はどんな意味?
A. 「そのために旅行する価値がある特別な料理」。味の高さにくわえ、一貫性と完成度が問われます。
Q4. 海外で三ツ星を取るには語学や文化理解は必須?
A. 必須です。食材の呼び名、宗教や習慣、接客の作法まで、文化の地図を身体化する努力が欠かせません。
Q5. 値段は高いほど星が増える?
A. 価格と星は別の概念です。評価は料理の質・一貫性・体験の完成度に基づきます。
Q6. 三ツ星の店は必ず正装が必要?
A. 店ごとの案内に従います。過度な香りの強いもの・カジュアルすぎる服装は避けるなど、清潔感を意識すると安心です。
Q7. キャンセル規定は?
A. 席数が限られるため、期日や人数変更の規定が明確な店が多いです。予約時の案内を必ず確認しましょう。
用語辞典(やさしく一言で)
- 懐石/会席:季節の素材を少量多皿で味わう日本の正餐。だしと火加減が命。
- 江戸前寿司:東京湾の伝統に根ざす寿司。漬け・煮切り・締めなど手当てで旨さを引き出す。
- だし:昆布やかつおで引く旨味の柱。香りと切れが命。
- おまかせ:料理長に選択を委ねる食事の形。旬や客の体調に合わせて最適化される。
- グリーンスター:環境配慮に先進的な店へ付与される印。
- 先付・八寸:懐石の序章を担う小品や盛り合わせ。季節の導入部。
- 口直し:甘味の前に置かれるさっぱりした一品。味覚を整える役割。
まとめ
日本人の三ツ星シェフは、細部の精度と引き算の美、そして更新を止めない姿勢で世界の頂を切り拓いてきました。三ツ星はゴールではなく、毎日を積み重ねるための約束。伝統を守りながら、土地・人・自然と対話する日本の料理は、これからも世界の食卓を驚かせ続けるはずです。旅先で、記念日で、あるいは学びの機会として——一皿の向こうにある哲学を味わってみてください。