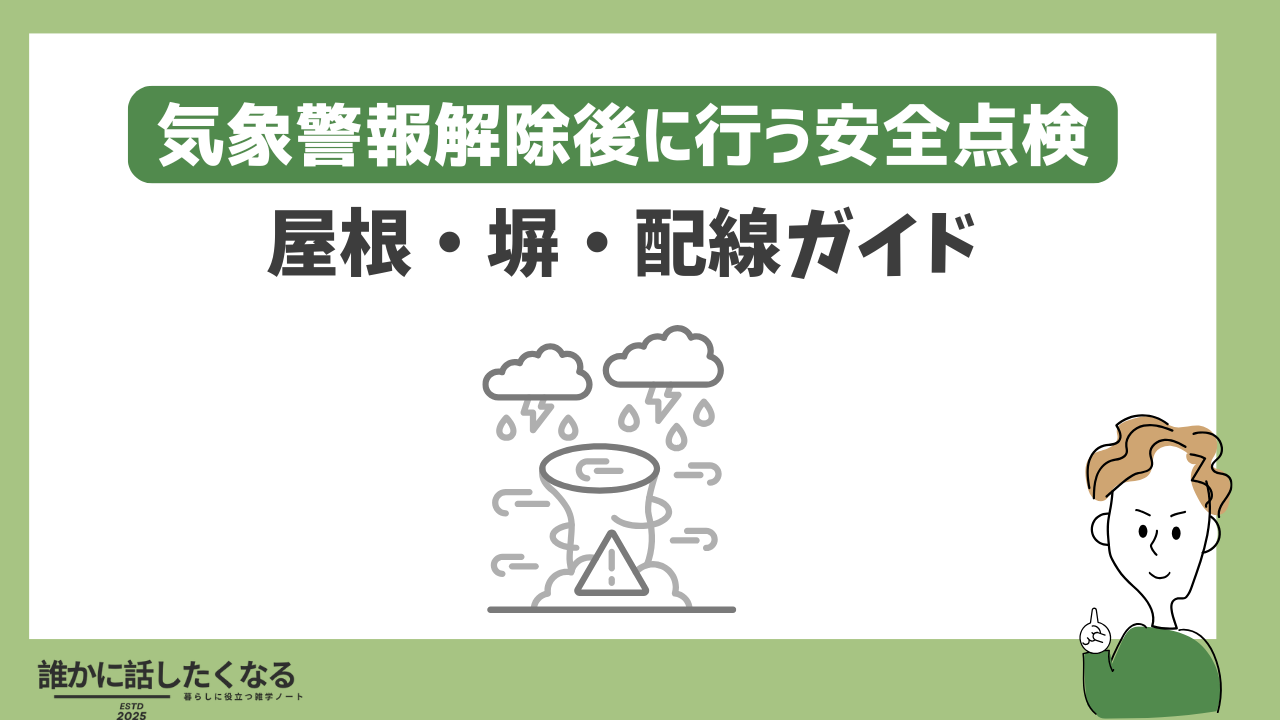「近づかない・触れない・一人で無理をしない」——警報が解除されても、住まいの周囲には見えない危険が残る。屋根・塀・配線はわずかな破損や緩みが二次災害の引き金になる要注意部位だ。
本稿は、家に入る前の外回り確認→屋内の安全確認→応急処置→専門業者への手配までを時系列で迷わず進められる実践手順として整理し、写真の撮り方・連絡先の控え方・保険請求に役立つ記録まで盛り込んだ。チェック表・早見表を多用し、現場でそのまま使えることにこだわっている。
警報解除後の行動計画:入る前に外を観察する
1)遠景チェック(離れて全体を把握)
- 離れた位置から屋根の浮き・欠け・ずれ、外壁のひび、電線のたるみを観察。
- 倒木・落石・瓦の散乱、塀の傾き、地盤の陥没がないかを広範囲に確認。
- **水位跡(泥の線)**を見つけ、浸水の高さを推定しておく(床下か、床上か)。
2)近景チェック(足元と頭上の危険)
- 足元:割れガラス、釘、金属片。長靴・厚手手袋・帽子・保護メガネを装着。
- 頭上:軒先の落下物、看板、ベランダの鉢。風で再落下の恐れ。
- におい:ガス臭・焦げ臭・油臭があれば近づかない。離れた場所から連絡する。
3)入室前の連絡と記録(単独行動を避ける)
- 家族・近所に所在と予定時間を伝える。一人での点検は避ける。
- 写真・動画は全景→中景→部分→品番/型番の順で。方位と寸法も写す。
- 電話が混み合う時は文字(SMS/メモ)で残す(日時・場所・被害状況)。
4)持ち物ミニリスト(入る前に)
- 長靴、厚手手袋、マスク、ヘッドライト、モバイル電源、養生テープ、油性ペン。
- ブルーシート(小)、結束バンド、火ばさみ、使い捨て雑巾、チャック袋(破片保管用)。
行動計画の早見表
| 段階 | 目的 | 見る場所 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 遠景 | 全体の危険把握 | 屋根・塀・電線・倒木 | 近づく前に観察 |
| 近景 | 足元・頭上確認 | 破片・落下物・におい | 長靴・手袋・帽子 |
| 入室前 | 連絡・記録 | 写真・動画・連絡先 | 一人で入らない |
| 携行 | 装備準備 | 防具・工具・記録用品 | 両手が空く装備で |
屋根・雨どい・外壁の点検:落下と浸水を防ぐ
屋根(地上からの目視に限る)
- はしごで登らない。地上から双眼鏡やスマホ望遠で確認。
- 瓦/スレートの欠け・ずれ、棟板金の浮き、谷樋の詰まり、アンテナの傾きを記録。
- 太陽光パネルは割れ・外れ・配線の垂れに注意。絶対に触れない。
雨どい・軒先(次の雨で被害が拡大しやすい)
- 詰まり(葉・泥・破片)と外れ・割れ。
- 縦どいの外れや支持金具の緩みは、次の雨であふれ→外壁汚損の原因。
- 軒天の染みは雨水の回り込みの合図。室内側の天井染みも併せて確認。
外壁・ベランダ(落下物と浸水のサイン)
- 外壁のひび、シーリングの割れ、塗膜の膨れ。
- ベランダ排水口の詰まり、手すりのぐらつき、タイルの浮きは触って確かめない(落下の危険)。
屋根・外壁の点検表
| 部位 | 兆候 | 応急の考え方 | 記録のコツ |
|---|---|---|---|
| 瓦/スレート | 欠け・ずれ | 触れない・近寄らない | 斜め上から日付入りで |
| 棟板金 | 浮き・はがれ | 風で飛ぶ恐れ→立入制限 | 棟全体を連写 |
| 谷樋/雨どい | 詰まり・外れ | 排水路の確保が先 | 詰まり位置が分かる角度 |
| 外壁 | ひび・染み | 雨養生は専門へ | ひびの長さと位置を記す |
| ベランダ | 排水詰まり | ゴミ除去(手の届く範囲) | ビフォー/アフター撮影 |
塀・門・地盤の点検:傾きと沈下を見逃さない
ブロック塀・石塀(倒壊の二次災害に直結)
- 傾き(上端の線が水平でない)、ひび、ぐらつき。
- 控え壁の有無、鉄筋の露出。古い塀は特に注意。
- 倒壊の恐れがあれば近づかず、通行人を遠ざける。ロープやコーンで簡易封鎖。
木製フェンス・金網(連鎖倒壊に注意)
- 支柱のぐらつき、さびた金具、根本の腐れ。
- 風向きに沿った一列の倒れは連鎖倒壊の前ぶれ。端部を仮固定して動揺を抑える。
地盤・犬走り・駐車場(沈下・洗掘の兆候)
- 地割れ・陥没、地盤の洗掘、雨水桝の沈下。
- 土間の割れが扉や門の開閉不良を起こすことがある。無理にこじ開けない。
塀・地盤の点検表
| 部位 | 兆候 | 立入判断 | 連絡先の目安 |
|---|---|---|---|
| ブロック塀 | 傾き・ひび | 近寄らない | 自治体/建築士/解体業者 |
| 石塀 | ぐらつき | 立入禁止措置 | 警察・道路管理者(はみ出し) |
| 木製フェンス | 支柱腐れ | 仮補強まで | 造園業者 |
| 地盤 | 陥没・洗掘 | 立入禁止 | 自治体・土木業者 |
配線・ガス・水回りの点検:二次災害を止める
電気(配線・分電盤・家電)
- 濡れた可能性がある場合、主幹ブレーカーを落とす。
- 分電盤の焦げ・変色・異臭、コンセントの焦げ・緩み。
- 延長コードの水ぬれは使用中止。通電試験は専門へ。
- 復電は段階的に:主幹ON→重要回路(冷蔵庫など)→一般回路の順で確認。
ガス(におい・メーター)
- ガス臭がしたら火気厳禁・換気せず退避。携帯電話は離れた場所から連絡。
- メーターの遮断表示を確認。自己復帰の操作は説明書に沿う(不安なら業者へ)。
- 器具栓のつまみ位置を必ず確認(開いたまま再開は危険)。
水回り(給排水・床下)
- 水道の濁り、給湯器の配管外れ、排水の逆流。
- 床下の水たまり音やにおいがあれば専門点検を依頼。
設備の安全点検表
| 設備 | 危険の兆候 | 初動 | 以後の流れ |
|---|---|---|---|
| 電気 | 濡れ・焦げ・異臭 | 主幹OFF・写真 | 電力会社/電気工事店へ |
| ガス | におい・遮断表示 | 退避・連絡 | ガス会社点検後に使用 |
| 水回り | 濁り・逆流 | 元栓確認・写真 | 水道局/設備業者へ |
応急処置・記録・連絡:次に備える
応急処置の範囲(無理はしない)
- 人が通る場所の破片回収(厚手手袋・火ばさみ)。
- 立入禁止テープや張り紙で周囲に知らせる。
- 雨養生(ブルーシート仮掛け)は高所作業を避け、地上で届く範囲のみ。
- 仮固定は結束バンド/ロープで落下防止を優先(原状復旧は専門へ)。
記録の撮り方(保険・見積もりに有効)
- 全景→中景→近景の順、方位と寸法を入れる。
- 撮影日と時刻が分かるよう設定。
- 見取り図に被害箇所を番号で記す。領収書・資材のラベルも保管。
連絡の優先順位(迷ったら命→インフラ→保険→工事)
1)危険が迫る場合:119/110、自治体。
2)電気・ガス・水道:各事業者。
3)保険:契約先。受付番号を控える。
4)工事:屋根・外壁・電気・設備の順に専門へ(相見積もりを基本)。
応急・記録・連絡のチェックリスト
| 項目 | 実施 | 備考 |
|---|---|---|
| 破片回収 | □ | 火ばさみ・厚手手袋 |
| 立入禁止表示 | □ | テープ・紙・油性ペン |
| 写真撮影 | □ | 全景→部分→品番 |
| 見取り図 | □ | 被害番号と寸法 |
| 連絡先控え | □ | 事業者・保険・自治体 |
| 領収書保管 | □ | 保険請求・確定申告に備える |
Q&A(よくある疑問)
Q1.屋根の一部だけなら自分で直せる?
はしご作業は落下の危険が大きい。登らない。写真記録→専門依頼が原則。
Q2.停電は解消したが家電が動かない。原因は?
濡れ・焦げ・異臭があると危険。主幹OFF→専門点検を待つ。内部乾燥に時間が必要な場合も。
Q3.ブロック塀のひびはすぐ直すべき?
傾き・ぐらつきがあれば近寄らず。道路に倒れる恐れは警察・道路管理者へも連絡。
Q4.浸水した床下はどうする?
放置すると腐れやにおいの原因。乾燥・消毒を専門業者に依頼。記録を忘れずに。
Q5.保険のために何を残す?
被害全景・近景・型番、見取り図、発生日・天候、連絡履歴。領収書も保管。
Q6.悪質な勧誘が来たら?
即決しない・前金を払わない・身元を確認。名刺と見積の会社名/所在地/許認可を確認し、相見積もりを取る。
用語辞典(やさしい言い換え)
主幹ブレーカー:家全体の電気をまとめて切るスイッチ。
棟板金(むねばんきん):屋根の一番高い所をおおう金属板。
雨どい:屋根の雨水を集めて地面へ流す管。
控え壁:塀を横から支える小さな壁。
洗掘(せんくつ):水が土をえぐって削り取ること。
自己復帰:止まったガスの流れを自分で元に戻す操作。
見取り図:建物の形や部屋の位置を簡単に描いた図。
谷樋(たにどい):屋根の谷部分で雨水を集める細い樋。
相見積もり:複数社から見積を取り比べること。
まとめ:警報解除は安全の確約ではない。遠景→近景→入室前の連絡と記録を守り、屋根・塀・配線の三重点検で二次災害を防ぐ。登らない・触れない・一人で無理しないを合言葉に、記録と連絡を先に、補修は専門へ。この順番が、住まいと家族を守る最短路だ。