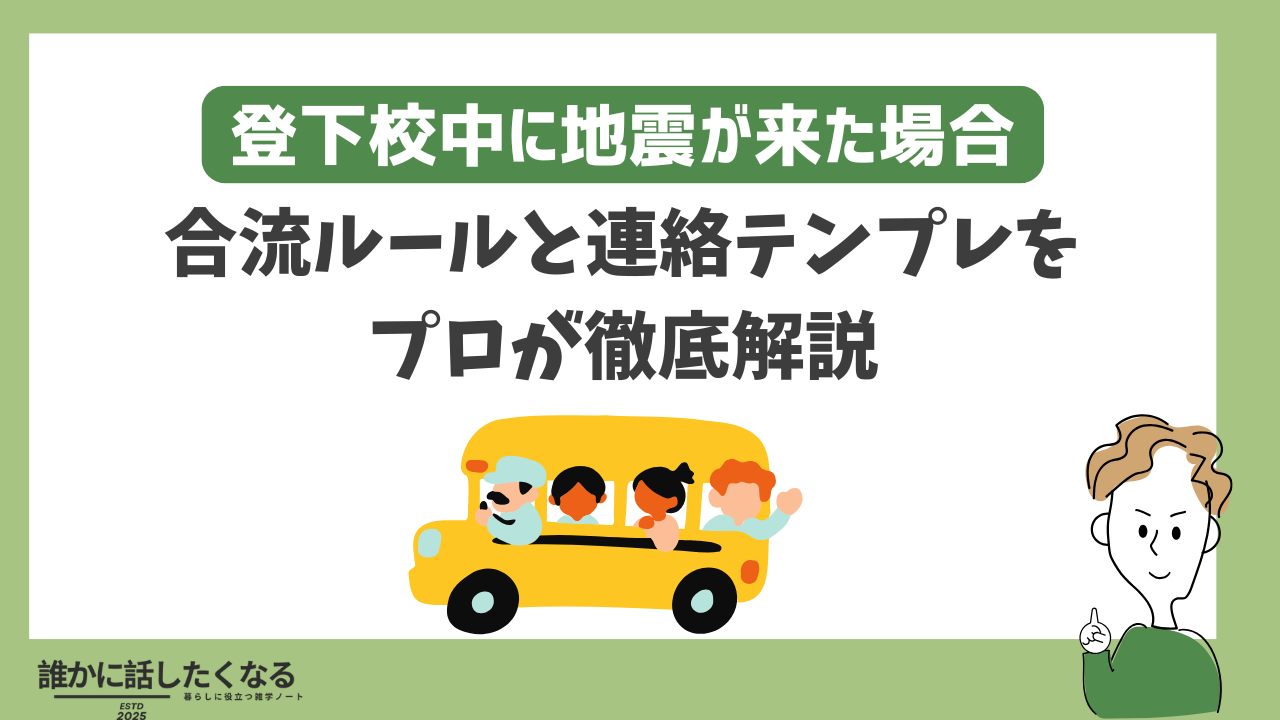登下校の最中に強い揺れ——大人がそばにいない時間帯にこそ、行動の順番と合流ルールが命綱になります。本記事は、子ども本人・保護者・学校の三者が同じ手順で動けるように、発生直後の安全行動、合流の決め方、連絡テンプレ、危険回避の地図作り、日常の訓練まで詳しくまとめました。
印刷してランドセルに入れられる短縮版にも使いやすい構成にし、表・チェックリスト・想定シナリオも拡充しています。
1.まずここだけ:発生直後の最優先行動と合流の原則
1-1.発生直後の3手順(止まる→守る→離れる)
- 止まる:走らない・立ち止まる。自転車は降りて脇に置く(倒しておくと転がらない)。
- 守る:頭を下げてランドセル/鞄で頭首を守る。ガラスに背を向ける。ヘルメット・防災ずきんがあれば着用。
- 離れる:塀・自販機・窓ガラス・看板・ブロック塀・古い家屋から2m以上離れる。電線が揺れている所は通らない。
1-2.合流の原則(どこへ向かう?)
- 学校の授業時間帯→学校に戻る/学校の指示に従う。
- 下校中で学校が近い(徒歩10分以内)→学校へ戻る。
- 自宅が近い(徒歩10分以内)→自宅最寄りの集合地点へ(自宅前は危険)。
- どちらも遠い→**事前に決めた第3集合(公園・広場)**へ。橋や高架は無理に渡らない。
1-3.保護者の迎え原則(車での迎えは?)
- 徒歩・自転車で迎えが基本。車の集中は渋滞・救助の妨げ・火災のリスク。
- 迎えは集合地点単位で。個別合流は行方不明の原因になるため避ける。
- 迎えが遅れる前提で、次へ移動する時刻と順番をカードに明記しておく。
1-4.ひと目で分かる判定フロー(簡略)
| いまの場所 | 学校まで徒歩10分以内? | 自宅/第2集合まで徒歩10分以内? | 行き先 |
|---|---|---|---|
| 学校の授業時間帯 | — | — | 学校(最優先) |
| 下校中・学校近い | はい | — | 学校へ戻る |
| 下校中・自宅側が近い | いいえ | はい | 第2集合(近所の公園) |
| どちらも遠い | いいえ | いいえ | 第3集合(広域避難地) |
“最初の3分”行動早見表
| 場所/状況 | 直後の動き | 次の動き |
|---|---|---|
| 歩行中 | 立ち止まり頭を守る | 危険物から2m離れ安全地帯で待機 |
| 自転車 | 降りて自転車を倒し離れる | 揺れが収まったら押して移動 |
| バス停付近 | 車両・電柱から離れる | 開けた場所で姿勢を低く |
| 商店街 | ガラスから背を向ける | アーケード外の空が広い所へ |
2.登下校ルート別:安全地帯・危険物・一時退避のコツ
2-1.安全地帯の見つけ方(広く・低く・落ちない)
- 広い歩道の内側、公園中央の広場、学校や公共施設の敷地内。
- 電線が交差しない空、ガラスが少ない壁面側、斜面や石垣から離れた場所。
- 店舗前は看板・ガラスが多いので角を曲がって一枚壁の内側へ。
2-2.危険物の回避(2mルール)
- ブロック塀・石塀・老木から2m以上離れる。
- ショーウィンドウ・自販機・看板・トラック荷台の真横に立たない。
- 川沿い・崖沿いは足元の崩れに注意し、橋を渡る判断は後回し。
2-3.交通・火災の二次リスク
- 揺れで車が急停止・急発進する。横断は信号無視でしない。
- ガス臭・黒煙を見たら風上へ移動。水辺へ退避はしない(液状化・津波)。
2-4.雨・暗い・雪の日の追加注意
- 雨:水たまりの下はマンホールずれや段差が隠れる。白線は滑る。
- 夜:反射材と小型ライトで自分の位置を知らせる。電柱間の暗い帯は避ける。
- 雪:屋根雪・つららの落下範囲を意識。凍結路はすり足で移動。
ルート危険/安全チェック表(家で事前に記入)
| 地点 | 危険物 | 離れる距離 | 一時退避候補 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 〇〇商店前 | ガラス窓 | 2m | 角の駐輪場奥 | 日よけ看板あり |
| ××公園沿い | ブロック塀 | 2m | 公園中央の広場 | 老木注意 |
| △△橋手前 | 高架・落下物 | 5m | 手前の広い歩道 | 渡らず待機 |
3.合流ルールの決め方:第1→第2→第3集合の三段構え
3-1.集合地点の選び方(家の前はNG)
- 広くて見通しが良い、落下物がない、24時間立入可。
- 自宅前はガラス・瓦落下の危険があるため避ける。道路の曲がり角も避ける。
3-2.三段階の集合ルール(時間差も決める)
- 第1集合:学校(授業時間帯は最優先)。
- 第2集合:近所の公園A(家から徒歩5分以内)。
- 第3集合:広域避難地B(学校からも近い)。
- それぞれ**待機時間(例:30分)**を決め、次へ移動する条件(例:合流人数/時刻/危険発生)を明文化。
3-3.引き渡しルール(誰が迎えに来るか)
- 迎え可能者を3名以上カードに記載(親・祖父母・近所)。
- 合言葉を決め、メモと身分証で確認。本人以外には引き渡さない。
- 兄弟姉妹の合流順(年上→年下)も紙に書いておく。
3-4.少人数・集団それぞれの動き方
- 一人の時:安全地帯で待機→近くの大人に声かけ→カードの順に連絡。
- 友だちと一緒:隊列を乱さず、2列横並びは避ける。リーダー1名・後ろ1名を決める。
- 低学年混在:歩幅を合わせる。走らせない。横断は手をつなぐ。
合流ルールのひな型(家族で埋める)
| 区分 | 場所 | 集合の目安 | 待機時間 | 次の行き先 | 迎え担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1集合 | 学校 正門前 | 授業中は学校 | 30分 | 第2へ | 父/母 |
| 第2集合 | 〇〇公園中央広場 | 下校中で自宅遠い時 | 30分 | 第3へ | 祖母 |
| 第3集合 | △△防災広場 | 学校も自宅も遠い時 | 60分 | 近居親族宅 | 近所佐藤さん |
4.連絡テンプレと情報共有:電波が混む前・復旧後
4-1.音声が通じない時の短文テンプレ(SMS/メール)
- **「無事/場所/移動先/次の連絡時刻」**だけを送る。絵文字・長文は避ける。
- 例:「無事。〇〇公園。30分待って第3へ。次12:30」
- 例:「母へ。学校→第1集合。正門前。次12:10」
4-2.保護者側テンプレ(学校・学童・近所へ)
- 例:「△△の保護者××。現在自宅。第2集合へ向かいます。到着12:20予定」
- 例:「近所の◇◇さん、お子さんを第2で合流可。合言葉『□□』」
- 例:「学童へ。今日は家庭の合流ルールで第3集合に移動します。」
4-3.連絡カードと身につけ方
- ランドセル内ポケットに防水カード(名前・学年・住所・緊急先・迎え可能者)。
- ホイッスル・小型ライトを肩ベルトに常備。夜間下校の反射材は前後に貼る。
- 小銭・テレホンカードを小袋に入れておく(公衆電話用)。
4-4.公衆電話・伝言サービスの使い方(基本)
- 公衆電話:受話器を上げ、硬貨/カードを入れ、短く要件→場所→次の時刻を伝える。
- 伝言サービス:家族の番号を決めておき、短い伝言(例:「無事。第2集合へ。次12:30」)を入れる。
家族連絡カード(必要事項の例)
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 氏名/ふりがな | 山田 太郎/やまだ たろう |
| 学年・組 | 3年2組 |
| 自宅住所 | ○○市□□1-2-3 |
| 保護者連絡先 | 090-XXXX-YYYY(母)/080-AAAA-BBBB(父) |
| 迎え可能者 | 祖母・近所の佐藤さん(合言葉:みかん) |
| 集合ルール | 第1:学校→第2:〇〇公園→第3:△△広場 |
5.日常の備えと訓練:1分×週1の反復で“体が覚える”
5-1.通学路の危険マップを家族で作る
- 危険物(塀・ガラス・看板)に赤、安全地帯に青でマーク。
- 待機できる場所を200〜300mごとに決め、雨の日版・夜版も作る。
5-2.家庭内ミニ訓練(時間指定で実施)
- 「いま揺れたら?」ゲーム:合図で止まる→守る→離れるを10秒で再現。
- 連絡テンプレ暗唱:「無事・場所・移動先・次の時刻」。
- 合言葉確認:迎え可能者と季節ごとに更新。覚えやすい言葉を選ぶ。
5-3.持ち物アップデート(軽く・身につける)
- 反射材・笛・小型ライト・予備マスク。冬はフォイルブランケットをA6に折って入れておく。
- 靴はかかとが踏めないタイプ、靴ひもは二重結び。雨の日は替え靴下を小袋に。
5-4.学校・地域と連携する
- 学校の引き渡し方法と避難場所を確認。
- 学童・習い事でも同じ合言葉・同じ集合ルールを共有。
- 近所の迎え可能者と地図を一緒に確認しておく。
家庭用チェックリスト(週1で〇)
| 項目 | 今週点検 | 備考 |
|---|---|---|
| 連絡カードの更新 | 合言葉の見直し | |
| 危険マップの確認 | 工事・新店舗の変化 | |
| 持ち物の整備 | 笛・ライト・反射材 | |
| 合流ルールの復唱 | 第1→第2→第3 | |
| 迎え可能者の確認 | 在宅状況の確認 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.学校が近いが門が閉まっていたら?
A. 正門付近の安全地帯で待つ。教職員や地域の誘導に従い、勝手に移動しない。裏門へ回ってはぐれるのを防ぐ。
Q2.保護者の勤務先が遠く、迎えが遅れる
A. 第2→第3集合へ時間差で移動するルールをカードに明記。迎え可能者(祖父母・近所)を事前登録し、合言葉で確認。
Q3.スマホが圏外・電池切れ
A. カードの情報で動けるように。公衆電話・伝言サービスを使う。次の連絡時刻を決めてから移動する。
Q4.兄弟で別ルートの時
A. 年上が先に安全地帯へ。合流は第2集合で。探し回らず、決めた時間まで待つ。
Q5.大雨・津波注意報が同時に出た
A. 水辺・川沿い・海沿いから離れる。高台の安全地帯を優先。橋は渡らない。
Q6.バスや電車に乗っている時
A. 車内では掴まって低く。無理に外へ出ず、係員の指示に従う。停車後は頭上の物に注意して降りる。
Q7.合言葉を忘れた
A. 身分証と迎え可能者リストで確認。本人以外には引き渡さない原則を守る。
Q8.友だちが泣いて動けない
A. 頭を守らせて一緒に安全地帯へ。大声で助けを呼ぶ。無理に走らせない。
用語辞典(やさしい解説)
- 安全地帯:落下・倒壊・火災から距離が取れる場所。広い歩道の内側や公園中央など。
- 第1/第2/第3集合:学校→近所の公園→広域避難地の順に決める合流の階段。
- 2mルール:塀・ガラス・看板などから2m以上離れて待つ基本ルール。
- 連絡テンプレ:**「無事・場所・移動先・次の時刻」**を短文で送る書き方。
- 風上:煙や臭いが流れてこない方向。煙から逃げる時に進む向き。
- 二次災害:地震後に起きる火災・転倒・落下・交通事故などのこと。
まとめ
登下校中の地震は、止まる→守る→離れるの10秒手順と、第1→第2→第3集合の三段構えが要。カードと危険マップを家族で作り、週1分の反復で体が先に動く状態にしておきましょう。
保護者は徒歩・自転車迎えを基本に、集合地点単位で合流。短文テンプレで連絡を統一すれば、混乱は大きく減らせます。最後に——「いま起きたらどう動く?」を今日1回だけ家族で声出ししてみてください。それが最初の一歩です。