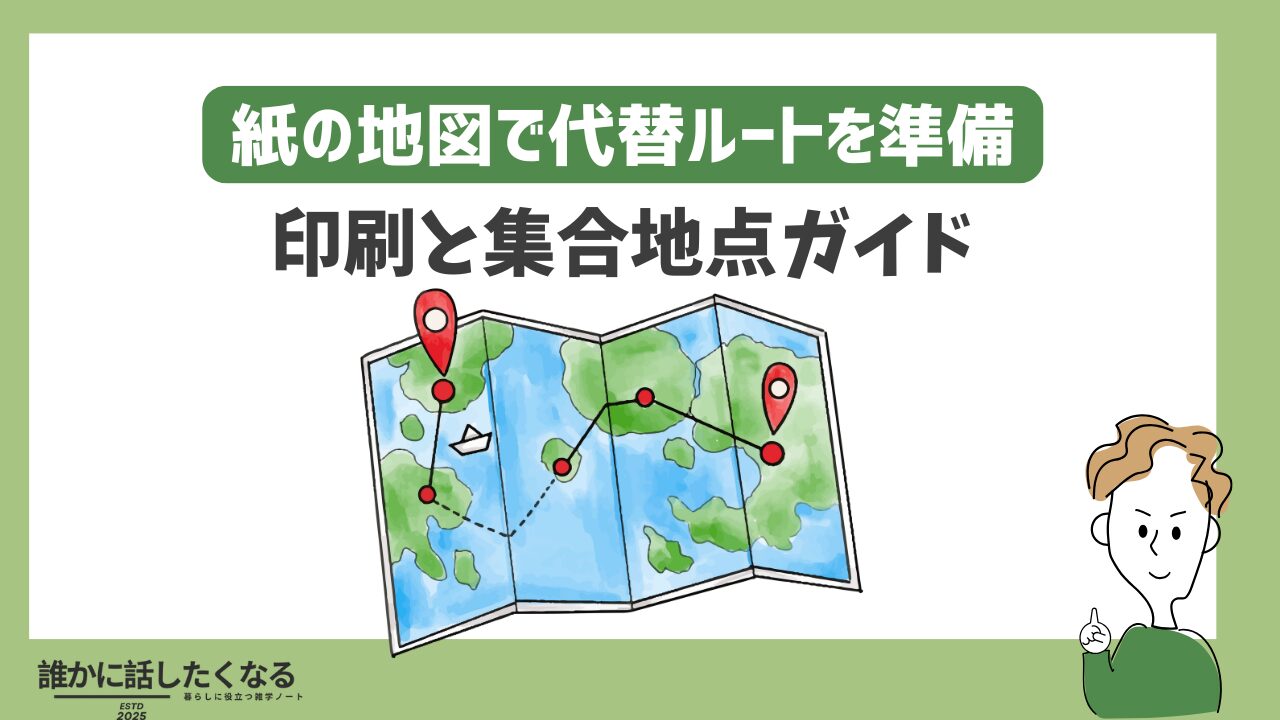電池が切れても、通信が途絶えても、紙の地図はあなたの行動を止めません。 本稿では、紙の地図を自宅で印刷して持ち歩く方法、代替ルート(メイン/予備/最終)を三層で設計する手順、そして家族や仲間と共有する集合地点の決め方までを、実務に落とし込んで詳説します。
さらに、方角・距離・地形の読み取り、見落としやすい危険箇所の洗い出し、キット化と更新のコツを加え、誰が見ても同じ動きになる書き込みルールに統一します。最小装備でも再現できることを重視し、横文字を減らした平易な言葉でまとめました。
1.紙の地図を“使える資料”にする印刷術
1-1.縮尺と範囲の決め方(徒歩/自転車/車)
- 徒歩:1:15,000〜1:25,000(1cm=150〜250m)。曲がり角・路地・階段が読める縮尺。避難路の細い抜け道も見落としにくい。
- 自転車:1:20,000〜1:50,000(1cm=200〜500m)。坂のつながり・川の横断点・踏切を把握。風の抜けや橋の幅もメモ。
- 車:1:50,000〜1:100,000(1cm=0.5〜1km)。幹線・高架・一方通行の集積を俯瞰。右折の多さは渋滞の種なので印を付ける。
縮尺と用途の早見表
| 縮尺 | 1cmあたり | 主な用途 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|---|
| 1:15,000 | 150m | 徒歩の詳細 | 路地まで読める | 広域が分割になりがち |
| 1:25,000 | 250m | 徒歩〜自転車 | バランス良い | 細道は現地で補う必要 |
| 1:50,000 | 500m | 自転車〜車 | 広域把握が容易 | 細部は別紙が必要 |
| 1:100,000 | 1km | 車の広域 | ルート構想に最適 | 迂回の細部が見えにくい |
1-2.印刷の設定と用紙選び
- 用紙:A4は携帯性、A3は視認性。両面印刷で表を地図、裏を凡例・連絡先・集合地点表にする。
- 紙質:耐水紙または普通紙+透明袋。鉛筆で書けることを優先。油性ペンはにじみにくい細字を選ぶ。
- 余白:上下左右15mm以上を書き込み欄に。更新日・作成者・配布先を明記して最新版管理を容易にする。
- 濃度/色:等高線・河川・建物が判別できる濃さに。淡い背景+濃い手書きが読みやすい。
印刷設定の早見表
| 項目 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 配置 | 中央寄せ・等倍 | 距離感が狂わない |
| 余白 | 15〜20mm | 書き込み欄・穴あけ余地 |
| 用紙 | A4またはA3 | 携帯性/視認性の両立 |
| インク | 濃いめ | 屋外でも読める |
| 裏面 | 凡例・集合地点・連絡先 | 一枚で完結 |
1-3.必須の書き込みと凡例(全員同じルール)
- 赤実線=メイン、橙点線=予備、黒破線=最終。
- 丸印=集合地点(数字で順番)、四角=立寄拠点(公園・避難所・駅・広場)。
- 矢羽根で進行方向、**×で通行止め・危険箇所、!**で注意。
- 点線の幅は予備<最終で差をつけ、色が分からない人でも形で識別できるようにする。
縮尺別・移動目安(平地・大人)
| モード | 勾配 | 1時間の目安 | 休憩込みの計画値 | 雨天時の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩 | ほぼ平坦 | 4〜5km | 3〜4km | 2.5〜3.5km |
| 自転車 | ほぼ平坦 | 12〜18km | 10〜15km | 8〜12km |
| 車 | 市街地 | 15〜25km | 10〜20km | 8〜15km |
重要:地図には**“最悪でもここまで”の到達圏を同心円で描き、無理な計画を避ける基準にします。子ども・高齢者同行なら徒歩は3km/h**を上限に。
1-4.折り方と保護
- 地図の中央が目的地になる折りにし、開けば一目で進行方向が分かるようにする。
- 透明袋の口を下向きに差し、雨水の侵入を防ぐ。洗濯ばさみで風対策。
2.代替ルートを三層で設計する
2-1.三層の定義(メイン/予備/最終)
- メイン(赤実線):最短・最速。橋・トンネル・踏切など要所が多く、止まると全体が詰まる。
- 予備(橙点線):メインの並走ルート。側道・一筋裏・並行する小さな橋を活用。距離はやや増でも止まりにくさを優先。
- 最終(黒破線):河川沿い・高台の縁・広い歩道など安全第一の遠回り。夜間照明の有無も評価。
2-2.“詰まりやすい場所”の洗い出し
- 狭い橋・古い踏切・工事中は赤×。
- 学校・大商業施設・病院の前は人と車が集中。時間帯で避け道を選ぶ。
- 川の合流点・谷底地形は冠水の常連。雨雲の向きも余白に記録。
2-3.判断の基準(歩道幅・曲がり数・勾配)
- 歩道の幅:すれ違い可を最低条件。ベビーカー・車いす同行は段差の少なさを最優先。
- 曲がり数:少ないほど迷いにくい。三手に分かれる交差点は進行方向に矢印を重ねる。
- 勾配:登りは距離×1.2倍の負荷で見積もり、下りは滑りやすさに注意。
ルート比較のチェック表(例)
| ルート | 距離 | 曲がり | 危険箇所 | 歩道幅 | 夜間照明 | 高低差 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインA | 4.2km | 8回 | 橋1・踏切1 | 中 | 多 | 小 | ◎ |
| 予備B | 4.8km | 6回 | 工事1 | 広 | 中 | 中 | ○ |
| 最終C | 5.6km | 4回 | なし | 広 | 少 | 大 | ○(日中限定) |
2-4.時間帯・天候で切り替える
- 朝夕:通勤通学で混雑。歩道の広さ優先に切替。
- 大雨:アンダーパス・川沿い低地は即回避。高台縁の最終ルートを選択。
- 降雪:日陰の坂は滑りやすい。曲がりを減らす遠回りが安全。
2-5.家族構成別の工夫
- 子ども同行:神社・公園・学校など安全に止まれる場所を1kmごとに設定。
- 高齢者同行:休憩用ベンチと公衆トイレを凡例に追記。
- ペット同行:立入不可の施設をあらかじめ地図に斜線で表示。
3.集合地点と連絡の設計:合流が最優先
3-1.一次・二次・三次の集合地点
- 一次:自宅から最寄りの広場・公園・神社(屋外で安全確認しやすい)。
- 二次:主要駅の改札外や総合公園の中央広場など、分かりやすい目印がある場所。
- 三次:高台の広場や沿岸から離れた地域センター。広域避難の起点としても使える。
3-2.“会えない時の先回りルール”
- 到着→10分待機→移動。合流できないときは番号の大きい集合地点へ。紙面の番号を丸囲みして目立たせる。
- 張り紙の置き場:掲示板・ベンチ裏・案内板の陰など、雨に濡れにくい位置。名前・時刻・次の行き先を一行で書く。
3-3.連絡手段の優先順位
- 通話が混むときは短文の通信(文字)。要件→場所→時刻の順で簡潔に。
- 電波が弱いときは高所・開けた場所へ移動。地下・厚い建物は避ける。
集合地点の記入テンプレ
| 番号 | 名称/目印 | 住所/座標 | 滞在目安 | 設備/備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ○○公園 北門 | 〇〇市〇〇1-2 | 10分 | 屋根/手洗い/夜間灯 |
| ② | △△駅 西口像前 | 〇〇市〇〇3-4 | 15分 | 人混み注意/屋内退避可 |
| ③ | □□地域センター前広場 | 〇〇市〇〇5-6 | 20分 | 高台/夜間暗い/ベンチ有 |
3-4.置き手紙の書式(紙切れ一枚で伝わる)
氏名/時刻/今から向かう番号と名称/同行人数/体調
例:田中 14:30 ②西口像前へ 3名 体調良
3-5.集合地点の安全基準
- 水際・狭い路地・建設現場は候補から外す。車の進入が少ない広場を優先。
- 夜間は照明の有無・見通しを評価欄に記入。
4.方角・距離・地形を“読む技術”
4-1.方位をつかむ(太陽・地形・建物・磁石)
- 太陽:朝=東、昼=南、夕=西。影の向きで大まかな方角を把握。
- 地形:川は低地へ、等高線が密=急坂。谷筋の風は向きが安定しやすい。
- 建物:学校の校庭は南向きが多い。神社は正面が南東〜南のことが多い。
- 磁石(コンパス):地図の北矢印と合わせ、磁針が振れたら金属から離れる。
4-2.距離の見積もり(指幅・歩数・時間)
- 指幅:地図上の親指の幅=約1cmを基準に150〜500m(縮尺で調整)。
- 歩幅×歩数:距離=歩幅(m)×歩数。大人の歩幅は0.7〜0.8m。
- 時間換算:徒歩は3〜4km/h、自転車は10〜15km/hを基準に休憩込みで計算。
4-3.渡れない・通れないの判断
- 増水した川、水没アンダーパス、火災現場は一律回避。遠回りでも安全ルートへ切替。
- 立入禁止・封鎖の標示があれば最終ルートに移行。無理をしないが鉄則。
等高線と傾斜の目安
| 等高線の間隔 | 傾斜の体感 | 代替の考え方 |
|---|---|---|
| 広い | なだらか | メインで良い |
| 中程度 | 少しきつい | 休憩点を増やす |
| 密 | 急坂 | 遠回りでも勾配のゆるい道へ |
4-4.現地での“迷いにくい”動き方
- 曲がる前に地図を確認、曲がった後にもう一度確認。間違いに早く気づくため。
- 三叉路では直進と斜めの区別を地図の形で確認。建物の角を目印にする。
- 昼と夜で景色が変わる。看板の明かりや信号の位置をメモ。
5.地図キットを作る:持ち運びと更新
5-1.持ち物チェック(封筒1つで完結)
- 印刷地図(A4×数枚):メイン・予備・最終の3層+広域1枚。
- 油性ペン(赤/橙/黒)・鉛筆・消しゴム:雨でも消えにくい組合せ。
- 方位磁石・メモ用紙・小さな付せん:張り紙や伝言に使う。
- 透明袋(防水)と洗濯ばさみ:雨と風の対策。
- 小型ライト・反射しおり:夜間の読み取りを助ける。
5-2.更新頻度と見直しポイント
- 3か月に1回、工事/新設道路/通行止めを反映。更新日を余白に記入。
- 季節イベント(花火・祭り)や通学時間帯で混みやすい道を更新。時間帯別メモを追記。
- 家族構成の変化(通園・通学・介助の必要)で集合地点と休憩点を再検討。
5-3.配布と保管
- 家族全員に同じ地図セットを配り、玄関・通学かばん・車内に1部ずつ。表紙に連絡先、裏表紙に集合地点テンプレを印刷。
- 劣化した地図は次回更新で交換。旧版は赤斜線で無効化して混乱を防ぐ。
地図キット 内容一覧(テンプレ)
| 種別 | 枚数 | 中身 | 書き込み |
|---|---|---|---|
| 地図:メイン | 1 | 自宅〜主要目的地 | 赤実線・危険箇所× |
| 地図:予備 | 1 | バイパス・裏道 | 橙点線・立寄拠点□ |
| 地図:最終 | 1 | 高台・川沿い | 黒破線・広い歩道 |
| 広域図 | 1 | 市全域〜隣市 | 主要幹線・避難広域 |
| 集合地点表 | 1 | ①②③の詳細 | 変更日・設備 |
| 連絡先シート | 1 | 家族/学校/職場 | 変更日・当番 |
Q&A(よくある疑問)
Q1.印刷が面倒。スマホの地図だけでは?
A.通信と電源が前提のため、広域災害では弱点になります。紙は“最後の保険”。小さく折って常時携帯が安心です。
Q2.地図を読めない家族がいる
A.色と記号をそろえた書き込みと集合地点の番号順移動**を徹底すれば、読む力が弱くても再現できます。**線の種類(実線/点線/破線)**での識別も有効。
Q3.夜間は見づらい
A.小型の電池ライトと反射材のしおり**をセットに。文字は太く大きく、曲がり角には矢印を重ねると迷いにくい。
Q4.視力が弱い/色弱の家族には?
**A.**線種(実線/点線/破線)と形(○□×!)**で判別できるようにし、色に頼りすぎないルールにします。拡大印刷も検討。
Q5.雨で地図が破ける
A.耐水紙または透明袋**に入れて携行。油性ペンでの書き込みは雨に強い。
Q6.道が封鎖されていた
A.迷わず予備→最終**へ切替。張り紙で移動先を残し、三つ目の集合地点で合流を狙います。
用語辞典(やさしい言い換え)
縮尺:地図の縮み具合。1:25,000は地上の25,000分の1。
凡例:地図記号の説明表。自分の地図にも簡単な凡例を付ける。
等高線:高さが同じところを結ぶ線。密だと坂がきつい。
踏切:線路を横切る場所。詰まりやすい要所。
高台:まわりより高い場所。津波や浸水から避難するときの候補。
アンダーパス:道路が掘り下げられている低い通路。大雨で水がたまりやすい。
まとめ:同じ記号、同じ手順、同じ動き
紙の地図は“共通言語”です。 記号・色・線種を家族で統一し、メイン→予備→最終の順に誰もが同じ判断をできるようにしておけば、非常時の足並みは乱れません。印刷→書き込み→配布→更新を一度整えてしまえば、日々の移動も備えもぐっと楽になります。到達圏の同心円・集合地点表・置き手紙の書式まで一枚に載せ、“見れば動ける”紙を常備しましょう。