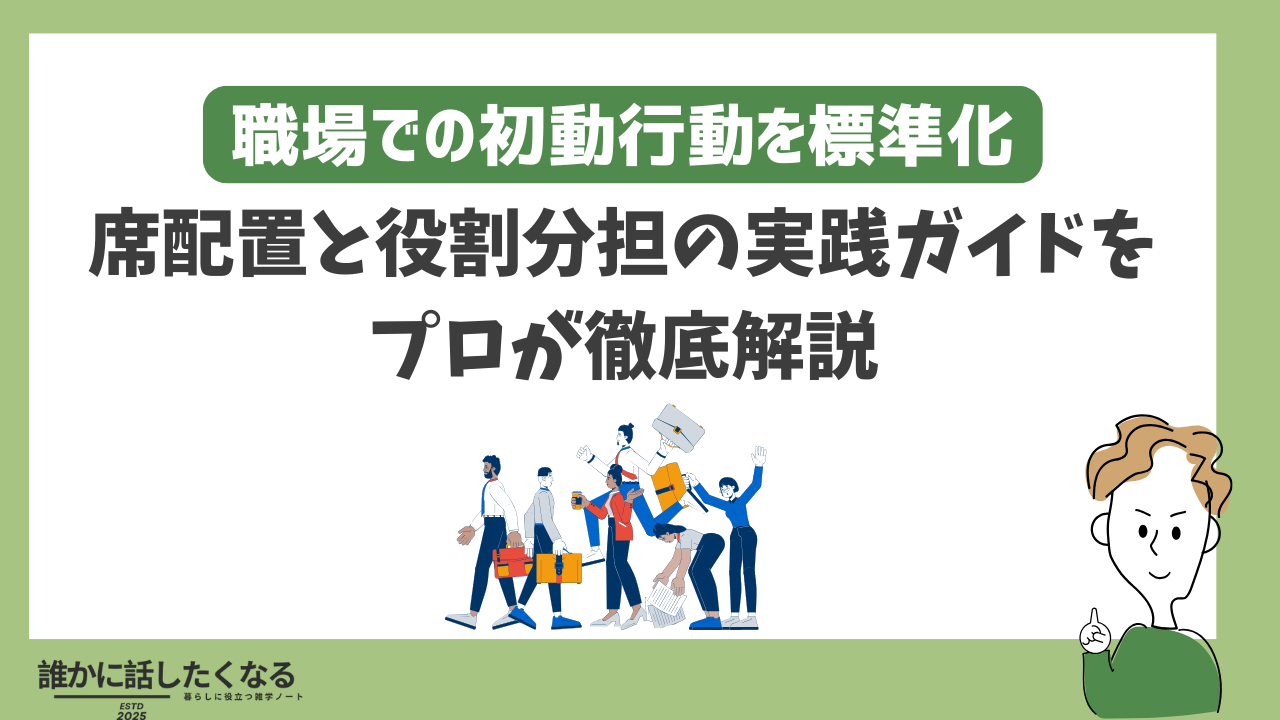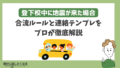「最初の10分」で、その日の被害と復旧スピードは大きく変わります。地震・火災・停電・通信障害・風水害など、突発事象に強い会社は、初動行動の標準化と席配置の設計、役割分担の明文化ができています。
本記事は、レイアウトの作り方から3分→10分→30分の手順、連絡テンプレ、訓練と備蓄の運用まで詳しくまとめました。小規模オフィス〜フロア複数の事業所まで対応できるよう、兼務のコツや在宅勤務者の扱い、来客・工事業者の安全まで踏み込みます。
1.まず結論:職場の初動行動を“見える化”する
1-1.初動の3本柱(安全→連絡→継続)
- 安全:人命最優先。姿勢を低く・頭を守る・二次災害を避ける。
- 連絡:点呼→被害共有→外部連絡を短文で。チャンネルは第一→代替→最終の順で切替。
- 継続:重要業務の最小限稼働を維持し、復旧計画へつなぐ。
1-2.標準化の要点(誰が・どこで・何分で)
- 誰が:役割カードを配布し、代理者まで決める(不在前提で設計)。
- どこで:避難場所・集合場所・臨時本部の三段構えを図で共有。
- 何分で:3分→10分→30分で達成目標と完了の合図を決める。
1-3.初動KPI(目標の見本)
| 時間 | 目標 | 完了のしるし | 担当 |
|---|---|---|---|
| 3分 | 安全確保・一次点呼 | 「A班10名全員無事」掲示 | 点呼役 |
| 10分 | 負傷/被害の把握・エスカレ | 被害表の共有完了 | 記録役・指揮役 |
| 30分 | 臨時本部立上げ・重要業務再開 | 当番表と連絡網の起動 | 指揮役・連絡役 |
1-4.レベル区分(社内発令の基準)
| 区分 | 状況の例 | 取る行動 | 解除の目安 |
|---|---|---|---|
| 注意 | 小さな揺れ・近隣停電 | 安全姿勢→簡易点呼 | 10分無被害で通常化 |
| 警戒 | 強い揺れ・設備停止 | 一次避難→全体点呼→連絡 | 設備復旧・安否完了 |
| 非常 | 火災・構造被害 | 退避→臨時本部→再配置 | 消防確認・立入許可 |
“最初の10分”を誰でも再現できるよう、フロア図・役割カード・短文テンプレをセットにするのがコツです。
2.席配置の最適化:通路・視線・動線で事故を減らす
2-1.基本レイアウト(通れる・見える・届く)
- 避難通路:90cm以上を確保。島間は120cmが理想。
- 視線:避難口・消火器・非常ベルが見える配置。背高家具で遮らない。
- 届く:救急箱・消火器は20m以内に1か所。AEDは出入口付近で人が集まる側に。
2-2.席の役割帯(フロント・ミドル・バック)
- フロント帯:受付・来客対応。声掛け役が座る。ビジターの退避案内を即実施できる位置に。
- ミドル帯:指示伝達・記録を担う記録役を配置。本部予定室に近いほど良い。
- バック帯:物資・機材に近い装備役が控える。倉庫・給湯室の鍵も管理。
2-3.障害物・落下物を減らす配置
- 高い棚は壁固定、重い箱は下段。通路上の延長コード禁止。
- 窓側の背高家具は30cm以上離間し、ガラス飛散の道を作らない。
- プリンター島は動線外へ移設。上部の物は置かない。
2-4.フリーアドレス運用のコツ(席が固定でない職場)
- フロアに役割台帳を一本。当番日の人は卓上カードを携帯。
- 島ごとに装備(懐中電灯・簡易笛・軍手・モバイル電源)を小分け配置。
- 朝礼で当日の代理者を宣言し、連絡先QRを配布。
2-5.配慮が必要な社員・来客の席
- 避難口近く・障害物の少ない席を優先。支援担当者も近くに配置。
- ビジターは受付で首下げカード+避難案内。集合場所の地図をカード裏に印刷。
席配置チェック表
| 項目 | 基準 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 避難通路幅 | 90cm以上 | 島間120cm理想 | |
| 消火器距離 | 20m以内/1台 | 壁表示あり | |
| 高棚固定 | 壁固定済 | アンカー番号記録 | |
| 窓側家具 | 離間30cm以上 | 飛散防止フィルム併用 | |
| AED位置 | 出入口付近 | 夜間も分かる札 | |
| 装備の分散 | 各島に小分け | 懐中電灯・軍手 |
3.役割分担の設計:3層×5役で抜けをなくす
3-1.基本の5役(小規模オフィス想定)
- 指揮役:全体の判断。避難・停電・退館などを決定。代理を必ず指名。
- 点呼役:点呼と安否表の作成。未返信者の追跡と再点呼も担当。
- 連絡役:社内外の連絡と記録。テンプレで短文送信し、時刻を明記。
- 装備役:救急・消火・AED。場所と鍵の管理。応急手当の呼びかけ。
- 記録役:時系列で行動を記録。被害表を更新。写真も添える。
3-2.拡張の2役(人数に余裕がある場合)
- 安全見回り役:廊下・階段・共用部の危険確認、来客誘導。
- 情報整理役:チャット・メール・電話の情報を整理して臨時本部へ要約。
3-3.3層体制(平時→初動→継続)
- 平時:教育・整備・訓練を担当。備蓄棚の期限を月次で点検。
- 初動(0〜30分):5役が近い席から順に起動。各自の安全確認→役割行動の順で。
- 継続(30分〜):交代表で休憩と復旧タスクを回す。在宅者は連絡役・記録役を支援。
3-4.代理・不在時の回し方
- 各役に代理1名。不在時は隣島が引き継ぐルールを掲示。
- 役割カードを卓上に立てる(色で識別)。首下げカードは移動時も見える位置に。
役割×作業早見表
| 役割 | 3分以内 | 10分以内 | 30分以内 |
|---|---|---|---|
| 指揮役 | 避難指示 | 被害判断・外部連絡許可 | 体制再編成・交代表決定 |
| 点呼役 | 点呼開始 | 安否表確定・未返信追跡 | 欠員補充・名簿更新 |
| 連絡役 | 内部チャット起動 | 外部先へ短文送信 | 重要顧客へ状況連絡・再送 |
| 装備役 | 救急箱/AED設置 | 小火の初期消火・止血 | 物資配布・休憩導線整備 |
| 記録役 | タイムライン開始 | 被害表更新・写真保存 | 報告書素案・改善点収集 |
| 見回り役 | 通路・階段確認 | 危険区画の封鎖 | 本部へ巡回報告 |
| 情報役 | 情報の重複排除 | 要約の掲示 | 関係者へ定時展開 |
4.初動手順を文章化する:3分→10分→30分テンプレ
4-1.共通の前提(3つの切替)
- 連絡手段の切替:社内チャット→SMS→固定電話→掲示板の順に落としどころを用意。
- 指揮系統の切替:指揮役→代理→総務責任者→現場最寄りの役職者。
- 場所の切替:自席→集合場所→臨時本部(会議室Bなど)。
4-2.3分(安全確保)
1)姿勢を低く、机の下で頭を守る
2)二次災害(火・落下・破片)から離れる
3)一次点呼:「A班10名、全員無事」
4)来客へ声掛け:「この場で低く、合図まで動かない」
4-3.10分(被害把握と連絡)
1)負傷・火気・設備を確認(電源・水・エレベーター)
2)安否表を更新(在宅者・外出者も記入)
3)外部短文:「無事/被害/次報時刻」
短文テンプレ(社外)
件名:本社 初動報 10:15
本文:人的被害なし。館内一部停電。次報10:45。
短文テンプレ(社内)
A班:全員無事。B班:1名救護対応。会議室Bに本部設置。
4-4.30分(臨時本部・継続運用)
1)臨時本部の設置(会議室B)
2)重要業務の最小稼働を決定(受注受付・保守窓口など)
3)交代表で休憩を回す。水・軽食の配布、トイレ導線の整理
4)訪問中の取引先に短文連絡:「安全確保済/退出案内の時刻」
4-5.事象別の注意点(地震・火災・停電・通信障害・風水害)
- 地震:エレベーター使用禁止。ガラス面から離れて移動。余震に備えて低い姿勢→待機。
- 火災:姿勢低く・口鼻を覆う。風上へ退避。防火扉は開放しない。
- 停電:非常灯・懐中電灯を即座に。サーバ・機器は記録役がシャットダウン手順をガイド。
- 通信障害:社内掲示板・紙の連絡票へ切替。集合時刻を決めて再集合。
- 風水害:窓から離れ、低層の浸水ラインを確認。帰宅指示は指揮役→全員へ一斉。
フロア図の凡例(掲示用)
| 記号 | 意味 | 補足 |
|---|---|---|
| ★ | AED | 出入口横に設置 |
| ■ | 消火器 | 20m以内配置 |
| ▲ | 非常口 | 通路幅90cm以上 |
| ● | 臨時本部 | 会議室B |
5.訓練・備蓄・見直し:続ける仕組みを作る
5-1.月例5分訓練(負担を小さく頻度を高く)
- ロールプレイ:指揮→点呼→連絡→装備→記録を持ち回り。
- 机上訓練:想定シナリオ(地震・停電・火災・風水害)を10分で回す。
- 抜き打ち:短文テンプレだけを日替わりで練習。時刻記入を徹底。
5-2.備蓄・装備の標準
- 救急箱・AED・消火器・懐中電灯・軍手を見える収納に。
- 簡易トイレ・飲料水・ブランケットは人数×3日分。非常食は半年でローテーション。
- モバイル電源と充電ケーブルを島ごとに配置。紙の名簿も常備。
- 工具(バール・カッター・結束バンド)を倉庫Bにまとめる。
5-3.振り返りと改善(事後10-24-72の節)
- 10分後:初動のできた/できないをメモ。
- 24時間以内:タイムラインと改善点を1枚にまとめる。
- 72時間以内:役割表・備蓄表を更新し、再訓練日を決める。
5-4.来客・工事業者・在宅勤務者の扱い
- 来客:受付が避難案内カードを渡す。集合場所を説明。
- 工事業者:責任者名と退避先を来館票に記入。火気作業は一時停止。
- 在宅勤務者:一斉メッセージ→未返信者へ電話→近隣確認の順。自宅の安全を優先。
備蓄チェックリスト
| 品目 | 基準量 | 期限 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 飲料水 | 1人1日3L×3日 | 備蓄棚A | |
| 簡易食 | 1人9食 | 備蓄棚A | |
| 簡易トイレ | 1人/日5回×3日 | 倉庫B | |
| ブランケット | 1人1枚 | 倉庫B | |
| 懐中電灯 | 各島1本 | 各島引出し | |
| モバイル電源 | 各島1台 | 充電ステーション |
Q&A(よくある疑問)
Q1.少人数の事業所では5役は多すぎませんか?
A. 兼務で構いません。指揮+連絡/点呼+記録/装備などに3役まで圧縮可能です。
Q2.障がいのある社員がいる場合の配慮は?
A. 支援担当者と避難補助具を事前に決め、席を避難口近くに配置します。
Q3.在宅勤務者の安否確認は?
A. 一斉メッセージ→未返信者へ電話→最終手段で近隣へ確認の順で。次報時刻を必ず書きます。
Q4.停電時の連絡は?
A. 携帯SMS・無線機・拠点電話の多重化を準備。紙の名簿も常備します。
Q5.机の下にもぐる必要はある?
A. 落下・飛散から守る最優先行動です。机が無ければ姿勢を低く、頭を守るが基本です。
Q6.エレベーターは使ってよい?
A. 不可。地震・火災時は停止・閉じ込めの恐れ。階段で手すり側を通行。
Q7.機密書類・現金はどうする?
A. 初動では人命優先。施錠だけ確認。収拾は安全確認後に行います。
Q8.取引先からの問い合わせ対応は?
A. 連絡役が短文テンプレでまず一報。「安全確保済/被害状況/次報時刻」で足並みをそろえます。
用語辞典(やさしい解説)
- 初動:発生から30分以内の最初の対応時間。
- 臨時本部:被害情報と指示を集約する仮の司令室。
- 安否表:在席・不在・負傷などを一覧にした表。
- KPI:達成度を測る目標指標。ここでは時間区切りの指標。
- 連絡テンプレ:決まった短文で伝える書き方。全員が同じ表現を使うための道具。
- 代理:本来の担当が不在のときに代わりに動く人。
まとめ
初動は安全→連絡→継続の順で進めます。席配置は通れる・見える・届くを基準に、役割分担は5役×3層で代理まで決める。3分→10分→30分のテンプレと月例5分訓練で、迷いをなくす。今日、役割カードとフロア図の凡例・連絡テンプレを印刷し、各席に置く——それが職場の強さを底上げします。