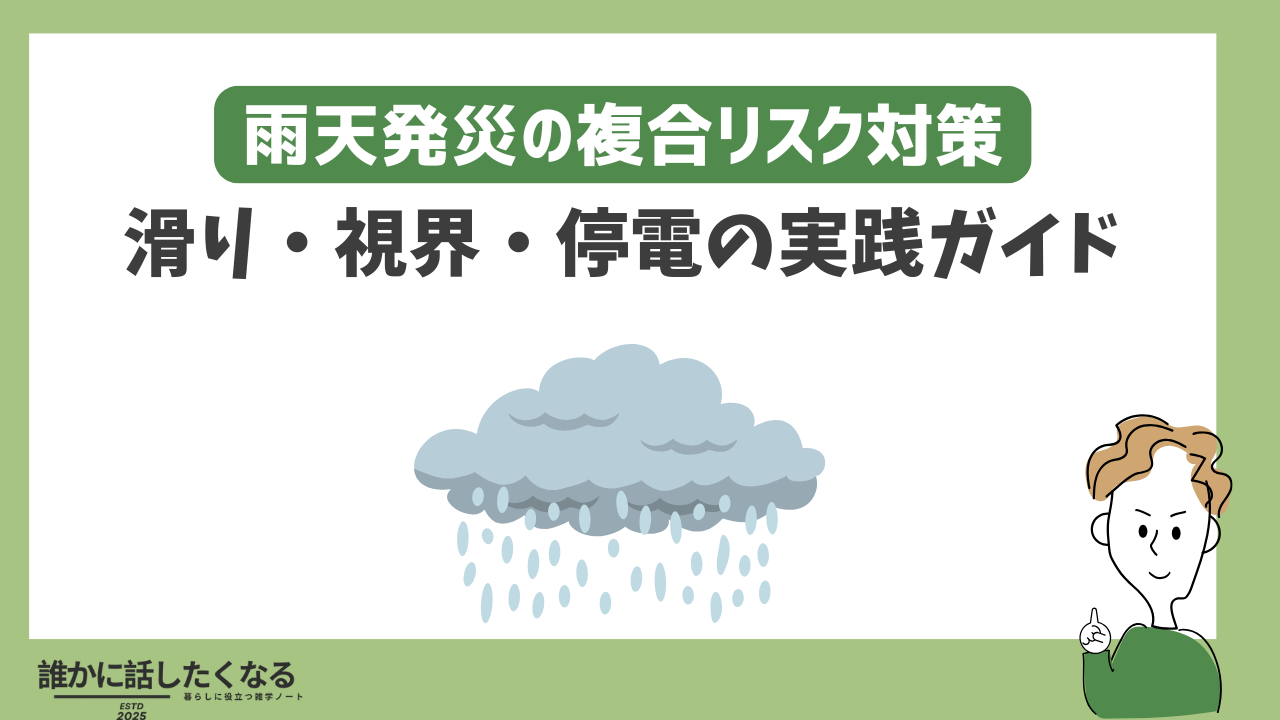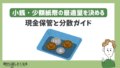要点先取り:雨の災害は“足元・見え方・電気”+体温・衛生で決まる
3本柱(滑り・視界・停電)を同時に管理し、2つの横糸(体温・衛生)を切らさない
雨天発災は、転倒(滑り)、見落とし(視界)、機能停止(停電)が連鎖して被害が拡大する。さらに体温の低下(低体温)と手指・目の衛生低下が合わさると判断力と体力が落ちる。
まずは玄関・通路・車・家電を前もって整備して「転ばない」「見える」「止まらない」を作る。そのうえで移動・屋内・車中・近隣連携それぞれの行動ルールを固定化すれば、当日の判断が速く、迷いが減る。
初動の7手(家族の合言葉)
1)足元:滑り止め靴・手袋、杖・傘の先端ゴムを確認。
2)視界:ヘッドライト+手持ちライト、反射材を手首・足首へ。
3)電気:モバイル電源・乾電池・懐中電灯を玄関下段に集結。
4)水:雨具の浸水チェック、替え靴下・タオルを人数分。
5)体温:薄手の防風上着とアルミ面ブランケットを1人1枚。
6)衛生:使い捨て手袋・拭き取り用ウェット・ごみ袋二重。
7)連絡:集合地点・連絡カードをポケット、耐水メモを玄関へ。
雨で“滑らない”家と通路づくり|玄関・屋外・車での足元対策
玄関・廊下の滑り対策(家の入り口を“乾燥地帯”に)
- 吸水マットを2枚体制(入口・内側)。入替用は洗濯済みを丸めて常備。
- 靴底ブラシ+水切りトレーを扉外/内に1つずつ。泥と水を家に持ち込まない。
- 段ボール・新聞紙を一時敷きして水だまりの拡大を防ぐ。
- 階段は一段目と踊り場に滑り止めテープ。手すりを必ず使う。
- 濡れ物動線(玄関→水切り→干し場)を一方通行にして交差をなくす。
屋外動線(家〜集合地点)を“転ばない設計”にする
- 側溝・マンホール・金属グレーチングは踏まない/跨がない。
- 白線・タイル・落ち葉では歩幅を狭く、重心をやや前に置く。
- 傘は短めで視界優先。レインポンチョ+つば付き帽子で両手を空ける。
- 荷物は前抱え禁止。背負うか体側に密着。片手を常に手すり・壁に使えるように。
足運び・姿勢の“コツ”
- 一歩を短く、接地は足裏全体→母指側へ。
- 下りは膝を軽く曲げて体重を落とす。上りはつま先で蹴らない。
- 転倒しそうな時はしゃがむ方向へ重心を落としてから手をつく。
車・自転車での足元(乗降・制動・握力)
- 車の乗降部に吸水タオル、ゴムマットで滑りを抑える。
- 自転車は制動距離が伸びる。金属板・白線は直進で跨ぐ。
- サドル・グリップの水分は袖やタオルで拭き取り握力低下を防ぐ。
- 靴底が磨耗していたら即交換。深い溝+柔らかゴムが基本。
路面別リスク早見表
| 路面 | リスク | 歩き方 | 回避策 |
|---|
| 金属ふた・グレーチング | 極めて滑る | 跨ぐ | 可能なら別ルート |
| 白線・タイル | 滑る | 小刻み歩行 | 白線外を選ぶ |
| 落ち葉・泥 | 滑る+沈む | 体重前寄せ | 土の少ない縁へ |
| 砂利・未舗装 | 不安定 | かかと短接地 | 杖・手すり活用 |
材料・道具の選び方(早見表)
| 用途 | 推奨 | NG/注意 |
|---|
| 靴 | 深い溝・柔らかゴム底 | 革底・摩耗スニーカー |
| 手袋 | 滑り止め付き | 素手・布薄手のみ |
| 傘 | 視界広・風抜き | 重く視界を遮る型 |
| 玄関マット | 吸水速乾・裏面滑り止め | 薄い布1枚 |
60秒ミニ訓練(家族で月1回)
1)玄関で靴底ブラシ→水切り→吸水マットの順に歩く。
2)白線・タイルを模したテープ区間を小刻み歩行で通過。
3)しゃがむ→立つを3回練習し、重心の落とし方を体で覚える。
雨で“見える”を保つ方法|視界・合図・灯り・眼の衛生
二灯+反射で“見える/見られる”を同時に確保
- ヘッドライト(拡散光)+手持ちライト(スポット)で足元と先を同時照射。
- 反射ベスト・バンドは手首・足首・リュックの肩紐に。
- 傘の外周やポンチョ裾にも反射テープを一本追加。
眼鏡・マスクのくもり対策
- くもり止め→軽く拭き上げ、鼻ワイヤ密着で上方曇りを減らす。
- 雨粒は“払う→拭く”の順。乾拭きで傷を付けない。
- 視界が悪化したら迷わず立ち止まる→**音(車・水)**で周囲確認。
合図のルール(家族・近隣で統一)
- 笛1長=集合、3短=助けて。
- ライト2回点滅=合流、連続点滅=危険。
- 耐水メモに「山田 14:30 公園へ」など移動先と時刻を残す。
自動車・自転車の被視認性を上げる
- 車はフォグ+ワイパー早め、冠水路は進入しない。
- 自転車は前後灯+反射板を高めの明るさで。レインカバーで灯りを覆わない。
- 車内ガラス内側の油膜は定期除去で曇りを予防。
視界・合図・灯りのチェック表
| 目的 | 手段 | 予備 | 点検 |
|---|
| 足元 | ヘッドライト | 電池/充電池 | 月1点灯 |
| 前方 | 手持ちライト | 小型を2本 | 月1点灯 |
| 目立つ | 反射材 | 追加テープ | 半年交換 |
| 眼の衛生 | 人工涙液 | 個包装数本 | 期限確認 |
停電に“止まらない家”を作る|電源・調理・通信・冷蔵の継続手順
電源の底上げ(まず安全、次に配分)
- モバイルバッテリー×家族人数(最低1台/人)。夜間はライト優先。
- ポータブル電源は定格出力・容量を本体にラベル。冷蔵庫・通信・照明の優先順位を決める。
- 延長タップは難燃・雷ガード。濡れ手厳禁、足元に水たまり厳禁。
家電ごとの“雨・停電モード”
| 家電 | 雨の日の注意 | 停電時の運用 | 優先度 |
|---|
| 冷蔵庫 | 扉開閉最小 | ポータブル電源→保冷剤で補助 | 高 |
| ルーター | 高所で水回避 | 予備電源→必要時のみ通電 | 中 |
| 洗濯機 | 漏電の恐れで停止 | 復電後に槽洗浄 | 低 |
| 照明 | ろうそく原則不可 | LEDランタンを部屋ごと | 高 |
照明・調理・通信の代替
- 照明:面発光ランタンを各部屋1台。吊り下げ場所を決めておく。
- 調理:カセットコンロ+ボンベ3本/週を目安。換気・耐熱ボードを準備。
- 通信:乾電池/手回しラジオ、スマホは省電力、充電は優先デバイスから。
電力配分の目安(例)
| 用途 | 消費の目安 | 1日あたりの運用例 |
|---|
| スマホ2台充電 | 10〜20Wh | 充電は昼間にまとめて |
| ルーター | 5〜10Wh/h | 連絡時のみ稼働 |
| LEDランタン | 5Wh/h | 就寝前後の短時間のみ |
| 冷蔵庫 | 50〜100Wh/h | 開閉最小+保冷剤で補助 |
感電・漏電の予防(雨ならでは)
- コンセントに防水キャップ、床近くは延長し高所へ退避。
- ブレーカーの場所と落とし方を家族で共有。
- 濡れた延長コードは使用中止→乾燥後点検。
状況別の動き方|徒歩・車・屋内・避難所・工事現場周辺・通学路
徒歩移動(子ども・高齢者・妊婦)
- 2人1組で歩く。歩幅は狭く、手すり・壁沿いを選ぶ。
- ベビーカーは補助にとどめ、背負子+親ザックが主力。
- 杖先ゴムの摩耗を確認、滑り止め付手袋で支えを持つ。
- 替え靴下で足の冷えを防ぎ、低体温を避ける。
車移動(やむを得ない場合)
- 冠水路・アンダーパスは進入禁止。
- ワイパー・タイヤ溝・ライトは月1点検、ゴムは季節前に交換。
- ポンピングブレーキを意識し、急ハンドル・急加速を避ける。
- 停車時はハザード+後方反射三角で被視認性を上げる。
屋内・避難所運用(濡れと人流を切り分ける)
- 濡れ物動線(入口→水切り→干し場)を1本に固定。
- 床は“入口から奥へ”一方向拭きで滑り水を広げない。
- 寝場所は出入口と水場から離す(人流と水気の交差を避ける)。
- 電源タップは腰高以上、コードは人流の外側を這わせる。
工事現場・看板・樹木周辺(近づかない)
- 足場・仮設塀・看板の風倒に注意。
- 街路樹の根元はぬかるみ+倒木の二重リスク。
- ビニールハウス・波板屋根の破片飛散を想定し、風下を避ける。
通学路・帰宅路の再設計(雨専用ルート)
- 橋・地下道・川沿いを避け、高い道へ。
- 30分ごとに屋根・トイレ・水の三点がある道を選ぶ。
- 一次→二次→最終集合の三段構えで合流しやすくする。
事前準備・点検カレンダー・Q&A・用語辞典
事前準備チェック(家/職場/車)
| 場所 | 物品 | 個数 | 点検頻度 | メモ |
|---|
| 家 | 吸水マット/玄関 | 2 | 月1 | 予備を丸めて保管 |
| 家 | LEDランタン | 部屋数 | 月1(点灯) | 吊り下げ場所固定 |
| 家 | カセットボンベ | 3本/週分 | 季節前 | 使用期限を記入 |
| 職場 | 反射ベスト/笛 | 1/人 | 半年 | ロッカー上段 |
| 職場 | ヘッドライト | 1 | 月1 | 乾電池同梱 |
| 車 | 三角反射板/非常信号灯 | 各1 | 半年 | 取り出し位置を統一 |
| 車 | 雨用ゴムマット | 1式 | 汚れ時 | 足元を乾燥保持 |
72時間タイムライン(例)
| 時間 | 重点 | 具体行動 |
|---|
| 発災0〜6h | 安全確保 | 足元・視界・電源の三点を起動、家族合流 |
| 6〜24h | 生活維持 | 雨専用ルートで移動、冷蔵庫は開閉最小 |
| 24〜72h | 体力維持 | 休息・保温・衛生を優先、電力配分を見直し |
よくあるQ&A(実践編)
Q1.長靴と防水スニーカー、どちらが安全?
A.水深が足首以上=長靴、舗装・軽い雨=溝の深い防水スニーカー。滑りやすさは靴底パターンで決まる。
Q2.懐中電灯はスマホのライトで十分?
A.両手が空くヘッドライトが基本。スマホの電池は通信に残す。
Q3.停電で冷蔵庫はどれくらい持つ?
A.開閉最小+保冷剤で数時間〜半日が目安。優先食材から消費。
Q4.傘とレインポンチョはどちらを持つ?
A.移動主体ならポンチョ+つば付き帽子で両手を空け、傘は風が弱い場面で補助。
Q5.車での水たまり走行は?
A.避ける。やむを得ない場合は低速直進・急ブレーキ禁止、対向車の波にも注意。
Q6.視界が急に白く曇った。
A.立ち止まってくもり止め→マスク鼻ワイヤ密着。無理に歩かない。
Q7.雨で体が冷えた。
A.濡れた靴下・上着を交換、風を止める外衣+ブランケットで体幹を温める。
Q8.電源が足りない。何を切る?
A.照明と通信を優先し、常時不要家電は切る。ルーターは連絡時のみ通電。
Q9.反射材はどこに貼るのが効く?
A.動く部位(手首・足首)+肩・背中。傘の外周にも一本。
Q10.避難所で濡れ物をどう管理?
A.入口→水切り→干し場を決め、一方通行で動かす。床は一方向拭き。
用語辞典(やさしい言い換え)
- 滑り止めテープ:階段や床に貼るザラザラ。濡れても滑りにくい。
- 反射材:光を返す素材。車や自転車から見つけてもらうためのもの。
- 面発光ランタン:広く明るい灯り。テントや部屋に向く。
- 冠水路:水で道が見えない場所。穴や段差が隠れて危険。
- アンダーパス:地下に潜る道路。水がたまりやすい。
- ポンピングブレーキ:小刻みに踏む方法。滑りを抑える。
- 低体温:体温が下がり動けなくなる状態。濡れたままが原因。
- 被視認性:周囲から見つけてもらいやすさ。反射材で上げる。
まとめ
雨天発災は滑り・視界・停電の三つを同時にさばき、体温・衛生を切らさないことが本質だ。足元を整える家と通路、見える装備と合図、止まらない電源と代替手段を平時から固定化すれば、当日の判断は驚くほど軽くなる。今日、玄関マット2枚体制・二灯照明・予備電源をそろえ、歩く・照らす・通電の手順を家族カードに書き、玄関下段に貼っておこう。