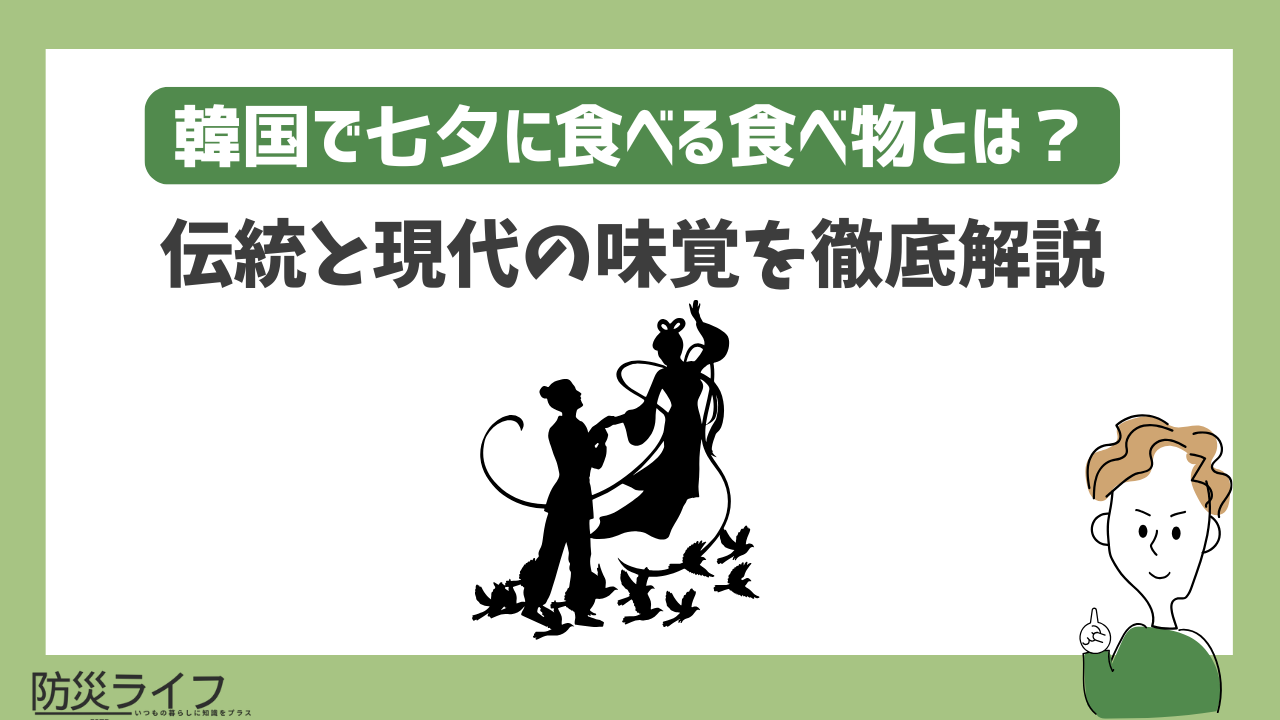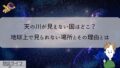七夕(칠석/チルソク)は、織女(직녀)と牽牛(견우)の物語に寄りそいながら、無病息災・家内安全・五穀豊穣を祈る日です。韓国では旧暦七月七日にあたり、雨や露、川の水など天の水を尊びつつ、小豆粥・小麦の薄焼き・七種の野菜など意味を込めた料理を囲みます。
本稿は、由来→代表料理→材料の意味→地域差→現代の工夫の順に、由緒と実用を一体で解説。作り方の要点・代替案・献立例・保存法まで網羅し表・Q&A・用語集も収録しました。
1.韓国の七夕(칠석)とは——意味と祈りのかたち
1-1.起源と伝来——乞巧奠が育んだ女手の祭り
七夕は中国の乞巧奠(きっこうでん)が源流で、手仕事の上達を願う行事でした。韓国でも早くから宮中や士族の家で行われ、機織り・裁縫・書の上達、そして学業成就を願う日として、しだいに民間へ広がりました。夜には星を仰ぎ、**ベガ(織女)とアルタイル(牽牛)**をたどって願いを言葉にします。
1-2.祈りの幅——恋の物語を超え、暮らしを守る日
七夕は恋の伝説だけではありません。健康・家族の安寧・作柄を気づかう日であり、赤いもの(小豆)で厄をはらい、旬のもの(ナムル)で体を整えるという、食の作法に祈りが宿ります。祖先への礼(祭祀)を重んじる家では供物として整え、のちに家族で分かち合います。
1-3.旧暦と季節の肌ざわり——麦と雨の節目
旧暦の七夕は梅雨明け前後。新麦への感謝と、暑さで弱りがちな胃腸をいたわる献立が理にかないます。雨は清めと恵みの象徴とされ、しとしと降る雨を吉兆と捉える土地もあります。
1-4.星と水の作法——天と地をつなぐ所作
川や井戸に向かって軽く拝し、その年の清き水をいただく所作が各地に残ります。髪や針を整える所作、手仕事の道具を清める所作など、技の向上と結びついた細やかな習わしも七夕ならではです。
1-5.家で整える基本の段取り
前夜に小豆を下ゆでし、朝に薄焼きの生地を仕込み、夕方に七種の野菜をゆでて和える——この三拍子で、無理なく伝統の骨格を守ることができます。
【表1】七夕の歩みと要点(韓国の受容)
| 時代 | 主な担い手 | 行事の核 | 食の要点 |
|---|---|---|---|
| 古代~中世 | 宮中・士族 | 手仕事の上達、星見 | 小豆粥・小麦料理 |
| 近世 | 都市と農村 | 家内安全、豊穣祈願 | 供物と家族の食卓 |
| 近代~現代 | 広く一般 | 健康・学び・家族行事 | 簡素化と継承の両立 |
2.七夕の代表料理——三つの柱で整える(作り方の勘どころ付き)
2-1.칠석팥죽(チルソク・パッチュク)——小豆粥で厄をはらう
赤い小豆を煮といた行事粥。赤は魔除けの色とされ、無病息災を願って食します。やさしい甘みの砂糖仕立て、塩をきかせた塩味仕立てなど家ごとの味があり、胃腸を温めて夏ばて予防にも役立ちます。
- 作り方の要点:小豆を一度ゆでこぼし渋を抜き、弱火でふくふくと割れるまで煮る。米あるいは餅玉を加えてとろみを合わせ、塩または砂糖で整える。仕上げに塩少々を打つと味が締まります。
- 甘味/塩味の分岐:甘味は砂糖・はちみつ、塩味は胡麻塩・ごま油一滴で香りを添えると満足感が増します。
- 保存:粗熱をとり小分けで冷蔵2日、冷凍2~3週間が目安。
2-2.밀전병(ミルジョンビョン)——小麦の薄焼きで五穀に感謝
小麦粉を水でのばし薄く焼いた皮で、ねぎ・にら・薬味などを包む素朴な一皿。巻物の形は願いを巻き込む象徴ともいわれます。麦の収穫どきに合わせた豊作祈願の料理です。
- 作り方の要点:小麦粉・水・塩少々を混ぜてなめらかな生地にし、薄く油をひいた鉄板で皮を焼く。具は軽く塩ゆでまたは炒めて冷まし、温かい皮でやさしく巻くのが割れ防止のこつ。
- 具の例:にら・ねぎ・じゃがいも千切り・豆腐そぼろ・ささ身など。辛味控えめでも満足感を出せます。
- 保存:皮は重ねて布で包み乾燥を防ぐ。翌朝は軽く蒸して復活。
2-3.칠석나물(チルソク・ナムル)——七種の青味で体をととのえる
旬の七種類をめどにした和え物。胡麻油・塩・にんにくなどで軽く味つけし、体に負担の少ない調理で栄養を取り入れます。何を七種とするかは地域と家の知恵が光ります。
- 選び方:色・食感・香りが重ならないよう、葉・根・豆・山菜を織り交ぜる。
- 下ごしらえ:さっとゆでて冷水に取り、水気をしっかり切る。味は薄めにして並べ、食卓で塩ひとつまみで調整すると全体がまとまります。
※済州島の**오메기떡(オメギトク)**は地域章で詳述します。
【表2】七夕の主な料理と込める願い・作り方の勘どころ
| 料理名 | 概要 | 込める願い | 勘どころ |
|---|---|---|---|
| 칠석팥죽(小豆粥) | 小豆を煮とろりと仕立てる粥 | 魔除け、無病息災 | 渋抜き→弱火→塩で締める |
| 밀전병(薄焼き) | 小麦の皮で具を巻く | 五穀豊穣、学び成就 | 皮は温かいうちに巻く |
| 칠석나물(七種) | 旬の青味を七つ | 体調を整える、自然への感謝 | 色と食感の取り合わせ |
3.材料に宿る意味——色・穀・青味の三拍子(栄養と代替の知恵)
3-1.小豆(팥)——赤で厄をはらい、胃腸をいたわる
赤は災いを退ける色。小豆は利水にも通じ、むくみや冷えが気になる時季に向きます。粒を残すと食べ応え、こすとのど越しが良くなります。苦手な人は白小豆やかぼちゃを合わせると食べやすくなります。
3-2.小麦(밀)——収穫への感謝と力の糧
麦は勤しみの実りの象徴。薄焼きは油を控えつつ腹もちがよく、働く体を支える主食になります。小麦が合わない人にはそば粉・米粉の薄焼きが代替になります。
3-3.七種の野菜(나물)——土と体の対話
豆もやし・ほうれんそう・つるむらさき・きゅうり・ぜんまい・人参・大根など、その土地の旬を七つほど。彩りは青・白・橙・緑・褐を意識し、目で食べる楽しみも大切にします。油は胡麻油のほかえごま油も合います。
3-4.香りと調味——少ない材料で満足感を出す
塩・醤(ジャン)・胡麻・にんにくを均衡よく。辛味を立てずとも、香りと温冷の対比で満足感が生まれます。年配者や子どもには酢少々で後味を軽くするのも手です。
【表3】材料の象徴と体への働き(めやす)
| 材料 | 象徴 | 体への働き | 合わせたい調理 | 代替候補 |
|---|---|---|---|---|
| 小豆 | 魔除け | 胃腸を温め、利水 | 粥、ぜんざい風 | 白小豆、かぼちゃ |
| 小麦 | 五穀豊穣 | 主食の力、腹もち | 薄焼き、蒸しもの | そば粉、米粉 |
| 七種の野菜 | 自然との調和 | ビタミン・繊維補給 | 和え物、さっとゆで | 季節の青菜で置換 |
| 胡麻・胡麻油 | しなやかさ | 香り・抗酸化 | あえ衣・仕上げ | えごま油 |
4.地域ごとの味と作法——土地が生む多彩さ
4-1.首都圏と地方——暮らしに合わせた簡素と本格
都市部では簡素に三品を整える家が多く、地方では祖先祭祀と一体の本格仕立てが残ります。家伝の手順が受け継がれるのも地方の強みです。供物は端正に少量ずつ、食卓では皆で分かつのが基本です。
4-2.済州島の오메기떡(オメギトク)——よもぎ香る島の餅
もち米・よもぎで作る島の餅。祖先への供物として供え、のちに家族で分かちます。黒糖・きなこをまぶす家もあります。海風の土地ならではの素朴で力の出る甘味です。七夕に添えることで祖霊の加護を願います。
4-3.北と南のナムル——味つけの違い
北はあっさり塩味、南は唐辛子を少量きかせる傾向。にんにく量や胡麻油の強さも土地で変わり、同じ七種でも風土の香りが立ちのぼります。山間部では山菜が増え、沿岸では海藻が添えられることも。
4-4.行事と市場——七夕前日の買い物風景
市場では新小豆・新麦・旬菜が並びます。小豆は粒が揃い、皮はりの良いものを、野菜はみずみずしさを選びます。薄焼きの皮は地粉を使うと香りが立ちます。
【表4】地域別・七夕料理の違い(例)
| 地域 | 主な料理の姿 | 味つけの傾向 | 行事との結びつき |
|---|---|---|---|
| 首都圏 | 三品を簡素に | 薄味・素材重視 | 家族の夕餉中心 |
| 農村部 | 粥・薄焼き・七種+供物 | 塩味しっかり | 祭祀と一体 |
| 済州 | オメギトクを供える | 甘味と香草 | 海の安全祈願 |
| 北部 | あっさりのナムル | 塩・胡麻油控えめ | 夏の疲れとり |
| 南部 | からみのナムル | 唐辛子少量 | 食欲増進 |
5.現代の七夕献立——家で無理なく続く工夫(時短・保存・盛りつけ)
5-1.時短と下ごしらえ——三つの要
(一)前夜に小豆をゆで置き、冷蔵。(二)薄焼きの生地を作り置き、朝焼いて冷ます。(三)ナムルはゆでて水気を切り、食べる直前に和えます。これで三十分仕上げが可能です。忙しい日はレトルトの小豆を塩で整えるだけでも所作は守れます。
5-2.行事食×喫茶の楽しみ——見た目もごちそう
小鉢を七色で並べ、星形の人参を添えるだけで晴れやかに。七夕かざり代わりに、糸巻きの箸置きや星の折り紙を置くと、子どもも喜びます。飲み物は麦茶やよもぎ茶がよく合います。
5-3.からだ思いの献立例——温と冷の呼吸
温(小豆粥・にゅうめん)で胃腸を守り、冷(胡瓜のナムル)で火照りをさます。生姜と紫蘇を少量きかせ、香りで食欲を呼び戻します。食後は果物少々で口をさっぱりと。
5-4.保存と翌日の楽しみ
小豆粥は冷やし粥にして朝食へ。薄焼きは再蒸しでやわらかさ復活。ナムルは軽く炒め直して混ぜご飯に。無理なく翌日へつなぐ工夫が、行事を暮らしへ根づかせます。
【表5】一汁二菜・七夕の献立(めやす)
| 位置づけ | 料理 | ねらい | 代替案 |
|---|---|---|---|
| 主 | 小豆粥(塩味) | 胃腸をいたわる、厄よけ | かぼちゃ粥、白小豆粥 |
| 副1 | 七種のナムル | 栄養の底上げ、彩り | 四種でも可、海藻を一品 |
| 副2 | 小麦の薄焼き | 主食の力、満足感 | 米粉・そば粉の薄焼き |
| 甘味 | よもぎ餅(地域に応じて) | 祖先への感謝、しめ | きなこ餅、黒糖蒸し |
よくある質問(Q&A)
Q1:旧暦の七夕はいつ?
年によって異なりますが、おおむね八月ごろです。地域の案内でご確認ください。
Q2:七種の野菜は決まりがある?
特定の決まりはありません。その土地の旬を七つほど選びます。豆もやしと青菜は定番です。
Q3:小豆が苦手な家族がいる場合は?
白小豆やかぼちゃ粥に置き換えたり、塩味のさらり粥にすると食べやすくなります。甘味が苦手なら塩ひとつまみで締めるとすっきり。
Q4:辛味を控えたい場合のナムルの味つけは?
塩・胡麻油・酢少々でさっぱりまとめ、にんにくは控えめに。香りづけは炒り胡麻で十分です。
Q5:オメギトクはどこで手に入る?
済州の菓子店や土産店にあります。家庭ならよもぎ団子で代用しても雰囲気が出ます。
Q6:前日にどこまで準備できる?
小豆の下ゆで、薄焼きの生地づくり、ナムルの下ゆでまで。仕上げの和えは当日が香り高いです。
Q7:小麦を避けたい場合は?
米粉・そば粉で薄焼きを。粘度は水分で調整し、焼き面を乾かしすぎないことがこつです。
Q8:供物の盛りつけの作法は?
端正・少量・対称を心がけ、置いた順を覚えておくと片付けも丁寧にできます。のちに皆で分かつのが基本です。
Q9:雨の日の楽しみ方は?
雨音の時間を設け、星物語や昔話を朗読。室内の灯りを落とし、食卓を七色で整えると、雨ならではの静けさが行事を深めます。
Q10:翌日に持ち越しても大丈夫?
小豆粥は再加熱すれば風味が戻ります。ナムルは水気をしっかり切って保存し、食べる直前に香り油を足します。
用語の小辞典(やさしい言い換え)
- 칠석(チルソク):旧暦七月七日の行事。七夕。
- 팥죽(パッチュク):小豆の粥。厄よけの色とされる赤が目印。
- 밀전병(ミルジョンビョン):小麦の薄焼きで具を巻く料理。
- 나물(ナムル):野菜の和え物の総称。ゆでて水気を切り、軽く味つけする。
- 오메기떡(オメギトク):済州島のよもぎ餅。供物としても用いる。
- 祭祀(チェサ):祖先に供え、感謝を伝える家の行事。
- 乞巧奠(きっこうでん):手仕事の上達を願う古い祭り。七夕の源流。
- 天の水:雨・露・川や井戸の清き水。清め・恵みの象徴。
- 醤(ジャン):味噌・醤油など発酵調味の総称。
- えごま油:えごまの種から搾る香りの油。仕上げに少量。
まとめ
韓国の七夕料理は、色(赤)・穀(麦)・青味(野菜)の三拍子で、厄をはらい、収穫に感謝し、体を整える知恵のかたまりです。伝統の骨格を守りながら、暮らしに合わせて簡素に整えることができます。小豆をことこと、薄焼きをさっと、七種をしゃきっと——祈りが食卓に宿る一日を、今年も静かに味わいましょう。