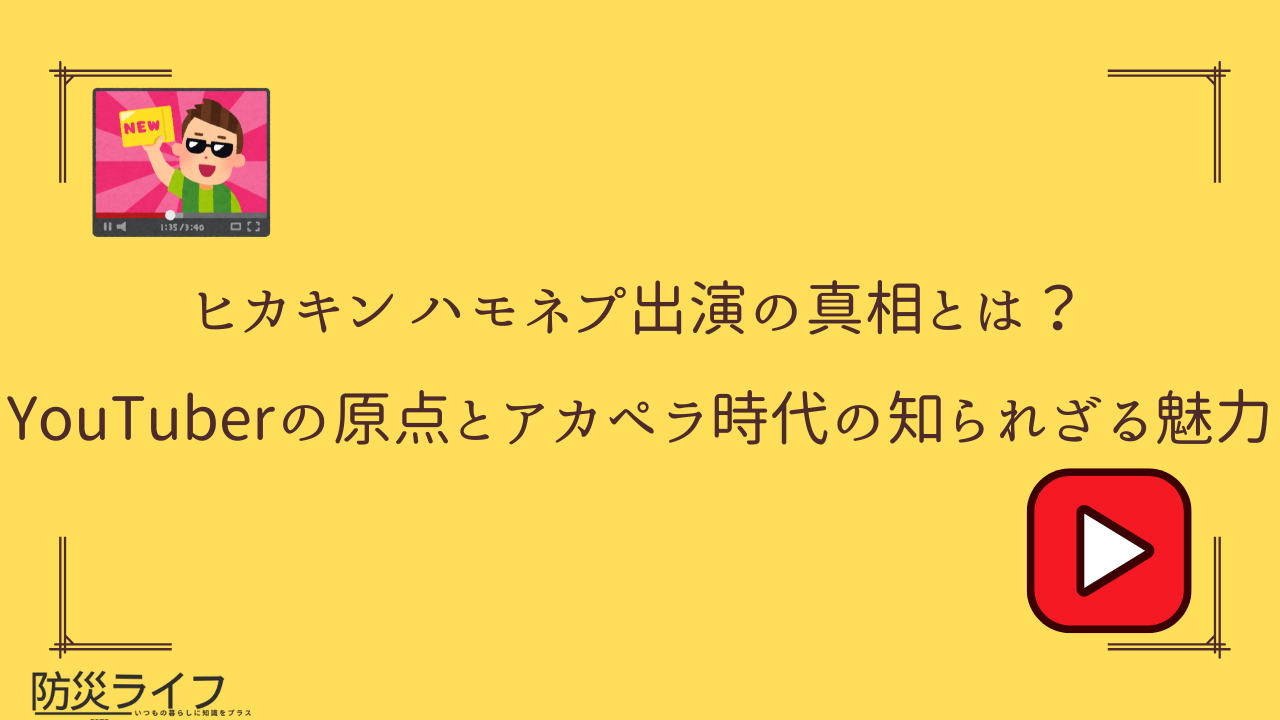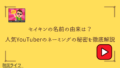登録者1,000万人超のトップYouTuber・ヒカキンの原点には、まぎれもなく「音楽」がある。 その象徴が、高校時代の**『ハモネプ』出演と、アカペラグループ「エアメール」での研鑽だ。
本記事では、出演の背景/当時の演奏/グループ内の役割/現在の動画づくりへの影響/テレビと配信のちがいに加え、準備の舞台裏・練習法・機材の基本・安全と権利の心得・実践テンプレまで踏み込み、表・時系列・チェック表で立体的に解説する。
1.ヒカキンとハモネプの関係とは?|音楽が生んだ青春の第一歩
1-1.高校時代、全国放送に挑む
新潟の高校に在学中、ヒカキンはアカペラ番組『ハモネプ』に挑戦。地元での練習を重ね、全国に声で勝負する舞台へ足を踏み入れた。これはのちの動画活動に通じる**「まずやってみる」行動力**の出発点である。
1-2.『ハモネプ』とは何か
学生を中心とした声だけの合唱・重唱で競う人気番組。楽器を使わず、**主旋律・ハモり・ベース・打楽器役(口の打楽器)**を分担し、声の重なりで曲を立ち上げる。青春の熱気がそのまま映る場で、技術だけでなく物語性も問われた。
1-3.番組内で光ったボイスパーカッション
ヒカキンは**口の打楽器(ボイパ)**を担当。キック・スネア・ハイハット・シンバル風音を切れよく切り替え、止める音(無音の間)も響きの一部として使い、演奏全体の押し引きを作った。
1-4.舞台裏の準備:当日の体と心を整える
- 発声と呼吸:短い息の連続と深い息を交互に行い、長く続けられる息を確保。
- 口まわりのほぐし:くちびる・舌・あごをやさしく回し、音の出だしを安定させる。
- 緊張の管理:手のひらを開閉、足裏で床を感じる。体感の安定が声の安定になる。
1-5.選曲の考え方:見せ場を先に決める
- 最初の20秒で伝えたい見どころを用意。
- 中盤に小さな山を2〜3回。
- 終わりの一押しとして、全員で止める間を合わせる。
当時の基本情報(整理表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 立場 | 高校生・アカペラ出場者 |
| グループ名 | エアメール |
| 担当 | 口の打楽器(ボイスパーカッション) |
| 見どころ | 細かな刻みと止めの妙、舞台での度胸 |
2.グループ「エアメール」の実像|チームと個の成長
2-1.名の由来と目指した音
「エアメール」には、『声をはがきのように遠くへ届けたい』という願いがこめられていた。ことばの壁を越える音の空気感を大切にし、明るい響きと物語性を両立させた選曲が多かった。
2-2.ヒカキンの役割と音づくり
彼は土台の拍を支えるだけでなく、効果音・環境音まで口で描き、「場面転換」を音で示す役も担った。細かな息のコントロールと音の止め方が演奏の立体感を生む核だった。
2-3.地元での反響と学び
地方紙や地域番組で取り上げられる機会も増え、応援してくれる目を意識しながら練習量が増した。本番で実力を出すための体調管理や、チーム内の声がけなど、舞台以外の学びも大きかった。
2-4.練習の組み立て(一般例)
- 単音の整え:キック・スネア・ハイハットを別々に。
- 連続の整え:ゆっくりから始め、止めの合図を全員で共有。
- 通し練習:本番さながらに入場→曲→礼の流れを確認。
2-5.曲目の選び方の基準
| 観点 | 目安 | ねらい |
|---|---|---|
| 音域 | 主旋律が無理なく歌える | 無理のない声量で安定 |
| 物語 | 見せ場が明確 | 観客の集中を保つ |
| 団結 | 役割が均等 | 誰かに負担が偏らない |
エアメールの役割分担(例)
| パート | 内容 | ねらい |
|---|---|---|
| 主旋律 | 曲の中心となる歌い手 | 物語の軸を伝える |
| ハモり | 和音を重ねる | 幅と厚みを作る |
| ベース | 低音で安定を作る | 曲の重心を下げる |
| 口の打楽器 | 刻み・効果音 | 躍動と静寂の設計 |
3.ビートボックスからYouTubeへ|音→映像へ進化した創作力
3-1.独学で磨いた技術
番組出演を機に、ヒカキンは海外の演奏映像や録音を参考にしながら独学を深め、音の分離(キックとハイハットを同時に出さない)や舌の弾き方など基礎を鍛えた。毎日短くても継続する練習法が柱となった。
3-2.転機となったゲーム音再現
投稿作**『Super Mario Beatbox』は、遊び心と技術が同居する代表作。おなじみの音を口で再現しつつ、間の取り方で笑いと驚き**を生み、世界の視聴者に届いた。
3-3.音楽の知見を動画編集へ
リズム感=編集のテンポ、音の止め=画の切り替えへと置き換え、見せ場の前に静けさを置くなど、音楽の作法を動画構成へ応用した。テロップや効果音の入れどころにも拍の意識が生きている。
3-4.初期の投稿戦略:短く濃く、先に見せ場
- 最初の10〜15秒で目玉を提示。
- 一本一本に役割(笑い/驚き/役立ち)を付ける。
- 終わりに次の一本の橋渡しを置く。
3-5.つまずきから学んだこと(一般化)
| つまずき | よくある原因 | 立て直し |
|---|---|---|
| 途中離脱 | 見せ場が遅い | 冒頭の見どころを前倒し |
| 音割れ | 音量の上げすぎ | 口とマイクの距離を安定 |
| 伝わらない | 専門用語が多い | やさしい言い換えに置換 |
音楽スキル→動画づくりへの写し替え
| 音楽の力 | 動画の力 | 具体例 |
|---|---|---|
| 拍の安定 | カットのテンポ | 視聴者の離脱を防ぐ |
| 強弱の設計 | 山場の配置 | タイトル→冒頭→中盤→結末 |
| 音を止める | 間の演出 | サムネ・見せ場の前に静けさ |
4.ハモネプ経験が今に生きる|ブランディングの核心
4-1.「音楽×映像×人柄」の型を確立
舞台で覚えた基本の礼や見せ場の作り方は、動画でもぶれない軸となった。家族で見やすい空気を守りつつ、驚きと安心の両方を届ける設計は、ハモネプ時代の誠実な姿勢に根がある。
4-2.「原点を忘れない」発信
節目の動画で口の打楽器や声遊びを取り入れ、出発点を示す。視聴者は成長の過程を物語として追えるため、長く応援したくなる。
4-3.若者の手本としての広がり
音楽から配信へ道をひらいた具体例として、学校や地域の場でも語られることが増えた。練習→舞台→配信の順に段階を踏む大切さを体現している。
4-4.ブランドの色と声:見た目と音の一体化
| 要素 | 役割 | 効き目 |
|---|---|---|
| 声の調子 | 優しくはっきり | 家族視聴の安心 |
| 色づかい | 明るい基調色 | 親しみと清潔感 |
| 口まわりの動き | 誇張しすぎない | 自然体で信頼 |
ハモネプの学び→現在の強み(要約表)
| 学び | 今の強み | 視聴者への効用 |
|---|---|---|
| 舞台度胸 | 大型企画でも安定 | 安心して見られる |
| 役割理解 | チーム制作の分担 | 作品の質が上がる |
| 音の設計 | 編集と演出に反映 | 飽きずに見られる |
5.テレビとYouTubeの共通点・ちがい|表現の場の本質に迫る
5-1.共通点:若者の「表現の舞台」
どちらも、情熱と工夫さえあれば実力を見せられる舞台。短い時間で魅せる力が求められる点は同じだ。
5-2.ちがい:拡散の仕組みと持続
テレビは一気に広く届き、配信は長く積み上がる。ヒカキンは両方の良さを理解し、狙いに応じた作品設計で結果を出した。
5-3.音の普遍性:言語を越える伝達力
声の重なりや口の打楽器は、ことばを超えて伝わる。どの国の人にも驚き→笑い→共感の流れを生みやすい。
5-4.協力の仕組み:一方向から双方向へ
| 観点 | テレビ(ハモネプ) | 配信(YouTube) |
|---|---|---|
| 観客との距離 | 会場中心 | コメントで直に交流 |
| 直し | 放送前に完結 | 反応を見て改善を重ねる |
| 広がり方 | 番組表に沿う | 共有や関連表示で連鎖 |
テレビと配信の比較(早見表)
| 観点 | テレビ(ハモネプ) | 配信(YouTube) |
|---|---|---|
| 広がり | 一度に大きい | 積み上がりが強い |
| 寿命 | 放送日に集中 | アーカイブで長生き |
| 直し | 事前で完結 | 反応を見て改善 |
| 交流 | 一方向が中心 | コメントで双方向 |
6.時系列でたどる|ハモネプから現在まで(概観)
| 時期 | 出来事 | 軸となった力 |
|---|---|---|
| 高校時代 | 『ハモネプ』出演、エアメールで活動 | 舞台度胸、基礎の練習法 |
| 学生~社会人初期 | 口の打楽器を研究、短い映像を投稿 | 継続力、工夫の積み重ね |
| YouTube初期 | 口だけでの再現動画が話題に | 「驚き×安心」の設計 |
| 現在 | 大型企画と人助け企画を両立 | チーム運営、誠実な発信 |
6-1.成長の指標(見える化)
| 観点 | 初期 | 今 |
|---|---|---|
| 練習量 | 毎日少しずつ | 計画にもとづく反復 |
| 作品設計 | 思いつき中心 | 台本・見せ場の設計 |
| 交流 | 反応を見る | 反応を次の作品へ反映 |
7.これから挑戦する人へ|まねしやすい練習・制作の型
7-1.練習(音)
- 1日10分でよいので毎日。
- キック/スネア/ハイハットを別々に安定させ、合わせない。
- **止める音(無音)**を練習に入れる。
7-2.制作(映像)
- 見せ場を先に決める(最初の20秒に置く)。
- 中盤に小さな山を2〜3回。
- 終わりに次の一本への案内を置く。
7-3.安全と配慮
- 著作権や施設の許可は早めに確認。
- 声・のどのケアを習慣にする。
7-4.一週間の練習例(配布推奨)
| 曜日 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 月 | 単音(キック・スネア) | 各5分 |
| 火 | 連続(ゆっくり) | 10分 |
| 水 | 効果音・止め | 10分 |
| 木 | 小曲30秒 | 10分 |
| 金 | 録音→聴き返し | 10分 |
| 土 | 通し+笑顔のあいさつ | 15分 |
| 日 | 休養・のどの手入れ | — |
7-5.小さな本番の作り方
- 家族や友人の前で一曲だけ披露。
- 録音・録画して改善点を一つだけ直す。
- 次回は一つ加える(見せ場/間/あいさつ)。
練習→制作の流れ(表)
| 段階 | すること | 目安 |
|---|---|---|
| 1 | 単音の安定 | 1〜2週間 |
| 2 | 短い連続 | 2〜3週間 |
| 3 | 30秒の作品化 | 1か月 |
| 4 | 反応を受け改善 | 継続 |
8.機材・録り方・安全と権利|失敗を先回りで防ぐ
8-1.機材の最小セット(家での録音)
| 道具 | 役割 | 代わり案 |
|---|---|---|
| マイク | 声を拾う | スマホ内蔵でも可 |
| 画面機器 | 映像を撮る | スマホで十分 |
| 明かり | 顔を明るくする | 机のあかりで代用 |
8-2.録り方のこつ
- 口とマイクの距離を手のひら一枚分ほど。
- 息が当たらない角度を探す。
- 音量は控えめに始め、後で整える。
8-3.安全と権利のチェック
| 観点 | 確認事項 | いつ |
|---|---|---|
| 場所 | 許可・近所への配慮 | 事前 |
| 音源 | 使ってよいか | 企画時 |
| 体調 | のど・唇の状態 | 当日 |
Q&A:よくある質問(拡張版)
Q1:ハモネプ経験がなくても音の動画は作れる?
もちろん。短い練習動画からで十分。毎日の積み重ねが最短の道です。
Q2:口の打楽器はどこから始めればいい?
キック(プ)、スネア(ツ)、ハイハット(チ)の三つを別々に。録音して自分で聴き返すと上達が早い。
Q3:音楽と編集のどちらを先に学ぶべき?
音の安定→編集のテンポ作りの順が取り組みやすい。音が安定すると編集で迷わない。
Q4:学校や地域で披露するときの注意は?
会場の許可・音量・時間を守り、笑顔のあいさつを忘れない。舞台は礼に始まり礼に終わる。
Q5:機材がそろわない場合の対処は?
スマホ一台で十分。明るさ・距離・角度を整えれば見やすく聞きやすくなる。
Q6:のどを傷めないこつは?
水分・あたため・無理をしない。痛みが出たら休むのが最善です。
Q7:うまくいかない時の心構えは?
一つだけ改善して次へ。完璧より継続が力になる。
用語の小辞典(やさしい言い換え)
ハモネプ:学生中心のアカペラ番組。声だけで曲を作る。
アカペラ:楽器を使わず、声だけで歌う。
ボイスパーカッション:口で打楽器の音を出す技。本文では口の打楽器と表記。
間(ま):音や動きをいったん止めて、次の見せ場を引き立てる時間。
通し:最初から最後まで続けて行う練習。
止め:音を同時に止め、静けさで見せ場を強めること。
まとめ|「声の青春」が今のヒカキンを作った
『ヒカキン ハモネプ』という切り口から見えてくるのは、声で世界を動かすという原点だ。舞台で学んだ礼と設計が、いまの安心して見られる大きな企画を支えている。音と映像が重なり合う場所で、これからも驚きとやさしさを届けつづけるだろう。