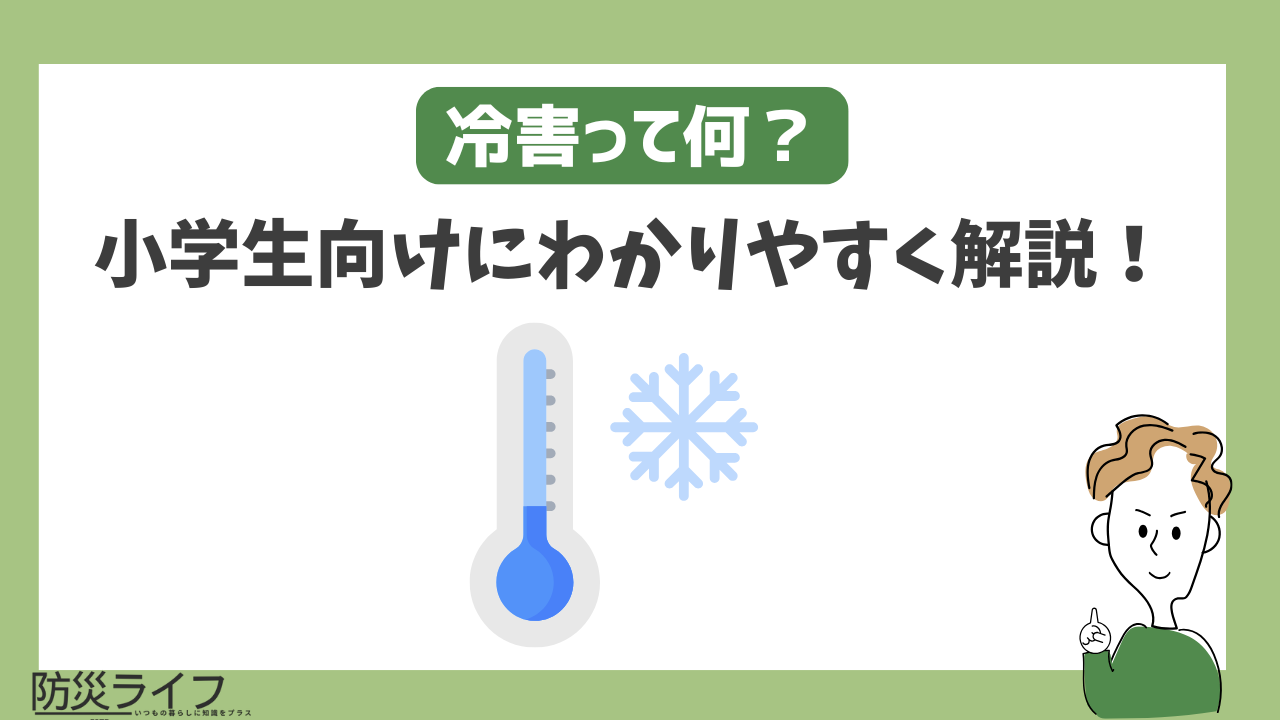はじめに、冷害(れいがい)は、とても寒い天気がつづいたり、気温が急に下がったりして、お米ややさいなどの作物(さくもつ)がうまく育たなくなるできごとです。作物だけでなく、わたしたちの食べものの値段や体の健康、学校・お店のくらしにも大きなえいきょうがあります。
日本ではとくに、東北や北海道などでおこりやすく、夏の終わりから秋のはじめに目立つことが多いのが特徴です。ここでは、冷害がどうやっておこるのか、どんなえいきょうがあるのか、そして安全にくらすために今日からできるそなえまで、やさしい言葉でくわしく説明します。
冷害とは?しくみと原因をやさしく
冷害(れいがい)の意味をおさらい
冷害は、ふつうならあたたかい季節に気温が低い状態がつづくことで、植物の成長(せいちょう)や実(み)のつき方が止まってしまうことをさします。とくにお米は、花がつく大切な時期に寒さがくると実がすくなくなるため、お茶わんによそうお米の量までへってしまうことがあります。
どうしておこるの?お天気のしくみ
冷たい空気のかたまりが、日本の上空に長い時間とどまると、昼でも気温が上がりにくくなります。そこに台風や長雨で日光(にっこう)がさえぎられると、地面や水田(すいでん)があたたまりません。結果として、植物は「いまは育つ時じゃない」と勘ちがいして、成長のスイッチを止めてしまうのです。さらに、風が海からふくやませという冷たい風が続くと、空気も土もひえたままで、**光合成(こうごうせい)**の力がよわくなります。
植物の体では何が起きているの?
植物は、葉っぱで光をあびて**デンプン(エネルギー)**を作り、茎(くき)や実におくります。ところが寒いと、葉のはたらきがにぶくなり、デンプンをうまく作れない→実におくれないという流れになります。お米では、出穂(しゅっすい)→開花(かいか)→登熟(とうじゅく)という順番で大きくなりますが、この出穂~開花に寒さがぶつかると、お花の受粉(じゅふん)がうまくいかず粒(つぶ)がへるのです。
どこで・いつ起こりやすい?地域と季節のポイント
日本のどこが注意なの?
東北地方や北海道は、太平洋のひんやりした空気のえいきょうを受けやすく、水田が多いこともあって冷害のニュースが出やすい地域です。山がちの地形では、夜に冷たい空気がたまり、朝の気温が下がりやすい場所もあります。海の近くでは、霧(きり)やくもりが増えて日照(にっしょう)が少なくなり、気温が上がりにくくなります。
季節はいつごろ?
いちばん気をつけたいのは、夏の終わりから秋のはじめ(8~10月)。お米でいうと「出穂から開花」の時期で、この時期に寒さが来ると実ができにくくなるからです。春や初夏でも、**おそ霜(しも)**が出ると、若い芽(め)がいたみ、冷害のような被害が出ることがあります。
ひと目でわかる地域と季節のめやす
| 地域 | 起こりやすい季節 | どうして? | 作物への主なえいきょう |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北の太平洋がわ | 8~10月 | やませ(冷たい海風)と長雨で地面があたたまらない | お米の実がすくない、野菜の成長がにぶい |
| 山あい・高い土地 | 初夏~秋 | 夜の放射冷却で朝の気温がさがる | 芽や花がいたむ、実が小さくなる |
| 日本海がわの平野 | 梅雨~夏 | くもりが多く日照がたりない | 葉の色がうすくなる、成長がおそい |
ワンポイント:同じ町でも、川べりや谷あいは冷たい空気がたまりやすく、畑の場所によって影響がちがうことがあります。
冷害が起こると何が起きる?くらしへのえいきょう
畑や田んぼで見られる変化
気温がひくい日がつづくと、葉の色があおみどりから黄色っぽくなったり、花がうまくつかなかったりします。お米は花がついてから実にかわる時期がいちばん弱く、粒(つぶ)の数がへることで、収かくの量が目に見えて少なくなることがあります。トマトやキュウリなどは、実の大きさが小さくなったり、実がなる回数がへったりします。
みんなの食卓やお店のようす
作物が少ない年は、スーパーでの品数がへる、または値段が上がることがあります。家計(かけい)にとっても心配ですが、学校や給食でもメニューをかえることが必要になるかもしれません。だからこそ、地域の野菜や保存しやすい食品を上手に使う工夫が大切です。
体と心への影響も忘れずに
寒い日がつづくと、体をあたためるエネルギーがいつもより多く必要になり、つかれやすく感じることがあります。野菜がへると、ビタミンがたりにくいことも。あたたかいスープや煮ものをとり入れて、体を中から守りましょう。気分が落ちこむこともあるので、家族で声をかけ合い、安心できる時間をつくることも大事です。
見つけたら気をつけたいサインと対策
| サイン | 家・学校でできる対策 |
|---|---|
| くもりや小雨が何日もつづく | 体育は室内中心に、体を冷やさない服装で過ごす |
| 朝晩の冷えこみが急に強くなる | 上着やネックウォーマーを用意、寝る前に部屋をあたためる |
| 野菜が高くなってきた | 冷凍野菜や缶詰を活用、旬(しゅん)の食材を選ぶ |
冷害にそなえる:家・学校・地域でできること
家での準備(じゅんび)
まずは、保存しやすい食べものを少しずつふやすことから。お米、めん、乾そう野菜、ツナやコーンの缶詰、冷凍やさいなどを、回しながら使う(ローリングストック)と、むだがありません。服は重ね着(かさねぎ)を基本にし、体の中心をあたためるスープ、みそ汁、湯たんぽなどを活用しましょう。停電や悪天候にそなえて、懐中電灯(かいちゅうでんとう)やモバイルバッテリーも確認します。
家の工夫アイデア
- 窓ぎわから冷たい空気が入るのをふせぐため、カーテンを二重にする。
- 朝いちばんにあたたかい飲み物をのんで体を目ざめさせる。
- 野菜が少ない日は、海そう・豆・きのこで栄養(えいよう)をおぎなう。
学校での行動(こうどう)
学校では、保健室や先生といっしょに体調の変化をこまめに伝えることが大切です。体育や外あそびは、風をさえぎる場所をえらぶ、休けいごとに水分とあたたかい飲み物をとるなどの工夫を。給食では、野菜が少ない時は海そうや豆など、べつの食材で栄養をおぎなうことも学びになります。
地域で助け合う(たすけあう)
冷害はひろい地域で同時に起きることがあります。町内会や学校のPTAで、天気の情報やお店の在庫を共有したり、おすそ分けをしたりするだけでも力になります。地元の農家(のうか)さんの直売所を利用することは、地域の食をささえる大切な行動です。
おうちの備えチェック表(今日から少しずつ)
| 項目 | できた? | メモ |
|---|---|---|
| 保存食(主食・おかず・野菜)のストック | 使った日と追加した日を書いておく | |
| 防寒グッズ(上着・毛布・カイロ) | 家族の人数ぶんを確認 | |
| 情報ツール(ラジオ・充電器) | 電池や充電の残量チェック | |
| 台風や大雨へのそなえ | ベランダの片づけ、窓の点検 |
農家(のうか)はどう対策しているの?
作物の育て方の工夫
農家さんは、寒さに強い**品種(ひんしゅ)**をえらんだり、ビニールハウスで気温を守ったりしています。田んぼでは水の深さを少し深くして、夜の気温を下げすぎないようにすることもあります。苗(なえ)を植える時期をずらして、一番さむい時期をさけることも大切です。
田んぼ・畑の守りかた
- 風がつよい日は、苗が冷えないよう防風ネットを使う。
- 雨が多い時は**排水(はいすい)**をよくして、土がひえすぎないようにする。
- くもりが多い時は、葉が光をうけやすいよう枝(えだ)を整える。
地域でできる応援
近くの直売所や学校の給食で、季節のものを食べることは、農家さんの力になります。おうちでも旬(しゅん)の食べ方を学ぶと、食べものを大切にする心が育ちます。
もっと知ろう!冷害Q&A
Q1. 冷害と「凶作(きょうさく)」は同じ?
A. ちがいます。**冷害は原因(寒さ)**のこと、**凶作は結果(収かくが少ない)**のことです。冷害の年は凶作になりやすいけれど、農家さんの工夫でへらせることもあります。
Q2. 都会でも冷害のえいきょうはある?
A. あります。スーパーの品ぞろえや値段にひびいたり、学校給食のメニューがかわったりします。
Q3. 家で簡単にできる「省エネ防寒(ぼうかん)」は?
A. カーテンを長めにしてすきま風をへらす、足もと用マットで床からの冷えをカット、湯たんぽで体の中心をあたためる、などが効果的です。
Q4. 冷害の年におすすめの食べ方は?
A. スープ、なべ、煮こみがおすすめ。冷凍野菜や豆、きのこ、海そうをつかって、栄養をまんべんなくとりましょう。
Q5. 天気予報では何をチェックすればいい?
A. **最高・最低気温、日照時間、風の向き(やませ)**を見て、数日先までの流れを家族で話し合いましょう。
ミニ辞典(じてん)
- やませ:夏でも海からふく冷たい風。東北の太平洋がわで多い。
- 出穂(しゅっすい):お米の穂(ほ)が出ること。ここから花がさき、実になる。
- 登熟(とうじゅく):実の中でデンプンがたまって大きくなること。
- 光合成(こうごうせい):葉っぱが光をつかってエネルギーを作るはたらき。
まとめ:冷害を知って、安心してくらそう
冷害は「寒さが長くつづく」ことから始まり、作物の元気がなくなることで、わたしたちの食卓や学校生活にも影響がおよびます。 でも、天気のようすをこまめにチェックし、保存しやすい食べものを回しながら準備し、体をあたためる習かんをつければ、きちんと対策できます。今日からは、家族で避難(ひなん)場所や連絡のしかたも話し合ってみましょう。知ることがいちばんの防災です。正しい知識と毎日の小さな準備で、冷害の年でも安心してすごせるようになります。