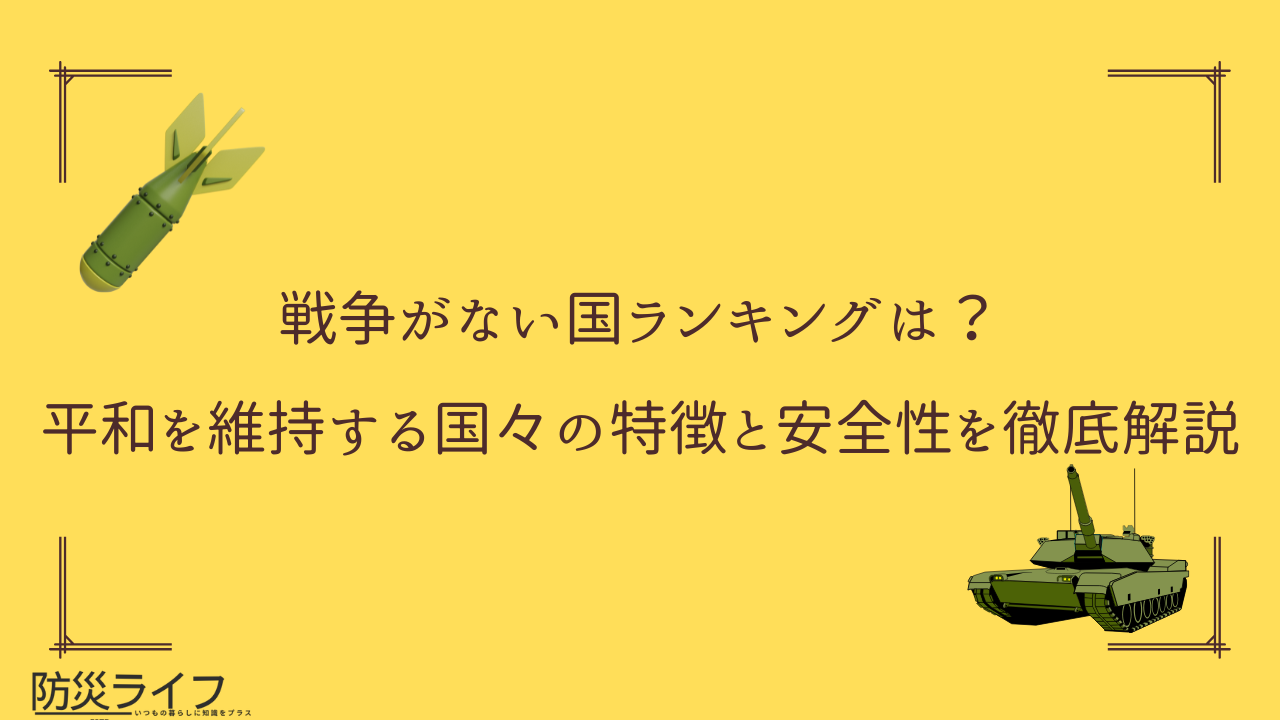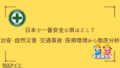導入文:
「戦争がない国」と一口に言っても、その中身は一様ではありません。過去の戦争経験の有無、近年の武力衝突への関わり、国内の治安、外交の姿勢、国民生活の安定など、いくつもの面を重ねて見て、はじめて実像が浮かび上がります。
本稿では、誰にでも伝わる言葉で評価の物差しを整えたうえで、平和度が高い国の顔ぶれと共通点を丁寧に読み解きます。結論は「一位だけ」を決めることではなく、どうすれば平和が続くのかを生活者の目線でつかむこと。旅行・留学・移住の判断に使えるよう、表と具体例を厚くし、日常の行動に落とし込める工夫まで示します。読み終えたら、地図を開いて自分に合う平和の形を選べる――それがこの記事のねらいです。
「戦争がない国」の定義と評価軸(まず物差しをそろえる)
定義の考え方(外への戦争・内の争い)
ここでいう「戦争がない国」とは、過去100年ほどの間に対外戦争や内戦をほとんど経験していない、または長い期間にわたり武力衝突から距離を置いている国を指します。これに加えて、現在も大規模な軍事衝突に関わっていないこと、国内の暴動や深刻な政治的暴力が少ないことを条件に含めます。つまり、外に対する戦争だけでなく、内側の平穏も見ます。たとえば小競り合いのような事件はあっても、国家の方針として武力で物事を解決しない姿勢が続いているか――ここが重要な分かれ目です。
この定義は万能ではありません。歴史の長さ、周辺地域の情勢、地理的な条件(島国か内陸国か)によって戦争に巻き込まれにくさは違います。そこで本稿では「ゼロか一か」ではなく、戦争から距離を保ち続ける力を広くとらえていきます。
評価の柱(六つの視点)
平和度を測るため、次の六つを柱にしました。点は低いほど平和度が高いと読みます。数値化は国の優劣を決めるためではなく、傾向を比べるための目安です。
| 項目 | 見るポイント | 点の目安 |
|---|---|---|
| 過去の戦争経験 | 100年ほどの間の対外戦・内戦の有無 | 無=0/小=1/有=2 |
| 軍事関与の少なさ | 他国紛争への関与度、同盟での役割 | 少=0/中=1/多=2 |
| 国内の治安 | 凶悪事件の少なさ、社会の安定 | 良=0/普=1/不安定=2 |
| 外交の姿勢 | 中立・対話重視か、仲介の実績 | 高=0/並=1/低=2 |
| 人の暮らし | 教育・医療・生活の安定 | 安定=0/並=1/不安=2 |
| 災害と備え | 非軍事の危機への強さ(災害・感染症) | 強=0/並=1/弱=2 |
読み方の要点:
- 一点だけ突出して良くても平和は続かない。 たとえば治安が良くても災害に弱ければ、混乱が社会不安に変わり得ます。
- 軍隊の有無より、使い方と位置づけ。 軍があっても専守防衛を守り、外交で火を消せる国は平和を保ちやすい。
- 暮らしの安定は最強の防波堤。 失業や格差が小さく、医療と教育が届いていれば、社会は揺れにくい。
ランキングの限界(数だけで決めない)
平和は時点で変わる性質があり、地理・資源・人口など国の事情も大きく効きます。統計の良し悪しは集計方法や定義に左右されます。だからこそ、数の大小に頼りすぎず、**「なぜ続いているのか」**を合わせて読むことが肝心です。小国が有利に見える場面もあれば、大国でも地域の分断を丁寧に埋める工夫で平和を保っている例もあります。数字は入口、中身は物語。この二段読みで、地に足の着いた理解に近づけます。
戦争がない国の顔ぶれ(例示ランキングと短評)
上位の例(五十音順ではなく性格順)
以下は平和度が高い国としてよく名が挙がる例です(順番は性格の近さで並べています)。小国が多いのは、周辺国と摩擦を作らない外交や国内の合意の作り方が機能しているためです。
| 立ち位置 | 国名 | 軍の位置づけ | 外交の型 | 国内の特徴 | 注意点のメモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 非武装・最小限 | アイスランド | 正規軍なし(沿岸警備) | 同盟はあるが対話重視 | 犯罪が少なく社会の結びつきが強い | 地理上、防衛は同盟依存 |
| 中立堅持 | スイス | 国土防衛のための体制 | 永世中立・仲介 | 政治参加が盛ん、治安良好 | 兵役制度など独自の仕組み |
| 非軍事優先 | コスタリカ | 1949年に軍を廃止 | 教育・医療へ投資 | 自然保護と観光立国 | 周辺情勢の変化に注意 |
| 対話と規範 | ニュージーランド | 防衛力は抑制的 | 非核・人権重視 | 治安良好、社会の合意形成 | 地震など自然災害への備えが要 |
| 平和憲法の下 | 日本 | 自衛目的の体制 | 国際協力・支援で貢献 | 社会基盤が整う | 自然災害が多く備えが要 |
| 和平仲介・対話 | アイルランド | 防衛は抑制的 | 欧州の中で対話役 | 教育水準が高い | 国際情勢の影響を受けやすい |
| 非武装に近い | パナマ | 軍なし(治安機関中心) | 交易と対話 | 国際輸送の要衝 | 経済変動の影響あり |
| 平和志向の小国 | ブータン | 小規模な防衛 | 国民の幸福重視 | 伝統と現代の調和 | 地理的制約が大きい |
| 対話と海洋国家 | ポルトガル | 防衛は抑制的 | 欧州の協調 | 観光と文化の力 | 経済依存の幅を広げる課題 |
| 多文化の安定 | カナダ | 防衛は抑制的 | 多国間協調 | 社会の包摂が強い | 広大ゆえの治安差に注意 |
| 超小国の合意 | アンドラ | 軍なし(警備中心) | 周辺と協調 | 観光・教育に強み | 経済の振れに注意 |
| 城郭国家の慎重さ | サンマリノ | 軍は儀礼中心 | 中立的 | 市民参加が濃い | 雇用は周辺依存 |
| 都市国家の秩序 | モナコ | 軍は儀礼中心 | 観光外交 | 監視と治安が機能 | 物価高と外的影響 |
| 山岳小国の協調 | リヒテンシュタイン | 正規軍なし | 近隣と協力 | 産業は安定 | 外に開く余地 |
| 南米の穏やかさ | ウルグアイ | 防衛は抑制的 | 対話重視 | 教育と医療を重視 | 近隣情勢の波に注意 |
ここに挙げた国々は**「長期にわたり戦争から距離を置いてきた傾向」や「対話と国内の安定を重んじる姿勢」で知られます。国名の順は優劣ではありません。国によっては自然災害や経済の波といった非軍事の課題が大きく、そこへの備え**が平和の土台を支えています。
短評の深掘り(三つの型)
- 非武装・最小限型:アイスランド、コスタリカ、パナマ、アンドラ、サンマリノ、リヒテンシュタインなど。軍を持たないか規模を最小限にして、教育・医療・環境へ力を振り向けます。国家の体格に合った安全保障を選び、周辺と敵を作らない関係を築くのが柱です。
- 中立・仲介型:スイス、アイルランド、ポルトガルなど。中立や仲介で紛争から距離を保ちつつ、対話の場を提供します。言葉の通じやすさや金融・外交の基盤がそれを支えます。
- 抑制的防衛・国際協力型:ニュージーランド、日本、カナダ、ウルグアイなど。国土の守りは保ちつつ、国際援助や平和活動に顔を出し、対話の規範を広げます。軍の使い道を絞り、国内の暮らしを厚くする発想が根にあります。
近年の流れと読み方
観光、移住、留学の人気で人の動きが増えるほど治安維持の工夫が必要になります。平和国家といえど、自然災害や感染症、経済の波は避けられません。「平和=無防備」ではないことを頭に置き、災害・情報・社会の三つの備えを重ねる国ほど、揺れにくい姿を保てます。国境を越える情報の速さが誤解や対立の火種になることもあるため、丁寧な説明と透明性が一段と重要になっています。
総合ランキング(編集部独自指標・参考)
算出方法の要点
本文の六つの柱(過去の戦争経験/軍事関与の少なさ/国内の治安/外交の姿勢/人の暮らし/災害と備え)をそれぞれ0〜2点で採点し、合計が小さいほど平和度が高いと読みます。小国や島国は地理の利点で有利に見える場合があるため、規模や地勢の差は注記しました。下表は現時点の傾向を示すもので、固定的な序列ではありません。
トップ10と短評(合計は推定・低いほど良い)
| 順位 | 国名 | 合計点 | ひと口解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 2 | 正規軍を持たず、対話と同盟で外の火を避ける。治安が良く、暮らしの満足度が高い。 |
| 2 | スイス | 3 | 永世中立と仲介の伝統。国土防衛は堅いが、対外戦には距離。政治参加が広く治安も安定。 |
| 3 | コスタリカ | 3 | 軍を廃止して教育と医療へ投資。中米の中で平和外交を重ね、観光と環境保護を両立。 |
| 4 | ニュージーランド | 4 | 非核の姿勢と対話重視。治安は良好。地震など自然災害はあるため備えが重要。 |
| 5 | アイルランド | 4 | 中立志向で対話役を果たす。学びの質と暮らしの安定が強み。国際情勢の波は受けやすい。 |
| 6 | ポルトガル | 4 | 協調外交で緊張を避ける。治安は落ち着く。観光依存の振れに注意。 |
| 7 | カナダ | 5 | 多文化の受け皿が厚く、対外関与は抑制的。地域差と広大さゆえの治安のばらつきに留意。 |
| 8 | 日本 | 6 | 平和憲法の下で専守防衛と国際協力。治安は良いが自然災害が多く、備えが平和の土台。 |
| 9 | ウルグアイ | 5 | 南米で比較的安定。教育と医療を重視し、対話で緊張を下げる。周辺情勢の影響は受けやすい。 |
| 10 | ブータン | 6 | 小国ならではの合意形成と幸福重視。地理的制約と雇用の幅の狭さが課題。 |
使い方:合計点は傾向をつかむ手がかりです。旅行・留学・移住では、本文の「目的別の見方」と重ねて判断してください。
小国(超小規模国家)の特別枠
アンドラ/サンマリノ/リヒテンシュタイン/モナコは、軍を持たないか儀礼中心で、周辺国との協定で安全を保っています。人口が少なく国土が小さいため、治安維持や合意形成がしやすい一方、雇用や価格が周辺依存になりがちです。指標上は高順位になりやすいものの、生活の実感は地域差が大きい点に注意。
項目別の上位(参考)
- 「過去の戦争経験が少ない」:アイスランド、コスタリカ、アンドラ、サンマリノ
- 「軍事関与が少ない」:コスタリカ、アイスランド、ブータン、アイルランド
- 「国内の治安が良い」:アイスランド、スイス、ポルトガル、カナダ
- 「外交の姿勢(中立・仲介)」:スイス、アイルランド、ポルトガル
- 「人の暮らし(教育・医療・生活)」:カナダ、ニュージーランド、スイス、ポルトガル
- 「災害と備え」:スイス、ポルトガル、カナダ(日本・ニュージーランドは備えは強いがリスクも大)
戦争がない国に共通する仕組み(平和が続く理由)
軍のあり方と抑止の考え方
軍を持たない、または最小限にとどめる国は、国土防衛の要点だけを整え、治安・防災・教育に資源を振り向けています。軍を持つ国でも、専守防衛を徹底し、海外での攻撃行動を取らない姿勢が平和を支えます。ここで重要なのは、軍事費の大きさではなく、使い道の明快さです。国民に**「何のための備えか」**が見えると、合意は長持ちし、外への誤解も生みにくくなります。
下表は、軍の位置づけと平和への効き方をまとめたものです。
| 位置づけ | 中身 | 平和への効き方 |
|---|---|---|
| 無し・極小 | 沿岸警備や治安機関中心 | 軍事衝突の口実を与えにくい。外交と防災が主戦場 |
| 専守防衛 | 国土防衛に限定 | 誤解を招きにくく、対話の場で信頼を得やすい |
| 仲介と連携 | 国際機関での協力 | 火消し役として周辺の緊張を下げる |
外交の型(中立・仲介・国際協力)
平和国家の多くは、中立宣言や対話の場づくり、国連などでの仲介や支援を重ねています。敵を作らない姿勢は、周辺国との信頼を厚くします。さらに、留学生や研究者の受け入れ、災害時の相互支援など、人の往来を通じた信頼づくりが長期の平和を育てます。**「いつも開いている窓」**をいくつ持てるかが、国の空気を穏やかに保つ鍵です。
国内の土台(暮らしの安定)
教育・医療・社会保障が整うほど、不満が暴力へ向かいにくい社会になります。地域の結びつきが強いほど、犯罪の芽を早く見つけて摘むことができます。加えて、報道の自由と情報の見える化は、うわさや誤情報が広がる前に火を消す力になります。少数者へのまなざしが行き届くほど、社会の底は固くなります。
平和を保つための政策と暮らし(国の手立てと市民の知恵)
学びと話し合い(合意づくり)
学校や地域で話し合いの練習を重ね、意見の違いを調整する力を育てる国は、対立が起きても暴力に頼らない道を選びやすくなります。授業での討論の型、地域での住民協議、職場での意見箱と第三者の調停など、小さな合意を積み重ねる仕組みが大きな衝突を防ぎます。言葉で橋をかける力が、国の空気をやわらげます。
危機への備え(災害・感染症・情報)
軍事ではない危機――地震・台風・豪雨・感染症・情報の混乱――への備えが強い国は、社会の混乱が暴力や差別に広がるのを防ぎやすいという共通点があります。避難所や医療の訓練を定期的に行い、家族の連絡方法を決め、うわさを見分ける力を育てる。これらは戦わずに守る力です。水・食料・薬の平時の備えは、いざというとき人心を落ち着かせ、**「誰かを責める空気」**を生みにくくします。
経済と自然のバランス
働き口の安定と格差の縮小、自然保護は、いら立ちや不満の広がりを抑える力になります。小さな不公平を丁寧に直す姿勢が、長い目の平和を支えます。景気が冷えても最低限の暮らしを守る網がある国は、恐れが怒りに変わる前に人を支えられます。森・川・海の自然の恵みに感謝しつつ守る文化は、奪い合いを遠ざける知恵でもあります。
結論と使い方(旅行・留学・移住の判断に)
目的別の見方(自分に合う平和の形)
平和の見方は目的で変わります。短期の旅行なら治安と医療の届きやすさが第一。留学なら学びの質と差別の少なさ。移住なら仕事と住まい、家族への手当が問いになります。
| 目的 | 見るべき点 | 合う国の例 | 暮らしの合う人 |
|---|---|---|---|
| 旅行 | 治安・言葉の通じやすさ・医療の届きやすさ | アイスランド、スイス、ポルトガル、ニュージーランド | 自然と文化を落ち着いて楽しみたい人 |
| 留学 | 学びの質・差別の少なさ・暮らしやすさ | カナダ、アイルランド、ニュージーランド、スイス | 研究に集中したい人、語学と専門を両立したい人 |
| 移住 | 職と住まい・社会の支え・家族への手当 | カナダ、ポルトガル、ニュージーランド、コスタリカ | 家族の時間を大切にし、地域と関わりたい人 |
リスクの見落としを減らすチェック
- 最新の安全情報を確認する(治安・感染症・天候)。
- 病院と日本大使館・領事館の場所を地図で押さえる(連絡先を紙にも控える)。
- 夜の移動は明るい道に限る(迷いやすい道は日中に下見)。
- 災害の季節を調べ、装備を整える(暑さ・寒さ・暴風雨)。
- お金と身分証の持ち方を二重化する(万一の紛失に備える)。
まとめ
平和は偶然では続きません。 非武装や中立だけでなく、教育・福祉・対話・備えがかみ合ってはじめて形になります。国の順位に一喜一憂するのではなく、なぜ続いているのかを学び、自分の暮らしに生かす――それこそが「戦争がない国ランキング」を読む意味です。今日できる一歩は、話し合いの練習・災害の備え・情報の見極め。この三つを自分の毎日に置くことから、戦わずに守る力は育ちます。